はなおくらレポート
箱木の千年家・衝原湖
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 今年は、春先に暖かい日が続き、さくらの開花が早まっていた。この時期からさくらを見るには、市内でも少し開花が遅めの北区でという事になった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
 |
箕谷駅を降りると、なにやら白いものがひらひら落ちてきた。雪か・・・と一瞬思ったが、さくらのはなびらだった。そこから市バスで「衝原行き」に乗り換え終点まで20分。この路線は本数が少ないので帰りの時刻を確かめておいた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
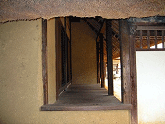 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 千年家全景 | 離れより母屋を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バスを降り、歩いて3〜4分くらいで日本で現存する民家としては最古といわれる「箱木家住宅」が見えた。受付らしき建物の中に年配の男性がおられた。彼は52代目現当主で、国指定重要文化財としての箱木家を守っておられる。先祖は三木城に仕える山田の庄の地侍で、庄屋で農業も営んでいたそうだ。千年家(せんねんや)とは「1000年経った家」というのではなく「非常に古い家」という意味だそうだ。昭和52年、衝原湖(つくはらこ)に、呑吐(どんど)ダムを造るために箱木家は解体され、70メートル南東に移築。解体時に調査したところ工法等から建てられたのは14世紀頃ではないかと推測されている。その際、一部の住宅は除かれ、母屋と離れが再現。当然、箱木家の人たちも、それまでこの家に住んでいたが、現在は隣の近代的な家に住んでおられる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
入場券(300円)を買い求めて、早速中に入った。入ってすぐに蔵があり、昔使っていた木製の農機具類が展示されていた。母屋は、昔話に出てくるような、萱葺屋根のどっしりとした家だった。外壁は、壁土のままで板などで囲っている様子はなかった。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 蔵 | 美しい屋根組み | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中に入ると、説明のテープが流れていた。とても暗いというのが第一印象だ。14世紀前後のころは部落の中心的存在であったといわれる事から当時の人たちの質素な生活ぶりが偲ばれる。見学者のために入り口の開け放された、火の気のない家はひときわ寒い。母屋に入ってすぐ右手は厩らしき造りになっており、今は農機具が並べられていた。後で聞くと農作業のために牛を飼っていたそうだ。この厩を含め全体が広い土間になっていた。土間に立って見上げると、太い梁の屋根組が美しい景色となっている。その上に萱を葺いているそうだ。柱は太く30cm位はあるだろうか、四隅は面取りされていたが、これは当時の家の格式の高さを示すそうだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
 |
土間の端には、茶碗から餅つきの道具まで生活用品が無造作に並べられてあった。3口のかまど、外へ直接排水ができる流し台。水がめはすぐ横に置いてあったのだろうか。勝手口から井戸までは飛び石が並んでいた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 部屋は、囲炉裏のあるおもての間、納戸、台所と3部屋で、全部、板の間になっていた。今のフローリングである。この家が建てられた頃はまだ、カンナはなく手斧(チョウナ)という道具で削ったそうで、表面はちょうどウロコを裏返しに並べたようだ。歩いてみると足の裏の感触も気持ちよい。 長い年月、燻され磨き上げられて黒光りし、なんともいえない上品な美しさだった。 |
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 土間の様子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 離れの一室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 軒は低く長いので、日差しが中まで届かず、夏は涼しかったと思われる。その分暗く、行灯に電球が灯っていたが、とても裁縫や書物を読むのは無理だろうと思った。 昔はロウソクを灯していたのだから、なおさら暗かっただろう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 囲炉裏のあるおもての間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
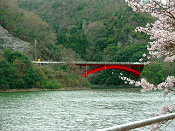 |
1時間程で見学を終え衝原湖・呑吐ダムへ。桜のこの季節には例年、大勢の人出があるのだが、いつになく肌寒い日でひっそりしていた。それでも遊歩道への入り口の桜は満開で十分楽しめた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 土手の桜は手入れが良くないのか、花つきも心なしか少なく感じた。よく見ると幹の陽の当たらない方にキノコがびっしり生えていた。このキノコはインターネットで調べてみると、桜の木などに寄生して木を傷めてしまう「カワウソダケ」のようだ。また、以前は湖の周りを貸しサイクリング車で楽しめたが、現在はやっていない。持込でサイクリングをしている人は見られた。 湖畔のベンチで持参したお弁当を食べ、早々に帰路につく。 季節外れの寒さに震えた1日だった。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 衝原湖 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームへ | |||||||||||||||||||||||||||||||