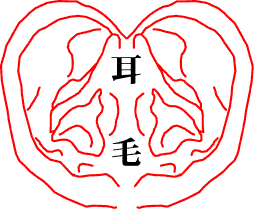 |
この話は以前、友人への手紙に書いたものに加筆したものです |
|
わたしが、その男に会ったのは、科学博物館の人類学部門の展示場です。 冬の平日の博物館は、人気もなく、湿っているのか乾燥しているのかわからない、すこし癖のあるにおいで満たされていました。 頭骨がずらりと並んだ展示ケースの前にその男はいました。人などいないと思っていたわたしはギョッとしたことを覚えています。 わたしは、べつに人骨に興味があったわけではありません。暇潰しに入った博物館で、きっちりと暇をつぶしていただけなんです。正直に告白すれば、博物館に入る前の仕事の打ち合わせで、わたしは生きたものにほとほと疲れていたからです。 館内は暖房が効いているにも関わらず丈の長いコートを着たままでいたこと除けば、別に男に怪しいところはありませんでした。 それでも、わたしが、男を避けるように男の背後を一メートルぐらい離れて通りすぎたのは、熱心に展示を見ている男を邪魔するのことに気がひけたこともありますが、生来の臆病のせいです。 男の背後を通り過ぎるとき、かすかに、男の服からは防虫剤の香りがしました。 「おい、あんた。知っているのなら教えて欲しいのだが、なんで、耳毛が生えるんじゃ」 わたしは男を通り過ごして充分に距離をとったつもりでしたが、振りかえるとすぐ脇にその男は立っていました。頬が少しこけ、髪が長く、顎に髭を生やしています。落ち着いた外見とは対照的に、目はキラキラと輝いていて、とんでもない悪戯を思いついた子どものようでした。 「は」 もし、口からでた言葉が見えるのであったら、わたしの「は」は、特太ゴチックで書いたような文字に見えたことだとおもいます。 男は急に顔をわたしの耳に近づけてきました。わたしは逃げようと思いましたが、男の手がわたしの耳をつかむほうが早かった。 「痛いっ!」 「ふん、おまえは生えていないんだな。まだ、若い」 「なにするんですか」 男はわたしの抗議など耳に入らないように、耳をわたしの顔に差し出しました。 「ほらここに毛が生えているだろう」 男の耳の穴をふさぐように、びっちりと毛が生えていました。これでは、風の強い日は、ゴォーゴォーとなって煩いのではないかと思ったほどです。 「この突起を耳珠(じしゅ)というんだが、ここに毛が生える。こんなところに毛が生える必要はないだろう。だけど生える。なぜだ」 「なぜだといわれても……」 「人間の体毛は、それなりに理由があって存在しているはずだ。いまでは限られた場所にしか目だった毛は生えていない。でもなんでこんなところに毛があるのかわからない部分もあるだろう。おまえさんも思ったことはあるだろう。どうだ? え」 「ええ、まま」 「頭髪や眉毛はいいとしよう。腋毛はなんのためにある? 髭はなんのためにある? 陰毛もそうだ。なんであそこに毛が必要なんだ? 服を着るようになったから毛がなくなったのか、それとも、裸の奇形の猿がうまれたから、衣服を身につけるようになったのかしらないが、まぁ、そんなことはどうでもいい。一番不思議なのは、ここに生える毛だ。なぜだ」 男は自分の耳たぶを引っ張りながら疑問を発した。それは、わたしに向けられたものではなかったのかもしれません。だけど、あまりに奇妙な話に、つい、答えてしまいました。 「さぁ、耳の穴が露出していると、ごみが入るとこまるからじゃないですか」 「おまえさん、できるね。だけど、おしい。ごみじゃなくて、虫だよ、虫。耳虫が入らないようにするためだ」 「耳虫」と聞き返すのを止めろと、わたしの心は命じていました。この男は狂っている、関わりあうとろくなことはない。これだから生きている奴は厄介だとわたしの心はひとりごとを言っていました。 でも、わたしの口は心の命令に反して聞き返していました。 「みみむしですかぁ」 「そうだ。耳虫だ。耳から入りこんで、鼓膜を食い破り、脳内に入りこんで食い荒らす奴だ」 だから止めておけといっただろうと、わたしの心はぶつくさ言っていました。 「その証拠をこうして探しているんだ。耳虫の痕跡がないかとおもってな。だが、ガラス越しじゃなにもわからん。手にとって、骨の内側を見てみないことにはな。それよりも、頭骨と一緒に掘り出された土壌分析をしなければだめだ。こんなにきれに掃除された骨じゃだめだ。こっちにこい」 男は、わたしがついてくるのが当然だと言うようにスタスタと歩き始めました。つい、わたしはついていってしまった。今思えば、毒を食らわば皿までの気持ちだったのかもしれません。 「こいつだ。こいつの頭の中を調べればいいのかもしれない」 こいつ――とは、ミイラだった。 「いままで、何体かミイラを手に入れて解剖してみたが、発見できなかった」 ここでわたしは「もともと、耳虫なんていないんじゃないですか」といってもよかった。 「数が少なければ、本当にいるかいないか、確定もできない」 サンプルの数を問題にするということは、案外この男はまともなのだと思いました。しかも、存在を確認するためでなく否定的な答えでもかまわないという潔ささえ感じました。 「どうおもう。おまえはいると思うか」 「いや、ぼくは素人だから」 「疑問を持つことに素人も玄人もあるか」 わたしはもう帰ろうと思いました。この人はわたしに答えなど求めていない、そう思ったからです。男はミイラをじっと見つめています。この隙に立ち去ろうと思いました。わたしは、ほかの展示に気を引かれた振りをして、徐々に男との距離をあけていきました。 男が追ってくる気配はありません。男はわたしに興味があるのではない、耳虫とやらに関心があるのです。 展示室の入口近くの展示ケースにようやくたどり着くと、ガラスに男の姿が見えないことを確認して、ヒョイと階段室に移動し、そのまま博物館を出て帰宅しました。 博物館で出会った妙な「耳虫男」のことは、その後、会う人ごとに話しました。メールで友人に紹介したりもしました。 一通り知り合いに話し終え、忘れかけていた時、わたしは仕事の帰りに駅の売店で見かけた新聞の見出しに足を止めました。 「猟奇殺人!? 犯人逮捕!! 脳の中に虫がいる」 ええっ!? と思ったわたしは、新聞を買い求め記事を読みました。 「都内で立て続けに、頭を割られる事件が発生していたが、その犯人が二五日逮捕された。男は『脳の中に棲息する耳虫を見つけたかっただけだ。殺すつもりなどなかった』と供述している。さらに男は『耳に無用な毛が生えるのは耳虫の存在を示唆している。だが、耳に毛の生える人間とそうでない人間がいる。それは、耳虫が好む人間と好まない人間が存在するということだ。耳毛が生える奴は、耳虫に好まれる、つまり、耳虫の餌になる人間だ。だから、耳の毛が生えている奴の脳を調べてみれば、耳虫が発見できるかもしれない』と供述しているという。警察は男の犯行動機に不審な点もあるとして、男の精神鑑定を行う予定である。……」 新聞には名前も顔写真も載っていませんでした。しかし、記事の内容は、あの日わたしが博物館で出会った男に聞いたことと同じでした。 帰宅したわたしは顔を洗った後、耳たぶをひっぱってみました。耳珠をひっくり返してみると、そこには、チョロリと毛が生えていた。鼻毛のように短いくせに手強い姿の毛です。 「こんなところに毛が生えるなんて、俺も年をとったな。いやだやだ」 わたしは、そうおもい、爪でつまんで、えいと引きぬきました。 わたしはあの男の耳毛を引きぬいてやれば良かったのかもしれません。 |
| ----おわり---- |
3号店メニューに戻る トップページに戻る King's Cafe エントランス |