ARPG フロム・ソフトウェア 2000 SLPS 25001 25時間
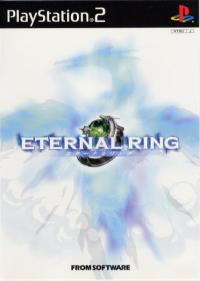 ©From Software
©From Software
あのフロム・ソフトウェア(アーマードコア,etc...)がPS2本体と同時発売するタイトルということで期待せずにはおられない作品であったが,プレイを終えてみて気づいたことは,自分を納得させようとしている自分の存在だった.
周知の通り,PS2では各社とも「如何に美麗なグラフィックを見せられるか」,この点に絞ってソフト開発を行ってきた.この点は新ハード(と,そのプラットホームで遊べるソフト)の魅力を広く一般に伝えるには非常にわかりやすく,その戦略自体は間違っていないと思う(事実,今までのゲームの歴史において,毎回行われてきた手法である).本作もその文脈に則り,デモでのドラゴンの動きには,「これでまた一段,ゲームのムーヴィーのクオリティーが上がった」と感じさせられるものがあった.
本作は,エターナル・リングを求めて「不帰の島」へと一人向かうカイン・モーガンを主役として進められる3D
ARPGであり,自社の「キングス・フィールド」の流れを汲むものである.この手のゲームにはありがちなのだが,プレイしてみてまず感じることが,「自分の歩行速度が絶望的に遅い」ことである.序盤に「パワーオブムーブ」という速度アップの指輪が入手できるのだが,それでも焼け石に水.ゲーム終了までコントローラーの○ボタンは押しっぱなしのままだった.サクサクと移動できてしまっては移動の速いプレイヤーに対して攻撃を仕掛けてくる敵キャラの動きも当然速くせざるを得ず,そのためマシン・スペック的に厳しく(なるのか?---なりそう.終盤,一部処理落ちするところがあったから.),またある程度のプレイヤーの技量が求められるようになるため,敷居を下げる必要があったとも考えられる.このあたりの調整にもう少し時間を割いていれば...そう,本作を語る上で避けて通れない言葉,それが「時間」である.一説によると,SCEIから開発ツールが提供されたのが99年9月頃とのことで,その時点から本体発売日の2000/03/04に間に合わせるには並々ならぬ苦労があったことは容易に推察される.本体発売日というデッドラインに間に合わせるため,細部のバランス調整をあきらめ,イベントの省略を行い,バグ(壁を通り抜けて敵の魔法攻撃が直撃する,etc...)を減らすことが十分行えないままのリリースとなったことは開発スタッフの人々にとっては誠に残念なことだったろうと思う.
さて,ゲーム自体だが,敵との戦いは
1.魔法で攻撃,ひるんだ隙に剣で突く,後退して再度魔法で攻撃,ひるんだ敵に剣攻撃
2.敵の懐に飛び込み,剣で攻撃,右周りをしながら常に敵の斜め横から横あたりの位置に立ち右周りをしながら剣でチクチク攻撃する
この2通りの手法だけを習得(というほど難易度が高いわけではない)すれば,ワンパターンでサクサクと進んでいく.1.はモーションの大きい打撃系のキャラ.2.は魔法で遠距離攻撃を仕掛けてくるキャラとその攻略法も敵キャラを一度見ただけで容易に推察できる.
また,魔法はタイトルにも現れているようにリングを装備することにより発動する.これらリングはリングの形で落ちていることもあり,また魔法石を組み合わせて作成することもできる.作成する魔法リングも終盤,レヴェル4の魔法石6個を組み合わせてできる各属性の最強魔法を一通り揃えれば,攻略の難易度はさらに下がることになる.
コマンド形式のRPGではラスボスとの戦いは前座からの戦いを含めると1時間以上は延々闘うことになるが,ARPGでは前座込みでも数分で片付くようにするのは正しい方向ではあり,またライト・ユーザーが,本人の技量によってどうしても解けない,という状況に陥ることは「努力すればダレにでも解ける」ことが前提となっているRPGというジャンルではあってはならないことである.そのため,限られた短期間で作り上げたこの方向自体は正しかったであろうし,またそれを実現したスタッフの努力も賞賛に値するものであろう.
昨今,古いメディアに取りあげられることが多い,「ゲームばっかりしてる人には人の死についての理解が乏しい」という意見への回答のように,ラスボスは感情を持たない子供であり,倒された後,死亡したライラのことを思い遣ることで初めて,感情を芽生えさせる.そのことをキャラ自体の体を成長させることで表現している.子供から大人へ,と.しかし,それまでの展開に対して取ってつけたようなメッセージはいかがなものだろうか.伝えようとしていることは大事なことではあるが,それはゲーム本編とは剥離しており,「伝えたいメッセージがあるから,そのためにこのゲームがある」のではなく,「ゲームはゲーム.でも,せっかくだから何かメッセージを入れよう.」という風に感じられる.
フロム・ソフトウェアは玄人受けする非常に魅力的な作品を多数リリースしてきたが,ここへ来て「脱・マイナー」への試行錯誤の過程にあるように思われる.そのための歩みよりであった,派手なグラフィックは功を奏したが,お手軽メッセージ付加(添付とも言える)は空回り.のりで貼ったつもりがプレイヤーの手元に届いた時には剥がれていた,と言ったところか...しかし,短期間であったのを鑑みれば,このレヴェルのクオリティーを持っていれば,「可」レヴェルではないだろうか.今後,じっくりと練った作品を作ってきたときには賞賛で迎えられるであろうことを信じている.(2000/06/18)
RPG スクウェア 1997 SLPS 02766 20時間
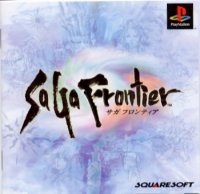 ©Square
©Square
キャラ選択式マルチ・シナリオRPG.あらかじめ用意されている7人(ロボットもいるが...)から,任意のキャラを選び,そのキャラが主人公となったストーリーを楽しむ(この場合,他の主人公キャラが脇役でストーリーに絡む構成),というアイデア自体は良かったがそれがゲームとしては上手く消化できていなかったのではないだろうか.ゲーム中に,進めない行き止まりが散見している.例えば,ブルー編では,他の主人公キャラでのプレイではイベントが発生すると思しき個所(神殿だったり,大広間だったり,開きそうな扉の前)では何も起こらない.あるいは扉が開かない,無理やりマップから追い出される,といったことが平気で行われる.プレイヤー側に「お好きなキャラを選んで,ストーリーを楽しんでください.」と提示しているその手が,無理やり,プレイヤーに作り手の意図を押し付ける.確かに,すべてを受け入れて作品に纏め上げるのは不可能なのかもしれない.各キャラに固有のエピソードを盛り込まないとキャラを選択する意味自体が消失してしまうので,それらの要素をどのように他キャラを選択した場合に処理するかは当然,開発会議の議題に上ったはず.それが「他キャラを使用した場合,ストーリーの進展が何も起こらないのだから,何もなくても良い.」というのは如何なものだろうか.作り手(神様)の手の平の上で遊ばせてやっている,という風に取れて仕方がない.
ゲームのシステムにも問題がある.一言で言えば,こなれていないのだ.煩雑なシステムを作り上げたのはコンシューマー機のタイトルとして適切だったのか?武器(+防具,アイテム),技術両方を装備する,ということ自体は否定しないが,装備する技術が「陽術」の中の「エナジーチェーン」など,深い階層にあるため,選択するだけでもわかりにくい.さらに,複数のキャラを抱えるパーティーの中から,均等に脇役キャラを育てる必要もあるため,ゲーム中,システム・ウィンドウを開いている時間が長くなりがちである.さらに,本作の肝心かなめの「連携」攻撃に関してもその発生しやすい攻撃方法がわかりにくい.また,その覚えた「連携」をシステム・ウィンドウのリストの上の方に移動させないと発生しにくい,など...「連携」をマスターせずにはラス・ボスに絶対勝てない作りにするのなら,どうやってわかりやすくするか,工夫すべきだったのではないか?
ブルー編でのストーリーでも,ルージュを倒したところで,スタッフ・リストが流れるだけで,「実はブルーとルージュは2人で1人でした.」と突き放され,今度は地獄へ...ラス・ボスを倒してもエンドと表示されるだけ.ストーリーとしては練った構成になっているが,これは映画やマンガの世界では許されるストーリーであって,プレイヤーに時間と労力を要求するゲームというメディア(特に,RPGというジャンル)では,カタルシスが得られない.作り手が自分たちの考えた世界に酔ってしまっていなかったのか?
あまりにも傲慢な作りに辟易させられた.うんざりだ.(2000/12/24)
RPG スクウェア 1998 SLPS 01160-1 75時間
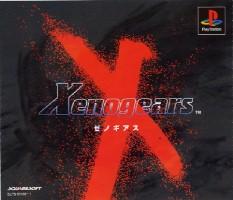 ©Square
©Square
高橋哲哉によるSci-Fi RPG.商品としてのターゲットとして明確に,アニメ・ファンでゲームの好きな人,もしくは,ゲーム・ファンでアニメの好きな人,つまり,アニメとゲームの交わる層と絞り込んでいる.こういったターゲットを明確に定めていることは,企業として重要であり,確実な収益を上げるためには,必要条件であるが,大抵のソフトは,人気声優起用であったり,アニメ・ファンにはわかる,ある種村社会的なお約束/楽屋落ち(あかほりさとる的,広井王子的なもの)に立脚しており,非常に閉じた世界観を構築しており,あくまでその場だけで消費されるものであることを自ら認めているような低レヴェルの作品が氾濫してるのが,アニメ/ゲームのクロスするあたりの作品群ではないか,というのが現状ではないか.その点,本作品は異なる.ここで展開されたのは,「既存のアニメ作品で表現されていた作品世界をゲームというフォーマットで提示する」,ということだった.つまり,通常30分26話で構築されるアニメをCD-ROM2枚のゲームとして提示することだった.
このスタイルは非常にチャレンジングな試みではあったが,それがゲーマーには受け入れにくいものとなってしまっていることは,事実である.アニメで頻繁に行われているような主人公にはどうしようもない状況(その段階では絶対に勝てない敵の出現(顔見せ),ストーリー上倒してはならない敵キャラ)をどうゲームで再現するか,この点の消化に問題を感じた.ゲームをプレイする場合は,ゲーマーは,さくさくと敵を倒してレヴェルを上げつつストーリーを進行していこう,としているのに,やたらと考える頭でっかちな主人公はゲーマーのやる気を殺ぐ形になってしまっている(特に武道会でのダンとのバトルなど).アニメなら主人公が苦悩するのは,ファンとキャラのシンクロを促し有効ではあるが,ゲームではこの点に問題点/シンクロ率低下をもたらしてしまっている.アニメ・ファンとアニメ,ゲーマーとゲーム,その両者のそれぞれの対象物に対する接し方の違いに関しての認識度の低さが,このようなゲーマーとキャラとの感覚の遊離を生んでしまっている.
一言で言えば,ゲームとしての完成度は極端に低い.問題点は以下に挙げるようなものがある.
1.やたらと多いエンカウント,これがゲームとしてのスピード感を完全に殺してしまっている.(ペルソナよりはましではある.)
2.わかりにくい3Dマップ.目的地がどっちなのかわかりにくい,エンカウント後,建物から出た後,イベント消化後等,事あるごとに,キャラの向いている方角が変えられてしまうため,いちいち方位を確認する面倒がある.
3.会話の処理の雑さ.ショップでアイテム購入時等,キャラ用のものを購入後,ギア用のものを購入しようとすれば,一旦,店での買い物トークを終了し,その後,再び,話しかけ,アイテム購入をしなくてはならないあたりは,制作者側の思考回路を覗いてみたくなるほどである.
2枚のディスクの内,大半を占めるCD-1で,上記の問題を感じる.CD-2では,若干,修正されている.CD-1とCD-2のプログラマーの能力の差が激しすぎる.はっきり言って,CD-1を製作した人達には,うんざりである.こんな奴等のソフトなんか2度と買いたくないものだ.はっきり言って,無能である.
しかし,CD-2自体にも問題点がある.それは,CD-2前半におけるただ,キャラによる回想シーンによる構成で戦闘だけを行うだけで進行してしまうあたりである.大風呂敷を広げたため,60-70時間で終了するゲームとしては,このあたりを駆け足で進まなくてはならなかった,というのは,わからないでもないが,逆に省けるエピソードも存在するわけ(奥行きのそれほどないリコというキャラは存在しなくても良かったような...)で,そのあたりの優先順位の付け方には疑問も残る.
ストーリー面では非常に特筆すべきものがあったように思われる.前述の通り,アニメをゲームで表現する,という通り,非常に重いテーマを扱っており,愛に飢えた人たちのそれぞれの愛の求め方,ここがメインであり,そこに人類創世などの大きなテーマを扱っており,CD-2に入ってから,CD-1で散々蓄積されたストレスを取り除いてくれる奥深さがあり,この点は高く評価できる.しかし,全体的に既存のアニメ作品をリミックスしたような印象を受ける.主たる作品としては「新世紀エヴァンゲリオン」が挙げられる.(作品を流れるテーマや,各種イベント,ゼーレの様な存在など.)また,「機動戦士Zガンダム」の世界観,「機動戦士ガンダム逆襲のシャア」からも「コロニー落とし」っぽいイベントなどもうかがい知れ,エレメンツのギアの合体シーン及び,合体後のギアは,「ゴライオン」,「ダルタニアス」の影響が,また,マリアのギアは,明らかに「巨神ゴーグ」だったり,と.挙げ始めるととどまるところを知らない.しかし,こう言った要素も制作者側の愛情が感じられるので,好感が持てる.「好きだからリミックスしている」のであって,「受けそうだからパ
クる」のではないのでこの点は賛否両論あるだろうが,個人的には,良の印象を抱いている.また,アニメ部もプロダクションIGも良い仕事をしていると言える.このあたりの作り込みは評価されてしかるべきだろう.
また,コマンド入力バトルは,新規のアイデアがすべてはずしている本作に置いて,唯一の成功した新しい要素ではなかっただろうか.
総論としては,長年アニメを愛して見てきたクリエイターが,愛のない3流プログラマーに足を引っ張られながら作った意欲作といった所だと感じた. (1998/02/28,1998/03/12一部改定)
ギャル コナミ 1995/1997 VX009-J2 (SLPM 86053) 10時間
 ©Konami
©Konami
ギャルゲーという1ジャンルをこれ1作で確立したとして歴史的作品として語られるこの作品をThe
Best再発版で評価してみる.高校に入学した主人公(プレイヤー)は,藤崎詩織から3年後の卒業式の日に告白されるのがゲームの目的として設定されている.この一見受動的にも思えるゲームのゴール設定だが,非常に画期的であった,と言える.基本は自分の行動(理系勉強,芸術,スポーツ,雑学など)を決めることで,各パラメーターを上げていき,理想の男性像に近づくように努力する育成シミュレーションである.画期的ではあるが,各キャラの性格付けが非常に平面的であることが問題である,例えば,プロレス好きな優美ちゃんには,スタジアムでプロレスがあればつれていくと好感度アップ,だとか,朝比奈さんには流行ものを押さえておけば良い,とか.斬新なゲームアイデアの上に構築される各キャラの平面さが,残念である.実際には,その日の気分だとか,その内容(プロレスだったりコンサートだったり)の如何で,いくらでも結果が変わるものなのに...そういった揺らぎがあっても良かったと思う.また,肝心の藤崎さんも最大公約数的な性格付けで,プレイヤーにどうしても藤崎ゴールという意識を持たせることが出来ていない.マニュアルやゲーム中で藤崎ゴ
ールだと言われるから藤崎ゴールを目指してプレイさせられているような印象がある.個人の趣味の入るものだから,誰をゴールに設定しても良いのではなかっただろうか.帰る時に「一緒に」っていう所を強調するあたりが,「ダメだわ.しらける.詩織.」なんて思わされて.かなり頭をあほにしてから楽しむゲームなのに...そこまであざといことをやられると,さすがに...ただ,このゲームがマニュアルとして機能するんだろうか.そんな行動をする新型マニュアル人間が出てくれば,それはそれでおもしろいような.
振り返ってみてゲーム中の3つの選択肢に対して,常に安全パイを選んでしまう自分がいることに気づいた.この手堅い選択肢を選ぶ考え方が,自分の現実生活と同じである,ということ.そのあたりの人に受け入れて欲しい自分,拒絶を恐れる自分が現れてしまっている,ここを痛切に感じさせられた.この現代の人と人の距離感,「拒絶を恐れる自分」,そのあたりがゲーム上で上手く表現されている.これは,ヴァーチャル・ラヴ/代用品ではなくて,もっと人間の本質を捉えた作品として高く評価されるべきではないだろうか.
続編では,平面的な描き方からの脱却をはかってもらいたいものだ.また,ターゲットの年齢層の高い同系統の作品があってもいいのではないか.総じて,良くできた作品だっただけに,今後の作品展開に期待したい.
(1998/03/13,1998/03/17一部改定)
鋼鉄のガールフレンド
ADV ガイナックス SLPS 01377〜8 2.5時間
 ©Gainax/project
Eva. TV Tokyo
©Gainax/project
Eva. TV Tokyo
90年代を代表するあの名作アニメのゲーム化.既発売のセガサターン版を完全移植.さすがにセガの名前ではリリースされず同作のアニメ製作会社(過去にサイレント・メビウス等のPCゲームを発売したこともある)ガイナックスからのリリースとなる.
ストーリーは原作のサイド・ストーリーとしての形態をとっており,霧島マナという転校生を軸にシンジになりきって,ストーリーを進行していくわけだが,これが,ゲームとして問題がありすぎる.というか,より厳密に言えば,「これをゲームと認めて良いのか?」---このようになる.アドヴェンチャーという形態をとっていることになるのだろうが,選択肢によってストーリーが変わることはなく,コマンドを総当たりする事で自然と進んでしまう,アドヴァンチャー・ゲームの欠点をそのまま具現化してしまっていること.その上,各場面において,3つの選択肢「見る」,「話す/考える」,「移動」の選択順序とそのリアクションに問題がある,つまり,制作側が自分の考える選択肢の選択順通りにプレイヤーが進めることを当然と考えてしまっていて,会話やキャラの反応(アスカが怒っている,なんていうコメントの後に,彼女を怒らせてしまうコマンドを選択するようなことがあったりして)が,前後してしまう,なんてことは度々.また,プレイヤーに選択をせまることがほとんどなく,ひたすら「見る」に徹するだけ.
このようなトンデモナイ内容のゲームだが,そこに流れるメッセージは,終盤,リョウジによって語られる言葉,ここに集約される.この事を言いたいがために,このゲームを製作したのか,というような内容である.ありきたりながらもあえてそれを,エヴァにはまって,なおかつゲームまで買ってしまうような人(LDも買ってるであろう,そういう人は.自分も含めて)に向けて,今もう一度提示しよう,っていうのは,あながち見当違いではないように思える.もう一度考えて欲しい人に向けて,テーマを提示すること,これには成功していると思う.
初めてつきあう事になった時のあの緊張感,うれしさ,etc...がごちゃごちゃになった頃を思い出させてくれる所などは,上手く再現されているものの,まったくかすりもしない「ときメモ」のパロディー等の遊び要素が機能していないところ,マナを探して夜の街を探索する所で,マップでのつながりがわかりにくい,等,先述の会話選択肢の不手際など,作り込みのなさが明かで,プレイしていて苦痛だったりするあたりは全体の評価を大きく下げてしまっている.これなら思い切ってゲームという形態を捨て,「見るだけ」にしてしまって,CD-ROMで提供されるエヴァの新作エピソードにした方が良かったのではないだろうか.
(1998/06/10)
インターナショナル
RPG スクウェア SLPS 01057〜60 45時間
 ©Square
©Square
名作RPG第7作.PSに移籍しての第1弾ということで,かなりの期待をもって市場に投入されたFF
VII.作品自体の評価が高かっただけに,細かいプレイ上での不便さ,等に不満の声が漏れていたが,本作(インター版)では,ルート表示アイコン(侵入可能な扉や出口等に表示される)が追加されることで,より快適に作品世界へと引き込むことに成功している.オリジナルからの変更点として,若干の追加イベントや新マテリアも存在するが,あくまでも基本は,オリジナルのままである.
さて,そのゲーム内容であるが,ゲームを終了させて感じたことは,「これは,通過点なのか,それとも到達点なのか.」ということだ.高々,20年程度の歴史しかないコンピューター・ゲームにおいて,これだけの感動を与えてくれるまでになるとは...ゲーム制作者の異常なまでの映画アレルギーがあるが,ここまでの作品を提示されると映画云々なんていうことで評価するのは,もはや意味をなさないのではないだろうか.ゲームはゲームとして,他のジャンルに対して全く卑下することなく,一つのジャンルとして評価されるべきであるし,また,現実にそうなっているように思える.CD-1ラストでのエアリスの他界するシーン,CD-2ラストでクラウド達,キャラ全員が「なんのために戦うのか.」,既存のRPGでは「そのゲーム中の世界に平和を取り戻すため.」といった大義名分のもとに進められていたが,今回は,「自分のために戦う.」というはっきりとした動機付けが成されており,非常にインパクトのある,ただプレイするだけではない,考えさせられ,感情移入出来るRPGとして,本作は高く評価されるべきである.かつて,ドラゴン・クエストの背中を追いか
ける形でスタートした本シリーズもいつのまにか,ドラクエを追い越し,時代をリードしていくシリーズへと成長することができたのは,ひとえにスタッフの努力以外に何もあり得ないが,歴代スタッフが明確に何を伝えるか,そこに主眼をおいて,製作してきたことで,いい子ちゃんなドラクエとは一線を隠すことが出来たのではないだろうか.既存の型にはまった大人達の求めるいい子ちゃんから,自分自身を見つめ,自分の頭で考え,そして答えを見つけるという,そういった価値観の上に立脚した名作である.
PS史上の名作.
(1998/03/28)
RPG スクウェア SLPS 01880〜3 47時間
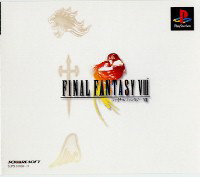 ©Square
©Square
偉大なる駄作.バランス感覚の欠如.PS最後の打ち上げ花火.そんな言葉が脳裏をかすめてならない.発売日の店頭の模様やバグの問題がニュースとして取り上げられるくらいの社会現象になった本作品だが,これはユーザーが求めていたものだったのだろうか?
PS版「ファイナルファンタジー」シリーズに求めるもの,とは一体どのようなものなのであろうか?
「その時代の最高峰のCGを見せてくれる作品」
「ドラゴン・クエスト・シリーズの持つ健全な思想を持った道徳的に正しい,とされるRPGに対するオルタナティヴ」
「2年に一度のお祭り」
人それぞれ自分の価値観を持って1999/02/11という日を迎えたことだと思う.シリーズを通してプレイしてきており,なお今もシリーズに対して熱い思いを抱いている人.途中であきらめが入るものの,技術的見地から見れば,素晴らしい以外の言葉の浮かばないCGワークに魅了される人.単に流行りモノは押さえておかないと,という人.さまざまなタイプの人を相手にして作品を制作しなくてはならなかったスクウェアの開発スタッフの苦悩は計り知れないものがあったであろうことは容易に察しがつくことである.
300万本というセールスを見込もうとすれば,継続的にゲームをプレイし続けてきているヘヴィー・ユーザーだけを相手にしていては到底達成出来る数字ではない.そこでグレイ・ゾーンであるライト・ユーザーの取り込み,これが欠かせない.そういう人たちにも伝わりやすいテーマの設定(これは「愛を感じて欲しい」という帯タタキにも入れるあたりからも,その狙いがあることは明か.).今のPSの表現能力を存分に引き出しての各キャラのヴィジュアル・デザインのモデルとしての実在のタレントの選び方(一部,リノアはホンモノが失速してしまったのではずした感が否めないが...).まさしく計算高い,ビジネスに長けた会社だと思わせる.
肝心のゲームだが,これは先ほども述べた通り,失敗作である.その問題点を挙げてみると以下のようなものがある.
1.ゲーム・システムの難解さ 折角新たに取り組んだ「ジャンクション・システム」が既存のRPGに慣れ親しんだプレイヤーや,ライト・ユーザーともに理解しにくいものとなってしまっている.魔法をドロー(敵から奪う)し,アクセサリーのように付けることが出来る,という斬新なアイデアながら敷居を上げてしまっている.このシステムを存分に運用しないとゲームのクリアが不可能となるだけに,チュートリアルだけではなく(そもそもチュートリアルという言葉自体を知らないであろう人が多数購入するであろう,ということが製作過程に思い浮かべることが出来なかったのだろうか...),取説などでも理解しやすい形で提示するくらいの配慮が必要ではなかったのか.
2.ムーヴィー垂れ流し このゲームでは,G.F.(ガーディアン・フォース,前作までの召還獣)を使って敵を倒すことが戦闘の基本となっている(敵キャラの強さの設定などが自キャラでの「たたかう」コマンドによる戦闘を拒絶している)が,召還するたびに,40〜50秒程度のムーヴィーを見せられることになる.ゲーム中,数百回におよびこれを見せられることになることは,いくら秀逸なムーヴィーでもうんざりさせられる.しかも,このムーヴィーの間は,プレイヤーは何もすることがないわけで,ゲーム世界から遊離させられてしまう.また折角のアクティヴ・タイム・バトルというシステム自体が破壊されてしまっている.オプションで,ムーヴィーのON/OFF設定くらいは用意しておくべきことではなかっただろうか.
3.稚拙なシナリオ 「愛を感じて欲しい.」というテーマ自体はゲームとして興味をそそられるものの,本編のヒロイン,リノアが愛を感じさせるような魅力がない.つまり,プレイヤーに「萌え」の気持ちを起こさせない.数を売ろうとするわけだから万人受けするキャラをヒロインに設定しようとしたところに問題があったのではないか.誰にでも納得するキャラ=誰もが中途半端に納得するキャラ.最大公約数を求めることになることはわかっていたはず.わざわざ宇宙にまで行って「ハグハグ」と言われれば,ゲンナリさせられてしまうことは否めない.ヒーロー,スコールが心を閉ざしたヒーローから3枚目で急に「リノア萌え」になるあたりの主人公の感情表現がされていないため,プレイヤーが納得してゲームを進めることが出来ない.操作可能なキャラがリノアを除いて全員同じ孤児院で育った過去があることをアーバイン以外が全員忘れている,という設定も,論理的に説明されていない.シナリオ・ライターのセンスを疑うような幼稚な内容である.
4.相変わらず見にくい3Dマップ スクウェア製RPGで以前から指摘されている課題である3Dマップでの移動可能場所がわかりにくい,ということが未だに改善されていない.入れる扉に矢印マークを表示する(FF
VII Internationalで導入したのに何故今回は廃止したのか.),あるいは,視点切替可能にするなどの配慮が必要である.問題点を解決する,という意識はないのだろうか.
あまりゲームをプレイしないライト・ユーザーも購入するソフトであるにも関わらず,このように問題の多い作品をリリースしてしまったスクウェアの責任は重大である.自宅にPSはあるものの数枚のソフトしか所有しておらず,話題作リリースだから,チェックしておこう,という気持ちで久しぶりにPSをプレイを始めたライト・ユーザーの中でどれくらいの人がラストまで辿りついたのであろうか?とっつきにくいあまり途中で投げ出してしまって,「ゲームなんてつまらない.単なる暇つぶしにしかならない.」などと判断されてしまっては,本作は売れたものの,今後そういった層を取りこんで大きなムーヴメントを起こすことは困難になってしまったのではないだろうか.その結果は次回作の数字で現れてくることと思う.
最後に,「ゲーム製作者の映画アレルギーの成果,ここに現れる.」という言葉を残したい.劇的な見せ方を練るあまり,ラストのアルティミシア戦の最後,一撃与える度にセリフを語るという,昔から映画で取られる手法の模倣であるが,RPGというゲームの性質上,既にそこまで辿りつくのに1時間以上の時間を費やして戦闘しているプレイヤーは,「早く倒れてくれ.一撃の逆転技を出されてはたまらない.」などの思考に支配されてしまっているのでセリフの重さを味わう余裕はない.そのためいくら伝えたいメッセージのあるセリフをしゃべらせようとしても,プレイヤーには響かない.また,もう一度そのような長時間の戦闘を行い,そのセリフを確認したい,という意識を持たせることの難しさも戦闘自体の長さを鑑みれば明かである.
「愛を感じて欲しい」という彼らから「ゲームに対する愛」が感じられなかった.
真性ゲーマーのアンセムであった本シリーズもライト・ユーザー志向によって,また今回も歴代のシリーズを楽しんできたファンの多くが離れてしまうことだろう.スクウェアは,もう一度彼らを呼び戻す秘策を隠し持っているのだろうか.
(1999/04/17)
RPG スクウェア SLPS 02000〜3 41時間
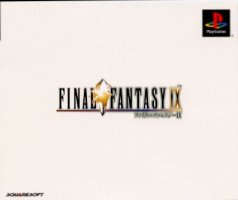 ©Square
©Square
Back To The BASIC!! 前作でコア・ゲーマーを失望させた本シリーズであるが,今作は,元来持っていた「ファンタジー」という言葉の意味をもう一度正面から見つめなおす,そんな作風で貫かれている.製作側のこの姿勢は,帯タタキに記された「クリスタル,再び.」,この言葉に込められている.
「ライト・ユーザー獲得」.これが本シリーズのような多額の制作費を投下し,世界規模での販売を必然的に求められる作品では,前提条件にある.また,「既に獲得したライト・ユーザーに次作も購入させる」という,さらに大きな課題も科されている本作は如何にして,これらの課題に取り組み,その成果を果たせたのか,今一度検証してみたい.
「ライト・ユーザー獲得」という課題に対して,前作(VIII)では,誰もが経験する「ティーン・エイジャーの恋愛」という一般的なテーマを軸にすることで,「ファンタジー」というと構えてしまう「ライト層」を取り込むことを目論んだ.これが結果的に,それまでシリーズを支えてきた「コア層」から失笑を買うことになった.
一方,本作では,前作製作チームの失敗を嘲笑うかのように(製作期間から鑑みて前作が不評を買う段階では,大枠は完成済みだったはずであるが...),ルーツへの回帰を唱え,オーソドックスなスタイルでユーザーの前に提示された.つまり,前作では,「ライト層」=「一般層」に対して歩み寄ることで彼らを取り込もうとしたのに対して,本作では,「コア層」向けのところに「ライト層」=「一般層」を引き込もうとしたと言える.
「コア層」に軸足を置いたことは,シリーズの勘所であった「クリスタル」を取り上げている点,そして作品中のムーヴィーでのキャラが村瀬修功氏(「新機動戦記ガンダムW」,「ガサラキ」)を迎えているあたりに,「わかってくれよ.」という送り手のメッセージが込められているように感じられる.
さて,どのようにして,「本作を購入したライト・ユーザーに次作も購入させる」気持ちにさせるか,だが,製作サイドの試みは,あまりにも王道な方法であった.つまり,「最後までプレイさせれば,感動が伝えられる」.そうすれば,絶対,次作も購入してくれるはず.そんな自信と誇りが感じられるスタンスで取り組んでいるのがゲームの中に感じられた.
それほどゲームをしない「ライト層」にどうやって最後までプレイさせるのか.この問に対しては,ゲームの難易度を下げることで対応した.つまり,ゲームとしては非常に「ぬるい」出来になっている.ゲーム中,常に「次,何をすれば良いのか.」が明示される.何かアイテムがあると思しき場所にはマーカーが表示される.セーヴできる個所が多い(小ボス戦の前には必ず用意されている).敵キャラが弱い(いつでもリジェネを使えば楽にラス・ボスが6分で倒せてしまうコマンド入力式RPGは今までなかったのではないか)...など,これだけ手取り足取りのフォローがあれば,いかにゲームをしないユーザーであろうと最後まで到達できるはずである.
このように敷居を低くした本作であるが,課題として以下のようなものがある.
1.調整のさじ加減に若干の疑問が残った.各キャラにアビリティーを覚えさせるために,ザコキャラと戦闘する機会が必然的に増えてしまうこととなったが,このエンカウントの多さがプレイ時間を冗長させてしまうことになっているのではないか(シリーズの旧作と比較すれば,短いのだけれど,ゲーム中心の生活を送らないライト層にはかなりの時間を占めることになっているはず).AP(アビリティー・ポイント)の調整が必要であったと思われる.
2.多数(8人)のキャラを上手く使いこなせていただろうか.ゲーム中では,戦闘で使えるキャラと使えないキャラがはっきりと別れてしまい,Disc-3の後半からジタン/スタイナー/エーコ/サラマンダーに固定されたままとなってしまった.場面場面でキャラを使い分ける,ということはなく,ストーリーの展開上強引に特定のキャラを固定されてしまう時以外は,「現状のメンバーで強いキャラ」を育てるだけであった.明らかなお荷物(ビビとダガー)の2人はストーリー展開上,大きな意味を持つが,その2人がゲーム中,プレイヤーによって育てられない,というのはキャラの能力バランスの設定ミスではないだろうか.
3.Disc-4のつくりにも疑問を感じさせられる.小ボスを1匹倒すごとにストーリーが説明される,というのは「ゼノギアス」で非難された点ではなかっただろうか.
4.ムーヴィーのクオリティーは本作でも上がったものの,現状到達したのは,人形劇(「プリンプリン物語」のよう)を思わせるものであった.どうも各キャラのパーツ自体が独立した印象を受け,それらがカクカクと動いているように感じられてしまう.(今までは,このレヴェルでの議論にならなかったので,技術的にここまで進歩してきたことを単純に賞賛すべきなのかもしれないが...)
Disc-4の展開には,往年の「少年ジャンプ」的な演出がされ,このあたりには,思わず「ニヤ」っとさせられるところがあり,ラストの30分に及ぶムーヴィーも定番でまとめられており,非常にオーソドックスであったように思われる.
前作の失望への回答としては,本作は手堅くまとめられている.ぬるく仕上がっているが,すべてを失うよりはマシなのではないか.本作でファンタジーを味わった「ライト層」が次作以降で何を求めてくるのか,非常に興味深い.
(2000/07/17)
ADV ヒューマン SLPS 91076〜7 9時間
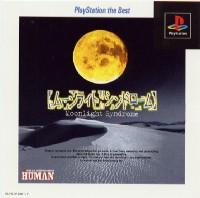 ©HUMAN
©HUMAN
人間不信に陥れられるゲーム.ゲームとして成立していないゲーム.プレイ中,度々感じさせられた正直な印象は,そのようなものだった.体裁としては,「トワイライト・シンドローム」の続編(登場人物も共通している.)となるのだが,前作との共通点は,キャラなどの設定のみ.今回は,プロローグ,エピローグを含めての全10話からなるオムニバス形式のインタラクティヴ・ムーヴィー志向のアドヴェンチャーである.このインタラクティヴ・ムーヴィー志向というのが癖もので,ゲームとして,遊ばせることを切り捨てている.つまり,製作者側としては,現代という時代を切り取って提示しよう,ということ,ここに主眼を置いて製作しており,プレイヤーは,ゲームとしては,当然あるべき謎解きの要素に頭を絞る,あるいは,選択肢総当りの義務的な処理を行うことはない.話を進めさせるために適度に手(指)を動かす程度,完全に傍観者にならずに適度に画面に意識をして見るためには必要な程度の作業を行うのみ.果たしてこれがゲームとして成立しているのか.
本作品の肌触りは,「serial experiments lain」と同じである.「serial
experiments lain」を見終わった後に感じる,自分とその周りの環境に対しての不安,恐怖,自分自身の存在の不確かさ,周りの人々と自分との関わり,人の感情の醜さ,重い空気,先行きの見えない不透明さと同時に自分の存在の脆さ,etc.....本作品での電波系のエピソード,「電破」などでは,このあたりの表現が,秀逸である.
確かに,マップがわかりにくいため,リルを探して団地内を移動するあたりは,フロア間を移動する階段が見えないため,勘で奥,手前,みたいなことをやらなくてはならない,というあたり,L1,L2,R1,R2などのボタンを使って,視点変更ができるなどの配慮があっても良かったのではないだろうか.雛代高校内を移動するときは,次に行くべき地点をマップで表示されるので,迷うことなくゲームの進行を行うことが出来,このあたりの作品の世界を堪能することに主眼を置いた作りは,正解なのだろうが,その配慮がもう少しあっても良かったように思われることが残念である.
作品を彩る要素として,「テクノ」があるが,この取り扱い方が,非常に上辺だけで,しっかりとした製作側の価値観のようなものが感じられず,現代を取り扱う要素として「テクノ」を取り上げているように感じられる.これは,製作側が,「今,旬だからって,テクノをチェックしてる奴等って,結構浅い,その場だけブームに乗っちゃえ」的上辺人間が多いことを暗喩しているとしたら,それはそれで凄いのだろうが...
また,主人公の女子高生ミカの軽薄さがプレイヤーとキャラとのシンクロ率の低下を招いている.途中で向こうへ行ってしまうし...「情報だけ」と本人が独白するようにそれだけの現代なのだろうか.彼女達への深い考察があるのだろうか?「現代の女子高生」と「」で括られてしまう人たち,詳細な考証(聞き込みによるキャラ作りなど)が行われたのか?どうもこのあたり納得できないようなところがないとは言えない.
このような些細なことをついているようだが,フィクションの世界で人を引き込もうとするのなら,その作り物の世界観で人をだませるぐらいの根拠(これは実際に正しい必要はない.それらしく思わせることができれば十分なレヴェル)が必要なのではないか.問いたいのはそこの部分だ.
最後に,本作品は,前述の通り,ゲームとしての文法を放棄した作りになっている.それでもあえてゲームとして本作品を提示したスタッフたちには,ゲームだからこそ伝えられることがあったはずである.それは,ゲームを楽しむ世代にこそ伝えたいメッセージの提示である.本来なら,このような作品は,活字媒体で提供されてしかるべき内容であると考えられる.しかし,その活字というメディア自体がその存在意義を問われるような時代に来ており,それでも今の「ポスト・Gen,
X」世代に伝えたいことがある,とすれば,ゲームという媒体を取る,これは誠に持って適切な選択であると思える.
(1998/12/21,1998/12/22一部改定)
RPG SCE SCPS 10039 45時間
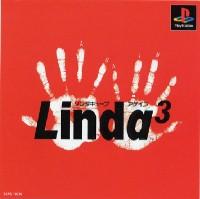 ©Sony
Computer Entertainment Inc. under license from Alfa System, MARS and NEC
Home Electronics, Ltd.
©Sony
Computer Entertainment Inc. under license from Alfa System, MARS and NEC
Home Electronics, Ltd.
「世界を救わないRPG」.これがこの作品を表現する上で一番わかりやすいものではないだろうか.作品の舞台となる植民惑星ネオケニアに隕石が飛来し,惑星自体が8年後に消滅してしまうため,それまでに惑星に住む動物を捕獲し,「ノアの箱舟」として他の惑星へと逃がして欲しいと,謎の知的生命体「アナビス」に依頼される.そこで主人公ケンとなり,ヒロインであるリンダと共に,この計画を遂行する,というのがこのゲームのプロットである.滅亡していく世界で,1種でも多くの動物を捕獲する,という限られた時間内で,コレクションしていく(と同時に捕獲した動物によって主人公たちは徐々にパワー・アップしていく)という遊ばせ方はなかなか秀逸なものだった.
捕獲には,動物を倒せば良いのだが,HPの2倍以上のダメージを与えると動物の肉体が飛び散り,死んでしまうため捕獲不能となるため,キャラがレヴェル・アップすると取りこぼしている弱い動物を捕獲するのが困難になるため,ゲーム全体をどのような順序で進めていくか,ということ,全体を見通した上でのゲーム進行が求められる.このあたり,繰り返し遊ばせるためのゲームの深み作りなのだが,これは残念ながら機能してないと言える.それは,マルチ・シナリオ構成となっており,「Merry
Xmas」,「Happy Child」,「Astro Ark」という3つのパラレル・ワールドを舞台にしたゲームを最初から遊べ,その後,シークレット・シナリオ「Last
Year」が遊べるようになっているのだが,パラレル・ワールドを舞台にした3つのエピソードを体験するため,繰り返しになってしまうルーチン・ワークと化してしまう作業にうんざりさせられてしまうためである.しかしそれを差し引いてもこのゲームは,すべてのシナリオを体験して欲しいと断言できる素晴らしい内容の作品である.それぞれのエピソードで語られる数々の悲劇,悲哀,憎悪の感情,そこにこそ表現される人間の悲しさ,はかなさ,どのエピソードも秀逸である.ケンの弟ネク(NEK)がリンダを我が物にしようとするあたり,妬みから来る人間の弱さ...etc...まじめな話,是非とも体験してほしい.下手をするとお使いゲームになってしまうRPGが多い中,本作は非常に骨太な内容でゲームとしてこのような表現を行えるというのは,ゲームも十分,一つの表現手段として確立されてきたものだ.そんなことを考えさせられた.
---余談だが,このゲームのオリジナルは,PCエンジンでリリースされていたこともあり,その筋の人御用達になっている.高山・リンダ・みなみには,萌えます.このゲームをしてる間だけは,「リンダーー!!」ってなります.すぐ覚めますけど.
(1998/12/19)
RPG SCE SCPS 10059 36時間
 ©Sony
Computer Entertainment Inc.
©Sony
Computer Entertainment Inc.
プロキオン製作のRPG.話題となったのは,+キーを用いたコマンド入力による戦闘方法だったわけだが,これが面倒くさいことこの上ないものだった.L1,L2キーにも決定,キャンセルが割り当てられているので,基本的には左手のみで入力できることになっているのだが,PSのコントローラーの形状のため,コントローラーの持ち方を考慮すると,左手だけでは,入力しづらく,結果的には,右手で決定,キャンセルを入力しなくてはならない,ということに気付かなかったのだろうか?入力方法だけならず,その入力回数の多さにも辟易させられるものだった.最後のボス・キャラとの戦闘に至るころには,各キャラに対して,9つのコマンドを入力,それを決定することから,12回のキー入力が必要となる.それが3人分あるわけで,うんざりさせられるものであった.対戦格闘ゲームの極めの爽快さをRPGでも味わえれば...という着眼点は悪くなかったが,その方法に詰めの甘さがあった.先にリリースされていた「ゼノギアス」での右手入力によるコマンド・バトルの方が適切だったと言える。なぜ,後からリリースされた本作品の方が出来が悪いのだろうか.
ストーリーとしては,<獣>という妖精を身につけることで各種魔法が使えるようになる時代,その<獣>を悪用する人間に対して,<聖獣>を身につけた主人公達が戦いを挑む,という設定になっており,作品に込められたメッセージは以下に示すような2つのものであった.<獣>自体の存在が悪ではなく,それを誤った使い方をする人間が悪い,ということ,つまり,科学と人間の接し方と同じようなこと,そして,過去にどのようなつらいことがあろうともそれを乗り越えて先に進んで行こうとする意志の大切さ,だった.
ゲーム自体としては,ぬるい.おこちゃま向きな,そんな甘いゲームだった.弱い敵キャラ,1本道なマップ,お使いだけで片付いてしまうフラグ立て,どんな人であろうとも必ず最後まで到達することが出きる敷居の低さ,それもまたゲーム・ファンの裾野を広げる上では重要な方向性の一つであることは否定しない.しかし,それならちゃんとパッケージにおこちゃま向け,と.対象年齢表示をつけるなどの配慮が合っても良いのではないだろうか.大きなお友達系ゲーマーが萌えられるキャラとして,ノアは十分だったのか?ろくにしゃべれない,知能の低いキャラ(彼女にいろいろと子供じみた質問をさせることで若年層のプレイヤーにも理解できるように助け舟を出す役割もわからないではないが...),戦闘終了時に,3人のキャラがしゃべるわけだが,これが,製作者側の神経を疑うような内容.ばかげたセリフをしゃべる3人に,それをしゃべる声優陣も中尾隆盛氏の出来損ないのような主人公,専門学校を出てきたところのようなロリ系だったりと...明かにゲーマーの嗜好が読めてないものだった.
途中で,それまでの経歴を振り返るところで,ムーヴィーを使って振り返れば,それまでの流れを上手く表現できるはずのところをテキストだけで紹介するにとどめてしまう一方(CD-ROM1枚にするためには割愛されてしまったのかもしれないが.),終盤では,長距離をわざわざそれまでのストーリーを思い返させることを狙って,歩かされる始末.このあたりのところはサクッと飛ばしてもらった方が良いのだが...しかもここでの会話が以前のまま,作品中の世界が変わった後なのに,そこがしっかりとフォローされてないあたりが惜しい.また,マップでの移動速度が絶望的に遅い,システム・ウィンドウを開くのに要する時間が遅いなど,ユーザーには,かなりのストレスをためる内容である.
丁寧に作られているのだが,作品の持つテーマもありがちなもので,新鮮味もなく,ただただこなして行くのみ,作品をプレイし終えて何かが残ったのか.スタッフ陣の努力の跡は感じられるのだが,彼らを纏め上げるべきなのに,ゲーム・ファンをなめているのか,というぐらいマーケットの考察不足のプロデューサー,うわべだけをなぞっただけでオリジナリティーのかけらも見られないシナリオライターといった中心で引っ張って行くべき人の技量のなさ,それが一番の問題だった.
(1998/12/13)
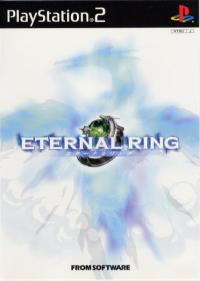 ©From Software
©From Software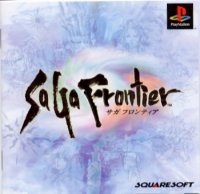 ©Square
©Square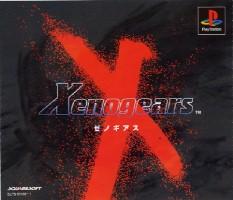 ©Square
©Square ©Konami
©Konami ©Gainax/project
Eva. TV Tokyo
©Gainax/project
Eva. TV Tokyo ©Square
©Square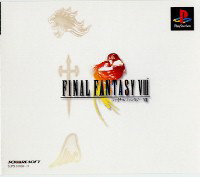 ©Square
©Square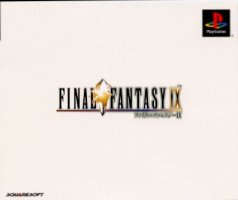 ©Square
©Square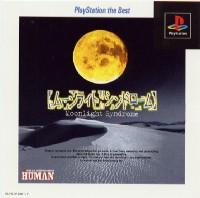 ©HUMAN
©HUMAN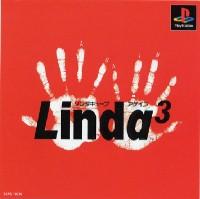 ©Sony
Computer Entertainment Inc. under license from Alfa System, MARS and NEC
Home Electronics, Ltd.
©Sony
Computer Entertainment Inc. under license from Alfa System, MARS and NEC
Home Electronics, Ltd. ©Sony
Computer Entertainment Inc.
©Sony
Computer Entertainment Inc.