水車見学番目の方です

水車の話し
さて、当ホームページの題名と成った水車小屋の水車についてちょっと説明したいと思います。
何故かって言うと水車を探してくる方が多いものでサービスてか
歴史
水力の利用は、風力に続き古く、水車の発明は紀元1世紀と言われていて
初め穀物の製粉に使われていた物が11世紀頃には、揚水・かんがい等に使われ初め、
18世紀には家内制手工業から工場制手工業に移った工業の工場動力として水車が利用されだし
やがて、19世紀おわりには発電に水車が用いられるようになりました。
水の力
水の持つ力とはなんでしょう?単に単にコップに水を入れて置いておくだけでは、なんの力も保有していない様に
見えますが、コップの底に水の重量(水圧)が係りますこれを圧力水頭と言います。
また、水の入ったコップを持ち上げると水には高さによるエネルギーを持ちますこれを位置水頭といいます。
流れている水は、速度エネルギーを持っていますこれを速度水頭と言います。
これらのエネルギーは時によっては、鉄砲水、土石流などに加わり凄まじい破壊力を生みます。
水車の力
水の力はどの様にして水車に働くのでしょう
上水槽に供給された水は水圧鉄管を通り水車に供給され放水路から川へ返されます、
この時上水槽の位置水頭のエネルギーを回転に変えます。
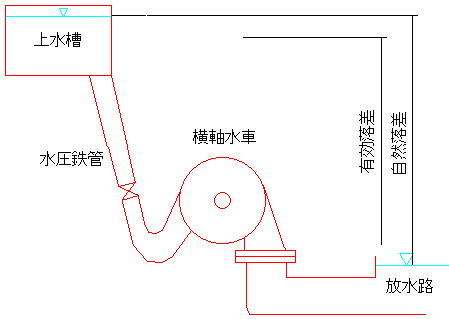
上水槽の水面と放水路の水面の差を自然落差と言い、実際の水車に掛かる位置エネルギーは、管路抵抗・水の粘度
などによりエネルギー損失がある為、実際に使用出来る部分を有効落差と呼びます
水車に掛かる位置水頭のエネルギーを回転に変えるまでの仕組みは、
位置エネルギーを速度エネルギーに変換し回転させる・・衝動水車>ペルトン水車
位置エネルギーを速度と圧力エネルギーに変換し回転させる・・反動水車>フランシス水車・プロペラ水車
などが在ります。
ペルトン水車
ペルトン水車は、19世紀後半にアメリカのペルトンが考案した水車です。
特徴として、流量が変化しても効率が安定していて使用しやすい効率は、86〜91%です
ペルトン水車は位置エネルギーをジェットノズルを使って速度エネルギーに変換し、バケットと呼ばれる
水車の羽根に水をぶつけて回転させます。
 バケットとディスク
バケットとディスク
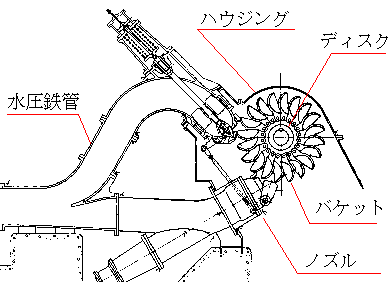 構造図
構造図
フランシス水車
フランシス水車は、19世紀フランスのフルネイロンが原型を製作し、その後改良されて
19世紀中ごろにアメリカのフランシスによって完成されました。
フルネイロン:1832年に50PSのフルネイロン水車を完成した。
特徴フランシス水車は、使用水量が少ない段階では効率の変化が大きく、落差やその他の条件で
異なりますが効率は、84〜94%です。
管路を流れてきた水は渦巻き状のケーシングからランナー(羽根車)に全周方向から
主軸に向かって直角に流入します。この時水は、圧力と速度エネルギーを持っていて
ステーベン(ささえ羽根)から狭い案内羽根を通過しランナーに入り回転運動に変換
されます。
 横軸フランシス水車
横軸フランシス水車
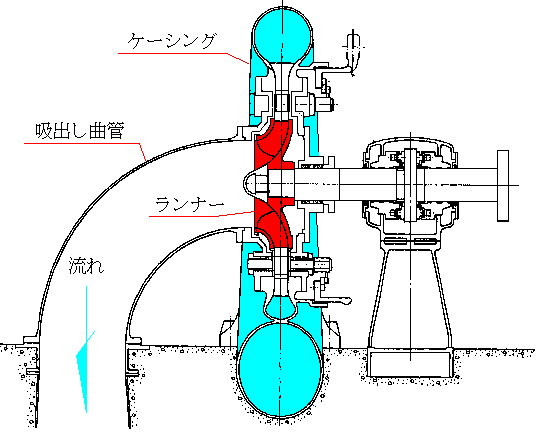
 縦軸フランシス型ポンプ水車ランナー
縦軸フランシス型ポンプ水車ランナー
日本最大30万キロワット
東京電力高瀬川発電所
黒塗りの人間が170Cmです
これらが代表的水車です。
このタイプで軸方向によって縦軸タイプと横軸タイプに分かれますが構造的には一緒で
縦軸はケーシングを地下に埋めてある事が多いです。
また、現代では揚水発電が盛んになってきました。
昼間電力需要が多い時に発電して夜間、火力や原子力で発電されあまった余剰電力によって、
水車を逆回転し下のダムから上のダムへ、くみ上げるポンプ式です。
もっと知りたいとか現物を見たいという方は、
東京電力さん梓川電力所のテプコ電力館に出かけられたらどうでしょうか?
上高地の帰りにでも一寸よって行くのも良いと思います。
更に西赤尾にある上平村の電力館とか
電源開発さんの御母衣ダム電力館なんて
飛越合掌ラインの途中にあって寄りやすいのではないでしょうか
白川郷や五箇山を楽しみながら一寸ドライブイン代わりに寄れる場所です。

|

|
|
御母衣電力館 荘川桜の移植をシアターで上映しています |
御母衣発電所のランナー |
関西電力