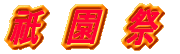
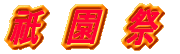
祇園祭は京都・八坂神社の祭りで、京都三大祭り(他は上賀茂神社・下鴨神社の葵祭、平安神宮の時代祭)、
さらには大阪の天神祭、東京の山王祭(あるいは神田祭)と並んで日本三大祭りの一つに数えられています。
また、飛彈の高山祭、秩父の夜祭りと並んで日本三大美祭及び日本三大曳き山の一つにも数えられます。
毎年7月1日から31日までの1カ月間、京都市内の中心部や八坂神社(東山区)で行われる長い祭りですが、
神輿渡御や山鉾巡行や宵山が中心となっています。
クライマックスとなる山鉾巡行と神幸祭(いずれも17日)をはじめ、多彩な祭事が絢爛豪華に繰り広げられます。
また宵山、宵々山には旧家や老舗での宝物の展示も行われるため屏風祭の異名があったり、
山鉾巡行では文化財が公道を巡るため動く美術館とも例えられます。
宵山・山鉾巡行
山鉾巡行は元々付け祭りだったようですが、現在ではこちらの方がはるかに大規模になり、祇園祭のハイライトです。
山鉾からは祇園囃子のコンチキチンという独特の節回しが聞かれますが、現在のような囃子ができたのは江戸時代からだそうです。
ゴブラン織りをはじめとする豪奢な山鉾の飾りも見どころの一つです。
また、山鉾には日本には存在しないエジプトのピラミッドやラクダなどが描かれたものが存在します。
かつては山鉾巡行自体が17日(前祭・さきのまつり)と24日(後祭・あとのまつり)の2度行われていたようですが、
1966年(昭和41年)より17日に統合されました。
山鉾の数は現在は32基(鉾9基・前祭の山14基・後祭の山9基)で、これも時代によって変化しているそうです。
山鉾は午前9時に四条烏丸を出発、午前中にコースを回り、巡行終了後は直ちに解体・収納されます。
このアルバムでは、山鉾のすべてを写真に取れませんでしたが、その一部をご覧ください。
| 長 刀 鉾 (なぎなたぼこ) |
俗に「籤取らずの長刀鉾」という通り、この鉾は17日の巡行に毎年先頭を承って、長刀を竿頭高くかざして 疾病邪悪を攘いながら厳然と進みますが、刀先は決して御所と八坂神社の方には向かないように注意しています。 現在はこの長刀は宝物として保存されており、鉾頭には軽い竹製に錫箔を張ったものが使われています。 またこの鉾にのみ五位の位を授かった稚児が正面に乗って巡行しています。 |
 |
 |
| 蟷 螂 山 (とうろうやま) |
「かまきり山」とも呼ばれ、かまきりと御所車の車輪が動くなど山鉾として唯一のからくりがほどこされています。 昭和56年、明治以降中絶していたものを100年ぶりに再興し巡行に加わっています。 |
 |
| 孟 宗 山 (もうそうやま) |
筍山とも呼ばれ、病身の母親を養う孟宗が、雪の中で母の欲しがる筍を掘り当てた姿をあらわしています。 見送りは、竹内栖鳳筆の白地墨画孟宗竹図です。 |
 |
| 函 谷 鉾 (かんこぼこ) |
鉾の名前は中国戦国時代斉の孟嘗君が家来の鶏の鳴き声によって函谷関を開けさせ脱出できたという故事によります。 前懸は旧約聖書創世記の場面を描いた十六世紀の毛綴で重要文化財に指定されています |
 |
| 綾 傘 鉾 (あやがさぼこ) |
山鉾の非常に古い形態を残している傘鉾の一つで、大きな傘と棒ふりばやしの行列です。 棒ふりばやしは赤熊をかぶり、棒を持った者が鉦、太鼓、笛に合わせて踊ります。 現在2基あり、傘につける垂り(さがり)は人間国宝の染織家森口華弘氏の友禅「四季の花」と 平成4年に町在有志の寄贈になる綴れ織「飛天の図」がある。 |
 |
 |
 |
| 伯 牙 山 (はくがやま) |
中国の周の時代、琴の名人伯牙が友人鐘子期の死を聞いて、その琴の弦を断ったという故事からきています。 前懸は慶寿裂の逸品です。 |
 |
| 鶏 鉾 (にわとりぼこ) |
中国発の時代に天下がよく治まり訴訟用の太鼓も用がなくなり鶏が巣を作ったという故事によるものです。 見送りはトロイの王子と妻子の別れを描いた十六世紀ベルギー製作の毛綴で重要文化財に指定されています。 |
 |
 |
| 菊 水 鉾 (きくすいぼこ) |
町内にあった菊水井戸にちなんで名付けられ、鉾頭には金色の菊花をつけます。 昭和27年88年ぶりに再興され、以来年々装飾が充実し、昭和の鉾としての偉容を示してきています。 |
 |
| 四条傘鉾 (しじょうかさぼこ) |
傘鉾の一つで、明治4年以降途絶えていたものを、昭和60年に町内の人々の努力が実り傘鉾の本体が再興され、 |
 |
| 霰 天 神 山 (あられてんじんやま) |
京都に大火があったとき、霰が降り猛火は消え、そのとき天神さまが降ってきたのでそれを祀ったのが起こりです。 山の上には欄縁に沿って朱塗り極彩色の廻廊をめぐらし、中央に唐破風春日造の神殿を安置してあります。 |
 |
| 月 鉾 (つきぼこ) |
鉾頭に新月をつけ、「天王座」には月読尊を祀っています。 |
 |
| 白 楽 天 山 (はくらくてんやま) |
唐の詩人白楽天が、道林禅師に仏法の大意を問うところです。 前懸はトロイ城陥落を描いた十六世紀の毛綴です。 |
 |
| 放 下 鉾 (ほうかぼこ) |
鉾の名前は「天王座」に放下僧を祀るのに由来しています。鉾頭は、日、月、星三光が下界を照らす形をしている。 新下水引は、華厳宗祖師絵伝を下絵にした綴織。 かっては長刀鉾と同様「人間の稚児さん」が乗っていましたが、昭和4年以降稚児人形にかえられています。 この人形は皇族より三光丸と命名され、巡行の折には稚児と同様、鉾の上で稚児舞いができるように作られています。 |
 |
 |
| 岩 戸 山 (いわとやま) |
天照大神の岩戸隠れの神話に由来しています。 天照大神、手力雄尊など三体のご神体を祀り、伊弊諾尊は屋根上に安置しています。 |
 |
| 船 鉾 (ふねぼこ) |
神功皇后の説話によって鉾全体を船の形にしています。舳先には金色の鷁、船尾には飛龍文の舵をつけています。 巡行のとき鉾の上には神功皇后と三神像を祀ります。 皇后の神像は岩田帯をたくさん巻いて巡行するが、それを祭りの後、妊婦に授与され安産のお守りとされるそうです。 |
 |
 |
あ と の 巡 行
祇園祭は1966年(昭和41年)まで「前祭」(7月17日)と「後祭」(7月24日)の2回に分けて山鉾巡行を行っていた経緯があり、
「前祭」では山に加え豪華絢爛な鉾が多数巡行するのに対し、
「後祭」では鉾の巡行が無く山のみの巡行で、小規模であることから
この諺(あとの祭り)が言われるようになったという説もあるそうです。
| 橋 弁 慶 山 (はしべんけいやま) |
弁慶と牛若丸が五条大橋で戦う姿をあらわしています。 これらの人形には永禄六年の古い銘があり貴重です。 |
 |
辻 回 し
見所の一つは辻回しと呼ばれる鉾の交差点での方向転換です。
鉾の車輪は構造上方向転換が無理なため路面に青竹を敷き水をかけ滑らして向きを90度変えます。
 |
 |
 |