 |
�@�@���@���@���@���@�́@�g�@�t |
 |
 |
 |
 |
���@�t�@��
���s�s�̐��k�[�A���s�s�k����t�����ɁA���̎��͂���܂��B�������͖k�R�������i�낭���j�B
1994�N�i����6�N�j�ɌÓs���s�̕������Ƃ��Đ��E��Y�ɓo�^���ꂽ�B
���S�ƂȂ錚�z���ł���ɗ��a���u���t�v�A���@�S�̂��u���t���v�ƒʏ̂���܂��B
��t�i���Ǝ��ω��a�j�A��_�t�i���{�莛�j�ƕ����āw���̎O�t�x�ƌĂ�Ă��܂��B
 |
�@�@���@���@���@���@�́@�g�@�t |
 |
 |
 |
 |
 |
�[�����i�������Ă��j ���X�@�a�D�݂Ɠ`�����钃���B ���芝���A�O���~�̐Ȃɏ���Ɠy�Ԃ���Ȃ�剮�ɁA�؍ȑ���`���œ���~�̖P���O�ƌĂ���i�̊Ԃ��A�Ȃ��Ă���B �������N�ɏĎ��������߁A���݂̌�����1874�N�i����7�N�j�ɍČ����ꂽ���́B 1997�N�i����9�N�j�ɂ���̏C�����s���Ă���B �Ȃ��O���~�̏����͒��ȂƂ��Ă͒�������V�̖��p�����Ă���A��ɂ悭�m���Ă���B�i�����̎ʐ^�j |
|
 |
 |
 |
���@���@��
�Β�ŗL���ȗ������B�P�S�T�O�N���̊Ǘ̐E�א쏟�����n���������̂ł����A���m�̗��ŏĎ��B
���̌�P�S�X�X�N�ɍČ�����A�Β�����̎��ɍ��ꂽ�Ƃ����Ă��܂��B
�킸���V�T�̔����̋�Ԃɑ召�P�T�̐�z�u���������́A�ɒ[�ɒ��ۉ����ꂽ���̒납�牽�������邩�́A
���������ӏ܂�����̂̎��R�ȉ��߂ƘA�z�ɂ䂾�˂��Ă��܂��B
 |
�������獶�E�߂��ʐ^ |  |
 |
 |
 |
 |
�@�@����ȑۂ̒������܂��B | |
���{�̉����k�A���v�X���т��x�R�s�ƒ���咬�s��8�̌�ʋ@�ւɂ���Č���90km�ɋy�ԎR�x�ό����[�g�ł��B
�����_���̔��͂⎺�����E��Ƀ����E�������ł̎U��ȂǂŊ�������厩�R�̒��ɑ��Â����A���A�k�A���v�X�̒��]�Ȃnj�������������܂��B
�t�̎c��A���Ă̐V�ƉԁA�Ă̗����̎p�A�H�̍g�t�ȂNjG�߂��Ƃɗl�X�Ȋ���y���߂�B����͍g�t�����̊ό��ƂȂ�܂����B
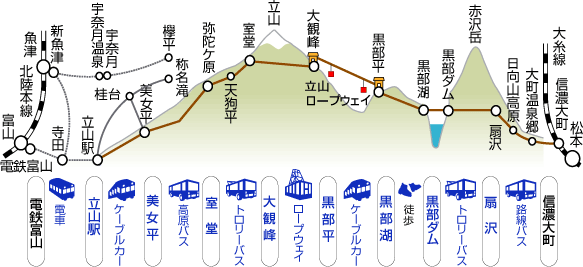
�P���ڂ́A�����ԂŐ��܂ōs���A��������A���y�����[�g�ŗ��R���z���A��Ƀ����܂Œ��s���A��Ƀ����z�e���ɏh���B
�Q���ڂ́A�����A��ϕ�A�������A�����_�������ό����Ȃ���߂��Ă��܂����B
��@�Ɂ@���@��
���R�̐��[�ɍL����n���n�̍��w�����B1����2���Ԃ̗V���������ɂ́A�召3000���̒r�����_�݁A���^�X�Q�Ȃǂ̌Q�����݂��܂��B
�o�X�₩��500m�̒n�_�ɁA���Ό��ƃJ���f������]����A���R�J���f���W�]�䂪����܂��B
 |
 |
 |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̓W�]�䂩��̉_�C |  |
 |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�h�������z�e�� |  |
 |
�����E������
�����i�ނ�ǂ��j����ю������i�ނ�ǂ�������j�́A��5���N�O�̗��R�̕��ɂ���Č`�����ꂽ�n���n�ł��B
 |
 |
| �S�������S�I�ɑI�ꂽ���̗��R�ʓa�̗N���́A�g�����[�o�X���ʂ闧�R�g���l�����̔j�ӑт��瓱�����Ă��邻���ł��B |  |
�����w�t�߂ɂ���~�N���K�r��~�h���K�r�͗��R�̉Ό��ł���A�n���J�ł́A���݂ł��ΎR���K�X�������o���Ă���l�q�����邱�Ƃ��ł���B
 |
 |
 |
 |
 |
 |
��@�ρ@��
��������g�����[�o�X��10���A���R���[�v�E�F�C�̏㑤�̉w�ł����ϕ�͕W��2316m�̂Ƃ���ɂ���܂��B
�w����~��Ă����̓W�]�䂩��̒��߂͂��炵���̂ŁA�f�ʂ�͐�\���ł��I
 |
 |
 |
 |
 |
 |
���@���@��
��ϕ�ƍ����_���̓r���Ɉʒu���鍕�����͕W��1,828m�B
���ɗ��R�A��ƃ��[�v�E�F�C�A���Ɍ㗧�R�A��ƍ����_�����L���钭�]���y���߂܂��B
�P�[�u���J�[�̉w�Ƃ��Ắi�S�̃��[���ő���S���̉w�Ƃ��Ă��j���{��W���������ꏊ�ɂ���w�ŁA
���R�g���l���o�X�̃g�����[�o�X���ɂ�莺���w���S���w�ƂȂ�܂ł͓��{�ꍂ���ꏊ�ɂ���S���w�ł����B
���R�����A���y�����[�g�̓r���Ɉʒu���A�������뉀�ƌĂ��D�ꂽ�i�ς��������뉀�̒��ɉw���u����Ă���B
 |
 |
 |
| ���[�v�E�F�C�̏㑤�̉w�A��ϕ�̉w�������܂��B �l�p�����̂悤�Ȃ��̂������ł��B �E�̎ʐ^�͍����_���̗l�q�ł����A�����Ԃɉ���Ă����̂��킩��܂��ˁB |
 |
 |
���@���@�_�@��
���R�����A���y�����[�g�ό��̏I���_�i���쑤����X�^�[�g����Əo���_�j�ɂ����鍕���_���B
1956�N���݂��J�n����A1963�N�Ɋ����B�����_���͐��̈��͂𗼊݂̎R�Ŏ�A�[�`���̃_���ŁA�����͓��{���186m�B
���b10�`15�g�����̕����́A���Ԍ���ł݂邱�Ƃ��ł��܂��B
| �����g���l���� �_���ł̍g�t |
 |
 |
 |
| �_������̕��� |  |
 |
 |
| �������A�����k�J�̗l�q |  |
 |
 |
�ɍ����i���˂��傤�j
�ɍ����́A���s�{�ɂ��钬�ł��B
���{�C��]�ޒO�㔼���̖k�����Ɉʒu���A�M���Œm���Ă��܂��i�d�v�`���I�������Q�ۑ��n��I��j�B
�C�ӂ��肬��Ɍ������ԏM���́A�P�K���M�̊i�[�ɂ̑��ɁA����Ȃǂ̕��u��Ƃ��Ďg���Ă���A�Q�K�͏Z���ƂȂ����@�\�I�Ȍ����B
�����P�V�N�ɂ́A�����ł͑S�����ƂȂ鍑�́u�d�v�`���I�������Q�ۑ��n��v�ɑI�肳��Ă��܂��B
 |
 |
 |
 |
�V�����i���܂̂͂����āj
�V�����́A���s�{�{�Îs�̋{�Øp�ɂ���i���n�ł��B
�]�ˎ��ォ�珼���i���݂̋{�錧�j�A�{���i���݂̍L�����j�ƂƂ��ɓ��{�O�i�̈�ɐ������Ă��܂��B
�V�����́A��7,000�{�̏��т���������3.2km�i��V���A���V���j�A��20����t����170m�قǂ̍��{�i�����j�ł���i�n�w��ł͍��B�j�B
�{�Øp�����A���h�C������Ă���B
 |
 |
 |
|
���h�C����́A����،˂ƕ��쐅�H�ɂ���āA�{�Øp�ւȂ����Ă��܂��B |
 |
 |
| �q�����E�R�� ���{�O����̂ЂƂŁA�q�b�������镶�ꂳ��Ƃ��ėL���ł��B �����ʂ�ɖʂ���R��́A�����t�Ƃ��Ă��s�̎w�蕶�����ŁA�O��n���ő�̎R��ł��B
|
 |
�V�����������낷�����R�ɂ��鐼��28�ԎD���̐������B
�����ɂ́A�߂������`�������铳�����̏���A���r�ܘY�̐^�����̗��A���{��̃p�m���}�W�]��Ȃǂ�����܂��B
 |
 |
 |
�����R�̔��Α��A�삩�猩���V�����ł��B
 |
 |
 |
�u�҂̂�����v�̏�ɏ���āA���Ε����������āA�҂̊Ԃ���V�������݂�Ƃ������@�ŎB��܂����B ���̕��i�́A�u�V�ɉ˂��鋴�v�A�u�V�ɏ��间�v�ȂǂƌĂ�Ă��܂��B |
 |
�a�̎R�E�F��{�{��Ё��F��Ó����ߒq���
�F��O�R�i���܂̂���j�́A�F��{�{��ЁA�F�쑬�ʑ�ЁA�F��ߒq��Ђ̎O�̐_�Ђ̑��́B
2004�N�ɁA�u�I�ɎR�n�̗��ƎQ�w���v�Ƃ��āA����R�ȂǂƂƂ��Ƀ��l�X�R�̐��E��Y�i������Y�j�ɓo�^����܂����B
�F��{�{���
�Â��́u�F�썿�i���܂̂ɂ܂��j�_�Ёv�Ƃ������ŌĂ�Ă��܂����B
�F��O�R�̒��S�ŁA�S����3000�Јȏ゠��F��_�Ђ̑��{�{�ł��B�Гa�����̏d�v�������ɂȂ��Ă��܂��B
�ƒÔ���q��_�i�f���j��_�j����Ր_�Ƃ��A�����ɏ��A�J�^�����A�O�Џ����A���a���ЁA��ʈ��S�A�務�����A
���ɐS�萬�A�ɂ����v�����邻���ł��B�܂��A�u�F��Ó��v�������A�R���̕�炵�ɂӂ���L���ȕ��͋C���y���߂܂��B
 |
 |
 |
| �P�T�W�i�̐Βi | ���@�� | �_�@�� |
 |
 |
| �{�@�@�a | |
���݂͎Гa�͎R�̏�ɂ���܂����A1889�N�i����22�N�j�̑�^���ŗ������܂ŁA�F���̒��F�ɂ���܂����B
�n���ȗ����̒��B�ɂ������Ǝv���A�����̍^�����N����܂ł͎Гa��������鎖�ԂȂǂɂ͂Ȃ�Ȃ������悤�ł����A
�����Ȍ�A�R�т̔��̂��}���ɍs�Ȃ�ꂽ���߁A�R�т̕ې��͂������Ȃ��K�͂ȍ^���������N�����A�����ꂽ�����ł��B
���݁A���Вn�̒��B�́u����v�i������̂͂�j�ƌĂ�A�咹���������Ă��܂��B
�Ȃ��A���̎��̑�^���Ŕ�Ђ����㗬�̏\�Ð쑺�̈ꕔ�̏W���̐l�X���A�����̂ĂĈڏZ�����悪�k�C���̐V�\�Ð쑺�������ł��B
| �F��{�{��Ђ����Ƃ��Ƃ������ꏊ�B����i������̂͂�j ���Вn�߂��ɓ��{��̑咹���i����33.9m�A��42m�j�����Ă��܂����B ���̑咹���̏㕔�Ɂu���@�G(�₽���炷�j�v������܂����B�i���E�����̎ʐ^�j ���@�G�͌F�쌠���̎g���������ŁA�O�{���̉G�ł��B ���{�T�b�J�[����̃V���{���}�[�N�ł�����݂ł��ˁB ���������ȍ~�A�F��{�{�͈���ɔ@���̐�����y�ƌ��Ȃ���Ă��܂����B�u�F���K�v�̎���A�����āu�a�̌F��w�v�̎���A�F��̒��S�n�͂�������������̂ł��B |
 |
 |
 |
 |
�F���
����i���������j�́A�a�̎R���̓ߒq���Y���ɂ���⓹�ŁA�F��ߒq��Ђւ̎Q���A�����ČF��Ó��E���ӘH�̈ꕔ�ł��B
���č�̓����ɑ�傪����A�ʍs�ł����Ă������Ƃ����̗̂R���������ł��B
�⓹�̗����ɂ܂�Ŗ和�̂悤�ɂ��т���v�w����������A��\�㉤�q�Ō�̈�ЁE���x�C���q�����ڂɁA
����S�N�̐[�����ؗ��̒��ɐΏ�̓������ǂ��čs���ƁA�����肫�����Ƃ���ɁA
�ݓn���ƌF��ߒq��Ђ�����A�ߒq��ւ������̈ʒu�ɂ���܂��B
 |
 |
 |
 |
 |
�F��ߒq���
�ߒq��i�Ȃ��̂����j�́A�a�̎R���ߒq���Y���̓ߒq��ɂ������ŁA�،���A�ܓc�̑�Ƌ��ɓ��{�O���e�ɐ������Ă��܂��B
�ߒq�̑�́u��̑�v�ŁA���̏㗬�̑�ƍ��킹�ēߒq�l�\���ꂪ����A�F��C���̏C�s�n�ƂȂ��Ă��܂��B
�F��O�R�̑���2�Ёi�F��{�{��ЁA�F�쑬�ʑ�Ёj�ł́A�����̐_�������߂ɂ�蕧�����p���ꂽ���A
�ߒq�ł͊ω������c����A�₪�Đݓn���Ƃ��ĕ������A���ݐݓn���͐�����ԎD���ł��B
 |
 |
 |
 |
�ߒq�R��т́A��ɑ��鎩�R�M�̐��n�ł���A��̑�͌��݂ł����_�Ђ̌�_�̂ł����āA
���_�Ђ̋����ɐ݂���ꂽ�ꌩ�䂩�炻�̎p�����邱�Ƃ��o����B�i���̎ʐ^�j
��̗����̊�Ղɐ�ڂ�����O�ɕ�����ė��ꗎ���邽�ߎO�̑�Ƃ������A
�܂��ߒq�̑�̑�\����Ƃ������Ƃ���ߒq�̑��Ƃ��Ă��B
 |
 |
 |
���n���́A������̒��Ƃ��Ă����A�g��F�썑�������̒����Ɉʒu���A�Y��ȌF����]�ޒn�ɂ���܂��B
���n�͌Î��ߌ~���˂̒n�Ƃ��Ė������A�I�B�˂̕ی�������āA�����ւ�h���܂����B
���E��̃X�P�[�����ւ邭����̔����قɂ́A�̒��P�T���̃Z�~�N�W���̖͌^���݂���A
�~�̐��Ԃ�ߌ~�Ɋւ��鎑���Ȃǂ��悻1,000�_�ɋy�ԋM�d�Ȃ��̂��W������Ă��܂��B
�킪���ߌ~���˂̒n�Ƃ��Đ̂��猻��܂ł̂��悻400�N�̗��j��ڂ̓�����ɋ����[�����ł��܂��B
| �@�@�W���i�ŗV�� |  |
 |
| �}���i�����E���͑��n������l�����̎��R�v�[�������ɂ���C�m�����قł��B �ٓ��ɐ���630�g���̑吅��������A�����g���l������F���ɐ������鋛�̐��Ԃ��ԋ߂Ɋώ@�ł��܂��B |
|
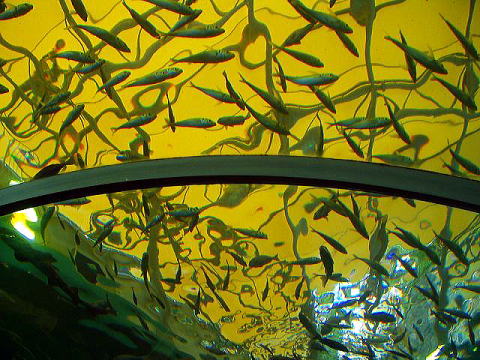 |
 |
 |
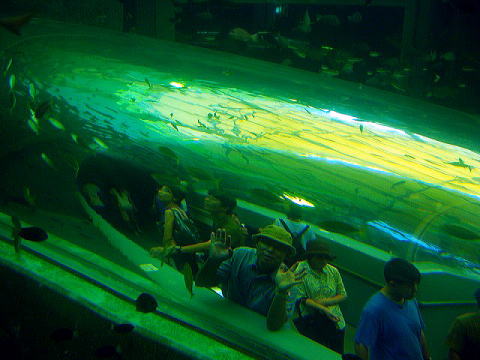 |
��@��@�~
�����m�ɖʂ����X���[�v��̊�ՂŁA���ɏ_�炩�����ߑł���g�̐Z�H���A���G�Ȓn�`���`�����Ă��܂��B
���̍L���͂����悻4�w�N�^�[���ŁA���疇�~����قǂ̍L���ł��邱�Ƃ����O�̗R���ł����ł��B
�O�i�ǁE�~�����ƕ���ŁA���l���̌i���n�Ƃ��Ēm���Ă���B
| ���i�͊�Ղ̏��������Ƃ͏o���܂����A�g�Q���ӕ�A�x�ߎ��͗������֎~����܂��B |  |
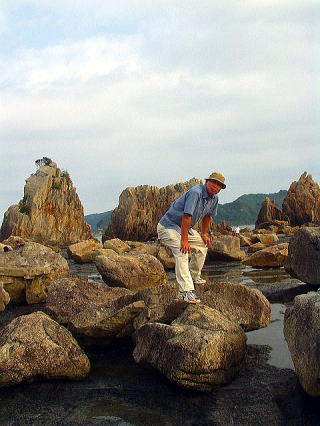 |
| ���̏ꏊ����]�ޗ[���̔������͔��ɗL���ŁA�L��ȑ����m�֒��ނ��̎p�ɂ́A�������܂��B |  |
 |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@���@���@�� | ||
 |
 |
 |
|
�����̊ό��^���[�B |
 |
�N�ԍ~�J��5000�~���Ƃ������E�L���̉J���ʂ��ւ���P���́A���ʂ̉J�������ȋC�ۏ����ݏo���A
��̓����v���ƕ��ԉ䍑���\���錴���т��`�����Ă��܂��B
���X�t�H�[���X�g�ƌĂ��R�P�̑����т�s��Ő��ʖL���Ȍk���Ƒ�Ȃǂ�����A
�܂��A�������������ɑ�\����鑼�ł͗ނ̖������R�̑��`�����邱�Ƃ��ł��܂��B
 |
 |
 |
 |
| �������@�F�@�C�g�U�T�̕����Ɠ|�ꂽ�藧�͂ꂵ���g�E�q����䃖�����ے����镗�i������o���Ă��܂��B | |
 |
 |
 |
 |
| ������ �C�g�U�T�̂��イ�����~���߂��悤�ȑ啽���B�����o��ƁA�ƂĂ����z�I�ł��B �Ð쐓�������h����^�Ƃ����_���V�c���Ɠ`���̑�E��������܂��B |
 |
 |
 |
| �����(�������Ⴎ��) �����R�[�X�����Ă̐�i�|�C���g�B��O�͎R�ブ�x�A��R�A�߉ރ��x�Ƒ�������A�R�A�ቺ�͐�����800m�̒f�R��ǁB �p�m���}�r���[�Ɨ�⊾�^�����̃X���������킦�܂��B ��ւ̔w�ɏ�����悤�Ȋ��o���炱��Ȗ��O�ɂȂ��Ă��܂��B ���Ȃ������Ƃ͑傫�Ȋ�̂��ƁB |
 |
 |
 |
| �V�I�J���݂苴 |  |
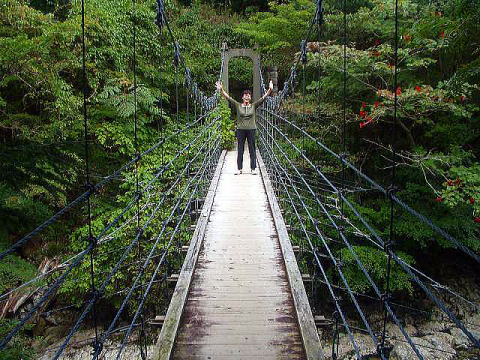 |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
| �n���̊ۂ�������u�W�]�� �n���̊ۂ�������u�W�]�ق́A������n�̍����i73.6m�j�ł��鈤���R�̒���ɂ���܂��B �k�͎����傩��}�g�R��]�݁A���Ɠ�͈�]�痢�ɑ����m�̑�C�����A���͛����P�Y�����\�㗢�l�܂Ō��n���܂��B �W����90���[�g���̓W�]�X�y�[�X�����360�x�̑�p�m���}���L����ɂ₩�Ɍʂ�`�����������ɂ���āA�n���̊ۂ��������ł��܂��B ���̎ʐ^�Ɏʂ铔��͌��i�蓔��ł��B |
|
 |
 |
|
�����P�Y ���q�̑�\�I�Ȍi���n�̂ЂƂł���w�����P�Y�x�́A�щ����̌Y�����i���傤�Ԃ݂����j�܂�10Km�ɂ��y�Ԑ�ǂ̊C�ݐ��ł��B |
 |
 |
 |
|
�����m�ɗՂޒf�R��ǂ̓h���}�ECM�E�f��E�v�����[�V�����r�f�I�Ȃǂ̃��P�n�Ƃ��Ă��D�܂�A���܂��܂ȏ�ʂɓo�ꂵ�Ă��܂��B�w�����P�Y�x�̌i�ς́A�u�C�H�i�g�ɂ��Z�H�j�v�ɂ��`������Ă��܂����B |
|
 |
 |