ジャポニズム |
||
さて、前回、印象派についての説明をやりましたので、ここではそこからもう少し発展させて「ジャポニズム」の話をしたいと思います。 |
||
■ ジャポニズムの幕開け |
||
ジャポニズム・ムーヴメントのきっかけとなったのは、19世紀後半からヨーロッパ各地で開催された万国博覧会で、なかでも影響の大きかったのは1867年、当時の新興都市パリで開催された時のものでした。 |
||
■ 印象派絵画にみるジャポニズム |
||
| 当時、ジャポニズムの洗礼を最も顕著に受けたのは、若い印象派の芸術家たちでした。彼らは、自身の作品にどのように日本美術を取り入れていったのでしょうか? ここでちょっと検証してみたいと思います。 まずはわかりやすいところから、モネの「ラ・ジャポネーズ」。 キモノに扇子にうちわと、「いかにも」な演出ではありますが、日本人のわれわれから見ると「和風」というよりは「エキゾチックな東洋趣味」てな感じを受けますね。 |
||
 「シャルパンティエ夫人とその子供たち」 ルノワール 1878年 |
さて、つづいてはルノワールの作品。 これは一見、何でもない絵のように見えますが、よーく見ると背景に日本風のすだれや絵が飾られていて、当時の上流家庭への日本美術の浸透ぶりがうかがえます。 もっとも、この絵で大事なのはそういう部分ではなくて、じつは全体の明るい色使いの方に注目してもらいたいのです。 現代のわれわれが見ると、「この絵のどこが特別なの?」と思ってしまうくらいあたりまえの描画なんですが、実はこのような明るい色使いは、当時のヨーロッパ絵画ではきわめて特殊なものだったんです。 次の、マネの「エミール・ゾラの肖像」を見てください。 全然明るさが違うでしょ? |
|
 「エミール・ゾラの肖像」 マネ 1868年 |
ヨーロッパの伝統的な写実主義、明暗法だとこんな暗い色調になるんです。 ルノワールの作品がいかに明るくて華やかな色使いか、こうして比較して見るとよく分かると思います。 ちなみにマネのこの作品、有名な「笛を吹く少年」が、サロンで不評だったにもかかわらず、浮世絵の技法を取り入れたその新しい試みをゾラが非常に高く評価してくれたことへの返礼として描かれたものです。 絵自体は伝統的な手法で描かれていますが、背景にはさりげなく相撲錦絵(2代歌川国明「大鳴門灘右エ門」)が配されています。 |
|
 「笛を吹く少年」 マネ 1866年 |
で、「笛を吹く少年」の方なんですが、これも言われないと浮世絵の影響を受けてる、なんてこと、普通はわかんないでしょうね。 この絵の場合、まず平坦な色調により、陰影を抑えて画面全体を浮世絵版画のような平面的な描写にしようとした努力がうかがえます。さりげなく、浮世絵風の「ふちどり」も施してありますね。しかし、まだ完全には伝統絵画から脱却できてはいないようです。 まあ、伝統的な写実描写から浮世絵風の描写に脱皮しようとする過渡期といいますか、実験段階のものと見ていいと思います。 ついでだから、マネの作品についてもう少しつづけて見てみましょう。 |
|
 「舟遊び」 マネ 1874年 |
「笛を吹く少年」から8年後の「舟遊び」になると、もうかなり浮世絵風といいますか、印象派風の画法を確立しているのがよくわかります。 色使いもあきらかに明るくなっていますし、何よりもその構図のとり方に大きな成長が見られますね。 |
|
 「ナナ」 マネ 1877年 |
もうひとついってみましょう。 1877年の作品。もうこの頃になるとカンペキですね。色使いはさらに華やかになってますし、対象物をより強調するために、右側の男性を画面から半分切り捨てるという大胆な描き方をしています。ヨーロッパの伝統的な手法からは考えられない描き方です。 画面の背景には屏風も描かれていて、マネの日本美術に対する造詣の深さをうかがうわせます。 |
|
 「舟遊び」 モネ 1887年 |
今度はモネの作品を見てみましょう。マネとモネ、ややこしいけど、まちがえないでね(笑) これも先ほどのマネの「舟遊び」と同じく、高めの視点から俯瞰する形で描かれており、実際、マネの影響もあるように言われていますが、いずれにせよこの「舟遊び」というモチーフ自体が浮世絵の影響によるものです。 絵の感じが、最初の「ラ・ジャポネーズ」に比べると、随分ふわっとしたパステル調に変わってきてますね。後年の「睡蓮」の雰囲気にだいぶ近づいてきている気がします。
|
|
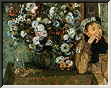 「菊のある婦人像」 ドガ 1865年 |
こんどはドガの作品です。 ドガは浮世絵から、構図のとり方という点で大きな影響を受けた画家です。 |
|
 「婦人と犬」 ドガ 1875-80年 |
この「婦人と犬」では、人物の表情を帽子で隠してほとんど見せないという大胆な構図をとりつつ、浮世絵風のふちどりまで施しています。 人物の顔の部分だけをクローズアップするというのも、おそらくは浮世絵の美人大首絵の影響ではないかと思われます。 |
|
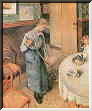 「田舎の小間使いの女」 ピサロ 1882年 |
ピサロも構図の部分で浮世絵の影響を大きく受けています。 この絵も、やや俯瞰する視点で描かれ(西洋の伝統手法では、必ず画家の目の高さから、遠近法を用いて描かれます)テーブルを画面から半分切り捨てたアンバランスな構図を取っています。 よく見ると、壁には日本画も飾られていますね。 |
|
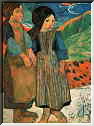 「浜辺に立つブルターニュの少女」 ゴーギャン 1889年 |
ゴーギャンはゴッホと並んで、浮世絵の影響を特に強く受けた画家として知られます。 ゴッホの場合は、浮世絵を通して、その背景にある日本文化や日本人の自然観といった精神的な部分を学ぼうとしたのに対し、ゴーギャンは構図、描画手法といった技術的な面で学んでいるような気がします。 この絵の場合、カラフルな色使いと「ふちどり」の描画手法、やや高めの位置からの視点、人物を中心からはずした構図、立体感を極力排除した平面的な画面構成などなど、まさしく「油絵で描いた浮世絵」という感じです。 |
|
| 浮世絵ギャラリーTOPに戻る | ||

