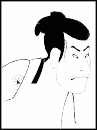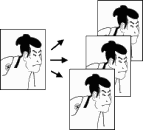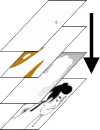| 浮世絵のできるまで | |||||||||||||||
| ■「ホンモノ」は世界に一つ? 浮世絵には、大きく分けて1枚ものの肉筆浮世絵と、木版画による浮世絵版画とがあります。
■浮世絵の製作過程 浮世絵は版画ですから、その完成までには、
というプロセスが必要です。 浮世絵の場合、特徴的なのは、この「下絵を描く」、「版木を彫る」、「紙に摺る」という3つのプロセスが、それぞれ専門職として分業化されている、という点です。 絵師は、版元(出版社)からの依頼により、下絵を描きます。ただし、何でも好きなものを描いてよいわけではなくて、絵の内容に関してはきちんと版元の企画意図に沿ったものを描かなければなりません。描き方にも細かいルールがあって、たとえば役者絵で3人横並びの絵を描く場合、「主役は必ず真ん中に配置しなければならない」といった具合に、その役者の格や歌舞伎の演目内容に応じて、人物の配置から描く大きさ、着物の柄まで、きちんとルールに則って描き分けなければなりませんでした。 さて、絵師の下絵が出来ると、次は彫り師の出番。下絵の線に忠実に版木を彫っていきます。 こうして版木が仕上がると、最後の仕上げは摺り師が行います。
■作業の流れ 以上、絵師、彫り師、摺り師の各プロセスでの役割をざっとご紹介したわけですが、ここで改めて全体の作業の流れを図で追ってみたいと思います。
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
いかがだったでしょうか。 浮世絵を製作するにあたって「検閲」があることや、絵の内容や色指定に、絵師よりも版元の意向が大きく影響したことなど、意外に思われた点もあったのではないでしょうか。 浮世絵というと、なんとなく現代の芸術家のように、浮世絵師が自由奔放に創作していたイメージが強いのではないかと思いますが、実はそうではなくて、絵師はあくまで請け負い仕事・納期仕事の「画工」でしかなかったのです。 重要なのは、主導権を握るのはあくまで版元だということ。 次回はそんな縁の下の力持ち、彫り師と摺り師の仕事ぶりについて注目してみたいと思います。 |
|||||||||||||||
→ もっと詳しく「浮世絵製作の手順(浮世絵ぎゃらりぃ)」 |
|||||||||||||||
→ もっと詳しく「彫りと摺りの技術 (浮世絵ぎゃらりぃ)」 |
|||||||||||||||
→ TOPに戻る |