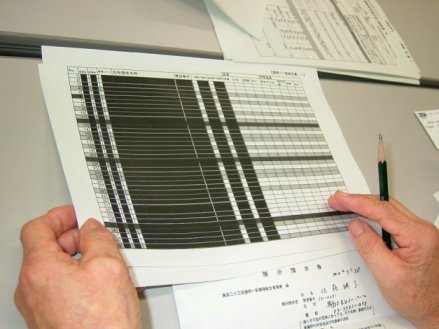僺僐捠怣乛戞151崋
栚師 |
|
EU偺怴偟偄壔妛暔幙婯懃 REACH
弶傔偰6暔幙偑擣壜懳徾偵 偍偝傜偄丗REACH偺宱堒偲尰忬 丂REACH偼丄Registration, Evaluation, and Authorization of Chemicals乮壔妛暔幙偺搊榐丄昡壙丄擣壜乯偱偁傝丄墷廈楢崌乮EU乯偺怴偟偄壔妛暔幙婯懃偺偙偲偱偡丅 丂REACH偵偼丄偄偔偮偐偺廳梫側婯懃偑偁傝傑偡偑丄偦偺偆偪偺傂偲偮偑"擣壜"偱偡丅擣壜懳徾偵巜掕偝傟偨旕忢偵崅偄寽擮偺偁傞暔幙乮崅寽擮暔幙乯偼丄摿暿偺嫋壜偑側偄尷傝丄巗応偵弌偡偙偲偑偱偒側偔側傝傑偡丅 丂杮擭2寧17擔偵REACH塣梡奐巒屻丄弶傔偰6暔幙偑擣壜懳徾暔幙偵巜掕偝傟偨偺偱丄杮峞偱偼傑偢丄偙傟偵偮偄偰夝愢偟丄師偵丄2007擭6寧1擔偵敪岠偟偨REACH偼丄尰嵼偳偺傛偆偵側偭偰偄傞偺偐偍偝傜偄偟傑偡丅 1. REACH偱弶傔偰6暔幙偑巊梡嬛巭偵 丂2011擭2寧17擔丄EU壛柨崙偺埾堳夛偼搳昜偵傛傝丄師儁乕僕偵帵偡6庬椶偺崅寽擮暔幙乮SVHCs乯傪丄弶傔偰REACH壔妛暔幙婯惂偺擣壜儕僗僩偵壛偊傞偙偲傪寛掕偟傑偟偨丅偙傟偵傛傝丄偙傟傜偺暔幙偵偮偄偰丄強掕偺婜擔傑偱偵摿椺怽惪傪偟側偄偲丄強掕偺婜擔乮擔杤擔偲偄偆乯埲崀偼偙傟傜偺暔幙傪巗応偵弌偡偙偲偑偱偒側偔側傝傑偡丅 丂REACH偺擣壜梫媮偼丄暔幙偺惢憿/桝擖検偵偐偐傢傜偢揔梡偝傟傑偡丅REACH偵偼擣壜儕僗僩偺傎偐偵丄擣壜暔幙偵巜掕偝傟傞暔幙偺岓曗儕僗僩偑偁傝丄尰嵼丄46庬椶偺岓曗暔幙偑儕僗僩偝傟偰偄傑偡偑丄偝傜偵7暔幙偑岓曗偲偟偰採埬偝傟偰偄傑偡丅崱夞偺6暔幙偺傛偆偵丄岓曗暔幙偺拞偐傜擣壜暔幙偲偟偰巜掕偝傟傞偲丄擣壜儕僗僩偵婰嵹偝傟傑偡丅 丂墷廈壔妛暔幙嶻嬈嫤夛乮Cefic乯偼丄崅寽擮暔幙偲偟偰岓曗儕僗僩偵嵹傞偙偲偼僽儔僢僋儕僗僩偵嵹傞偙偲偱偁傝丄栤戣偱偁傞偲庡挘偟偰偄傑偡偑丄娐嫬抍懱偼岓曗儕僗僩偵嵹傞偙偲偱丄惢憿幰偼擣壜懳徾暔幙偵側傞慜偵惢憿傪傗傔傞僀儞僙儞僥傿僽偑摥偔偲偟偰岓曗儕僗僩偺懚嵼傪昡壙偟偰偄傑偡丅 丂暷壔妛夛乮ACS乯偺僆儞儔僀儞丒僯儏乕僗C&EN偵傛傟偽丄Cefic偺儊儞僶乕偱偁傞墷廈壜慪嵻拞娫懱嫤媍夛偲暷壔妛嫤媍夛乮ACC乯偺僼僞儖巁僄僗僥儖椶埾堳夛偼丄DEHP傪堛椕丄帺摦幵丄偦偺懠偺墳梡暘栰偱宲懕偟偰巊梡偡傞嫋壜傪EU偵媮傔傞偱偁傠偆偲曬偠偰偄傑偡丅 丂崱夞丄弶傔偰擣壜暔幙偵巜掕偝傟偨6暔幙偼壓婰偵帵偡捠傝偱偡丅
2. REACH偺偍偝傜偄 丂2003擭5寧偵墷廈埾堳夛偵傛傝弶傔偰偦偺僪儔僼僩偑敪昞偝傟偰埲棃丄墷廈楢崌乮EU乯撪偺傒側傜偢丄悽奅拞偱懡偔偺棙奞娭學幰偵傛傞寖偟偄媍榑偲儘價乕僀儞僌偑峴傢傟偨屻偵丄2007擭6寧1擔偵REACH偼敪岠偟傑偟偨丅 丂栺3枩庬偁傞偲偄傢傟傞懳徾壔妛暔幙乮1嬈幰摉傝惢憿乛桝擖検偑1僩儞/擭乮t/y乯埲忋偺暔幙偼2018擭傑偱偵強掕偺僨乕僞偲偲傕偵抜奒揑偵搊榐偝傟丄傑偨旕忢偵崅偄寽擮偺偁傞壔妛暔幙乮崅寽擮暔幙乮SVHC乯乯傕摿掕偝傟丄摿暿側擣壜偑側偄尷傝巗応偵弌偡偙偲偑偱偒側偔側傝傑偡丅 丂崱傑偱偵僺僐捠怣偱丄壗搙偐REACH偵偮偄偰徯夘偟傑偟偨偑丄嶐擭11寧30擔偵REACH偺嵟弶偺搊榐偑掲傔愗傜傟偨偙偲丄媦傃丄偡偱偵徯夘偟偨偲偍傝丄杮擭2寧偵6庬椶偺崅寽擮暔幙偑弶傔偰擣壜暔幙偵巜掕偝傟偨偙偲側偳丄傂偲偮偺嬫愗傝傪寎偊偰偄傞偺偱丄夵傔偰REACH偺棟擮丄惉棫偺宱堒丄庡梫側僾儘僙僗丄尰忬偵偮偄偰偍偝傜偄偟傑偡丅 2.1. REACH偺棟擮 丂REACH偺崻掙偵偼懡偔偺廳梫側棟擮偑崬傔傜傟偰偄傑偡偑丄偦偺拞偱摿偵廳梫側棟擮偲偟偰丄師偺7偮傪嫇偘傞偙偲偑偱偒傑偡丅 仴僲乕僨乕僞丒僲乕儅乕働僢僩 丂旐奞偑弌傞傑偱偦偺暔幙偼埨慡偱偁傞偲傒側偡偺偱偼側偔丄埨慡偑妋擣偝傟偰偄側偄壔妛暔幙偼巗応偵弌偝側偄丅 仴棫徹愑擟偺揮姺 丂壔妛暔幙偺桳奞惈傪旐奞幰偑棫徹偡傞偺偱偼側偔丄壔妛暔幙偑埨慡偱偁傞偙偲傪壔妛暔幙偺惢憿幰偑棫徹偡傞丅 仴梊杊尨懃 丂桳奞惈偑壢妛揑偵姰慡偵偼棫徹偝傟偰偄側偔偰傕丄崌棟揑側寽擮偑偁傟偽丄帠慜偵梊杊慬抲傪偲傞丅 仴戙懼尨懃 丂傛傝埨慡側戙懼暔幙枖偼戙懼曽朄傪扵偟丄嵦梡偡傞丅 仴巗柉嶲壛 丂惌嶔寛掕僾儘僙僗偵巗柉傪嶲壛偝偣傞丅 仴忣曬岞奐 丂寛掕偺僾儘僙僗傗埨慡偵娭傢傞慡偰偺壔妛暔幙忣曬傪巗柉偵暘偐傝傗偡偄宍偵偟偰丄岞奐偡傞丅 仴堦悽戙栚昗 丂桳奞壔妛暔幙偐傜堦悽戙埲撪偵扙媝偡傞丅乮師悽戙偵巆偝側偄乯丅 2.2. REACH惉棫偺宱堒 丂1990擭戙丄EU偱偼壔妛暔幙偑恖偺寬峃偲娐嫬偵媦傏偡塭嬁偑寽擮偝傟偰偄傞偺偵丄EU巗応偵弌偰偄傞10枩庬偵媦傇壔妛暔幙偺傎偲傫偳偵僨乕僞偑側偔丄埨慡惈偑妋偐傔傜傟偰偄側偄偙偲偑栤戣偲側傝傑偟偨丅 丂偦偺偨傔偵巗応偵弌偰偄傞慡偰偺壔妛暔幙偺埨慡傪妋偐傔丄崅偄寽擮偺偁傞壔妛暔幙傪巗応偐傜側偔偦偆偲偡傞戝偒側攇偑EU撪偵婲偙傝傑偟偨丅 丂2003擭偵墷廈埾堳夛偑REACH埬傪敪昞偡傞偲丄偦傟偵斀懳偡傞壔妛嶻嬈奅傗傾儊儕僇傪拞怱偲偡傞惃椡偺寖偟偄掞峈偑偁傝丄摉弶偺REACH偼屻戅偟傑偟偨丅偟偐偟嵟廔揑偵REACH偼2007擭6寧1擔偵敪岠偟傑偟偨丅 丂怴偨側壔妛暔幙婯懃REACH偵偼丄搊榐丄昡壙丄擣壜偲偄偆庡梫側僾儘僙僗偑偁傝傑偡丅 2.3. REACH 搊榐僾儘僙僗 丂帠嬈幰偼丄惢憿丒桝擖検偲儕僗僋偺戝偒偝偵傛傝丄2018擭傑偱偵壓婰偺僗働僕儏乕儖偱抜奒揑偵壔妛暔幙傪搊榐偡傞偙偲偵側傝傑偟偨丅 仴2008擭6寧1擔乣12寧1擔 丂婛懚壔妛暔幙偺梊旛搊榐傪峴側偆丅梊旛搊榐傪峴側傢側偄偲丄埲壓偵帵偡壔妛暔幙偺検偲摿惈偵傛傝愝掕偝傟偨婜尷傑偱搊榐傪墑挿偡傞尃棙偑幐傢傟傞丅 仴2008擭12寧1擔乣2010擭11寧30擔 丂丒1,000t/y 埲忋偺壔妛暔幙乮*1乯 丂丒100t/y 埲忋偺悈惗惗暔撆惈媦傃悈惈娐嫬偵挿婜塭嬁偺偁傞壔妛暔幙乮*1乯 丂丒1t/y 埲忋偺敪偑傫惈丒曄堎尨惈丒惗怋撆惈乮CMR乯偺偁傞暔幙乮*1乯 丂搊榐偼2抜奒偱峴側傢傟傞丅ECHA傊偺怽惪偵摉偨傝丄ECHA傊偺忣曬傪弨旛偡傞偨傔偵丄摨堦壔妛暔幙傪埖偭偰偄傞夛幮偼壔妛暔幙忣曬岎姺僼僅乕儔儉乮SIEF乯偵嶲壛偟側偔偰偼側傜偢丄偦偙偱偼庢傝傑偲傔怽惪幰偑慖弌偝傟丄壔妛暔幙媦傃撆惈僨乕僞偺徻嵶彂椶傪嶌惉偡傞丅 丂師偵丄擇師怽惪幰偼丄帺幮偵娭楢偡傞忣曬傪娷傫偩寉偄暥彂傪採弌偡傞丅 丂ECHA偵傛傟偽丄2010擭11寧30擔掲傔愗傝偺搊榐偺寢壥丄20,175審乮彂椶乯丄3 483暔幙偑庴棟偝傟偨丅 仴2013擭5寧31擔掲傔愗傝 丂丒100乣1,000t/y 偺壔妛暔幙壔妛暔幙乮*1乯 仴2018擭5寧31擔掲傔愗傝 丂丒10乣100t/y 偺壔妛暔幙壔妛暔幙乮*1乯 丂丒1乣10t/y 偺壔妛暔幙壔妛暔幙乮*2乯 乮*1乯壔妛暔幙埨慡惈曬崘彂乮CSR乯乮桳奞惈昡壙媦傃儕僗僋昡壙乯偑昁梫 乮*2乯桳奞惈昡壙偺傒昁梫 2.4. REACH 偺昡壙僾儘僙僗 丂ECHA偼丄帠嬈幰偐傜採弌偝傟傞壔妛暔幙埨慡惈曬崘彂乮CSR乯偺撪梕偵偮偄偰丄3偮偺娤揰偐傜昡壙傪幚巤偟傑偡丅 乮1乯彂椶偺弲庣惈僠僃僢僋 乮2乯採埬偝傟偨僥僗僩庤朄偺専徹 乮3乯暔幙昡壙 丂2010擭偵偍偗傞昡壙偵娭偡傞EHCA僾儗僗儕儕乕僗偼師偺傛偆偵曬崘偟偰偄傑偡丅
丂REACH偱偼丄杮峞慜敿偱夝愢偟偨偲偍傝丄崅寽擮暔幙乮SVHC乯偑擣壜懳徾偲側傝丄擣壜暔幙偵巜掕偝傟傞偲摿暿偺擣壜偑梌偊傜傟側偄尷傝丄巗応偵弌偡偙偲偑偱偒側偔側傝傑偡丅 丂REACH戞57忦偼崅寽擮暔幙傪丄師偺摿惈傪帩偮暔幙偲偟偰掕媊偟偰偄傑偡丅 乮a乯敪偑傫惈暔幙乮C乯 暘椶1a媦傃1b 乮b乯曄堎尨惈暔幙乮M乯暘椶1a媦傃1b 乮c乯惗怋撆惈暔幙乮R乯暘椶1a媦傃1b 乮d乯擄暘夝惈丄惗懱拁愊惈媦傃撆惈暔幙乮PBT乯 乮e乯嬌傔偰擄暘夝惈偱崅偄惗懱拁愊惈傪桳偡傞暔幙乮vPvB乯 乮f 撪暘斿偐偔棎惈傪桳偡傞偐丄枖偼擄暘夝惈丄惗懱拁愊惈媦傃撆惈傪桳偡傞偐丄枖偼嬌傔偰擄暘夝惈偱崅偄惗懱拁愊惈傪桳偡傞傛偆側暔幙偱偁偭偰丄乮d乯枖偼乮e乯偺婎弨傪枮偨偝側偄偑丄乮a乯偐傜乮e乯偵楍婰偟偨懠偺暔幙偲摨摍儗儀儖偺寽擮傪惗偠偝偣傞偲偺壢妛揑徹嫆偺偁傞暔幙丅 2.6. 僫僲暔幙偺庢埖偄 丂2007擭6寧偺REACH敪岠帪偵偼傑偩廫暘偵媍榑偝傟側偐偭偨僫僲暔幙偺REACH偱偺埖偄偵偮偄偰丄媍榑偑巒傑偭偰偄傑偡丅 丂2009擭4寧7擔丄墷廈媍夛偼墷廈埾堳夛偵懳偟丄慡儔僀僼僒僀僋儖偵傢偨偭偰愽嵼揑側寬峃丄娐嫬丄枖偼埨慡偵塭嬁傪媦傏偡惢昳拞偺僫僲暔幙偺慡偰偺墳梡偵偮偄偰丄僲乕僨乕僞丒僲乕儅乕働僢僩尨懃傪姰慡偵幚巤偡傞偨傔偵丄慡偰偺娭楢偡傞朄婯傪儗價儏乕偡傞傛偆墷廈埾堳夛偵梫媮偟傑偟偨丅 丂2009擭4寧24擔敪昞偺墷廈媍夛僾儗僗儕儕乕僗偼丄媍夛偼墷廈埾堳夛偵懳偟丄摿偵壓婰偺娤揰偐傜REACH傪尒捈偡偙偲偺昁梫惈傪専摙偡傞傛偆媮傔傞偲偟偰偄傑偡丅 丂丒1僩儞埲壓偱惢憿枖偼桝擖偝傟傞僫僲暔幙偺娙棯壔偝傟偨搊榐丅 丂丒慡偰偺僫僲暔幙傪怴婯暔幙偲傒側偡偙偲 丅 丂丒慡偰偺搊榐僫僲暔幙偵偮偄偰朶業昡壙傪敽偭偨壔妛暔幙埨慡曬崘彂偺採弌丅 丂丒僫僲暔幙帺恎丄挷嵻拞丄傑偨偼惉宆昳拞偺慡偰偺僫僲暔幙偺撏偗弌丅 2.7 傑偲傔 丂REACH偺奣擮偑弶傔偰採婲偝傟偰偐傜10擭嬤偔宱夁偟偨尰嵼偱傕丄REACH偺棟擮偼岝傝婸偄偰偄傞傛偆偵尒偊傑偡丅晛曊揑側棟擮偩偐傜偱偟傚偆丅 丂SAICM偵傛傟偽丄2020擭傑偱偵壔妛暔幙偵傛傞桳奞側塭嬁傪側偔偡偙偲偵側偭偰偄傑偡丅擔杮偺壔怰朄傕僲乕僨乕僞丒僲乕儅乕働僢僩尨懃偵婎偯偒丄惢憿幰偵僫僲暔幙傪娷傫偱丄慡偰偺壔妛暔幙偺僨乕僞傪採弌偝偣丄崅偄寽擮偺偁傞暔幙傪摿掕偟丄偦傟傜偑巗応偵弌側偄傛偆偵偡傞偙偲偑偱偒傞傛偆丄敳杮揑偵夵惓偡傋偒偱偡丅乮埨娫晲乯 |