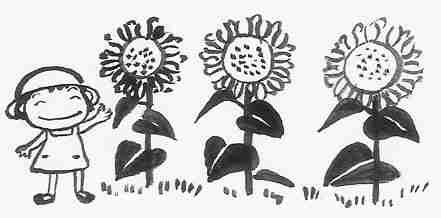ピコ通信/第131号
目次 |
|
市民団体共同声明
「日本政府に水銀輸出禁止法の制定を求める」 なぜ共同声明を出したか 2009年6月25日、当研究会を含む国内3、海外1の団体(注)の呼びかけ人は、「市民団体共同声明 日本政府に水銀輸出禁止法の制定を求める」 を国内外で発表し、8月31日までに賛同市民団体を募るキャンペーンを開始し、すでに国内36団体、海外21団体から賛同を得ています。共同声明は本号ピコ通信に同封し、また当会のウェブサイトにも掲載していますので、賛同いただける団体はぜひ連絡ください。 http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/mercury/mercury_cso_master.html 本稿ではなぜこのようなキャンペーンを開始したかの背景を説明します。 1.水銀は人体及び環境に極めて有害 ▼日本では水俣や新潟で悲惨な体験をし、有機水銀(メチル水銀)の神経毒性についてはよく知られています。しかし無機水銀であっても水銀蒸気の吸入による毒性があり、また環境中に放出されるとバクテリアなどの作用でより有毒なメチル水銀となります。 食物連鎖を通じて魚類に蓄積する水銀の60%〜95%はメチル水銀であると言われており、先進国では主に魚類からメチル水銀が取り込まれます。 ▼途上国の零細な金採鉱現場では、金鉱石から金粒子を選鉱/濃縮し、水銀を用いて金と水銀の合金(アマルガム)を作り、この合金を加熱して水銀を飛ばし、金を得ています。これにより金採鉱現場の労働者や周囲の人々の健康が蝕まれ、環境を汚染しています。 この様な零細金採鉱労働者はアジア、南米、アフリカなど全世界で約1,000万人近くいると言われています。 2.水銀使用の削減は世界の動きである。 2.1 国連環環境計画(UNEP)の取り組み ▼UNEPでは、2001年より地球規模での水銀汚染に関連する活動を開始しており、本年2月のナイロビでの第25回管理理事会で、法的拘束力のある「国際水銀条約」の制定に向けて取り組むことが全会一致で決まりました。 このUNEPの水銀削減の柱は次の2点からなります。 (1) 水銀輸出を禁止し、世界の市場に水銀を出さない。 (2) 非鉄精錬、水銀含有廃棄物、廃止した塩素アルカリ・プラント等から回収される水銀(余剰水銀)は市場に循環しないよう永久保管施設を作り、封じ込める。 ▼2009年3月にバンコクでUNEPアジア水銀保管プロジェクト・ワークショップが開催され、当研究会も参加しました。このワークショップにはアジアのほとんどの主要国(16ケ国)と米国の計17ケ国、国際機関、およびアジアとアメリカのNGOs計8団体が参加しましたが、アジアの水銀問題の取組に主導的な役割を期待される日本政府はこのワークショップに参加しませんでした。 このワークショップの狙いは次の通りでした。 (1) アジアで封じ込まれるべき水銀の予想量に関する専門家の報告書を検証すること。 (2) 余剰水銀の長期的な安全保管のために考慮されるべきオプションと問題を検討し、ワークショップ後の詳細な実施可能性調査の実施とそこから得る勧告につなげること。 (3) 回収水銀封じ込めのための水銀保管施設の開発を検討すること。 詳細はピコ通信127号(2009年3月)をご覧ください。 2.2 EUの取り組み ▼2005年、欧州委員会は、地域及び地球規模での水銀汚染に目を向けた包括的な計画である共同体水銀戦略を発表しました。この戦略では、欧州委員会は、水銀使用の制限とEUからの水銀輸出の禁止を提案しています。 この戦略の重要な点は国際的な行動の支援と推進であり、そのひとつが世界の水銀供給、貿易、及び需要の削減で、UNEPの水銀プログラムの求めるものと一致します。 ▼2006年に発効したRoHS 指令により、水銀など6物質について規定値以上(水銀 は1,000ppm)含有する電気・電子製品は市場に出せないことになりました(適用除外はある)。 ▼2008年9月、水銀輸出を禁止し、余剰水銀を安全に保管する規則が採択され、2011年に発効することになりました。 ▼UNEPにおいては、法的拘束力のある水銀条約を主張し、世界の水銀削減の取り組みにリーダーシップを発揮しました。 2.3 アメリカの取り組み ▼アメリカでは水銀削減のための様々な取り組みが行われていましたが、2006年7月に米EPAは水銀ロードマップを発表し、環境中の水銀を削減するための活動によるこれまでの成果と今後の取り組みについて、米国のみならず国際的な視点からの展望を示しました。 ▼2008年10月に米議会は、水銀輸出を2013年に禁止する法案を採択しました。この法案は現大統領であるオバマ上院議員(当時)が上院における法案提出者でした。 ▼この法案は、2010年までに民間企業から排出される金属水銀の長期的管理と保管方法を策定することを求めています。 ▼UNEPにおける水銀削減の取り組みにおいてアメリカは当初、EUが主張する法的拘束力のある水銀条約の制定に反対し、自主的な取り組みを主張していました。 ▼しかし、本年2月のナイロビ会議の直前に、法的拘束力のある国際条約に賛成するという180度の劇的な政策転換をして世界を驚かせました。水銀に取り組む世界のNG0sは、オバマ政権によるこの政策転換を歓迎しました。 3.日本の現状 3.1 アジアで唯一の水銀輸出国 ▼国内の水銀消費は、電池、蛍光灯、高輝度放電灯(HIDランプ)、水銀柱血圧計など年間15トン弱ですが、一方、非鉄金属精錬や水銀含有廃棄物等から生成されるリサイクル水銀を2006年:約250トン、2007年:約220トン、2008年:約157トン、海外に輸出しており、日本はアジアで唯一の水銀輸出国です。 ▼輸出水銀の大半を途上国が占め、零細な金採鉱現場で水銀が使用され、人の健康と環境を脅かしていると言われています。 ▼熊本日日新聞2009年6月20日の記事によれば、経済産業省は「輸出段階で用途や輸出先などを確認するが、最終的に輸出先国で水銀がどのように管理されているのか把握していない」としています。 ▼また同記事によれば、環境省は「必要不可欠な需要がある現状で輸出を止めると、管理の行き届かない国で新たな採掘を招く」と述べていると報じています。 ▼これは環境省の詭弁であり、日本に求めらることは水銀輸出ではなく、途上国の廃棄水銀の安全な回収のための技術移転です。もし途上国に必要不可欠な水銀需要があるなら、その水銀回収技術に基づく回収水銀を充当することができるはずです。 ▼水銀輸出を禁止するとリサイクル水銀を保管しなくてはならず、立地の問題があるので国内保管はしたくないというのが日本政府の本音ではないのでしょうか。有害な余剰水銀を輸出して途上国に押し付けるというのは、中古品名目で使用済み電子機器を途上国へ輸出して厄介払いするのと同じ構造です。 ▼本年3月にバンコクで開催されたUNEPのアジア水銀保管プロジェクト・ワークショップでは、全ての参加国/団体が余剰水銀の永久保管の必要性に合意しましたが、日本政府はこのワークショップになぜか参加しませんでした。 4.国際NGOsの指摘 ▼水俣を経験しているのに、日本政府は水銀削減の国際的リーダーシップを発揮していない。日本の市民社会も、「国内及び世界の水銀削減」に十分に取り組んでいるように見えないと国際NGOsは指摘しています。 ▼しかし、市民組織が日本政府に働きかけ、日本が水銀輸出禁止を決め、日本、EU、米国の三大国が足並みを揃えれば、世界の水銀輸出禁止に決定的な弾みがつくとしています。 5.日本の市民社会がなすべきこと 水俣病問題では、加害企業チッソを事業継続会社と補償債務返済会社に分離し、認定基準の見直しも行なわれない水俣病特別措置法案が7月15日に施行となりました。 私たちは、水俣病に対する国と加害企業の責任をあくまで求めるとともに、水銀の輸出禁止/余剰水銀の永久保管/使用削減を政府に求めていく必要があります。(安間武) 注:呼びかけ団体 ・化学物質問題市民研究会 ・有害化学物質削減ネットワーク ・ダイオキシン環境ホルモン対策国民会議 ・Ban Toxics! / Zero Mercury Working Group, Philippines |