我が偽りの罪
群集と混乱は、神父二人を乗せた車を容易に通してくれそうになかった。後続の車のことなど顧みず、その場に車をうち捨てて、片手にステッキ、片手にパイプを引っつかんだまま、派遣執行官“プロフェッサー”は車の助手席を飛び出した。
一瞬の遅滞もなく同時に、運転席のドアが弾け飛ぶように開く。傍らに音もなく気配もなく、僧衣の裾を翻して並んだ友の、揺るぎない気配が今の教授にはありがたかった。
飛び出しかかった姿勢を、ぐいと胸を張るようにして無理矢理押しとどめる。
「走った方が良いのでは? ウィリアム」
アルビオン貴族らしくきびきびと、ステッキを抱えて歩く――つまり決して走ろうとしない教授に、友たるハヴェルはそう声をかけてみた。
案の定、意地っ張りな紳士は片手のパイプを捻りながら、器用に肩をすくめてみせた。
「神父トレスが追っていったんだ。ユーグの馬鹿さ加減が発揮される余地はあるまいよ」
弟子のことなどかけらほども心配していません。そう言いたげに教授はことさらのんびりと言って、またかつかつと歩き始める。今日は散々この頑迷なる友をからかって楽しんだだけに、ハヴェルはそれ以上口を出そうとはしなかった。
代わりに出したのは助け舟である。
「しかし私はもう少し急ぎたい。せっかく協力したのですから、神父ユーグの悲願が成就される様子を、この眼で確認したいではありませんか?」
「君がそう言うなら仕方ないね」
即座に返した教授は、己の発言の直後に、ハヴェルがなんとも言えない微妙な表情――おそらく笑いをこらえたのだろう――を隠し、顎を撫でたことに気づいた。
「……ちゃんとついて来たまえよ」
珍しく、ポーカーフェイスを崩した仏頂面でそう言い捨てると、“ソードダンサー”の師匠たるその優雅な身ごなしで走り出す。
縮地の足取りに遅れることなく、すぐ斜め後ろを駆けながら、ハヴェルは風の声に紛れて囁いた。
「きっと無事だよ、ウィリアム」
「当然さ」
振り向かず走る――器用なことにパイプを咥えたまま――教授の口元から、煙とともに千切れ飛んだ言葉を、機械化歩兵の聴覚は決して逃さなかった。
「……感謝する、ヴァーツラフ」
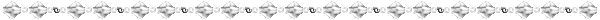
二人の神父の視線の先で、傷だらけのたくましい背から、細剣の切っ先と共に鮮血が噴き出した。だが、サイドカーの運転席にあったもう一人の神父は、鮮やか過ぎるその赤を作り物の眼差しに宿してなお、引き金を引いて剣士に加勢しようとはしなかった。
すべてにおいて合理性を優先させるはずの、その機械人形がどうして発砲せず、同僚の決闘じみた戦闘を見届けるにとどまったのか。その理由を、人形自身は決して認めようとはすまい。
だが、二人の神父は人形の意識に上らぬ真実を、人形以上に理解していた。
夜明け遠き闇夜、人形は、剣士の血のような赤光でぎらぎらと瞳を輝かせたまま、サイドカーから飛び降りて駆け出した。片手のジェリコM13を、腰のホルスターに叩き込みながら。膝をついた血塗れの青年、ただ彼だけに向けて矢のように。
それを見た教授の足取りが、ケープの裾を揺らして緩み……止まる。
「ウィリアム?」
すぐ傍らに、ゆっくりスピードを落として並びながら、だが、聖者に喩えられるその静謐な眼差しは、友の顔を覗き込もうとはせず、友の見つめるものを、視線を追って共に見つめた。
人形が剣士を抱え、何かを何度も呼びかけている。呼びかけているということは、生き延びる見込みがあるのだろう。剣士の手が震えながら伸び、人形の僧衣の袖を掴んだ。……最高の知性に作り上げられた、その義手が。
何を語っているのか。もしかしたら、それは味気ない損害評価報告なのかもしれない。それでも、人形は剣士を抱えて離さず。遠目に見た剣士の眼差しは、……死を含みながらかすかに笑っていた。
「……苦労するよ」
剣士と人形から目を離さず、つぶやいた教授の声がかすれた。
「意地っ張りな馬鹿弟子を、持つと……本当に苦労する」
「彼は師匠に似たのですよ、ウィリアム」
言いながら、ハヴェルはほんのかすか、友の横顔の見えぬ位置へと下がってやった。「あぁ…言ってくれるねぇ」と嘆息しながら、頭痛を感じたかのようにこめかみを押さえてみせた、その肩がわずか震えた。
「復讐」という名の軛に繋がれた、二人の子供を見守り、援けて10年。決して若くはない彼らにとっても、その年月は短いとは言えない。
「出会った頃から、貴方は意地っ張りで頑迷なアルビオン紳士だった……覚えていますか?」
「何を言うのかね、急に」
深紅の法衣が、群集の向こうにチカリと閃く。軛負う子供のひとり。未だ復讐成らざるひとり。二人の神父にとって愛しい、だが、……時に歩む道の離れ行くめぐし児。
豪奢な深紅と黄金に向け、近づきかけた教授がふと、歩みを止めた。ハヴェルがついて来ようとしないことに、気づいたのだ。
だが「どうしたね」と振り返る前に、ハヴェルはその背に言葉を継ぐ。
「貴方は決して、己の中に他人を受け入れようとはしませんでしたね。飄々としたポーズも、私には身食いしているようにしか見えなかった。当時はそれが、随分と苛立たしく思えたものです……」
振り返りかけて片足を引いた姿勢のまま、教授は身体の動きを止めた。なぜかそうして、振り返らずに肩越しにわずか横顔を見せたまま、教授は黙って友の言葉を聞いていた。
『僕のことは放っておいてくれないか、異端審問官殿。どうせ僕は、罪深きバベルの塔の住人さ……君が手を下さなくても、早晩地獄に落ちるだろう』
そう言って、皮肉げに片目をすがめてみせたアルビオンの若き学者。
「罪」とは恐らく、己の研究に婚約者を巻き込んで死なせてしまったという一事ではなく……「知」という深淵の因業、そして、それにとり憑かれた己自身をも指していたのではあるまいか。
若き天才の眼に、狂的な喜びをもってクローンを組み上げるゼベット・ガリバルディの姿は同族嫌悪と映らなかったか。メフィストフェレスの微笑をもって、知への誘惑をそっと耳に吹き込んだアイザック・バトラーの、その言葉に一瞬たりとも心が揺らぎはしなかったのか。
「神の――心弱き者の為の教えは、貴方を救うことは出来なかった。貴方を救ったのは……」
誰かによく似た、緑の瞳がゆっくりと彼方を見た。視線の先に、人形と剣士。人形と同じ義眼であるはずなのに、どうしてそうも深く静けさをたたえることができるのか。
「……貴方を救ったのは、きっと……貴方に救われた子供たちだったのでしょうね、ウィリアム」
笑みやわらかなる眠り姫に、大空馳せる銀の身体を作り上げ、
忌まわしき知の業によって生まれた人形の、整備に心を砕いて育て、
……すべてを奪われた腕なき子に、再び立ち上がるための力を叩き込んでやり、
そうして、孤独にして偏屈だったはずの、研究者は気づいたのだ。
手のかかる「作品」たちが増え、不器用にもがきながら、懸命に自分を見上げていることに。
自虐と厭世にだらだら浸かっている暇など、自分にはないのだということに。
気づいたのだ、神の手も、神の教えの手も、……教えを伝える者たちの手も、借りることなく。
……友の力に、すがることなく。
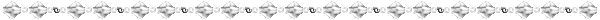
「……人のことが言えるかね、頑迷なる元異端審問官殿」
気づけば友たる科学者は振り返り、表情の伺えぬ、だが、穏やかな眼をまっすぐに、ハヴェルの義眼へ向けていた。
「私が……何です?」
その問いには直接答えず、片手に握りしめたまま忘れていたパイプを、教授はゆっくり口にくわえた。
ステッキを片手に抱えたまま、マッチを取り出そうとして目の前に、しゅ、とオレンジの炎がともる。「ああ、ありがとう」と慣れた様子で答えると、ハヴェルの差し出したマッチの炎から視線を外し、教授は細く煙を吐き出した。
溜息のように。
「僕はねぇ……君に救われたくはなかったんだよ、ヴァーツラフ」
「ウィリアム……?」
「あの頃の君ときたら、異端審問局とは衝突し、神の教えには行き詰まり、げっそりやせた顔をしながら、他人を救うことばかり熱心で……今だってそうだが、自分のことはまるっきり放ったらかしだ。思いつきはしなかったのかね? どうせ神に救われるんだろう君のことを、それでも少しは救ってみたい人間がいるという事実には」
よどみなくすらすらと言い上げた、ついでのように最後に告げられた言葉の意味を、ハヴェルが自覚する前に、教授は目元にかすかな苦笑をはいた。
「お互い、意地を張ったものだね……10年間も」
パイプの火を貸し借りする仕草まで、慣れきるほどの時間だったのに。
「……そろそろ、時間です」
物静かに視線を伏せて、ハヴェルは友へそう告げた。「そうか」と懐中時計を眺めやった視線を、上げて教授は斜めにハヴェルを見返した。
「ミラノ公に挨拶しなくて良いのかね?」
「そうですね……いや、やめておきましょう。今顔を合わせたら、私はまた説教をしてしまいそうだ」
「結構なことじゃないか。大いにしてやりたまえよ」
そう言いながらも、それ以上、共に来ることを強要しようとはせず。教授はパイプに手を添えてみせる仕草を挨拶に代え、軽く首を傾げてみせた。懐中時計の蓋が、パチリと音を立てて閉まる。
「ウィリアム」
背を向けかけた男を、なぜか不意にハヴェルは呼び止めた。
別段、気にとめた風もなく、常の泰然とした立ち居振舞いのままに、友は振り返る。
「何だね?」
「我々は……」
ひどく珍しいことだが、ハヴェルは言いかけた言葉を喪ったかのように、ふと声をつまらせた。
どちらかというと多弁な友も、今はそのポーカーフェイスでおし黙ったまま、次の言葉を待つ。
沈黙は一瞬で壊れ、すぐにハヴェルは、落ち着いた――少なくともそう聞こえる――声で言葉を継いだ。
「……我々は、この十年間……互いに良き友たりえたのでしょうか?」
それは、言葉にしてしまえばあまりにも、……彼らの十年を一言で取りまとめることの不可能さを証明したかのように、あまりにも陳腐な問いであった。
互いに、互いの足手まといになりたくはないと、対等な友人でありたいと、意地を張るうちにいつのまにか、彼らの助けを必要とする他の若者たちが増え、今度は、それに忙殺されて過ごした十年。
その十年に培われたものを、「友」の一言で言い表せるはずもない。だからこそ、ハヴェルは一瞬、悔いるように言葉をとどめたのだろう。
……その陳腐な問いを投げられた教授は、明晰な灰色の脳細胞に何を計算させているのか、ポケットに入れたままの片手で、カチ、カチ、と懐中時計の蓋の留め金を鳴らしたまま、しばし黙考して動かない。
だがやがて、もう片方の手が、友に火を借りたパイプに伸びて、それを口元からわずか離した。
「……良き友であったかと聞かれれば、勿論、『然り』と答えはするが」
時に悪戯小僧のような光も浮かべる眼差しが、ポーカーフェイスのまま、穏やかにひとつまたたいた。
「だが、その普遍的かつ常識的な言葉に加えて、我々はもう少し……
……そうだね、もう少し、気恥ずかしい響きの何かだったのではないかと、今は思うよ」
仲間とか、相棒とか、家族とか、……もしかしたら、それらより強いかもしれない何か、とか。
沈黙は不快なものではなく、だが、――あるいはそれゆえに、破ることを許されぬものであるように思えた。
だから二人は、上空を彼らの銀乙女が飛来するまでの数秒を、その沈黙を味わうことに費やした。
「ケイト君のおでましか」
照れ隠しのようにそちらを見上げ、教授はハヴェルから視線を外す。
「これで神父ユーグも、神父トレスも一安心ですね。……私もやっと、旅立つことができる」
旅立つ先については言わず。瀕死の剣士と、その剣士をしっかり抱えて群衆や警官を威嚇している人形についてそう触れ、ハヴェルはそっと微笑した。
「そう、これで一安心……ようやく一区切りだ」
天を見上げたまま、教授は何気なく言ってみせる。
「ローマにもどってきたら一度、僕の実験室に遊びに来たまえ。僕らもそろそろ、十年間張った意地の、落としどころを話し合うべきだよ。
そうは思わないかね、我が友よ?」
「そうですね、是非」と答えたハヴェルの声に、なぜかかすかな胸騒ぎを覚えて教授が振り返った時、そこに友の姿はなかった。
「ヴァーツラフ……?」
任務に出かけたのだろう、そう理解してはいても、呼ばずにはいられず、姿を探すように一歩踏み出しかける。
だが人垣の向こうで、悲鳴のように弟子を呼ぶ声が連鎖したため、結局、教授の意識はそちらへと向けられざるを得なかった。
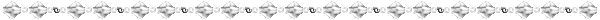
「主よ、」
興奮した群衆の向かう先とは逆に、足早に進みながらぽつりと、静謐なる聖者の唇より懺悔がこぼれる。
「わが偽りの罪を許し給え……」
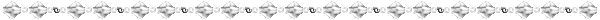
この任務を最後に、かの友の敵となることを知りながら
与えた答えは、
確かに、せめて主のみには懺悔すべき偽りの罪に違いなかった。