背の君
扉の軋む音に、ほの蒼く光るトレスの両眼がぎろり、と動いた。
「ありがとう。いい湯だった」
他の派遣執行官より格別に動きやすさを追及した、その僧衣のズボンだけをはいた気軽な姿……タオルで長い金髪を適当に拭きながら、ユーグが現れたところだった。
たしかに、ユーグが湯を使う間、周辺を警戒していたのはトレスだ。だが、汗腺も皮脂腺も持たぬトレスはもともと、頻繁な入浴など必要としない。第一、片方の入浴中、もう片方が哨戒に立つのは二人一組なら当たり前のことだった。
礼は不要だ、と言いかけたトレスに向かって、「ほら」と何かが投げつけられる。それが手元に落ちてくるまでに、トレスはその解析を終えていた。40度前後の水分を含んだタオルだ。既に、ユーグの義手で固く絞られている。
「ヴァトー神父?」
銃を持たぬほうの手でそれを受け取る。刀を持たぬほうの手でそれを投げたらしい、金髪の神父は、寝台に向かうためにトレスに背を向けたところだった。
「ガルシア神父の言っていた通り、埃っぽい街だ。君も身体を拭うぐらいするだろう?」
無防備に晒された、芸術のように整えられた背。濡れて重く貼りついた髪を、鬱陶しげに両手でまとめ、ぐっ、と持ち上げたために、傷だらけのその背に綺麗に筋肉が浮き上がった。
殺人人形は片手にタオルを持ったまま、その光景を黙って見つめている。彼の正確無比な眼差しは、爆発的な力を生み出す筋繊維の、その一本一本が伸びやかに屈伸する様さえもを、見取っているかのようだった。
「……神父トレス?」
背がねじれ、ユーグが肩越しに振り返る。トレスは黙って、ユーグを見返した。
「拭かないのか? それとも温かいのが不満だったか?」
冷えてしまったタオルを視線で差し、ユーグはやや困惑したように、整った眉を軽く寄せる。
「確かに水のほうが好ましい。だが卿は俺より自分の手配をするべきだ。背中が濡れている」
「すぐ乾くさ」
手にもったタオルで、絹糸のような金髪をいい加減に拭き終わると、ユーグは面倒くさげに答える。ファンの尼僧たちが見たら、あまりの無造作ぶりに卒倒しかねない。
ほの暗い灯りの光を、濡れて弾く白い背中――トレスはその背中に向かって、手袋を脱ぎながら重い靴音を立てて歩み寄った。
近づいてくる足音に、早くもベッドに滑り込もうとしていた身体の動きが、ぴたりと止まる。その手からタオルを取り上げて、トレスは軽く圧するようにして、慎重に背から水分を拭き取りはじめた。
くすぐったかったのだろうか。咽喉を鳴らすようにして短く笑い、ユーグは軽く身をよじる。トレスの鋭敏な触覚は、タオルの下でうねる筋肉の動きを捉えた。湿った髪が水滴を散らしながら揺れ、手袋を脱いだトレスの素手を、踊るように叩いた。
「髪を持ち上げていろ」
拭く端から濡れていく背に業を煮やしたらしく、トレスはそう言って容赦なく、ユーグの髪をまとめて肩の向こうに放る。
「どうせなら、ついでに髪も拭いてくれ」
手酷い扱いを受けた髪を、嫌がらせのようにわざとぴしゃりと跳ねさせて背中に流し直し、涼しい声でユーグは答えた。
「…………了解した」
奇妙なところで面倒見の良いトレスは――あるいは、口論の手間を惜しんだのかもしれないが――、大人しくユーグの髪を、やはりタオルで挟んで押すようにして拭き始める。
以前より、ユーグは突如、子供じみた甘えや我侭を、トレスにぶつけて困らせていた。不思議なことに、トレスがまた実に鷹揚に、その我侭を受け入れるのだ。実に不自然な関係を、ごく自然に築き上げている二人だった。
座れば良いものを、立ったまま作業をはじめてしまったせいで、トレスは背伸びをしてユーグの髪を拭かなければならない。時々、踵がわずかに浮き沈みする音が聞こえてユーグは、こっそりと含み笑った。
いつの頃からか、ユーグはトレスに髪をいじらせることが多くなった。ミラノ公の護衛で公の場に出る時は、彼もレオンのように、そこそこ姿を整えて侍さねばならない。だがユーグは義手の不調だの、時間がないだの、両手がふさがるのが不安でならないだの、とにかく理由をつけてはトレスに髪を整えさせる。HCシリーズに細かな編み込みの仕方を教えたなど、世界広しと言えども、この我侭な剣士ただひとりであった。
髪を拭き終わり、トレスの手が驚くべき正確さで、絡まった髪を解いていく。時折、地肌を冷たい指が滑り、ユーグの肩をすくめさせた。
「――終了した。就寝を推奨する」
水気の格段に減った髪が、背中にゆるやかに流れている様を、殲滅し終わった死体を眺めるのと何ら変わらぬ無機的な眼差しで眺め、トレスは厳かに作業の完了を宣言した。
「ありがとう。気持ち良かった」
機嫌良く、正直な感想を述べてユーグはトレスに向き直り、その僧衣の襟に手を伸ばした。
「……ヴァトー神父?」
冷ややかな声で名を呼びながら、トレスは手から逃れて一歩下がる。身長差を鑑みて、必要的にトレスより大きくなる一歩で、ユーグは開いた距離をあっさり詰め、眼前の頬を人差し指で軽くこすった。
「かなり埃っぽいぞ」
「問題はない。自分で洗浄する」
「遠慮するなよ」
「『遠慮』? 否定。俺は――」
パチン、と僧衣の襟の留め金がひとつ外される。
「“ソードダンサー”」
「眼が冴えてしまったんだ。何か作業でもしているうちに、眠くなるかもしれない」
ユーグの感覚から言えば、おかしな気など欠片ほどもなかったのに――任務中なのだから当然だ――、やわやわ背中など撫でられたせいで、すっかり悪戯心がかきたてられてしまったのだ。多少、この人形のひんやりした肌を楽しんでから眠っても、さほどの罪にはなるまいという思いがあるのだろう。
お話を聞くまで眠らない、と駄々をこねる幼児のようなユーグを、トレスはしばらく冷たい眼差しで見上げていたが、言うことを聞いてやらないと埒があかない、と悟ったらしい。やがて黙って僧衣の留め金を外し始めた。
「俺の両手がふさがるんだから、君の両手は空けておけばいいさ。それが正しい二人一組の在り方だろう?」
やんわりと、トレスの両手を外させて、カチリ、カチリとその留め金を外してやる。まさしく人形の如く、無表情に硬く立ち尽くしているトレスの、その目蓋、作られた者特有の整い方を見せる睫毛のラインを、ユーグは優しく、指先でくすぐるように辿った。そんなことをしても、人形は笑わぬと知ってはいたのだが。
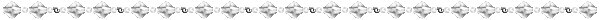
「ほら、僧衣の埃を叩いて来たらいい」
ユーグと同じ格好――上半身裸になったトレスの、人工皮膚に隠れぬメンテナンス・ハッチには、無数の防塵テープが貼りつけられていた。それを眺めながら、脱がせた僧衣をトレスの肩に引っ掛ける。僧衣とユーグを見比べてから、大人しくそれを持って窓へ向かう、可愛い人形の仕草を確認し、ユーグは浴室へ向かうと手桶に水を汲んだ。パン、パン、と僧衣を叩く音が聞こえる。それがなぜかひどく可笑しくて、肩を揺らせて笑えば手桶から、水が少し跳ねてユーグの手を濡らした。
ユーグはトレスに身を整えさせるのと同じほどに、トレスの身を整えるのが好きだった。モニカに言わせれば、「この人形フェチが」の一言で終わってしまうその嗜好の理由は、ユーグ自身にもわからない。本当に、人形遊びをするように、トレスをかまって楽しんでいるだけのような気もする。だが、ユーグには、トレスがそれを嫌がっていないという本能的な確信があった。何せ五年間、生死を分かち合っている。
寝室に戻れば、先程より更に埃っぽくなったトレスが、黙然と僧衣の皺を伸ばしている。それを取り上げ、片手で器用にハンガーにかけてやると、ユーグは手桶をベッドサイドのテーブルに置いた。
「……俺の身体を卿が拭くことに、メリットがあるのか?」
「心配なら両手に銃でも握ってたらどうだ?」
「否定。俺に『心配』という感情はない。ただ――」
「口と眼を閉じてもらえないと、顔が拭けないんだが」
「…………」
怒るという機能を持たない、気の毒な機械化歩兵は黙って口と眼を閉じた。何となく、くちづけを誘っている顔のように見える。……そんな、脳味噌の溶けたことを思いつくのは恐らく、ユーグただ一人なのだろうが。
人差し指を伸ばし、下唇を軽く押してみると、ぱちり、と、一度閉ざされたはずの瞳が開いてユーグを見た。
「……すまない」
思わず真面目に謝ってしまったのは、心あらぬはずのその眼差しに、どことなく、咎めるようなものを感じたからだったのかもしれない。言い訳のように、触れたままの指先を、軽く拭うようにすべらせる。トレスはしばし、その意志強げな眼差しでユーグを見つめていたが、やがて、黙ってまた眼を閉じた。
先ほど絞ったタオルを片手で、しっかり引き結ばれたトレスの顎をもう片手で捕え、ユーグはタオルをそっとあてる。
眼を閉じて微動だにせず、ただ、大人しく世話を受ける機械化歩兵の顔は、常よりもさらに、非生物的に人形めいていた。
100キロを片手で持ち上げるとは思えない、その小柄な肩。人間に似せた骨格――あるいは骨格に偽装されたギミック――の、硬い手触りをタオル越しに辿る。目を開けろといわれるまで開けないつもりか、トレスは瞳を開こうとしない。
皮下装甲の弾力を確かめて、腕を取り、埃を拭って、黒子一つない、作り物のすめらかさを確かめる。擦りすぎると産毛が抜けるらしいから、撫でるだけにとどめて、す、と腕を持ち上げてみた。トレス自身が動きを手伝ってくれているらしく、その腕は人間のものよりずっと軽く感じられた。
脊椎に添って穿たれた接続孔を、丁寧に撫でているうちに、いつしかユーグの手は止まっていた。言われるがままに後ろを向き、背を晒していたトレスが振り返らぬまま、「ヴァトー神父」と冷ややかに名を呼ぶ。
綺麗に真っ直ぐ並んだ脊椎のラインと、そのすぐ両脇の接続孔の感触。ユーグの、タオルを持たぬほうの手がそこに伸びる。
首と肩の継ぎ目、その中心、脊椎が尖って浮き出ているポイントを、作り物の素手がひたりと押さえた。
「ヴァトー神父?」
「……これがすべて……」
接続孔を塞いだ防塵テープを、爪の先でちりちりと引っかき、ユーグは低い声で囁いた。
「これがすべて、人の手によって造り出されたものだとは……とても信じられん」
脊椎の凹凸に添って指を上下させながら、それきり黙り込んだユーグの手はゆっくりと、ひどくゆっくりと下に滑っていく。
その手が、脊椎上の旅を終えて下衣のベルトに辿りつこうとした瞬間、突如、ぐ、とその脊椎はしなやかに、筋肉を伴ってねじれ歪んだ。
その、あまりに完全な、滑らかな動きへの驚きから、ユーグが我に返った時には、裸の上体をねじって振り返ったトレスが、あの変わらぬ強い眼差しで彼を見上げている。
「……あ、」
少年のような羞恥を眼差しに上らせて、ユーグはトレスから手を引いた。気まずい沈黙は、だが、HCシリーズらしく、コンマ数秒しか続かなかった。
「卿には睡眠が必要だ」
何を考えているか窺えぬ、感情の動かぬ眼差しでユーグを見つめたまま、トレスはユーグの手からタオルを取り上げる。
「後は俺が自分でやる」
「……そう、だな」
酔ってもいないのに、己を取り戻そうとするかのように頭をひとつ振り、ユーグはトレスから一歩後ずさる。
「時間になったら……起こしてくれ」
「了解した」
ユーグから取り上げたタオルを、手桶に突っ込みながらトレスはあっさりと、背を向ける。
整いすぎた、非現実的に接続孔の穿たれた、……それがゆえに蠱惑的なその後姿から、ユーグは無理矢理眼を背け、背を向けて、ベッドの中へと滑り込んだ。
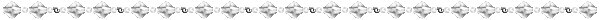
眠らぬ機械化歩兵が、体内時計のアラームに動き出した時、ユーグはまだ眠っていた。その重量によって床板を軋ませながら、それでも、精一杯音をたてずにトレスが歩み寄っても、向けられたままの、シーツにくるまった背中が動くことはなかった。
「――……」
トレスの唇が開く。起こすために名を呼ぼうとしたのかもしれない。
だがその唇は閉ざされ、代わりに、トレスは静かに手を伸ばした。
半ばうつぶせに、背を晒して眠っている、その男の――自然物でありながら、奇跡のように整った脊椎の流れ。
はっきりと詳細まで記憶された、背の無数の傷跡は、今はシーツに隠れて見えない。トレスはひとつ、ふたつ、と、その鋭敏な触覚でユーグの脊椎の数を数え始めた。上から下へ。昨夜、ユーグがトレスにしたように。
「う……」
小さくうめき、逃げるようにユーグの身体がよじられ……その背は猫が伸びをするように、不意にぐぐ、とばねをたわめて丸くなった。
まるで、ありもせぬ息を呑んだかのように、表情のないトレスの、唇がつと開かれる。「生きている者」の、……改造も異能も何も持たぬままの、ただ鍛錬だけが生んだそのしなやかさを、人工皮膚から伝えられて驚嘆したかのごとく。
「……神父トレス」
寝起きの掠れた声に、トレスがユーグの顔へと、視覚センサーの焦点を絞る。
背を向けた状態のまま、乱れかかる金の滝に半ば隠れた翠の眼が、細められ、人形の身を射抜いていた。
「…………」
ただ、黙って相手の次の言葉を待てば、罪深き通常人はどこか貪欲に、ちらりと笑う。
「朝っぱらから、あまり人を欲情させないでくれ」
理解不能、再入力を、と言う前に、伸びやかにふわりと上体を起こし、「おはよう、“ガンスリンガー”」と目元で笑んだ男の顔は、常と変わらぬ“ソードダンサー”のものだった。
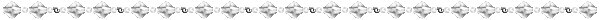
何事もなかったかのように、二人、埃を叩いた僧衣を着込み、宿を出る時にふと、ユーグはつぶやいた。
「お互い、ないものねだりだな」
互いに互いが、正反対の背を持つがゆえに、その背の持つ奇跡に惹かれ、ふらりと手を伸ばさずにはいられない。
だから、背を向けた相手に手を伸ばす。……向き合うことを恐れてもなお。
「――理解不能だ」
頑なな機械化歩兵は前を向いたまま、ただぽつりとそう答える。
そして奇しくも同時に、ガンスリンガーはホルスターに、ソードダンサーは刀の鞘に、触れてその存在を確かめた。
それさえも示し合わせたように対称的な、彼ら二人のその武器を――
ガンスリンガーがその「背」に吊り下げ、ソードダンサーがその「背」に負った、彼ら二人そのもののような、その、武器の存在を。