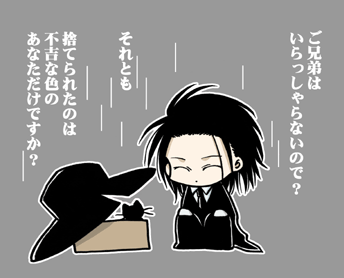正しい迷子の探し方
多くのタクシー運転手の例に漏れず、馬車もまた、雨の日の運転が好きではなかった。
古傷の疼くような、こんな冷たい氷雨の夕暮れは、流していても客を拾えるはずがない。かといって、駅前は少数の法人タクシーが乗り入れを独占している。第一、この視界の悪さが忌まわしい。
馴染みの客から電話でも入るまで、不貞寝を決め込むべきか。あるいはどこか路肩に停めて、傍らのレストランから人が出て来るのを待つべきか。
そんなことを考えながら、それでも無意識に、歩道の客の姿を探しているうち、視界の隅を、何か――がひっかいたような気がした。
そう思った時にはすでに、馬車の手はハザードランプのボタンに伸びていた。
路肩に車が停まったのは、その客のぴったり真横だった。助手席側の窓を開けると、冷たく湿った空気が、数滴の雨粒とともに流れ込んできた。
「何しちゅうん」
そう、できるだけやわらかく声をかけると、車道に背を向けていたその生き物が、雨粒滴る髪を揺らせて静かに振り向いた。
常の通りの、あの黒い帽子をかぶっていたら、もしかしたら、見つけることができなかったかもしれない。だが、ほとんど膝をつくようにして、歩道の隅にかがみこんでいる死神は、病的に白いその顔を、氷雨に無造作に打たせたままだった。
「こんばんは」
相変わらず、馬車の最初の問いは無視して、ものやわらかなテノールはそう言葉を返した。もはや気にせず、「おう」と口の中でつぶやいて、馬車は辛抱強く、「何をしちゅう」と問いを繰り返す。
「見ています」
何を、と問いを重ねかけて、だが、馬車は口をつぐんだ。赤屍の帽子が、今日に限って彼の頭の上に存在していない、その理由を知ったためである。
ダンボールの箱の上にかぶせられた、その帽子の下から、ハザードランプの灯りをきらきら反射する小さい丸が二つ、覗いていた。
「ニィ」
せいいっぱい存在を主張した、その鳴き声を聞いて馬車は嘆息する。
「猫か」
「黒猫が一匹。他は見当たりませんでした」
「一匹?」
「他は拾われていったのでしょう。黒猫は不吉だと言いますから」
常と変わらぬ、貼りつけたような笑みが、氷雨に濡れているだけで、全然別の表情に思えて、馬車はふと、視線を逸らした。
「馬車?」
「……乗り」
後部座席の自動ドアを開けてから、ちら、と視線をやって渋い顔になる。
「それは積まん」
赤屍は、さも当然のように、ダンボールを持ち上げて馬車のタクシーに乗り込もうとしていた。
「え?」
ひどく不思議そうに、赤屍は首を傾げて馬車を見る。
「だめなのですか?」
「誰ンくで飼う気ィなが」
「あなたの家ですよ。だめなのですか?」
「いかんち」
にべもなく言ってから、ぽたぽたと水滴をシートに落とす赤屍が、珍しく、やや途方に暮れたような顔で、首を傾げたまま固まっているのを眺めやる。
おそらく、赤屍は予想もしていなかったのだ。馬車が、この濡れて震えた小さな黒猫を、家に入れることを拒絶するなどとは。
「ニィ」
帽子の下で子猫が鳴いた。
「えいか」
運転席から振り返り、馬車は社内を覗き込む赤屍の、その眼の奥を見つめるようにしてゆっくりと言った。
「ウチにゃ、はや黒猫ぉ飼っちゅうが、そン世話でぎっちり手いっぱいじゃ。それに仕事が仕事ながで、餌ぁやれやぁせん」
「第一、猫は、先に去ぬるがやき、そいがつらい。
……これ以上は、飼わん」
赤屍は、猫と馬車を見比べて、元通り、歩道の隅にダンボールをそっと置いた。
一瞬ためらった手が、帽子をそのまま、ダンボールの上にかぶせて再び立ち上がる。
運転席からその手を引き、引きずり込むように車におさめて、馬車は自動ドアを閉めた。
後部座席に転がり込んだ赤屍が、半ば倒れたようなやわらかい姿態を見せたまま、低い声でつぶやく。
「あなたが、既に猫を飼っているとは知りませんでした」
「ほうか」
「黒猫は不吉なのでしょう?」
「……」
バックミラーで、もぞもぞと起き上がった、その黒衣をつくづくと眺めやる。
相手がわかってないと知りながらも、どうしても照れに声が出にくく、馬車はひとつ咳払いをしてから言った。
「皆そう言うきンど、わしにとってはそうでもねぇぜよ。おらんと、その、据わりが悪ィきにゃあ」
「随分と可愛がっているのですね。メロメロという奴ですか」
その声に不満のような、嫉妬のようなものを聞きつけてますます照れが先に立ち、馬車は運転席に突っ伏したくなった。
「馬車?」
「…………たしかに…………まっこと可愛ぇがね」
どさくさに紛れたこっぱずかしいその言葉も、当然、相手に通じるはずもない。
「わかりましたよ。その猫が嫉妬するから、他の猫が飼えないのでしょう。よくも私に隠れて、そんな猫を囲い通してきたものです」
「ほとほと、お前は正しいぜよ」
赤屍の指摘が、「黒猫という語が一体誰のことを指しているのか」を除けばことごとく的中していることに、もう穴があったら入りたい気分で、ぐったりと馬車は運転席に沈み込んだ。
自分の見つけてきた猫が、いつから住みついているともわからぬ黒猫に押しのけられたのが腹立たしいのだろう。いつまでもふてくされている赤屍を、風呂場に放り込んで馬車は夕食の準備にとりかかった。
どうせ持久戦になるだろうと、冷めても美味い料理を選び、食卓に並べて自分はソファに座り込み、あちこち引っ掻き回して猫を探しているらしい赤屍を、のんびりと待つ。
「猫なんていないじゃないですか」
腹立ちもピークに達したらしい赤屍が、ソファの隣にどすんと座り込んで談判の姿勢をとったのを、横目で眺めて馬車は、プシ、と缶ビールの蓋を開けた。
「馬車!?」
「せからし……そこらにあるき、ほれ。……目の前に」
面倒くさげに――と見えるが実は必死の照れ隠しで――ぶっきらぼうに、顎で洗面所の方を指す。
「は? 何があるんです? 目の前なんて鏡しか、……………………鏡?」
「……おったじゃろ」
気まずい沈黙を忘れたくて、馬車は缶ビールをほとんど一気飲みの勢いで飲み干した。
そんな馬車の気持ちなどまったく斟酌しない、長い長い沈黙が容赦なく彼にのしかかる。
誰か助けてくれ、と、自業自得の心にうめいた時、ひたひたと、無音の気配が馬車の傍らに忍び寄った。
ソファの背後から、彼の顔を覗き込もうとしているのだろう。すぐ耳元に息がかかる。
そして、
「にゃーお」
笑いを含んだテノールが、反則としか言いようのない甘さで一声、鳴いた。
もう振り返ることもできず、ただ、猫を真似て、背後から肩口に頭を摺り寄せてくる、その、湿ったままの頭をぐしゃぐしゃヤケクソで撫でてやる。
「あの猫も、」
撫でられながら、人の言葉を話す黒猫はひっそりと囁いた。
「こうして撫でてくれる相手が、見つかったでしょうか」
罪の意識を持たぬ獣の、戯れの言葉と知ってはいても、その言は、人間である馬車の胸をちくりと刺す。
「……来ィ」
己の膝を叩いてみせると、まだ猫になったつもりなのか、赤屍はおとなしく、ソファを避けて歩いてくると、すとんと馬車の足下に座り込んだ。
膝に乗せられた頭を、適当に拭いてやりながら、言えない一言を馬車は飲み込む。
――頼むから、わしより先には死ぬな。
「……よう言わん」
「何をです?」
「別に」
ぽんぽんと背中を叩いてやって黙らせると、馬車は、冷たい雨の中で震えているであろう子猫に思いをはせる。
平気で一ヶ月ほども家を空ける上に、いつのたれ死ぬともしれぬ裏稼業のこの身が、あんなやわやわした子猫を飼えるはずもない。
――わしには、こんぐらいがちょうどええがで。
気まぐれに、一時飼われてくれるだけの……飼い猫の振りをした野良猫。
残酷な思想しかつむがぬ頭をこの膝に乗せて、なついた家猫のような振りをしているこの、闇色の死神ぐらいが、ちょうど良い。馬車はそう思っていた。
……たとえいつか、この死神が、かぶった猫の皮を脱ぎ捨てて、馬車の手の届かぬところにためらうことなく駆け去ろうとも。
「にゃーお」
欠伸混じりにもう一度、ふわふわと死神は鳴いてみせる。
黒い帽子の下の、せいいっぱい背伸びした鳴き声を……思い出してまた、馬車の胸はかすかに痛んだ。