(08/9/27掲載)
アンタールの初稿と第2稿の比較
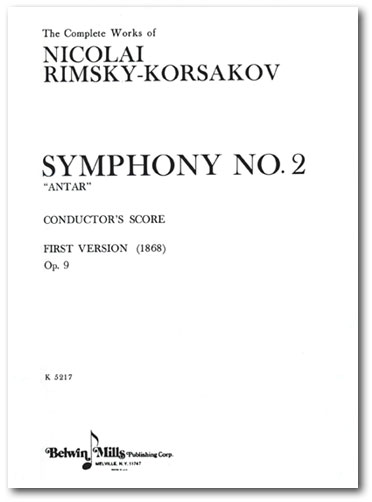
この度、指揮者の新田さん経由でアンタールの初稿(「第1稿」)を入手することが出来ましたので、第2稿との比較を試みてみました。なお、ここに掲げた相違箇所は特に目立つところだけを取り上げただけで、その他にも多くの細かい箇所が異なっています。
※この比較は第2稿のスコアを元になされています。スコアをお持ちでない人にとっては不親切かもしれませんが、ご容赦下さい。
■第1楽章
【小節数】(増減は初稿を基準にしていますが、小節数、練習番号などは第2稿によっています)
- 初稿298小節 第2稿289小節(最初の小節はアウフタクト)
- Mの5小節目(192)アウフタクトから始まるホルンの「アンタールのテーマ」最後の実音「Gis-Dis-Eis」のフレーズが3回から2回に縮小(−2小節)。
- P(224)アウフタクトからの同じホルンのテーマの最後のフレーズが、2回から1回に縮小(−2小節)。
- 242小節目のハープのカデンツァが、記譜が2小節から1小節に(−1小節)。
- S(253)の5小節目から入っていたH(140)からの4小節分をカット(−4小節)。
- 合計9小節のカット。
【オーケストレーション】(第2稿を元にした比較。同じ部分の再現は最初に出てきた場所だけ表記)
編成:
|
- 1:Fg3本のアンサンブル(Hrなし)。
- 9a:Va、VnIと続く上昇音型とユニゾンのCl、Fgがない。
- 25a:Vaのテーマのバックは、木管ではなくHrとTbのアンサンブル。
- 97:クライマックスでのFl、Picなし。
- 126a:Fl3本によるアンサンブルは、Vn3人(弱音器付き)のソリ。
- 148:Vaのテーマとユニゾンのコール・アングレなし。
- 158a:VnIIとVaのピチカートはHpIIに。
- 160:FlのテーマはVnが。
- 164:HrのテーマはClが。
- 182:ヘミオレのリズムが、シンコペーションに。
- 184:Vnと木管のテーマが逆転。
- 242:Hpのグリッサンドは、アルペジオ。
- 243:ClのテーマはFlが。
- 249a:VnIIのテーマとユニゾンのObなし。
- 252:Vc、Cbのピチカートなし。
- 265:ClのテーマはFlが。
- 285a:弦、木管ユニゾンのテーマは、Vaのみ。最後はディミヌエンド、ppで終わる。
■第2楽章
【小節数】
- 初稿243小節 第2稿238小節
- H(148)から半小節早く始まり、9小節目(156)に半小節休符を入れてイーブンに。そのあと4小節追加(+4小節)。
- 161小節目から168小節目までの経過部を、1小節カット(−1小節)。
- 169小節目からKの前(176)までの間に、最後のフレーズを縮小して4小節カット(−4小節)。
- Z(205)からのエンディングを4小節カット(−4小節)。
- 合計5小節のカット。
【オーケストレーション】
編成:
|
- 11:木管八分音符のアウフタクトなし。
- 17:Tbに四分音符のアウフタクトあり。
- 148:低弦のオスティナート半小節遅く始まる。それを受けるVnの合いの手の音型が変化。
- 161:ここからK(185)の前までは、対旋律の音型など大幅に変化。
- 206:ここから最後までも大幅に変化。M(220)までの盛り上がりの前に、「アンタールのテーマ」がフルートに登場。Mの先の同じテーマ(倍に拡大)も、VnIとユニゾンのObはない。
なお、初稿のスコアには、「付録」として、第2楽章の異稿が収録されている。これは141小節の長さしかなく、17小節に現れるファンファーレ(?)のテーマも出てこない習作のようなもの。
■第3楽章
【小節数】
- 初稿174小節 第2稿164小節
- A(8)の前の1小節をカット。
- D(24)の2つ前の小節をカット(1小節カット)。
- N(90)の2つ前と4つ前の小節をカット(2小節カット)。
- U(143)の前の6小節をカット。
- 合計10小節のカット。
【オーケストレーション】
編成:
|
- 1:HrI,IIのシンコペーションなし。
- 4:シンバルは1拍目だけ。
- 12:Hrがシンコペーションのリズム。
- 21:弦楽器はなし。
- 24a:テーマはVIとVaのユニゾン(32aからはVnIとVcI)。
- 36:グラン・カッサなし。Timがトライアングル、シンバルと同じリズム。HpIIも同じリズムのアコード。弦のピチカートはグラン・カッサ、タンバリンと同じリズム。
- 44a:VnのテーマとユニゾンのObと、Va,VcのテーマとユニゾンのFgはなし。
- 52a:ObのテーマはVcが(アウフタクトは三連符の頭なし)。
- 56a:Fgのテーマ(後半+Va)はClが(アウフタクトは三連符の頭なし)。
- 56:VnIのテーマは引き続きVaが。
- 58:VnのテーマはFlが。
- 60:弦とユニゾンのFgはなし。木管伴奏のリズムが頭打ちだけ。Flはオクターブ下。
- FlとユニゾンのClはなし。
- 68:伴奏はここから76からと同じ三連符のパターン。
- 100:Fl、Obアウフタクトあり。
- 108:Timロール。トライアングルなし。
- 112:弦とユニゾンの木管なし。
- 114:Picの前打音なし。4拍目にHp。
- 119:Hpなし。Timロールなし。トライアングルなし。
- 143a:Vc、CbとユニゾンのFgなし。
- 144a:VaとユニゾンのClなし。
■第4楽章
【小節数】
- 初稿198小節 第2稿207小節
- 冒頭に第1楽章のAllegretto vivaceの部分を12小節追加(+12小節)。
- G(92)の後に1小節追加(+1小節)。
- I(118)の後に1小節追加(+1小節)。
- K(132)の後の6小節をカット(−6小節)。
- Oの2小節目(171)の後に1小節追加(+1小節)。
- P(196)の前の小節をカット(−1小節)。
- Pの5小節目(200)の後に1小節追加(+1小節)。
- 合計9小節の追加。
【オーケストレーション】
編成:
|
- 13:ここが楽章の頭。コール・アングレの伴奏にClが加わる。
- 44:Hpが入る。
- 46:Flは次の小節の1拍目まで。十六分音符ではなく八分音符。
- 60:ClとHpの分散和音のパターンが異なる。
- 76:Flの分散和音のパターンが異なる。Hrのテーマはコール・アングレ。
- 83:Fgのテーマはコール・アングレ。
- 92:Flは10小節間ノンブレス。
- 93:Vaのテーマはコール・アングレ。
- 99:ObのテーマはCl。
- 106:ObのテーマはFl。
- 132:Vnは八分音符頭打ちのパターン。Vaはなし。
- 139:弦のテーマはVaとVcIだけ。木管は6/8ではなく1/2のパターン(147からは6/8)。
- 148:Hpがなくなる。
- 162:Flの分散和音なし。
- 196:ObのテーマはFl。
初稿から第2稿への改訂の経過を見てみると、確かに無駄だと思われるフレーズを短くするなどの推敲の跡はみられます。しかし、初稿のオーケストレーションには、ある意味拙さの中にも、まさに20代のリムスキー・コルサコフの「若さ」が感じられるような箇所も見受けられます。ぜひ、実際にその演奏を「音」として聴いてみたいものですが、現在はこの稿による演奏は公式の録音としては存在していません。没後100年という記念すべき年だからこそ、このような珍しいものを録音して発表するには又とない機会だと思うのですが。