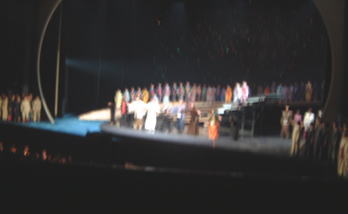|
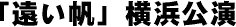 |
| 吉田ヒレカツ |
2002年10月6日 神奈川県民ホール大ホール
(2002/10/17記)
横浜の中華街を抜けて、山下公園の木立が見えてきたときに感じられたものは、海を渡る潮風の香りであった。この山下公園に面した神奈川県民ホールが、今回の私の目的地である。はるばる海を渡って異国に船出をした侍の物語を、このような海をすぐ見下ろせる会場で見るというのも、何かの因縁なのであろうか。
支倉常長という、伊達藩の侍を扱ったこのオペラについては、私はこの場で幾度となく評論を試みてきていた。1999年に仙台市の委嘱で作られたこの作品の初演、そして翌年の再演に臨んで、あたかも私自身がその公演に関わってきたかのような、いささか冷静さを欠いた視点で語っていたことを、諸君は忘れてはいないことだろう。事実、幸運にも一つの作品が出来ていく過程をつぶさに見ることが出来る立場にあった人間としては、その初演にあたっても完璧な客観性を持って対峙するということは、もとより不可能なことであった。しかし、そのようなけっして公正とは言えない見方をもってしなくとも、あの作品は充分に高い完成度を持って、私達に力強い主張を伝えていたことは、私以外の評論家の手になる論評を読んでいただければ明らかであろう。
今回の横浜公演は、演奏者も演出などのスタッフもその仙台市による初演とは全く異なる陣容で臨んだという。もちろん、委嘱元である仙台市も一切のかかわりがないのは言うまでもない。このような形で公演が行われること自体、この作品が一つのオペラとしての独立した価値をもっていたことの証左であり、先ほどの初演の際に私が記していた「作品のグローバル化」の見事な実体化と言えよう。やはりこの作品は、日本のオペラ史上に重要な位置を占めるべく生まれてきたものであったのだ。
横浜の「遠い帆」のステージは、ごくオーソドックスなものだった。オーケストラは通常のピットの中に収まり普通の観客からは、その姿が見えることはない。緞帳の代わりに障子の桟を模した引き戸が立ててあり、ステージを隠すとともに、幕開きの児童合唱の際に歌詞を映し出すという、スクリーンのような役割も果たしていた。その引き戸が開かれると、ステージ中央の円形の階段が目を引く。半円形のその階段は回転するようになっており、場面に応じて様々な形態を見せるという仕組みだ。ただ、一見してこの装置はバイロイトのヴォルフガング・ワーグナーあたりの古臭い演出を参考にしているのがはっきり見て取れてしまい、多少興ざめであったことは正直に告白しなければならないだろう。この階段がかなりの高速で回転している上を、歌手たちが歌いながら歩き回るという所作も、あまり意味のあるものとは思えなかった。してみると、仙台での佐藤信の演出というものは、独創性といい、観客に訴える力といい、実は相当に並外れていたのだったということが、改めて認識されるのである。今回の演出家も決して才能のない人ではないのだろうが、いかんせん「オペラ」にこだわりすぎて、いささか常識的なものになってしまった感は否めない。もっとも、それ以前に、この公演には問題がありすぎた。それは、音響処理にかかわるものである。今回は音響担当のスタッフが写真入でプログラムに掲載されているぐらいだから、この点は最初から力を入れていたのであろうが、結果的には公演を助けるどころか、邪魔になる要素でしかなかったことを、ここに強く訴えたい。なにしろ、歌手の声がすべてスピーカーを通したものしか聴こえてこないところへ持ってきて、その音がいかにも機械的でキンキンしたとても不愉快なものであったのだから。この程度の大きさのホールであるならば、肉声だけで充分歌手の声は伝わるはずだ。おそらく言葉を明瞭に聴かせる助けとして、音響装置の力を借りたのであろうが、逆にその言葉すらこの醜い機械音でさらに不明瞭になってしまっていたのだから、何おか言わんやである。
演奏についても、述べなければならないだろう。最初に合唱が聴こえてきたときには、そのレベルの高さに一瞬驚いたものである。とても訓練の行き届いた声、完璧なアンサンブル、特に男声の充実ぶりは仙台公演のメンバーの比ではなく、冒頭の地の底から湧き出るような深い声が、見事に響き渡っていた様は見事なものであった。しかし、曲が進んでいくうちに、その合唱が何か物足らないものに思えてきたのは、いったいどういうわけだろう。確かに「音」としては非の打ち所のない立派さなのだが、節々の「ことば」に、何か現実味が欠けているのである。例えば「遠い帆」や、「権力者」といった言葉からは、仙台公演ではあれほど感じることが出来た訴えかけるものが、まるで聴こえてこなかったのだ。最後の「薨(みまか)った」という悲痛なつぶやきも、まるでよそよそしいものだった。よく言われていることではあるが、音楽を音楽たらしめているのは、決して譜面にかかれたことだけではないのだということが、このことによってはっきり理解できるのではないだろうか。仙台公演では、世界で初めてこの作品を音にするという、いわば使命感のようなものがあったのであろう。出演者たちの熱のいれようと来たら、なみなみならないものがあったと聞いている。その結果、技術的には拙いものであっても、それを補って余りある気迫のようなものが、作品に見事な命を吹き込んでいた。
おそらく、この作品は、これからも場所を変え人を変えて上演され続けていくことだろう。しかし、初演で得られた感動を体験したものとしては、この横浜公演にはいささかの歯がゆさを感じないわけには行かなかった。クラシックの音楽作品というものは、一旦楽譜に書かれてしまえば、あとは作ったものの手を離れて独り立ちしていくとは、よく言われることである。しかし、今回の公演の、初演とのあまりの落差の大きさ(誤解のないように補足しておくと、これは決して技術的な水準ではなく、あくまで私が受けた感銘ということである)を体験してしまうと、もしかしたらそれは必ずしも真実ではないのではないかという思いに駆られてしまう。少なくとも、初演が持っていたある種の力を伝えるすべは、現在の記譜のシステムには全く欠如しているのである。それを補うものは、もっと広い意味での伝統とか文化といったものの持つ、固定化することの出来ない要素であろうか。かつて武満あたりが言っていた「持ち運びの出来ない音楽」を、この作品の中に見るのは早計過ぎるだろうか。