 |
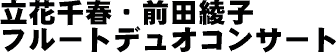 |
| 吉田ヒレカツ |
2002年3月11日 仙台市シルバーセンター
(2001/3/12記)
 |
春の訪れも近いとみえて、日中はめっきり暖かい日が増えてきたように思えてくる。そんな暖かさに誘われて、一昨日は昼間の演奏会に行ってみたのだが、2年前にも聴いたこの韓国人の指揮者はどうも私とはとことん相性が悪いとみえて、やはり失望感を味わわずにはいられなかった。
そんな折、女性フルート奏者が2人というコンサートのお誘いを受けた。もっぱら重厚な音楽を聴くことに慣れている私としては、いささか場違いな思いもあったのだが、自称カリスマのいかにも作為的な厚化粧の音楽を聴いたあとの口直しにはよいのかもしれないと、出掛けてみる事にした。
会場は仙台シルバーセンターという、私にとっては初めての場所。中に入ってみると、客席の勾配が急で、そんなに奥行きが無いにもかかわらず、ステージははるか下の方に見えるという、いささか窮屈なホールであった。収容人員は300人程度であろうか、そのうち、8割程度が埋まっていたようである。
登場した演奏家の姿を見て、軽い驚きを感じたのは、私だけではなかったようだ。女性2人はよいとして、男性のピアニストまでが、申し合わせたように髪の毛を茶色に染めているのであった。あろうことか、男性の髪がもっとも目立つ色なのである。それよりも驚いたのは、女性がイブニングドレスではなく、黒いパンツスーツというのであろうか、ズボンにジャケットという服装だったことだ。髪も短く切ってあるから、あたかも宝塚の女優さんのような感じがしてしまったものだ。となると、背の高い立花さんの方が男役、前田さんは娘役という設定なのであろうか。
もちろん、これは外見だけで判断した勝手な想像だったのだが、1曲目の大バッハのトリオソナタが始まった時、この見立てがまんざらでなかったことに気付いてしまった。立花さんの音は芯のはっきりしたいわば男性的な響きなのに対して、前田さんはやや細めの、言ってみれば女性的な音だったからだ。音色だけではなく、歌わせ方にも前田さんの場合、ややもってまわったところがあるが、立花さんはリズム的な曖昧さは殆ど見られないといった具合。したがって、ゆっくりした楽章においては、それぞれの持ち味を聴き比べて楽しむことができる反面、早い楽章では、おのおののリズム感、フレーズ感の相違から、若干縦の線の乱れが見られたのは惜しまれるところだ。
前半のプログラムは、この大バッハを含めて、長男のフリーデマンや次男のカール・フィリップ・エマニュエルなど、バッハ家の作品であったが、この倒錯感すら感じられるコスチュームで演じられる(そう、彼女達はただ吹くだけではなく、まるで舞のようなしぐさで音楽に彩りを添えていた)後期バロックの音楽は、あたかも19世紀末のサロン音楽のような様相を呈していたのであった。近頃流行りの禁欲的なアプローチからは遠く隔たった、濃厚なまでの煌びやかな世界が、そこには繰り広げられていた。フリーデマンのデュエットの緩徐楽章の官能的なことといったら。
休憩をはさんだ後半のステージが始まると、更なる衝撃に遭遇させられることになる。彼女達は、前半の黒いスーツを脱ぎ捨て(もちろん楽屋で、だが)、いともあでやかなドレス姿で登場したのである。立花さんは薄い緑色、前田さんは薄い紫色、確か、パステルカラーとかいったような、そんな淡い色調の、とても趣味のよいいでたちであった。立花さんのドレスの丈が若干短めに見えたのは、やはり「男役」にこだわる私の偏見だったろうか。
最初のドップラーの二重奏が始まると、ステージにはまるで一歩早く春が訪れたかのような、華やかな雰囲気が漂っていた。あたかも花と戯れる二羽の蝶々のように、軽やかな笛の音とともに舞い踊る妖精の姿が、そこにはあった。思えばこの曲は、カールとフランツという、髭面の兄弟が自分達で演奏するために作ったものであったはずだ。このような華麗な状況下で演奏されることを知ったら、如何様に思うのであろう、などという無用の想像をめぐらせてしまったものである。
このステージ、デュエットだけではなく、それぞれがソロを聴かせる場面も用意されていた。前田さんのレパートリーはガーシュインの「ラプソディ・イン・ブルー」を自由に編曲(真島俊夫)したもの。原曲の「ブルー」でけだるい側面だけを強調したような、いささか退屈な曲である。ジャズの語法を取り入れてはいるが、しょせんは借り物に過ぎない優柔不断な音楽、さらに、きちんとしたビート感に乗るべき箇所での、演奏者のリズム感の欠如が、なんとも中途半端な印象しかもてないものになってしまっていた。
それに対して、立花さんが演奏したカルク・エラートの「ソナタ・アパッショナータ」には、心底敬服させられた。フルート1本のこの難曲を、彼女は暗譜で、まさに「熱情」を込めて吹ききっていたのである。その堂々たる音楽には、瀟洒なコスチュームが場違いのように感じてしまえたのは、彼女にとっては嬉しい誤算だったのかも知れない。いや、それだからこそ、あえて丈の短めな、「男」を思わすような仕掛けにこだわったのでは。実は、6年程前、折があって彼女の演奏を聴いたことがあったのだが、あの時とは別人のような充実した音にも驚かされた。もちろん、メカニカルなテクニックの習熟度には、いささかの不安も感じられないものであった。
このステージ、他にはダマーズの1997年の新作と、クーラウの作品が演奏されていた。めくるめく華麗な技巧の世界、もっぱら立花さんのフルートの方に耳が行ってしまったのも、やむをえないことだろう。彼女の成長振りに確かな手応えを感じた反面、相方の前田さんにはいまだ発展途上の才能しか見出すことが出来なかったのだから。
ピアノ伴奏の山田武彦さんについて、言い忘れるところだった。この才気あふれるピアニストは、絶妙なアンサンブル感覚を持って、フルーティストたちをサポートしていた。前半のステージでは、多彩な装飾を施したリアリゼーションでサロン的な雰囲気を高めていたし、後半では的確なダイナミックスで独奏者たちと対峙していた。その上で、自分自身は完璧な黒子役に徹していたのだから、これは得がたい人材に相違ない。