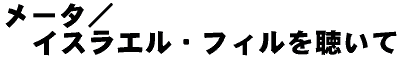|
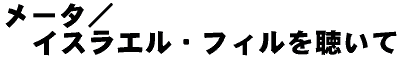 |
| 吉田ヒレカツ |
2000/3/3記
私の人生はもはや黄昏というべきなのだろうか。しかし、ここで雑誌や新聞の連載なんかはやめにして、のんびりと余生を送りたいと思っても、編集者が許してはくれまい。私のなにげない一言が、CDの売り上げに微妙に影響を及ぼしているなどということを聞くにおよんでは、ここでおいぼれるわけにもいかないような気になってくる。
そんな折、あろうことか、とあるホームページからの原稿依頼が舞い込んだ。コンピューター社会というものは、もはや私の理解をはるかに越えたところまで突き進んでいるようだが、このような場で最後の一花を咲かせるのもいいだろう。なによりも、このホームページには、私の娘のサザエが大変お世話になっている関係で、むげには断りきれないという事情もあるのだが。
さて、そのような次第で、このところ何度か鎌倉の自宅から仙台まで足を伸ばす機会があった。折にふれて演奏会の批評などを書いてみようと思っている。
今回はズビン・メータが指揮をしたイスラエル・フィルの演奏を聴きに来てみた。プログラムはリムスキー・コルサコフのシェエラザードとショスタコーヴィチの第5交響曲。いささか、年寄りには腹にもたれる曲目だと思っていたが、シェエラザードの最初のヴァイオリンソロを聴いて、それは杞憂にすぎないことに気がついた。なんという魅力たっぷりの音なのだろう。ホール全体に響きわたるとても上質な、押しつけがましいところがちっともない音色。これが聴けるのなら、もう今夜は強迫感とは無縁の心地よい一時が約束されよう。コンサートマスターだけでなく、弦楽器全体がとても瑞々しい、艶やかな音色。アンサンブルの確かなことと相まって、音が出た瞬間から豊かな音楽が導きだされている。ここでのメータの確かなバランス感覚に裏打ちされたコントロール能力の高さには驚くばかりである。一見なにもやっていないようでて、その実、とてつもない能力をオーケストラから導き出すことに成功しているのだ。些細なことだが、トライアングルの一撃にあれほどのデリカシーを込められる指揮者など、少なくとも実演ではお目に掛かったことがない。
全合奏で思い切り盛り上げても、常に節度を忘れないのも好ましいことだ。そして最後の和音が消えたあとに訪れる静寂…、のはずだった。ところが、都会の悪しき習慣がこの地方都市にまで押し寄せて来たのには、いささかびっくりしてしまった。「ブラボー」とでも叫んだのだろうか、私がもっと若くて元気だったら首を絞めて殺してやろうと思ったくらい、醜悪で間の抜けた声。あれだけはやめてほしいものだ。間髪をいれずに大声を出すことは自己満足以外のなにものでもなく、他人に不快感を与えることのほかにはなんの効果もないことを知るべきだろう。宮城県民会館の1階席、右よりに居たあなたのことですよ。
気を取り直して後半を聴くことにしよう。実は、シェエラザードにほとんど不満は無かったのだが、あえて言わせてもらうと木管とホルンの首席奏者がいささか弱かった。フルートなどは音が低めだし、メータがあまり締めつけないのをいいことに、勝手に間延びさせて全体の足を引っ張っていたと言えなくもない。ファゴットもかなりあやしげなテクニック。ところが、ショスタコーヴィチになったら、木管は全員入れ替わって、ひとまわり年を重ねたようなベテラン達がトップの座にいた。これで少しは不満が解消されることだろう。
しかし、そんな次元の話ではなかった。1楽章が始まるやいなや、私はこのオーケストラのとてつもない能力にさらに打ちのめされることになるのだ。まるでシェエラザードとは違う音、あの芳醇さとは対照的な冷たく乾いた音が聞こえてきたのだ。荒涼としたロシアの大地を思わせる弦楽器に、木管も暗めの音色で応える。首席奏者の人選は、はたして偶然だったのだろうか。これが2楽章になると、また明るい音色がもどってくるために、この楽章の空騒ぎ的な性格がはっきりしてくる。ということは、この楽章、ひいてはこの曲全体のアイロニカルな性格を誰が聴いてもわかるように表現しているのでは。例のヴォルコフの「証言」は、いまだに真贋論争が続いているようだが、このように音楽自体で語らせることによって、この曲に込められた作曲者の意図をおのずと明白にしようとしているのではないか。だから、とことん厳しい3楽章(84小節目のクラリネットの悲痛な叫びは忘れられない)のあとで、あの4楽章が始まれば、これはもう勝利や歓喜とは全く無縁の、底知れぬ絶望の裏返しであることは誰の目(耳)にも明らかになってくるのである。
パンフレットでは、金子某という若造が得意気に楽譜についての蘊蓄をたれていたが、今夜のように、音楽だけで作曲者の思いが直接的に伝わってくるという体験の前では、そのような皮相的ものは完璧に色あせてなんの価値ももたなくなってくる。
アンコールは白鳥の湖のワルツ。ここでの弦楽器は、さらにうってかわってふわふわした肌触りのとっても上品な音色。チャイコフスキーがお祭り音楽だなどと公言してはばからない指揮者がいるそうだが、そのような輩にはこういう演奏は思いもつかないことだろう。隅々まで配慮の行き届いた上等な料理を腹一杯食べたような、充たされた一夜であった。
それにつけても思い返されるのは、ほんの一月ほど前に聴いたチョン・ミョンフン指揮によるフランス国立管弦楽団。私のまわりには、「良い演奏だった」と言う人も多かったが、私はあまり感心できなかった。寄る年波には勝てず、良い演奏を感じ取る感覚が衰えてしまったのかとあの時は不安になったものだったが、本当に素晴らしい演奏にはこうして素直に反応できるのだから、何の心配も要らなかったのだ。
メータは、オーケストラのメンバーから楽々と能力を引き出していたが、チョンは自己の思い入れだけが強くてアンサンブルすらまともに整えられない有り様だったから、とても音楽に酔いしれるような気分にはなれなかった。見かけのカリスマ性などにまどわされず謙虚に演奏に立ち向かう姿勢が、私たち鑑賞者にも求められてはいないかしら。