-----この危険は、いつ何時あなたの身に降りかかるかもしれない
PET
「ロシアンブルーってネコなんだ。でもね、青くないんだ。髪の毛が・・・」
「髪の毛じゃない、毛並みだよ。」
父親は訂正した。子供は少し考えてからいい直した。
「だから、けなみが灰色!でね、触ると・・・マリアの持ってる毛皮のコートみたいすべすべしてふわふわして柔らかいんだ。それでね。目はね!緑だよ!緑!すごくきれいなんだ。」
子供は熱心に言った。しかし父親は笑うと息子の顔を見て言った。
「おれは青が好きだな。」
「青なんて好きじゃない。オスカルと・・・」
「母さんだ。」
父親は訂正した。子供は気づいて言い直した。
「母さんと同じなんて、青なんてぜんぜんきれいじゃない。」
「お前の目と同じだよ。おれは絶対青が好きだけど。」
父親は笑って言った。子供は少し照れくさそうな顔をしたが、すぐにふて腐れた様子をして言った。
「だけど!青より緑のほうがきれいだし、それにかっこいいよ。」
「きれいなのはわかったよ。でも猫は駄目だ。ベベがいるからね。」
「だから僕がする!ちゃんとえさもあげるし、トイレだって教える!」
「お前にはまだ無理だよ。」
「大丈夫だよ、ちゃんとできる!」
しかし、父親は聞き入れなかった。
「駄目だよ。お前にはまだ早い。金魚はどうなった?それからハムスターは?」
「今度はちゃんとするから!」
「駄目だ。ハムスターの時、約束したろう?当分は駄目だって、まず自分の事が自分で出来るようになるまでは飼わないって約束だったよな。」
父親は息子に尋ねた。子供は口をへの字に曲げると父親を睨んだ。父親は苦笑した。
「あと1年たってその時まだ猫が欲しかったらもう一度考えよう。だからまず、自分の事は自分で出来るようにだよ。」
「オスカルだって出来ないのに、ベベを飼ってる。」
「オスカルじゃない。」
「母さんはいつも父さんにしてもらってる。それなのにべべを飼ってる。オスカルはずるい。」
「そうじゃなくて・・・」 父親は言いかけて苦笑すると言った。
「いいか、母さんはちゃんと出来るんだぞ。だけど、おれがしたいからしてるんだ。」
「なんでするの?ごはんも作ってあげるし、みんなの所はお母さんがするんだよ、ぜったいへん。」
「変じゃないよ。」
「へんだよ!」
「よそはよそ、うちはうちだ。これはおれの趣味なんだから・・・」
「しゅみってなに?」
子供の質問に父親は一瞬躊躇した。しかしすぐにいつもどおり優しげに微笑むと答えた。
「つまり、父さんが好きでしてるってことだ。好きだからしてる。分かるか?」
「うん、だけどオスカルは・・・」
「母さんだ。」
「だけど母さんは本当はできないのに・・・」
「母さんは何でも全部出来るんだ。」
子供は到底納得したとはいい難い、疑り深い顔つきで父親を見つめた。父親は苦笑して言った
「とにかくだ。母さんの事はいいからまず自分のことだ。朝は自分で起きる。それから、言われなくても歯を磨く。まずこれからだ。分かったか?」
「・・・分かった。」
子供は渋々答えた。
「よし、じゃあまず宿題からだ。作文をかかなくちゃいけないんだろう?家族についてだったか?」
「先生は飼ってるのでもいいって。」
「じゃあ、ベベのことを書けばいい。」
「だけどベベのことは、みんな知ってるし、それにベベはオスカルが飼ってる犬だし。」
「だから、母さんと呼べ。」
父親はまたしても訂正をして、困ったような顔をした。
「あのな、どうしておれは父さんて呼べるのにオスカルは呼ばないんだ?」
「アンドレは、父さんだけどオスカルはオスカルでいいもん。」
子供はふて腐れて答えた。
「駄目だ、ちゃんと母さんと呼べ。」
「だってオスカルはすぐに父さんをひとり占めするし、それにお母さんぽくないし。」
「駄目だ。」
父親は珍しく強い口調で言った。子供はこれ以上我を張るとどうなるかよく分かっていたので仕方なく頷いた。
「・・・分かった。」
子供は俯いて返事をした。それを聞くと父親は子供を抱いて頬にキスをした。子供は少しだけ嫌そうな顔を作ると父親を見た。
「僕はもう1年生じゃないんだからな。2年なんだぞ、キスしたり抱っこしたりするな!」
その様子に父親は思わず微笑んだ。妻にそっくりな子供は、まるで妻が照れ隠しの時見せる顔と同じだったので、今度は反対側の頬にキスをしてから言った。
「ああ、分かってるよ。」
「ぜんぜん分かってないじゃん!」
子供は父親の腕から逃れると睨んだ。その様子が父親には撫で繰りまわしたいほど可愛らしく見えたが、父親は今度は我慢して微笑むだけにした。
「分かったよ、もうしないから。だけど作文はちゃんと書くんだぞ。」
「書くけど、ベベの事は書かない。他のにする。」
「他の?」
「・・・うん。」
子供はそれだけ言うと部屋を出て行った。
子供が出て行くと父親はふうと大きく息をついた。
子供は自分の部屋に戻るとランドセルから作文用紙を取り出すと机に置いた。
子供は作文用紙を睨んだ。子供はベベの事は書きたくなかった。書いた作文は一人づつ発表する事になっていたのだ。
ベベは目立つ犬だった。アフガンハウンドの背の高い優雅な姿は人目を引いた。クラスでも知らないものはなかった。
どうせみんな、知ってる!知ってるって言うんだ。関口や佐々木は自分の犬みたいに話すんだ。僕が発表しなくても。
子供は少しだけ悲しそうな顔をすると題名を書いて、それからつまらなそうに作文を書き始めた。
次の日、書かれた作文は皆の作文と同様、国語の授業で発表された。
子供は少し緊張しながら作文を読んだ。読んでいる間も、読み終えてからも、クラスメイトは特別何も言わなかった。担任の教師も 「大木さん、よく出来ましたね。」 と言っただけで特別何も言わなかった。
子供はほっとした。
つまんない話だけどやっぱこっちにしてよかったよな。
国語の時間が終わると作文は集められた。それは、担任の教師によって添削され後日返された。
子供は夜になってその日に配られた懇談会のお便りなどと一緒に、大きなソファに寄り添うようにして座っている両親に差し出した。
「こんだん会のプリントは来週までだって。」
母親はそれを受け取りそれを開くと横にいる自分の夫と共に目を通した。それから彼女は作文に気づいて、懇談会のプリントを夫に渡すと二つに畳まれた作文用紙を開きながら子供に尋ねた。
「何だこれは・・・」
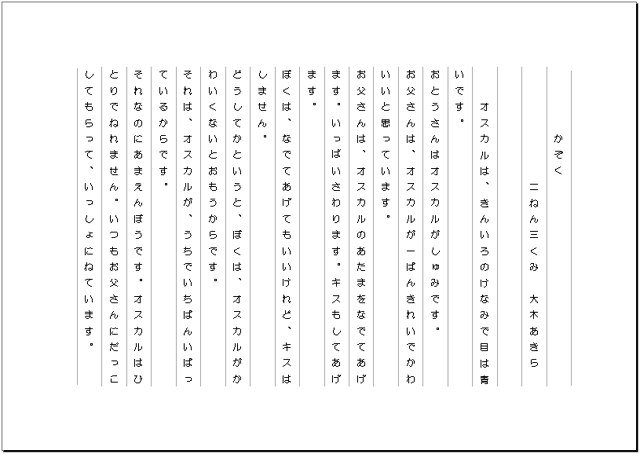
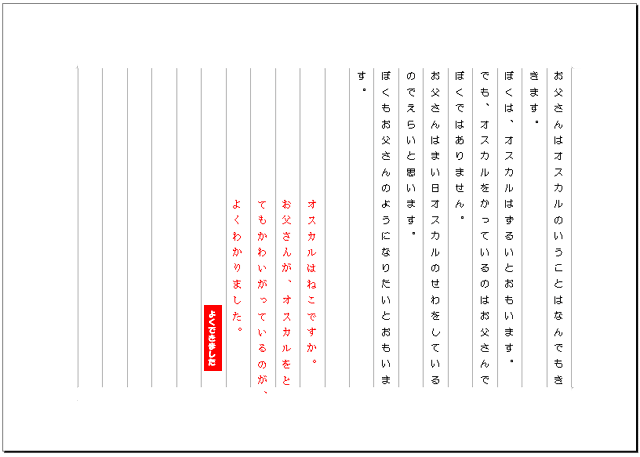
子供は側にいた“ベベ”を撫でてやりながら言った。
「かぞくの作文だよ。この前、こくごの時間にはっぴょうしたやつ。」
母親と父親はほぼ同時に顔を上げた。
「発表・・・した?」
「うん。一人ずつ前へ出てね。」
それから子供は思い出して言った。
「そうだ!先生に違うって言ってない。あした学校へ行ったら言っとくね。ネコじゃなくて・・・」
「言わなくていい!」
母親は叫んだ。その声が余りにも大きかったので子供は驚いて母親の顔を見た。母親は慌てて付け加えた。
「その必要はない。先生も・・・気を悪くされると困る。」
「気を悪くって?」
母親は答えなかった。代わりに父親が答えた。
「いやつまり・・・先生には言わなくてもいいってことだ。えーとその・・・大したことでは・・・ないからな。」
それを聞くと子供は頷いた。
「あと名前を書いちゃったけど、今度はちゃんとお母さんて書くから・・・」
「書かなくていい!」
母親は言った。子供は怪訝そうに母親を見つめた。
「これでいい。わたしのことを書く時はオスカルでいい。これでいい。そうだ、わたしは大木優李だからな。ゆうり!これでうまく行く。ああオスカルでいいんだ。」
「オ、オスカル。それはちょっと・・・」
「もうこれでいい!」
母親は叫んだ。
「オスカル。それよりもだな、問題は・・・」
「これでいい! それから懇談会は・・・わたしは行かない。おまえが行け。」
「オ、オスカル。」
母親は子供を見た。
「懇談会はアンドレが行く。いいな。」
「それはべつにいいけど。」
子供が答えると母親は立ち上がりさっさと部屋を出て言った。父親も慌てて立ち上がり後を追いかけようとしたが、その前に気づいて子供を見た。
「アキラ、お前な・・・」
「なに?」
「つまりその・・・言葉の使い方が間違ってる所がある。」
「でも先生は直してないよ?」
「いや、だから・・・」
父親は言いかけて止めた。それから少し考えてから子供に言った。
「いいか、飼ってるんじゃないからな。それから世話をしてるんじゃなくてだな。」
「じゃあ、なんて書くの?」
「つまり、一緒に暮らしてるんだ。いいか、おれとオスカルは結婚してるんだ。」
「そんなの知ってるよ。だから?」
「だから一緒に暮らしてるんだ。」
「僕も一緒に暮らしてるよ。」
「だから暮らしてるだろう?」
「違うよ。べべといっしょだ。オスカルはべべを飼ってる。父さんはオスカルを飼ってる。」
父親は眩暈がしそうになったが、気を取り直して辛抱強く言った。
「だから違うだろう?ベベは犬なんだ。オスカルは人間だ。人間の場合はだな、飼ってるんじゃなくて・・・」
「でも父さんがオスカルの世話をしてる。オスカルは父さんがいないとなんにもできない。ベベと一緒だ。」
「だから言ったろう。あれはだな、しないだけであって本当は何でも出来るんだって・・・」
「だけどこの前、オスカルは言ってたよ。父さんがいないと何も出来ないって。」
「あ、あれはだな・・・・」
「オスカルは言った。」
子供は言った。 父親は困り果てて子供を見た。
「この話は今度時間がある時しよう。それと、今度作文を書く時は、学校へ持っていく前に必ず見せるんだぞ。いいか、必ずだぞ。分かったな。」
「うん、分かった。」
「よし!」
それだけ言うと父親は部屋を出て行こうとしたが、思い出して子供に尋ねた。
「この作文の最後にお父さんみたいになりたいって書いてあったよな。あれって本当か?」
子供は申し訳なさそうな顔をすると目を伏せて 「・・・少しだけ。」 と答えた。
父親は優しく微笑むと子供の頭を撫でた。
「少しでも、父さんはうれしいな。」
子供は顔を上げると、 「オスカルのことじゃなければ全部父さんみたいになりたいと思う。」 と答えた。
父親は笑うと、子供を抱きかかえて頬にキスをした。子供は父親を睨んだが何も言わなかった。
「ありがとう、アキラ。父さんはすごく嬉しいぞ。」
父親はそれだけ言うと、子供を降ろして急いで部屋を出て行った。
子供は少しだけ寂しげな様子で父親の出て行った扉を見つめた。
その時“ベベ”が子供に鼻をすり寄せたので、子供は笑って犬を撫でた。
「ベベ、ぼくはオスカルみたいに泣き虫でも甘えん坊でもないんだぞ。父さんと同じ男なんだからな。」
| back |