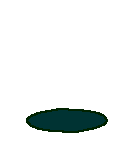
店内は思いのほか明るく広々としており、数組の客がすでに席についていた。入り口を入ったところからカウンターを隔てて調理場があり、働く調理人の姿が丸見えである。カウンターの反対側、湖に面した部分が食堂である。大小のテーブルがいくつか配置され、天井まで届く大きなガラス窓に面して食事できるように工夫されている。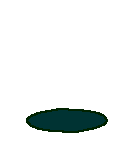
湖に向いた眺望窓に接した3つのテーブルのうち、両端はすでに先客に占領されていたため、真ん中の二人用の小さなテーブルに案内された。最初は窓を背に、顔を調理場の方に向けて座ろうとしたが、これではせっかくの湖が見えない。そこで、湖に正対する方の椅子に座り変えた。
窓の外を見渡せば、眼下の芝生のすぐ先から湖が始まっており、その湖面の中の向こう岸に近い部分には右側から濃い緑色にけぶる低い半島が長く突き出している。晴れてはいるものの、多少の雲が風に乗って、ちぎれたり伸びたりしながら、ゆっくりと北の方に流れている。
皿数こそ少ないものの料理人の創意を感じさせる品書きを見ながら注文を終えるのと同時に、両側の客の会話が耳にはいってきた。自分から見て右側は、中年女性が主体の7人のグループ。左側は、2人の母親と2人の子どもという取り合わせ。7人組の方はリレーでもするかのようにひっきりなし誰かが紙巻きタバコを吸い、互いに声高にフランス語で話をしている。幸いなことに煙はあまりに当方に流れてこない。一方、4人組の方の会話はは基本的にスイス・ドイツ語で、小学校低学年相当の年齢の子ども同士で話すときだけフランス語である。
そういえば、このあたりはスイスの中でもフランス語圏とドイツ語圏(スイスの彼らの話す言葉も仮にドイツ語に含めるとして)の移行するあたりのはずである。普通、二つの言語の境界を越えて旅を進めるときには、所持金の両替とかパスポートの確認だとかに気を使うものであるが、ここではそれがない。国境がないからである。言語境界線の向こうもこちらも、食事の勘定はスイスフランで払えばよい。物価も同じ、車の制限速度も同じである。斜面に沿って葡萄畑が這い上がる風景も、取り立て変わり映えしない。言語境界線のあちら側も、こちら側も、欧州の一部でありながら欧州共同体の外側という、同じ境遇の土地である。
スイスという国の形をよくよく考えてみれば、その国境線が言語境界線をも兼ねているのは、スイス南西のグラウビュンデン州(フランス語ではグリゾン州)がイタリアと境を接する、スイス国境全長に対すれば比較的短い区間だけである。この山深い州ではレト・ロマンシュ語とスイス・ドイツ語を話すので、イタリア語を話すイタリアとの間で言語境界を構成するのである。それ以外のスイス国境はといえば、フランス語圏であるスイス・ロマンドはフランスと国境を接し、イタリア語圏であるティチーノ州はイタリアに接し、スイスの政治経済の中心であるスイス・ドイツ語圏の諸州はドイツと国境を接しているので、言語の段差によって国の輪郭が浮かび上がるような仕組みになっていないのである。もっともグラウビュンデン州とイタリアの国境ですら、果たして言語境界といってよいものやら。なぜなら、国境の向こうのイタリアのその付近はオーストリアからイタリアに割譲された地域で現在でも自治州になっており、住民はドイツ語を話すことが認められているからである。
こういった地理的事情に加え、スイスの国語の一つではあっても公用語にはなっていないレト・ロマンシュ語がドイツ語とイタリア語のある種の移行型であることを思い返せば、そもそもスイスという国自体、言語によって国の輪郭が規定されているのではないとみて、ほぼ差し支えない。
ではいったい、スイスという国の形を縁どるものは何であるのか。その目に見えないものは、いったい何か。
ここまで漠然と考えを巡らせたとき、給仕が一皿目の牛の骨髄入りスープを持ってきた。ついでに彼氏を捕まえ、この土地はフランス語圏かドイツ語圏かと問うと、ここはどちらかと言えばドイツ語を主に話すようだ、という答えが戻ってきた。そういえば、この給仕は、先ほどから、右側のテーブルにサービスするときにはフランス語で、左側のテーブルにサービスするときには地元のドイツ語でと、器用に言葉を使い分けている。おそらくこの付近の住人は、ほとんどが本格的な二重言語話者なのであろう。
行儀が悪く褒められたことではないが、スープを食べ終えた後の間を利用して、手元の旅行案内を開いた。その付録の地図によれば、眼前に広がるビール湖(フランス語ではビエンヌ湖)は正に言語境界線上に位置している。地図の上では、裏手の山を含めて周囲の土地全般はフランス語圏を示す黄色に塗られているももの、湖の西岸に沿って非常に細長く紫色の舌が伸びており、ドイツ語圏がビールの町からこの村まで下ってきているのを示している。いわば、7人組が煙草をふかしている右側のテーブルこそがフランス語圏の北限であり、4人組のいる左側のテーブルがドイツ語圏の南限なのである。そして窓の外の美しい風景を眺めながら僕が食事しているテーブルの中心を、目に見えない言語境界線が東西に通過していることになる。
よく注意してみれば、この食堂の料理こそ、北と南の移行型である。先ほどのスープはどちらかというとドイツ語圏の料理であるが、今、目の前に運ばれてきた混合サラダは、フランス語圏でクリュディテと呼ばれる、食べやすく加工した生野菜の盛り合わせであり、フレンチドレッシングと相俟って、ついついパンが進んでしまうという代物である。比較的上等の白ワインは地元産のものであるが、ジュネーブからローザンヌあたりで産するワインのようにすっきりしていながら、ある種のドイツの白ワインのような芳香もある。要は、料理全体としてみれば、それは美味であり文句の付けようがないのであるが、それはフランス料理でも無し、ドイツ料理でも無し、自らの味の尺度に照らしたとき、誠に素性を特定しにくい代物なのである。
行儀の悪いついでに、今朝ジュネーブで買い求めた新聞をテーブルの上に広げた。日本の新聞で言うと社説に相当するものが載っているページに、元スイス大使と称する人の意見が載っていた。話題は、しばらく前に開かれたフランス語圏諸国会議におけるフランスのシラク大統領の演説内容から始まっていた。この元外交官氏が言うには、英語は言語そのものとそれが媒介すべき文化が分離しているという点で、普遍的言語であるといえるが、フランス語はフランス文化と切り放して考えられない部分が多い。つまり、あるカリブ海の国の作家が英語で小説を書くのと違い、フランス語でものを書いてしまうと、仮に書き手がフランス人でないとしても、その著作はフランス文学に組み入れ、その一部と見なされるようになってしまう。またフランス語とドイツ語を比較すると、ドイツ語で著作するオーストリア人の作家が持たないであろうような葛藤を、フランス語で著作するスイス人は持っているのではないか、というような趣旨であった。
確かに一理ある、と思わせる意見である。かつて、フランスのド・ゴールがカナダのケベックを訪れ、地元市民の独立意識を鼓舞するような発言をしたことがあったし、今でも、ケベック州首相がフランスを公式訪問するような場合には、そこに意図せずして政治的な意味合いが生じるように思われる。それは、ケベックの州旗に未だに白い百合があしらわれているという事情にも起因するが、メキシコの首相がスペインを訪問するような場合とは明らかに状況が異なることは確かである。
スイスの国境が言語境界線と一致していないのと同様、スイスの内部の州境ですら、言語境界線とあまり一致しない。このビール州がそうであるように、フリブール州(ドイツ語ではフライブルク州)も、ヴァレ州(同じくワリス州)も、ドイツ語区域とフランス語区域に跨っている。
こうしてみると、スイス人が国境を意識し、州境を意識するときには、それは言語の違いということではなく、全く別の時限の、何らかの観念上の「違い」が作用している、心理的境界を形成しているのだといえるだろう。
よく知られているように、スイス人は、先ず、町あるいは村という共同体に帰属する。次いで、その共同体の構成員という資格で、ある州の州民という立場が生まれる。そして最後に、ある州の州民であるということから、スイス連邦の国民であるという第三の帰属が生まれる。彼らは、いわば三重のナショナリティを持っている。現代のフランス人やドイツ人がお互いに出身地を尋ねられたときに、私は南の出身だ、とか、東の方からきた、とか言って済ますことができるのと対照的に、スイスでは、何処其処の町の南の谷を上っていったところの村の出身だ、というところまで言わないと、なにか物足りない。
スイス人の頑固なまでの村民意識、州民意識が内に向いた結果としての連帯意識とか完全主義的行動を見ていると、同じ意識が外に向いたときに生じる排他的意識あるいは自己疎外感ともいうべきものは、自然に理解できる。ミューラーという監督が撮った「山の焚き火」というスイス映画があるが、あの主人公達の病的ともいえる感性は、スイスの民の性質を最も濃縮して表現したものであろう。私はスイス人が他の民族に比べて異常なのであると言いたいのではない。世界中の多くの地域の民は、交通手段が現在ほど発達していない時代にあっては、多かれ少なかれスイス的な感性を共有していたのではないか。人間が長い歴史の間、肌身離さず携えてきたその感性は、多くの場合、失われ、あるいは失われつつあるけれども、スイス人の心の奥底には、それを今も垣間見ることができるように思われる。それに後進性とか、山国根性とかいう負の評価を与えて非難することは容易であるけれども、それでは簡に失するように思われる。
 スイスは、言語的多様性と宗教的多様性を、歴史を通じて克服したかのように見える。本来であれば、相互不信の十分な理由、互いに殺し合うだけの十分な理由になり得る差異を自らの中に包含しつつ、平和と繁栄を享受している。
スイスは、言語的多様性と宗教的多様性を、歴史を通じて克服したかのように見える。本来であれば、相互不信の十分な理由、互いに殺し合うだけの十分な理由になり得る差異を自らの中に包含しつつ、平和と繁栄を享受している。
スイス人は、自らの国家の歴史が、現在進行中の欧州統合に一つのモデルを与えたと信じている。実際、その通りであろう。しかしながら、そのスイスの中の熾き火は本当に消えてしまっているのであろうか。それとも、かつてフランス語圏のジュラ州がベルン州から独立したことに端的に示されたように、言語や州境の違いといったものは底辺を脈々と流れているのであろうか。多言語・多民族・他宗教の旧ユーゴスラヴィアが血を流し、その流血を止めることができずにもがき苦しんでいる欧州の姿を、現在、スイス人はどのように眺めているのだろうか。
スイスとは何か。それは私にとって、永遠の謎であるように思われる。
(1996年5月初稿:1999年4月加筆・改題)