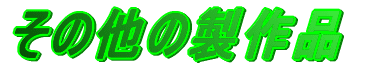 |
|---|
| ここでは、ジャンルがはっきりしない「その他」の作品について紹介します。 |
| わが家のテレビ今昔物語 テレビがテレビ台に化けちゃった、というお話(高校2年頃) |
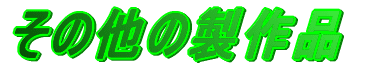 |
|---|
| ここでは、ジャンルがはっきりしない「その他」の作品について紹介します。 |
| わが家のテレビ今昔物語 テレビがテレビ台に化けちゃった、というお話(高校2年頃) |
| 家に初めて白黒テレビが入ったのは昭和30年代末期と思われる(記憶がない)。当時の標準的なスタイルともいうべき「金属ケース入り、4本足」の早川電機(現シャープ)製真空管式(17インチぐらい?)だった。どこかの親類から譲り受けた中古のようでよく故障したがその頃のわが家は経済的に楽な状態ではなく、壊れるたびに、近所の電気屋に来てもらい修理して使っていた。テレビ番組はちょうど白黒からカラーへの転換期で、カラー番組の冒頭には「カラー」という字幕が入っていたが、白黒受像機で見れば当然白黒のままで、「画面にカラーって書いてあるのに、何でカラーで見えないんだよ!」と子供心によく思ったものだった。 家にカラーテレビが入ったのは、それからだいぶたった小学2年のとき。きっかけはその半年ほど前に、向かいの家がカラーテレビを導入したことに違いない。(わざわざ見に行ったのでよく覚えている) 当時のカラーテレビのCMの中には「隣のテレビにゃ色がない、うちのテレビにゃ色がある」というのがあって、近隣との競争心を煽って売り込もうという露骨な商魂がまる出しのものがあった。 ついでに言うと、そのころNHK総合テレビで、16時05分から「受信相談」という番組があって、(なぜ正確に時間を覚えてるかというと、番組のテーマソングが「よじごふん、よじごふん・・・」という詞で始まっていたから)番組では、「カラーテレビにはカラー用アンテナを」としきりに宣伝していた。そのカラー用アンテナというのがまた、「色のついた」アンテナで、中には赤・青・黄の3色に塗り分けたキワモノもあった。勘のいい人ならわかると思うが、当時NHKの受信料は「普通(白黒)契約」と「カラー契約」の2本立てで、当然「カラー」のほうが高い。NHKに「うちはカラーにしました」と喜んで連絡する人はあまりいないだろうから、NHKの集金人がカラーテレビのある世帯を見分ける画期的な方法として考えたのが、アンテナメーカーや販売店と協力して、「カラーテレビはカラー用アンテナに取替えないときれいに映らない」と視聴者に思い込ませ、色つきのアンテナを屋根に上げさせて、短期間でカラー契約を増やすのに一役買ったのである。 「幸福の黄色いハンカチ」という映画があったが、NHKにとっては、「幸福の色つきアンテナ」だったろう。 余談はさておき、わが家にとって最初のカラーテレビは「ナショナルパナカラー、型番TK510DU(19インチ)」だった。19インチというのは現在なら小型テレビの部類に属するが、当時のカラーテレビは19インチといえどもキャビネットがすごく大きく、120cm四方ぐらいはあった。カラーテレビ=調度品という時代であり、木製の豪華な家具調のキャビネット(実は飛騨地方の地場産業でつくられていたという)で、まさに一家のステータスシンボルと呼ぶにふさわしかった。 この初代カラーテレビは私が高校2年の時までだから、通算9年使ったことになる。今から考えるとちょっと短いようだが、この機種は真空管が27本、一部トランジスタという玉石混交で、消費電力は310Wも喰った。昭和40年代というのはテレビ番組がどれも面白くて、結構長時間見ていたから、当然真空管がボケてくる。そのうち画面が暗くなる、色が付かなくなる、同期が合わなくなるといった症状が出てくる。その都度買った店の修理技術者、Oさんが修理に来てくれた。この人はとても優秀な方で、私も彼の修理する姿から多くのことを学ばせていただいた。のちにOさんは独立して電気店を構えた。(そんなわけで、うちの家電はほとんどそこで買っている。) しかし高校2年の時、とうとう三原色の「青」が出なくなった。ちょうどテレビの勉強をしていた時だったので裏ブタをあけて見ると、ブラウン管のヒーター3つのうちひとつが点いていないではないか。これを直すにはブラウン管の交換しかない。しかし買ってから9年も経過して補修部品はもうないだろうし、2度の石油ショックを経験したので、もうこんな「大飯喰らい」とはオサラバしたい。 ということで、修理はあっさりあきらめ(情けない!)、2代目(ナショナルパナカラー、22インチ、型番は忘れたが「クイントリックス」のCMで一躍有名となった機種。もちろん半導体式)に買い替えとなった。 しかしそれまで使っていた家具調パナカラーはキャビネットがすばらしく、このまま捨てるのは惜しい気がしたので、下半分と天板を「テレビ台」という形で再利用することにした。テレビが完全に半導体化された昭和50年代以降、大きなキャビネットは必要なくなり、コストダウンのため足を省き、テレビ台を別に用意して載せるという方針に変わったので、どうしても台が必要となったからである。しかしその頃の市販のテレビ台なるものは安っぽいものばかりで、古風な我が家の茶の間にはマッチしなかった。これなら自作したほうが重厚なものができると確信した。もともと木工はあまり得意ではないが、電子工作のできる環境も整っていなかった当時の私にとっては工作欲を満たす唯一の素材だった。「真空管パナカラー」の中身は使えそうな部品は外し、あとは細かく分解して廃棄した。40KG6Aという水平出力の球や、450V耐圧のケミコンなどは送信機に使えそうなので保存してある。電源には贅沢にもチョークを2個使用してあったので、これは真空管アンプの製作に役立てた。 |
| 結局このテレビ台は、カラー2台目の「クイントリックス」で約15年、カラー3台目は、「National」から「Panasonic」ブランドに変わった「画王(がおう、27インチ、BS対応)」で、これは18年以上使用し(このブラウン管テレビは画質音質とも素晴らしく、まだまだ使えましたが)、2011年、例の悪名高い「完全地上デジタル化政策」によってデジタル受像機への買い替えを余儀なくされ、それでもぎりぎりまで粘ってだいぶ値段が安くなってから、37インチ液晶画面、LEDバックライトの「VIERA(ビエラ)」に買い替えました。 このとき、ひとつ問題が起こりました。自作のテレビ台にはビデオレコーダ等を収納する場所がありません。ブラウン管式ならテレビの上にもなんとか置くことができました。ところが薄型テレビは上に何も置けないのです。実際、テレビと一緒にブルーレイの録画機も買ったのでこれの置き場所に困りました。VHSビデオデッキに比べると小さいものなので、台を改造して中に収納することも考えましたが、なんだか面倒くさくなって、結局テレビと録画機に合わせてテレビ台も新調してしまいました。 というわけで、初代カラーテレビの外枠から作った自作テレビ台は33年間も使用してとうとうお払い箱となりました。現役のテレビだった期間も含めると実に42年間もわが家の茶の間に置かれていたことになります。真空管式パナカラーTK−510DUはそんなすばらしいテレビでした。長い間お疲れさまでした!(おしまい) |
|---|