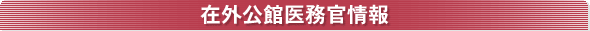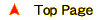旅行者医学ガイド
旅行者医学ガイド
 SARSを新規に追加しました。
SARSを新規に追加しました。
Traveling Doctorとして、この分野だけはやはり解説しないわけには行かないだろうということで、このコーナーを作ることにしました。
一般的に言われている俗説が、本当に正しいのか?
必要以上に危険をあおっているものもあれば、いい加減で危険なものもあるように思われます。
実際に、旅行をしている旅行者の目から、これらの常識を医学的に解説してみたいと思います。
但し、これはあくまで医師でもある一旅行者の見解ですので、私の言うことを鵜呑みにして、不利益を得たとしても、一切責任は取りません。
また、私は全ての病気に関して詳しい知識、経験をもっているわけではなく、なかには成書などを見て書いた記述もあります。
ですから、あくまで参考にするにとどめ、実際はご自分の責任で行動してください。
予防接種
 現在、入国に際して予防接種が義務付けられることがあるのは、黄熱病だけです。
接種証明書を必要とする国は、ベニン、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ、コンゴ、コートジボアール、
フランス領ガイアナ、ガボン、ガーナ、リベリア、マリ、ニジェール、ルワンダ、サントメプリンシベ、トーゴ、旧ザイールなどです。
現在、入国に際して予防接種が義務付けられることがあるのは、黄熱病だけです。
接種証明書を必要とする国は、ベニン、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ、コンゴ、コートジボアール、
フランス領ガイアナ、ガボン、ガーナ、リベリア、マリ、ニジェール、ルワンダ、サントメプリンシベ、トーゴ、旧ザイールなどです。
黄熱は発症すると、致死率60%ですので、ワクチン接種は行う方が良いでしょう。
ワクチン接種できる場所はイエローカードを発行できるところに限られており、予約をする必要があったりします。
曜日も決まっていたりしますので、事前に調べておく必要があります。
コレラは、現在流行しているコレラ
はエルトール型で、致死率は1%以下であり、予防接種の有効率が50‐60%で有効期間も数ヶ月であることを考えると、
接種する意味は少ないでしょう。
A型肝炎は、不活化ワクチンがあり、有効期間は15‐20年と長いです。
40歳以下の日本人は抗体陰性者がほとんどですので、先進国以外を旅行する場合、接種することが望ましいでしょう。
破傷風は致死率30%、全世界で分布しており、受傷する可能性のある場合は、
接種することを勧めます。1回で50‐90%、2回でほぼ100%の抗体陽性率となり、3回で10年以上有効です。
大抵の医療機関で破傷風のワクチンはありますので、最も簡単に接種できるはずです。
狂犬病は日本では全く見られませんが、世界では年間3万人が死亡しています。
致命率はほぼ100%で、野性動物との接触が予想される場合は、接種したほうが良いでしょう。
その有効率は高く、副作用は発熱、発疹などが6%で見られるとのことです。
以下に旅行先別に推奨される予防接種チャートを示します。ご参考までに。(日医雑誌 第124巻第9号p1181より)
|
ワクチン名/派遣地域
|
北米
|
中南米
|
東アジア
|
南アジア
|
中近東
|
アフリカ
|
西欧
|
東欧
|
ポリオ
|
×
|
×
|
△
|
○
|
△
|
△
|
×
|
×
|
ジフテリア
|
×
|
×
|
×
|
×
|
×
|
×
|
×
|
×
|
破傷風
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
日本脳炎
|
×
|
×
|
○
|
○
|
×
|
×
|
×
|
×
|
A型肝炎
|
×
|
△
|
○
|
○
|
○
|
△
|
×
|
×
|
B型肝炎
|
×
|
×
|
○
|
○
|
△
|
△
|
×
|
×
|
狂犬病
|
△
|
△
|
△
|
△
|
△
|
△
|
△
|
△
|
黄熱病
|
×
|
○
|
×
|
×
|
×
|
○
|
×
|
×
|
コレラ
|
×
|
×
|
×
|
×
|
×
|
×
|
×
|
×
|
腸チフス
|
×
|
×
|
○
|
○
|
△
|
△
|
×
|
×
|
髄膜炎菌性髄膜炎
|
×
|
×
|
×
|
×
|
△
|
△
|
×
|
×
|
ペスト
|
×
|
×
|
×
|
×
|
×
|
×
|
×
|
×
|
○:接種が必要、△:場合によっては接種必要、×:接種不要
輸入感染症
輸入感染症とは、日本では本来無いか、もしくは流行していない病原体で、外国から持ち込んで発症した感染症を指します。
こういった病気の専門家は日本では非常に少なく経験も少ないので、日本で治療するより、
経験豊富な現地の医者がいる病院で治療した方が良いことも多いのです。
もちろん、田舎にいるときは、その国の首都に行った方が良いでしょう。
田舎では医薬品も少ないし、優秀なドクターも少ないからです。
旅行者下痢症
 輸入感染症のなかで最も多いのは、下痢でしょう。
東南アジアに旅行した後で下痢が続き、心配して病院に来る人は結構多いけれど、そのほとんどは単なる細菌性下痢で、
整腸剤や軽い下痢止めを飲めば問題のない場合が普通です。
輸入感染症のなかで最も多いのは、下痢でしょう。
東南アジアに旅行した後で下痢が続き、心配して病院に来る人は結構多いけれど、そのほとんどは単なる細菌性下痢で、
整腸剤や軽い下痢止めを飲めば問題のない場合が普通です。
よく海外では生水を飲むなと言われます。
では、生水とは一体なんなのでしょうか?
ミネラルウォーター以外の水を生水としたら、実際、生水を一滴も飲まないで旅行をすることは不可能です。
シャワーの水も、水道の手洗いの水も生水ですし、食材を洗うのも、コップを洗うのも生水です。
熱帯でおいしい生ジュースも生水になります。
では、生水には危険な病原菌が沢山いて、一滴でも飲んだら、すぐ下痢になるのでしょうか?
日本人が海外で下痢をするのは、日本で飲んでいる水が軟水なのであるのに対し、海外では硬水であるのも主な原因なのですが、
それをもって生水には病原菌がうようよいると思っているようにも思います。
歯を磨くにもミネラルウォーター、生野菜は食べず、コップも使わない。
食事は屋台では食べず、高級レストランのみ、というような人はいますが、
これでは、旅行の重要な要素の一つである食の楽しみが制限されてしまい、私は全くナンセンスだと思います。
生魚や傷んだ食材で下痢をするのは外国も日本も同様です。
逆に言えば、火の通ったものなら、屋台の食事でも問題ないわけです。
シャワーを浴びても水を少しは飲むのに、コップについたわずかな洗いの水を気にしたってしょうがありません。
 細菌感染というのは、病原菌と人体の免疫力の力関係によって決まります。
少々病原菌が体内に入ったところで、免疫力がしっかりしていれば、コップについたわずかな菌で必ずしも感染するとは限りません。
細菌感染というのは、病原菌と人体の免疫力の力関係によって決まります。
少々病原菌が体内に入ったところで、免疫力がしっかりしていれば、コップについたわずかな菌で必ずしも感染するとは限りません。
ですから、飲み水に異常に神経質になるよりも、旅行日程などに配慮して、体力を落とさず、
栄養を十分とるようにすることの方がよほど大切だと私は思います。
実際私は、場末の食堂で、水差しの水をコップ一杯のんで食事をするなんてことは数限りなくやってきましたが、
そのために下痢をしたと思われることは一度もありませんでした。
そういったときの基準は、現地の人間が普通に飲んでいるもの、食べているものは大丈夫というごくあたりまえの原則です。
現地の人間でも赤痢、コレラには罹患します。毎日食べている人間が発症しないわけはない。
つまり、通常皆が食べているようなものなら、われわれが食べても、危険な感染症になる可能性は低いわけです。
もちろん、通常の細菌性下痢にはなる可能性はありますけどね。
かえって、旅行者用に特別に作られた贅沢料理の方が私は心配です。というのはそれをモニターする人は皆旅行者ですから。
高級レストランで慣れない食材を使って、少数の人間のためになれない料理をする方が、思いもつかない感染症になる危険が高いのではないかと私は思います。
しかし、実際旅行をしていると確かに下痢をすることはよくあります。
そこで問題になるのは、一体どういうときに病院に行かなくてはならないのか?ということです。
まず、血便がでたら、これは観念した方が良いでしょう。
血便は赤痢の可能性があります。
但し、血便=赤痢ではありません。
ひどい細菌性の下痢でも血便にはなります。
しかし、血便がでるような状態のときは、通常の細菌性下痢でも病院に行ったほうが良いでしょう。
但し、痔のある人、頻回の下痢で肛門が切れた場合は、便に血が混じっていても問題ありません。
見分けるには、便自体が赤黒いのか、通常の便に赤い血が混じっているのかを見ればわかります。
便は普通の色だけど、紙に血がつくというのは、痔、もしくは肛門の出血ですから問題ありません。
血便でなくとも、コレラなどの場合は病院に行かねばなりません。
コレラの場合、「米のとぎ汁様」という典型的な便になるので、容易に分ります。
毒素原生大腸菌の場合も同様の下痢になります。熱は出ないことが多いそうです。
典型的な重症コレラは無処置の場合、24時間以内に死亡するそうですが、
現在世界各地で見られるコレラのほとんどはエルトール型なので、
適切な処置をすれば致死率は1%以下だそうです。よって、さほど恐れる必要はありませんが、早めに病院に行くことを勧めます。
日本に帰ってきてしまった場合は隔離になりますし、滞在場所が全て消毒の対象になりますので、
やはりできるだけ早く病院に受診することを勧めます。
コレラでなくとも、下痢、発熱がひどい場合、脱水になります。
特に熱帯、亜熱帯では簡単に脱水が進行します。
コレラだけでは死にませんが、脱水になると容易に死にます。
ですから、通常の細菌性下痢でもひどい場合は、水分を補給しなければなりません。
しかし、こういう場合、通常水を飲んでもすぐ下痢して吸収されません。よって他の方法で水分を補給する必要があります。
現在ではORSといって、食塩3.5g、塩化カリウム1.5g、重曹2.5g、
ブドウ糖20gを1リットルの水に溶かしたものを飲むのが良いとされています。
これは、スポーツドリンクでも代用が効きます。
但し、重症な場合、口から飲むことすら出来なくなるので、そういった場合は点滴などをする必要があるため、
病院に行ったほうが良いでしょう。
抗生剤の使用はケースバイケースです。症状も無いうちから、予防的に内服するのは、耐性菌を作ることにもなるので、勧められません。
通常のサルモネラ、キャンピロバクター、
腸炎ビブリオなどの軽症の下痢の場合、抗生剤は通常使いません。
中等度以上の下痢の場合、ST合剤(商品名バクター)、ニューキノロン系(商品名クラビット、バクシダールなど)を使い、
アメーバ赤痢などではメトロニダゾール(商品名フラジール)、
コレラではテトラサイクリンを使います。
これらの抗生剤と整腸剤、下痢止めで直らないときは、病院に行く必要があります。
発熱
 旅行中、下痢に伴って、また下痢とは別に高熱が出ることがあります。
単なる熱だけなら、解熱剤で対処すれば、何とかなります。
たとえば、バファリンは市販薬は0.5gで一日4錠までとなっていますが、実際は一日6gまで飲めます。
つまり、市販薬なら1回4錠、一日3回まで可能です。飲み薬で効かない場合、また、飲み薬が飲めない場合、坐薬を使う方法もあります。
インダシンやボルタレンなどの坐薬は即効性があり大抵の熱は下がります。
しかし、特殊な感染症の場合、単に熱を下げてもまたあがるだけで、根本的な治療にはならず、それだけでは命とりになります。
旅行中、下痢に伴って、また下痢とは別に高熱が出ることがあります。
単なる熱だけなら、解熱剤で対処すれば、何とかなります。
たとえば、バファリンは市販薬は0.5gで一日4錠までとなっていますが、実際は一日6gまで飲めます。
つまり、市販薬なら1回4錠、一日3回まで可能です。飲み薬で効かない場合、また、飲み薬が飲めない場合、坐薬を使う方法もあります。
インダシンやボルタレンなどの坐薬は即効性があり大抵の熱は下がります。
しかし、特殊な感染症の場合、単に熱を下げてもまたあがるだけで、根本的な治療にはならず、それだけでは命とりになります。
高熱といって、まず頭に浮かぶのはマラリアでしょう。
なかでも、熱帯熱マラリアは致死的なので、診断が遅れないようにする必要があります。
連日40度以上の発熱が続く場合、可能性が高いので、こういった場合はすぐに病院に行きましょう。
マラリアにはいくつか種類があるので、まず血液の検査をして、
鑑別する必要があります。
もし、自分が行った病院で、血液の検査をしないまま、薬だけを渡されたような場合は、その医者はあやしいと判断して、
その病院は信用しないで、他の病院に行った方が賢明です。
マラリアには汚染地域があるので、
いま自分が汚染地域にいるのかどうかを確認する必要があります。
熱帯熱マラリアの汚染地域はサハラ以南のアフリカ(高度1000m以下で年間降水量2000mm以上)、
東南アジア(特に、ネパール南部平野地帯、インドの農村、インドシナ半島の山間部)と南米(アマゾン流域とエクアドルの海岸線)です。
汚染地域では、地域によって流行している種類が違います。
現在、マラリアはクロロキン耐性などの耐性株が増えてきているので、
素人が適当にマラリア予防薬を選んで飲むのは効果的ではありません。
最も簡単なのは、現地の薬局に行き、勧められる薬を飲むことです。
私はマリではパルドリン、ジンバブエではデルタプリンを勧められました。
薬局では現地のマラリア情報も仕入れられるので、
心配な人は行って聞いて見ることを勧めます。
また、熱帯熱マラリアの潜伏期は3週間以上であり、短期の旅行の場合、
発症は日本になるし、予防薬は入国前から飲む必要があるので、薬を飲むメリットがあるかどうかは微妙です。
少なからず副作用もあるので、私自身は飲みませんでした。
マリのバマコで初日に50箇所以上蚊に刺されましたが、幸い発症はしませんでした。予防薬を飲むことは否定しませんが、
短期の場合、飲まずに蚊に刺されても、必ずしも発症するわけではないわけです。
もちろん長期滞在の場合は、感染する可能性があがります。この辺はご自分で判断してください。
ことマラリアに関しては日本の医者はほとんど経験がないので、
発症して日本に帰ってきても、診断が遅れたり、治療薬が入手困難だったりする可能性が高く、
必ずしも良い治療が受けられるとは限りません。ですから、現地で発症した場合、現地、
もしくはその国の旧宗主国で治療することを勧めます。
他の原因の発熱で、重症化する可能性があるのは、デング熱、
腸チフスなどによるものがあります。いずれも初期は39‐40度の発熱が続きます。
デング熱はヒトスジシマ蚊という蚊によって媒介されるウイルス性疾患です。
東南アジア、インド、中米などで見られ、熱発した後に出血傾向となりショック死するという経過をたどることがあります。
私はスリランカの病院で患者さんを見ましたが、ウイルス疾患なので、特効薬はなく、入院しても、
点滴をしながら対症療法をするだけです。
したがって、感染しないようにすることが重要であり、そのためには、蚊に刺されないようにすることしかありません。
腸チフスは潜伏期が8‐10日、1‐2週間でバラ疹という発疹がでます。
便秘にも下痢にもなり、治療しない場合は3‐5週発熱が続き、昏迷状態となり、時に致命的になります。
法廷伝染病ですので、日本で発症した場合はすぐ病院に行かねばなりません。
これらの伝染病は、疑わしいときは必ず病院に行くことが必要です。
通常の下痢などの感染症に伴った発熱に関しては、細菌性の発熱ですので、高熱の場合抗生剤などの内服を勧めます。
抗生剤の種類は、下痢の場合と同様で、ST合剤やニューキノロンなどがお勧めです。
肝炎
 旅行者で問題になる肝炎は、A型肝炎です。
A型肝炎はウイルスでうつる肝炎で、経口感染、
つまり、汚染された水や食べ物を食べることにより感染します。
臨床症状は、一般に風邪症状(発熱、食欲不振、倦怠感)で発症しますが、その後、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)になります。
A型肝炎は重症化して、劇症肝炎になることは少ないですが、
黄疸がでるような状態では医療機関を受診し、しかるべき診断、治療を受ける必要があります。
旅行者で問題になる肝炎は、A型肝炎です。
A型肝炎はウイルスでうつる肝炎で、経口感染、
つまり、汚染された水や食べ物を食べることにより感染します。
臨床症状は、一般に風邪症状(発熱、食欲不振、倦怠感)で発症しますが、その後、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)になります。
A型肝炎は重症化して、劇症肝炎になることは少ないですが、
黄疸がでるような状態では医療機関を受診し、しかるべき診断、治療を受ける必要があります。
日本にはA型肝炎ウイルスが昔はあったのですが、今は衛生環境が改善し、国内ではほとんど感染しません。
従って、若い人で免疫を持っている人はほとんどいないと思われます。
アフリカ、東南アジア、中南米などはA型肝炎ウイルスの感染の危険が高いので、これらの地域に行く場合、
ワクチンを接種することをお勧めします。
A型肝炎という位なので、実はB型肝炎、
C型肝炎というのもあります。
B型もC型もウイルス感染で移りますが、A型と違い、感染は血液を介して起こります。つまり、エイズのように、
感染者の体液、血液が体内に入らなければ、感染することはありません。
逆にいえば、感染者との性交渉、医療機関での針指し事故などで、感染する可能性があります。
B型肝炎は、時に劇症肝炎として死亡することがあり、
劇症化せず持続感染になった場合も将来的に慢性肝炎、肝硬変、肝癌へと進行していきます。
感染者はアジアで2億2千万人、アフリカで5千万人いるそうであり、アジア、アフリカの旅行に際しては十分気をつける必要があります。
C型肝炎は劇症化はしないものの、感染後十数年してから、
肝硬変、肝癌となっていきます。
現在の日本人の肝癌発症の80%はC型肝炎によるものであり、
そのほとんどは輸血によって感染した人たちです。
ですから、通常の旅行をしている分には感染の危険はありませんが、医療機関での針刺しでは感染する可能性があります。
高山病
日本では一番高いところでも富士山の山頂ですから、3000m台です。
しかし、海外旅行では、ネパール、ペルーなど富士山の山頂並みのところに都市があったり、
ボリビアのラパスなどは4000mの場所に空港があるいうところもあります。
そういう場所では、低酸素により、高山病が発症することがあります。
日本語では高山病として一括して扱うようですが、海外では、Alutitude sicknessとAlutitude diseaseに分けており、
前者は低酸素による諸症状を指し、後者はさらに悪化して、脳圧が亢進して脳症を呈した場合を指すようです。
しかし、どちらも低酸素による一連の病態ですから、ここでは高山病として一括して扱うことにします。
高山病に関しては私は今まで二回の経験があります。1回は、キリマンジャロの登山途中、約4000−4800m地点。
もう一回は、ペルーのチチカカ湖、(3850m)からボリビアのラパスにかけてです。
 どちらも気をつけて、ゆっくり高度順応をしようと試みては見たものの、結局だめでした。
これは個人差が大きくて、大丈夫な人は大丈夫ですし、駄目な人は駄目。
体力のあるなしはあまり関係なくて、屈強な若い男がくたばっているそばで、線の細い女の子が平気な場合もあります。同じ人
でも、そのときの体調次第でかかったりかからなかったりするそうで、ベテランの登山者が高山病にかかっているそばで、
初心者の登山者が平気だったりもするそうです。
どちらも気をつけて、ゆっくり高度順応をしようと試みては見たものの、結局だめでした。
これは個人差が大きくて、大丈夫な人は大丈夫ですし、駄目な人は駄目。
体力のあるなしはあまり関係なくて、屈強な若い男がくたばっているそばで、線の細い女の子が平気な場合もあります。同じ人
でも、そのときの体調次第でかかったりかからなかったりするそうで、ベテランの登山者が高山病にかかっているそばで、
初心者の登山者が平気だったりもするそうです。
高山病はひどくなると死ぬ病気ですから、かかったら無理せず、順応するまで寝ているか、
それでも駄目な場合は低地に早く戻るしかありません。
高山病の予防で、一般に良く言われているのは水を沢山飲むということです。
その理由は、脱水になるのを防ぐというのですが、欧米人はそれこそ、がばがばと飲みます。
6‐7リットル飲むように言う人もいますが、これは明らかに過剰量だと私は思います。
余計に飲んでも単にオシッコが増えるだけで意味がないと思います。
脱水を防ぐという意味では、2‐3リットルで十分で、自分のオシッコが薄く量が出ていることを確認すれば十分だと思います。
また、高山病になってしまったら、これは水を飲むどころではありません。
南米ペルーなどでは、コカ茶が効くと現地の人間は言っており、ガイドブックにも書いてありますが、私自身に関しては、
効果がありませんでした。
また、ダイアモックスという利尿剤が効くという言い伝えが欧米人の登山者の中にあります。
しかし、ダイアモックスは医学的にいうと、どうして効くのか不明です。
実際私は、ダイアモックスも飲んでいきましたが、高山病になりました。
私の高山病の症状は、頭痛、吐き気、食欲不振、階段を登る時の動悸、などでした。
頭痛に関しては、ボルタレンと偏頭痛薬であるクリアミンを試してみました。
ボルタレンは頭痛にすぐ効くけど4〜5時間しか効果が続かないのに対し、クリアミンは。ゆっくり効くけど、
継続的に約12時間効くきました。従って、高山病による頭痛にはクリアミンを1日2錠、飲むことを私はお勧めします。
また、薬は頭痛を止めることができますが、食欲は戻りません。
最終的に、高山病の治療は低地に戻ることなので、症状がひどく、薬が効かない時は、早く低地に戻ることです。
低地に戻ると嘘のように症状がなくなります。
AIDS
エイズはHIVというウイルスの感染で発症します。
感染は主に性交渉でおきるので、HIV陽性の人にあっても、必要以上に恐れる必要はありません。
日本では、まだそれ程身近な問題にはなっていませんが、海外では相当数のHIV感染者があり、
その大部分は異性間感染であり、社会問題になっています。
特に、アフリカ、東南アジアなどの売春婦の感染率は高く、公表されている感染率は30‐80%となっていますが、
実際はもっと高いと思われます。従って、海外でその手の人と性交渉を持つ場合は、相当覚悟をした方が良いでしょう。
性交渉を持たなくとも、AIDS汚染地域ではHIVに感染する機会があります。それは医療機関です。
私は、インドでリキシャーに引っ掛けられて、足を怪我しました。
そこで、病院に行って縫うことになったのですが、縫った後、注射をするのに、明らかに回し打ちと思われる注射器を使われました。
幸いHIVには感染しませんでしたが、途上国の医療機関では、まだまだそういったところがあります。
もし、自衛手段を講じるとすれば、自分用の注射器や針を持参するということになりますが、
一歩間違うと麻薬中毒者と思われかねないので、難しいところです。
また、注射の回し打ちでは、B型肝炎なども感染する可能性があります。
AIDSは現在は治療法も進み、直すことは難しいものの、AIDS発症をかなり遅らせることができるようになりました。
ですから、万が一感染した場合、早目に医療機関を受診することが、重要です。
SARS

平成15年4月現在、主に、東アジアで急激に広がっている、治療法のない重篤な呼吸器疾患、重症急性呼吸器症候群(SARS)が、
重大な問題となっています。
4月17日現在、報告数は3389人、内死亡者数は165人であり、死亡率は4.8%。感染すれば必ず死ぬと言うわけではありません。
地域は、日本も含む27カ国に及んでいます。
この報告に関しては、中国の報告数が疑問視されており、1457人という数字はおそらく過小評価であり、
これよりはるかに多い患者数がいるだろうといわれています。
SARSは、コロナウイルスという種類のウイルスにより起こりますが、今のところ効果のある薬剤はないとされています。
症状は、38℃以上の高熱、痰を伴わない咳、息切れと呼吸困難。
レントゲン写真では肺炎の所見が見られ、頭痛、筋肉のこわばり、食欲不振、全身倦怠感、意識混濁、発疹、下痢などが
見られることもあるそうです。
感染は飛沫感染で、感染力はインフルエンザよりも弱いということです。
潜伏期は3-6日ですから、旅行して帰国してから発症ということもあります。
抗生剤も無力であるそうですから、感染予防をすることが最も重要となります。
日本ではまだ1人しか報告患者がいませんから、旅行をしなければ感染する可能性は少ないです。
この際、旅行しないという選択もありますが、それでも旅行をしたいと言う方も多いでしょう。
危険を少しでも避けるためには、どういうことを考えればよいかというと、まず、単なる観光目的の旅行なら、旅行先を検討ことです。
いまのところ、患者の報告数の上位は、中国、香港、米国、シンガポール、カナダ、ベトナム、台湾です。
どうしても、今年のうちにこれらの国に旅行しなければならない事情が無ければ、他の国や地域を旅行先にする方がよいでしょう。
特に、この時期、中国、香港に行くならかなり気をつけた方がよいでしょう。
中国なら、広東省は避けるべきです。北京市も注意をしなければならないですが、出入国が北京の場合が多いでしょうから、
入らないわけには行かない場合も多いでしょう。香港は広東省から本土の中国人が流入してくるので、もちろん危険です。
ベトナムはハノイで集団発生をしているようですから、なるべくホーチミンにいた方がよいかもしれません。
しかし、ベトナム国内で患者が移動している可能性もありますので、ホーチミンが安全ともいいきれません。
どうしてもこれらの国に行きたい場合は、一般的な感染症の感染予防、手洗いを励行する、人ごみを避ける、疲労をためず栄養をとる、
というようなことをするしかありませんが、感染のリスクがあることは念頭におくべきでしょう。
しかし、上記のように死亡率は4.8%ですから、かかれば必ず死ぬわけでもありません。熱発をして風邪症状が出た場合は、
ためらわず病院に行き、早期に治療を開始することが肝要です。
SARSに関しては、今後新しい情報がどんどん出てきて、状況も大きく変わる可能性がありますから、
適宜ご自分で情報を入手するようにしてください。
国立感染症研究所のページなどに情報があります。
以上、海外医療事情に付き、もっと詳細な情報を知りたい方は、下記のページにアクセスしてください。
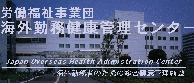
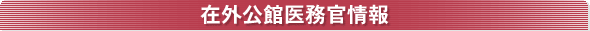
参考文献:海外渡航者の診療ガイド 治療、vol.79、7、1997

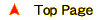
 旅行者医学ガイド
旅行者医学ガイド SARSを新規に追加しました。
SARSを新規に追加しました。 現在、入国に際して予防接種が義務付けられることがあるのは、黄熱病だけです。
接種証明書を必要とする国は、ベニン、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ、コンゴ、コートジボアール、
フランス領ガイアナ、ガボン、ガーナ、リベリア、マリ、ニジェール、ルワンダ、サントメプリンシベ、トーゴ、旧ザイールなどです。
現在、入国に際して予防接種が義務付けられることがあるのは、黄熱病だけです。
接種証明書を必要とする国は、ベニン、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ、コンゴ、コートジボアール、
フランス領ガイアナ、ガボン、ガーナ、リベリア、マリ、ニジェール、ルワンダ、サントメプリンシベ、トーゴ、旧ザイールなどです。
 輸入感染症のなかで最も多いのは、下痢でしょう。
東南アジアに旅行した後で下痢が続き、心配して病院に来る人は結構多いけれど、そのほとんどは単なる細菌性下痢で、
整腸剤や軽い下痢止めを飲めば問題のない場合が普通です。
輸入感染症のなかで最も多いのは、下痢でしょう。
東南アジアに旅行した後で下痢が続き、心配して病院に来る人は結構多いけれど、そのほとんどは単なる細菌性下痢で、
整腸剤や軽い下痢止めを飲めば問題のない場合が普通です。 細菌感染というのは、病原菌と人体の免疫力の力関係によって決まります。
少々病原菌が体内に入ったところで、免疫力がしっかりしていれば、コップについたわずかな菌で必ずしも感染するとは限りません。
細菌感染というのは、病原菌と人体の免疫力の力関係によって決まります。
少々病原菌が体内に入ったところで、免疫力がしっかりしていれば、コップについたわずかな菌で必ずしも感染するとは限りません。
 旅行中、下痢に伴って、また下痢とは別に高熱が出ることがあります。
単なる熱だけなら、解熱剤で対処すれば、何とかなります。
たとえば、バファリンは市販薬は0.5gで一日4錠までとなっていますが、実際は一日6gまで飲めます。
つまり、市販薬なら1回4錠、一日3回まで可能です。飲み薬で効かない場合、また、飲み薬が飲めない場合、坐薬を使う方法もあります。
インダシンやボルタレンなどの坐薬は即効性があり大抵の熱は下がります。
しかし、特殊な感染症の場合、単に熱を下げてもまたあがるだけで、根本的な治療にはならず、それだけでは命とりになります。
旅行中、下痢に伴って、また下痢とは別に高熱が出ることがあります。
単なる熱だけなら、解熱剤で対処すれば、何とかなります。
たとえば、バファリンは市販薬は0.5gで一日4錠までとなっていますが、実際は一日6gまで飲めます。
つまり、市販薬なら1回4錠、一日3回まで可能です。飲み薬で効かない場合、また、飲み薬が飲めない場合、坐薬を使う方法もあります。
インダシンやボルタレンなどの坐薬は即効性があり大抵の熱は下がります。
しかし、特殊な感染症の場合、単に熱を下げてもまたあがるだけで、根本的な治療にはならず、それだけでは命とりになります。
 旅行者で問題になる肝炎は、A型肝炎です。
A型肝炎はウイルスでうつる肝炎で、経口感染、
つまり、汚染された水や食べ物を食べることにより感染します。
臨床症状は、一般に風邪症状(発熱、食欲不振、倦怠感)で発症しますが、その後、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)になります。
A型肝炎は重症化して、劇症肝炎になることは少ないですが、
黄疸がでるような状態では医療機関を受診し、しかるべき診断、治療を受ける必要があります。
旅行者で問題になる肝炎は、A型肝炎です。
A型肝炎はウイルスでうつる肝炎で、経口感染、
つまり、汚染された水や食べ物を食べることにより感染します。
臨床症状は、一般に風邪症状(発熱、食欲不振、倦怠感)で発症しますが、その後、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)になります。
A型肝炎は重症化して、劇症肝炎になることは少ないですが、
黄疸がでるような状態では医療機関を受診し、しかるべき診断、治療を受ける必要があります。
 どちらも気をつけて、ゆっくり高度順応をしようと試みては見たものの、結局だめでした。
これは個人差が大きくて、大丈夫な人は大丈夫ですし、駄目な人は駄目。
体力のあるなしはあまり関係なくて、屈強な若い男がくたばっているそばで、線の細い女の子が平気な場合もあります。同じ人
でも、そのときの体調次第でかかったりかからなかったりするそうで、ベテランの登山者が高山病にかかっているそばで、
初心者の登山者が平気だったりもするそうです。
どちらも気をつけて、ゆっくり高度順応をしようと試みては見たものの、結局だめでした。
これは個人差が大きくて、大丈夫な人は大丈夫ですし、駄目な人は駄目。
体力のあるなしはあまり関係なくて、屈強な若い男がくたばっているそばで、線の細い女の子が平気な場合もあります。同じ人
でも、そのときの体調次第でかかったりかからなかったりするそうで、ベテランの登山者が高山病にかかっているそばで、
初心者の登山者が平気だったりもするそうです。