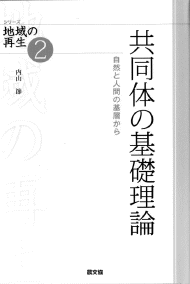HOME>過去号>83号
講演会報告―内山節さん講演会
共同体を「人と自然の関係」から考える
この間、「無縁社会」なる言葉に象徴されるように、私たちは各種の「しがらみ」から解き放たれ、「個人」を謳歌する一方で、「個」が「孤」に陥りがちなことから、人間関係の希薄さ、拠り所のなさ、規範の崩壊など、さまざまな問題に苛まれている。同時に、その半面として、「地域社会」「コミュニティ」「共同体」などへの注目や憧憬も日増しに高まっている。孤立した人間がいかにして共同性を回復できるのか。これは、将来の社会を展望していく上で、避けて通れない課題だろう。この点を考えるべく、当研究所は昨年10月、北大阪商工協同組合、関西よつ葉連絡会との共催で、共同体を積極的に再評価する著作を刊行されて間もない内山節さん(哲学者)にお越しいただき、お話を伺う機会を持った。以下は、その概要であり、構成および文責は当研究所にある。
はじめに
この間、さまざまな場面で「コミュニティ」や「共同体的な関係」の重要性が叫ばれています。ご存知のように、戦後の日本は、自立した個人の社会をどう創るかという方向で動いてきましたが、ここにきて、その限界がいろいろな形で露呈し、「関係作り」「結び合う」「助け合う」、そんな言葉が氾濫する時代になっています。誰もが同じことを言い出すので、何か落とし穴があるのではないか、と疑いを感じてしまうほどです。とはいえ、私たちが互いに結び合う社会を作っていくことが、いま非常に重要な課題であることは間違いありません。問題は、「結び合う」ことの中身をどれほど深めていけるか、でしょう。
実は、私は昨年まで2〜3年間、総務省の系統の災害防止に関する委員会に出ていました。そもそも日本の場合、災害防止というのは防災工学を軸とした工学系の仕事です。私は人文系の人間なので、防災工学なんて全く分からない。その上、政府にあまり好感を持っていません。だから、なぜ私のところにそんな話がくるのか、不思議な気がしました。
そこで話を聞いてみると、最近は災害防止の軸をコミュニティの建設に置くようになっているそうです。考えてみれば、それば一番安上がりな災害防止でもある。このように、国や自治体が言うコミュニティ作りには、行政のコストを安くできるという発想もある。
つまり、私たち自身が生活したり働いたりする中で、このように個人がバラバラになっている社会のあり方はまずいという思いと、国や自治体の側から、いわば従来のシステムでは持たなくなっているところにコミュニティが必要だという問題意識が重なっている。それが、現在のようなコミュニティ重視の時代の背景ではないか、と思います。
実際、個人がバラバラになった社会というのは、個人がシステムに管理されていく社会でもあるわけです。人間は一人では生きていけない。しかし、直接的なつながりや結びつきは薄れていく。となれば、人と人の間は「市場」であったり「国家」であったり、あるいは「企業」であったり、そうしたシステムがつないでいくことになるけれども、それは同時にシステムに管理されることでもあるわけです。
たしかに、最近の風潮としては、何でもかんでも国が手を出すのはよくない、そうした介入を極力少なくして、むしろ私たち自身の方に権限を戻すべきだ、というような議論も増えています。でも、とくに具体的な対策になると、「行政がもっとしっかりやるべきだ」とか、「これは国の課題だ」とか、そうした結論になってしまいがちです。むしろ、本来なら、「対策は自分たちでやる、その予算もよこせ」と言うべきなのに、そうはならない。
結局、システムに管理されながら生きるということに慣れてしまったのかもしれません。とすれば、私たちはそうした状態からどうやって抜け出し、自分たちの世界を自分たちで作り直すかという課題に向かって踏み出さなければいけない。いま共同体という言葉が出てきているのは、まさに自分たちの世界をどう作るかという課題と深い関係がある気がしています。
「共同体」とは何か
私は、最近『共同体の基礎理論』という題の本を農文協から出しました。題名から、大塚久雄さんの『共同体の基礎理論』(1955年)を想い出す方もおられるでしょう。実は、私が初めて読んだ共同体に関する本が、まさにそれでした。当時は教科書的な役割を果たし、長らく歴史的名著とも言われました。ただ、大塚さんの場合、共同体は古くて封建的で、個人の自由もないから、早く壊して市民社会に移行しなければいけないものだ、という観点で共同体が捉えられていたように思います。
また、伝統的な地域共同体は大なり小なり自然と強い結びつきを持っていますが、それについても、「人間が自然に隷属している」とか、「文明を形成できていない」といった捉え方をしていました。自然と人間との強い結びつきは、いまなら肯定的な意見が圧倒的に多いと思いますが、出版された当時は、まさに人間が自然から自立していない証と見られていたわけです。そこで、私としては、半世紀も過ぎると同じ共同体の捉え方がどこまで変わったのか示そうと考え、あえて同じ題名をつけました。
ただ、書き始める際に改めて考えてみると、もともと日本語には「共同体」という言葉はなかったように思い至りました。私の知る限り、少なくとも一般的な言葉ではありません。日本では明治30年あたりに、外国の文献を集中的に翻訳した時代があります。その際に、それまで日本語にはなかった言葉が初めて登場してくるのです。仏教用語なども使って、かなり無理やりに新しく言葉を造るわけですね。
たとえば、「社会」という言葉ができたのも、その頃です。「個人」や「自然」という言葉も、同じように造られました。それまで日本では、「社会」にあたる内容を示す言葉として「世間」が使われていましたが、世間は社会のような構造体ではありませんから、世間と訳すとズレてしまう。そこで、社会という言葉を造ったのでしょう。
「共同体」という言葉も、やはりその頃に造られたと思います。おそらく、元来の日本語では、「まち」とか「むら」という言葉で言い表していたはずです。行政単位としての町や村ではなく「うちのむら」や「おらのまち」。それを、あえて「共同体」という言葉を使うことで、そこにヨーロッパの共同体と同じようなものを見ようとしたわけです。
しかし、そうなると今度は、ヨーロッパの共同体と日本の共同体は果たして同じなのか、という問題が出てきます。私は、両者には大きな違いがあると思います。違いは主に二つ。一つは、ヨーロッパの共同体が人間だけをメンバーとする共同体であるのに対して、日本の共同体は伝統的には自然と人間の共同体であり、決して自然を排除せず、自然を共同体の構成メンバーとしていることです。
たとえば、私たちの伝統的な了解では、「まち」や「むら」と言う場合、それらは自然を含めてできており、決して人間の集まりだけを指しているわけではありません。それは「むら」よりも小さい単位を指す集落とか部落といった言葉でも同じです。決して人間だけの集落や部落ではなく、あくまで自然と人間の空間を指して呼んできたはずです。
その点に関連して、40年ぐらい前、私が上野村に行き始めた頃に聞いて、印象に残った表現がいくつかあります。たとえば、村のおばさんたちは、大きく伐採された森の状態を指して、「あそこの森が悲しげだった」と言うわけです。あるいは、快晴で森の奥まで日差しが届いていた状況を指して、「今日の森は楽しげだった」とも言っていました。つまり、人間と同じレベルで森を表現するような自然との関係があるのです。
それから、もう一つの違いとして、ヨーロッパの共同体が生きている者たちだけの共同体であるのに対して、日本の共同体は死者を含んでいることが挙げられます。死者というのは、要するに、その地域を作ってきた先人たちのことです。先人たちを含めて社会が成り立っており、いま生きている人たちだけには限定されない。それを表現する言葉としては、「ご先祖さまが見守っている」という形になるわけです。
ちなみに、ここで言う「ご先祖さま」というのは、単に我が家の先祖ではなく、我が家も含めて「まち」や「むら」を形づくってきた先人全体を指しています。もともと江戸期以前はそうでした。それが「我が家のご先祖さま」に限定されるのは、江戸時代に幕府が寺に戸籍管理をやらせ、過去帳をつくらせたためです。ただ、そうした感覚が完全に消えたわけではなく、葬式の中では比較的後々まで残ったと言えます。実際、葬式は一般に、亡くなった人の家単位ではなく、地域単位で行われるのが習わしでした。戦後かなり後までその習慣が残った地域もあります。
さて、同じ「共同体」という言葉を使っても、日本の場合には「自然と人間」「生者と死者」の共同体という特徴がある。そうなると、たとえば「自治」という言葉で示される内容も変わってきます。ヨーロッパ社会の自治は、実は原理的には非常に単純です。というのも、生きている人間たちの自治だからです。実際には複雑な問題があるとしても、原理的には人間たちが議論を重ね、自分たちでルールを作り、それを実行に移せばいい。
ところが、日本の自治はメンバーに自然や死者が入っているため、そもそも一筋縄ではいきません。会議をしても、もちろん自然や死者は何も言いませんから、最終的には生きている人間が決定するしかない。ところが、生きている人間たちは自分たちの都合だけでは決定できません。自然や死者の意見を慮って反映させなければならない。考えただけでも困難ですが、その際に重要な役割を果たしているのが、実は祭や年中行事なのです。
というのも、祭や年中行事を通して、自然の神さまを降ろしたり、ご先祖さまにきてもらったりということを、絶えず繰り返していく。それらを通じて、自然や死者を身近に感じ、その意見を配慮する。だから、日本の祭や年中行事は決して単なる神事でもイベントでもなく、自治の仕組みに組み込まれている。
それこそ、祭の準備などで人々が集まり、議論することで自治の機能を果たすと同時に、自然やご先祖さまとつながり続ける。それがなければ、日本の自治は成立しない。これは、ヨーロッパの自治を基準にすれば、はなはだ曖昧かもしれませんが、だからといって日本には自治がないわけではない。むしろ、日本の自治は非常に複雑だということです。もっとも、祭がイベント化し、年中行事が衰弱してしまった今日の状況を見ると、その中でどのように自治ができるのか、非常に深刻な課題だと思います。
人間と「共同体」の深い関係
ところで、そもそも人間はなぜ共同体を必要としてきたのでしょうか。実は、これは人間の本質と深く関わっているように思います。従来の公式見解では、人間の本質は知性です。つまり、人間に知性があり、知性を働かせて道具をつくったり文明をつくったりできたために、いわば生物界の頂点に立ったわけです。これは、極めてヨーロッパ的な考え方と言っていいでしょう。たとえば、デカルトの「我思うゆえに我あり」は、すべての物事は疑えるけれども、それを考えている私が存在することは疑えないという意味です。言い換えれば、知性こそが人間存在の本質だと言っている。ここからヨーロッパ近代の思想や歴史がつくられていった。だから、基本的に知性中心主義、人間中心主義なのです。
しかし、むしろ私は、人間という生き物が生物界において極めて弱い生き物だったことに着目します。実際、人間は他の動物に比べて、感覚器官も身体能力も繁殖力も、どれを取っても突出したものがありません。むしろ、劣っていると言ってもいい。そんな生き物が、なぜ生き延びてこられたのか。それは結局、自然との間や人間同士で多様な関係を結ぶことができたからだと思います。つまり、関係の多様さこそが人間を作り出したのではないか、ということです。
自然との関係で言えば、たとえば牛の場合は、草さえあればあれだけの身体を作る能力を持っている。ところが、人間は草だけではダメで、穀類であれ肉であれ魚であれ、さまざまなものを食べないとやっていけない。また、動物たちは地面に落ちているものや腐りかけのものを食べても大丈夫な力を持っていますが、人間はウイルスにも弱いし菌にも弱い。火を使って料理したり、そもそも食べ物を調達するにも道具を使ったり集団作業をしなければできない。つまり、自然との間にそうした多様な関係を作らなければ、人間は人間として生きていけず、そうした多様な関係を作っていくうちに、他の動物とは違う人間らしさ、つまり人間の本質が生まれたと言えるのではないか。
他の動物たちは、人間のように多様な関係をつくらなくても生きていける。だから、必要な部分での反応や頭の回転は大したものだけれども、必要としない部分については基本的に捨象しています。しかし、人間は直接生存と関係ないことにも関心を持ったり、自分たちの世界に取り込んだりしてきた。そのようにして多様な関係をつくらないと生きていけないからです。人間の知性は、むしろこうした過程でできてきたように思います。
目的としての「共同体」
ところで、いまコミュニティや共同体といった言葉が多用されるようになっていますが、その背後には、コミュニティや共同体を作ると何かいいことがある、何かの役に立つというように、コミュニティや共同体に「機能」を求める意味合いが感じられます。たとえば、独居老人が孤独死したけれども、コミュニティがあれば少しは状況が違ったはずだ、とか。もちろん、そうした指摘は間違いではありませんが、それはあまりにも機能論的なコミュニティ論だと思います。果たしてコミュニティや共同体は、必要に応じて引っ張り出してくるようなものでしょうか。私としては、それよりも、人間の本質そのものが多様な関係を必要とするというところから、コミュニティや共同体を捉え直した方がいいのではないかと考えています。
欧米では、1917年にマッキーヴァーが『コミュニティ』という本を出したあたりから、次第にコミュニティに関する議論がなされるようになり、最近ではアメリカのパットナムなどのようにコミュニティを「ソーシャル・キャピタル(社会資本)」として捉える議論が盛んです。つまり、コミュニティの存在そのものが非常に有効な資本であるという位置づけです。実際にアメリカでは、コミュニティのない人たちに融資した場合には焦げ付く可能性が高く、コミュニティのある人たちは焦げ付きが少ないということで、こうしたコミュニティ観が投資基準に利用されています。
これは極端な例ですが、こうした機能論的なコミュニティ観は、今日のコミュニティをめぐる論議に多かれ少なかれ共通していると思います。もちろん、それはそれで一定の有効性はありますが、私としては、やはり機能論一辺倒ではなく、人間の本質というところで位置づけたいと考えています。
そこから現在の状況を、あるいは現在に至る近代化の歴史を見ると、それは人間が多様な関係を自ら切り捨て、徐々に個に向かっていったものと見ることができます。言い換えれば、それは人間の自己否定の始まりであり、だからこそさまざまな問題が生じ、逆にコミュニティや共同体への要望も高まっているということです。
ちなみに、マッキーヴァーの定義によると、アソシエーションはある目的に基づいて人々が作った一つの結合体ないし組織体ですから、人為的に作ることができます。ところが、コミュニティは生まれてくるものであり、人為的に作ることができない。これが自分たちの共有された世界だという感覚が発生したときに共同体になるのだから、その意味ではコミュニティを作ることは不可能なのです。
では、人間はコミュニティが生まれるのをただ待っているだけかというと、そうではない。あちこちにアソシエーションができると、コミュニティが生まれるのも早くなる。コミュニティそのものは人為的に作れないけれども、アソシエーションができることでコミュニティができる可能性も高まる。マッキーヴァーはこのように捉え、この見解は社会学の中で踏襲されてきました。
ただ、マッキーヴァーのようにアソシエーションとコミュニティを区別しなければならないのかどうか、疑問もあります。私は、コミュニティというのは二重概念だと思っています。一つ一つの小さいコミュニティも、それが積みあがっている状態もコミュニティです。人間が何らかの概念に沿って意図的に作ったものなら別ですが、コミュニティは気がついたらできているようなものです。それに対してわざわざ概念規定する必要があるのか、というのが正直なところです。
要するに、自然にあったものをどう見るかということですから、見方はいろいろあっていいのではないでしょうか。ただ問題は、そうした見方によってどんな結論が出てくるかということです。マッキーヴァーの場合、コミュニティは作れないけれどもアソシエーションは作ることができる。アソシエーションを作っていけばコミュニティが早く生まれる。そうした形で一つの社会像を構想したのだから、それでいいわけです。
いま、国や自治体の側から言われているコミュニティ作りは、まさしく機能論的なコミュニティ論ですが、私たちが、やはり自然との関係や人間同士の関係が重要だと言う時の関係性とか、コミュニティとか共同体というのは、むしろ人間の本質の回復という面を持っていると思います。手段としてではなく目的としてのコミュニティ、共同体、多様な関係。それがなければ、我々は自らを否定することになる。その目的に向けて、これからどういう社会をつくったらいいか、そうした筋道で物事を考えたほうがいいと思っています。
こうした視点からすれば、共同体を作ってきたのは個々の人間ではない。むしろ、人間と自然との関係、人間同士の関係、その多様な関係こそが共同体を作ってきたと考えられる。だから、いまコミュニティや共同体の重要性が叫ばれながら簡単に再生できないのも、ある意味で当然です。それは、作る主体を個々の人間に求めているからです。もちろん、小さな関係は作ることができます。ただ、その関係がさらに関係をつくるような、多様な形で重なっていかないとダメです。多様な関係が重なっていったときに初めて、そこに共有された社会ができている。それがコミュニティであり、共同体だと思います。
「共同体」のイメージと実際
この点に関連して、これまで私が何度も直面してきた反応があります。私は一年の半分ほどは上野村にいますから、コミュニティとか共同体という言葉を使うと、「上野村ならそうでしょうけど……」と言われます。たしかに上野村は山奥の僻地で、都市部とは隔絶されてきました。いまでも最寄りのコンビニまで、車で往復1時間半かかります。そんなところだからこそ伝統的な共同体が残っていると思われ、「上野村はいいでしょうけど、都市部はそうはいかない」となるわけです。私はそれに対する答えを模索しながら、ある時、そもそも共同体の捉え方に大きな誤解があるのではないか、と思い至りました。
たとえば、先ほど触れた大塚久雄さんの共同体論は、ある地域に構成メンバー全員が鎖でつながっているようなイメージで共同体を捉えています。その後1970年代あたりから、たとえば玉城哲さんや森田志郎さんたちによって、大塚さん流の共同体論に疑問が投げかけられ、一定の留保をつけて、あるいは全面的に、共同体を肯定する見解が現れました。いまは、むしろ肯定論の方が多いかもしれません。しかし、実は否定論も肯定論も、一つの地域に構成メンバー全員が結びつけられた状態として共同体を捉えていたと思います。
ところが、上野村にいると、そうした見方は実態から外れていると分かります。たとえば、私が上野村で暮らしているのは、8軒しかない山奥の集落です。しかも、人家は一ヶ所に密集しているため、8軒は家族といってもいいほどの関係にあります。それこそ、夕飯を作るのが面倒臭い時に、隣に行って「お腹すいた」と言えば、「あり合わせでいいか」とか言いながら食べさせてくれる。そのさらに隣でも同じです。
これは、非常に強い共同体と言えますが、そうした関係が共同体のすべてかと言えば、そんなことはありません。たとえば、上野村は明治に、江戸期の村が七つくらい一緒になってできました。江戸期の村というのは、だいたい歩いていける範囲です。いまでも、その範囲で物事を決めないと都合が悪いことがある。この範囲での関係は、日常生活で言えば、集落よりも希薄です。しかし、それでも常に助け合うような仕組みはある。その意味では、一つの共同体が形成されており、私は普段、二つの地域共同体を感じながら暮らしています。
ところが、たとえば道路のように、さらに大きい範囲で決めなければならない問題が出てくると、上野村という括りが必要になる。そのときには、上野村として一つの共同体が形成されるわけです。上野村は人口1400人しかいませんが、日常生活では江戸期の村よりさらに希薄な関係にならざるを得ません。日常レベルでは、やはり関係は小さい単位に向かって濃くなっていくのは間違いありません。
ところが、共同体は、実は地理的な範囲にとどまりません。上野村は林業が盛んですから、林業者の共同体をはじめとして、いくつもの職能別の共同体があり、かなりの結束力を持っています。それ以外にも、お寺の檀家の共同体、神社の氏子の共同体、あるいは念仏講の共同体とか、実に多様なものがある。それらは、ある場面では主軸の役割も果たします。また、構成メンバーが困っているときには、ほとんど無条件に助け合う気風を持っています。
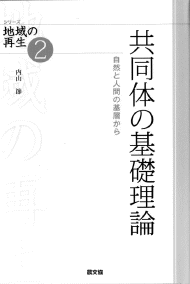
●内山節『共同体の基礎理論―自然と人間の基層から』農文協、2010年
被災者と「共にある」こと
【大石】確かに、補助金や交付金、雇用などでがんじがらめにされてしまったところでは、「脱原発」は出てこない。仮にそうした声が主流となり、現実の力となった場合、地域経済は崩壊してしまう。あえて言うなら、原発を続けても崩壊、原発を止めても崩壊、そんな厳しい状況がある。だから、戦後の日本社会全体を捉え返すことなしに、個別原発の問題を語ることはできないと思います。
しかし、都会にいる人々も、ちょっと離れた私にしても、そうした捉え返しの言葉を持っているかと言えば、持っていない。それはやはり、途方もない苦しみを背負った岩手・宮城・福島の人たちから発信されることによって、戦後の、そして現在の日本社会を撃つものとなるはずです。
逆説的に言えば、東北は東京から見捨てられることによって自立の契機を持つことができるのではないでしょうか。そして、私たちはそれに寄り添うことしかできないのではないでしょうか。「日本がんばれ」とか、知ったこっちゃないですよね。
【司会】常総生協では、今回の事態に対して、組合員さんからどんな反応が寄せられていますか。
【大石】初めての事態ですから、組合員さんたちも自分で考えざるを得なません。理事会の立場は、出荷制限や風評被害に抗して生産者を支えるのが前提であり、あとは調理の工夫や家庭での対策で放射性物質の摂取を調整すべきだ、というものです。生産者からくるものは基本的に供給をストップしません。それでも、とくに組合員をやめる人はいないですね。ただ最近、初めてきちんとした反論がありました。大意は、生産者を支えることと何でもかんでも受け取って食べることは違う、というものです。
もちろん、私たちも、現在の野菜はもちろん、今後の肉や米に含まれるであろう放射性物質の年間総量をある程度想定して、公衆被曝の年間線量限度を超えないように考えてはいます。しかし、これは福島の人たちの苦しみをどう分かち合うかという問題として捉えるべきだと思います。できるかぎり安全を守りつつも、生協運動として問われているのは、まさにその点でしょう。だからキャッチコピーなどで「この汚染された身体をもって現代文明を考えないといけないのではないか」と書いています。実際、葉物野菜は一週間で平均の77%くらいに落ちましたが、理事会としての考え方を伝える中で、やがて通常に戻りました。
配送の組合員さんは5000人くらい。店舗利用の組合員さんが2000人くらいいますが、物資支援のために店舗の食品を根こそぎ持って行っても、とくに文句は出ませんでした。むしろ、「ありがとう」と言われたほどです。
いずれにしても、震災の被災者や原発事故の被害を受けた生産者と「共にある」ということがどういうことか、今回の事態を通じて知ることができなかったら、生協の実現しようとしているものは単なるお題目になってしまうと思います。それに、後の世代へ教訓を残すこともできないでしょう。私としては、水俣と賀川豊彦という自らの原点に照らして今回の事態に取り組みたいと思っています。
「多層的共同体」の発見
さらに言えば、村では20〜30人くらいで地域づくりのグループを組んでいますが、そうしたグループもすぐに共同体的になるのです。というのは、狭い村ですから、誰が所属しているか、村中が知っているわけです。東京や大阪なら、隣の人が何をやっているか知らない方が普通かもしれません。しかし、村では参加していない人たちでも、他の人たちが何をやっているか、みんな知っている。
そうなると、誰もが知っている中で活動しますから、メンバーが辞めたりすると具合が悪い。辞めたことが村中にすぐバレてしまうし、事情が不正確に伝わったりすると、あらぬ噂が広まって大変な事態が起きる可能性もあります。何らかの活動をすれば、誰かが抜けたり辞めたりすることは当然ありますが、そのときには非常に気を遣う。どんな理由で抜けたり辞めたりしたのか、誤解が生まれないように村中に口コミで分かるようにしないといけません。
というより、そんな状況ですから、できるだけ抜けてほしくない。そうなると、お互いがお互いの事情を可能な限り尊重するような状態になってきます。だから、全員が必ず一緒にやろうとは言いません。それぞれの都合をそれとなく勘案しながら、できる人はやっていくというスタイルになっていくわけです。
さらに、誰かが困っているときには全体で支援もするし生活も支えるという形になっていきます。つまり、継続できる基盤を全体で支えるということです。たとえば、それが木工を生業にしている人たちなら、売れ行きが悪くて困っているということになれば、メンバーたちは売り先を考える。それは、当人たちが頼んだわけではなく、会議で議論して決めたわけでもない。誰もがごく当り前のように、何とかしようと思い、自分の知り合いに連絡したりして、買ってくれる人を探す。そんな状態ですから、単なる集まりさえ、すぐに共同体的になってしまう。
いかにも「むら社会」のあり方と思われるかもしれませんが、こうした多様な共同体が積みあがっているからこそ、実は「うちのむらは共同体的である」と言い方ができるのです。つまり、共同体というのは、一つのものに全員がつながっている状態ではなく、さまざまな共同体が積みあがって形成された共同体と考えるべきだと思います。
もちろん、そうしたさまざまな共同体の中には、自然と関わる共同体もあります。しかし、その中でも、林業者が自然と結んでいる共同体のあり方と、農民の結んでいるあり方には違いがある。上野村には木工を生業とする人たちがたくさんいますが、そうした木地師たちの自然との結び方も独特なものがあります。木地師たちの場合は木材を通してつながっていますから、山林を通じてつながっている林業者とはズレがある。だから、一口に自然との共同体と言っても、その中にはさまざまな共同体が積みあがっている。その総体を通じて、人間と自然との、人間と人間との関係、それらに基づく共同体が実感されるわけです。
私は、そうした共同体のあり方を、多様な共同体が層をなしているという意味で、「多層的共同体」と表現しています。共同体は基本的に多層的共同体なのです。そう考えれば、都市部でも同じではないでしょうか。村の共同体を、すべてが地域社会につながった状態と考えた場合、都市部の共同体を作ろうとすると、「ウルトラ町内会」のようなものになってしまう。そんな全員参加型の強大な地域共同体のようなものは、基本的にあり得ません。また、仮にできたとしたら、鬱陶しくてたまらないでしょう。
現実は、そうではなく、多様な共同体が層をなしているのです。いわば、コップの中の炭酸水みたいなものです。炭酸水の中にある無数の小さい泡、その一つ一つが共同体なのです。泡の一つ一つを見ると、あまり変化しない泡もあれば、大きくなっていく泡もある。大きくなって分裂する泡もあるし、逆に萎んでいく泡もある。消えてしまうものもある。それでも、コップの中には絶えず同じくらいの泡が詰まっている。
つまり、長く続くしっかりした共同体もあれば、もう少し緩やかな共同体もあるでしょう。だんだん大きくなっていく共同体もあれば、逆に小さくなってしまう共同体もある。ときには、うまくいかずに消えてしまうものもある。それでも、後からいくつもの共同体が現れ、社会全体では常に共同体が詰まっている。だから、都市部の共同体を構想する際も、あちこちで小さな共同体が生まれ、それが積み重なったものと捉えるべきでしょう。
都市における「共同体」の可能性
こうした観点から歴史を振り返ってみると、実は江戸の町は非常に共同体的です。長屋も一つの共同体ですが、それだけではありません。たとえば出身地別の共同体もあります。記録に残っているものとしては、たとえば新潟の農家の次男坊、三男坊たち。江戸には絶えず土木工事があり、労働力が不足気味だったため、いわば出稼ぎにやってきたのです。出稼ぎにきた人たちは、当時は江戸の外れだった四谷のあたりにある安い長屋に集まります。というより、先に新潟から来ていた人たちが元締めとなって、地元から人を呼び寄せるわけです。右も左も分からなくても、そこを訪ねて挨拶すれば、同郷者ということで住まいを斡旋してくれたり、仕事を紹介してくれたりする。
当時は給料は日当で払われますが、全部使わないようにして一生懸命貯める。ある程度貯まってくると田舎の実家に送金する。当時はすでに為替の仕組みができていますから、両替商を通じて送金できました。それを繰り返して、だいたい3年ぐらいすると、地元から、“実は近くで開拓された新田が売りに出されている、お前がこれまで送ってきたお金で買える、だから村に戻ってこないか”という手紙がきたりする。だいたい江戸で3年ぐらい働いた後、郷里に帰って新たに農民として出発するパターンが多かったようです。もちろん、それほど広い農地ではなく、どうにか食えるぐらいでしょうが、そうやって80%ぐらいの人が新潟に帰ったらしい。しかし、残り20%ぐらいの人は、酒や博打に溺れたり、江戸で所帯を持ったりするようになり、江戸の下層民として暮らすという、そんな歴史をたどったようです。こんな共同体があり、もちろん職能別の共同体もある。
あるいは、やはり江戸の町は、当時のような歩きが基本の社会では、自然が遠いわけです。従って、自らの共同体と自然との間を結ぶのか、工夫が必要になります。それが「講」という集まりです。人々は遠隔地の霊山を信仰する山岳信仰の集まりとして講を作り、それによって自然との関係を自らの共同体に持ち込んだのです。しかも、講は自発的に作った信仰集団であると同時に娯楽集団でもあり、月に1回例会を開いては酒を飲んだりしていました。とはいえ、間違いなく助け合い集団でもあります。講は田舎にもありますが、江戸のような都市部の講には田舎とは違った特徴を持っています。それは、お金を使って助け合いをすることです。
田舎の助け合いは、基本的に生産物と労働力の提供です。農家なら、困っている人にお米をあげる。稲刈りのときに病気になった人がいれば、みんなで代わりに稲刈りする。ところが、都市部では仕事がバラバラだし、必ずしも直接生活に役立つものを作っているわけではない。病気で臥せている人にかんざし職人がかんざしを5本もあげたって意味がない。あるいは、かんざし職人が病気だからといって、誰もが代わりにかんざしを作れるわけではない。だから、都市部の助け合いはお金のやり取りという形を取ることになります。
講というのは単なる集まりではなくて、メンバー全員の承認を経た20〜30人という比較的少数の成員からできていることが多い。つまり、信頼できる仲間だけで作られる。都市部の講の場合、メンバーに困った人があれば、たとえば全員が1万円ずつ供出する。そうすれば20〜30万ぐらいが集まるので、困っている人に貸す。なぜ貸すのかといえば、あげると貰った方は負担になるからです。しかも、利息まで取る約束をする。利息はだいたい1割くらいの場合が多いですが、前払いです。つまり、仮に30万円をかすとすれば、実際に借りるのは27万円で返済は30万円。ただし期限はありません。利息が過度に増えるのを防ぐためです。要するに、いつでも30万円を返済すればいいわけです。
でも、困って借りるわけなので、当然ながら返済が苦しい場合もある。あるいは、本人は返そうと思っても、そこそこ時間も経ってしまったし、貸した方は借りた方の暮らし向きを知っていますから、あえて返済を求めない場合もある。しかし、それを直接言えば相手も傷つく。だから気を遣う。ところが、そんな場合に合わせて、講は「代参」という仕組みを持っていたのです。これは、自分たちが信仰している霊山に、借りた者が代表でお参りに行き、全員のお札をもらってくるものです。そうすると、「ありがたいことをしてくれた」というので、借りた者を傷つけることなく借金をチャラにする大義名分ができる。
都市部の共同体の一つの特徴は、実はこうしたお金の有効な使い方にありました。それが顕著に発揮されたのが、1920年代の昭和恐慌の時期です。この時、生活に行き詰まった人々を救うために、人々は信仰という部分を抜きにして、本当に助け合い部分だけで講を作りました。それらは、「無尽」と呼ばれたり、「頼母子講」と呼ばれたり、ただ「講」と呼ばれたり、さまざまな形がありましたが、これもやはり20〜30人の信頼できるメンバーが集まって、仲間内でお金を融資し合うものでした。日本中あちこちで、自然発生的に生まれと言われています。実は、現在の信用金庫の多くは、こうした民衆の相互扶助的な金融を母体にしています。現状からすれば、いつの間にか原点を忘れて単なる金融機関になってしまった、と言わざるを得ませんが……。
ともあれ、こうした歴史をたどってみると、共同体のあり方も、まんざら夢がないでもないと思います。つまり、いろんな小さな共同体をたくさんつくっていけばいい。そうすると、当然にも一人が二つ三つを掛け持ちをする場合も現れますが、それも含めてたくさん講を積み上げることです。内容はどんなものでも構いません。ただし、それが共同体であるためには、一つだけ重要なことがある。それは、メンバーに誰か困った人が発生したときには無条件で助けることです。それがなければ共同体ではない。単なる趣味のサークルです。逆に、それさえあれば、形や内容は問わないということです。
生命活動の系としての「共同体」
私は、もともと社会というのは、自然と人間の生命活動の体系だと考えています。つまり自然の生命活動があり、そこで生まれたものを人間たちの生命活動が加工したりする。そうして、さまざまな生命活動がつながっていく。自然の生命活動と人間の生命活動がさまざまなものが積みあがって一つの体系を作っている。それが社会だと思います。
それをよりよく運営するために、人々は市場を作ったり、貨幣を作ったりする。それ以外にも、いま我々が経済、政治と呼んでいるものも、すべてその生命の系をうまく運営していくための手段だったはずです。ところが、いつの間にか、手段が主人公になって、目的であった部分を圧殺し始めた。それが現代社会ではないでしょうか。
とすれば、私たちはそれをどうやって元に戻すか。つまり、経済も国家も手段の位置に戻して、自然と人間の生命活動の体系を本当の主人公に戻すということが、現在の私たちの課題だと思います。そのためには、まさに生命のつながりが見えるような関係をどう作っていくか。一枚岩のつながりではなく、さまざまな小さな生命の系のようなものをどう作るか。生命の系であるからには、メンバーに困難が発生したときには当然、生命の系自体を維持するためにも、みんなが無条件で助け合うことが必要なはずです。
とすれば、たとえば「お見舞い講」でも作ったらどうだろうか。いまテレビをつけると、「安い掛け金で大きな給付」といったような形で、朝から晩まで保険会社のCMが流れています。しかし、あれだけCMが打てるということは、おそらく多くの人が入っているとしても、掛け金に比べて実は給付は微々たるものでしょう。
そんなものに頼らなくても、たとえば30人で「お見舞い講」を作ればいい。誰かが入院したら、メンバー全員が1万円ずつ無条件でお見舞いを出す。当事者を除いて29万円が集まる。多少の病気なら、それで済むはずです。不幸にして重病なった場合には、一人5万円ずつでも10万円ずつでも決めておけばいい。10万円ずつなら290万円ですから、手術をしても入院しても何とかなるでしょう。あるいは、病人が出ないときにも毎月1000円とか5000円という形で積み立てておく。これで搾取率ゼロの保険ができるわけです。
ただ、現代は人々の移動も激しく定着性がない、実際に信頼できるメンバーを30人集めるのは大変です。とはいえ、我々が少し知恵を使うだけで、一味違った助け合いができるのです。自分はいつも出すばかり、貰うことがないのは健康な証拠。逆に、いつも貰っているのは気の毒なことで、気に病むことはない。非常に人間的だと思います。
私たちがさまざまな知恵を出し合いながら、決して一枚岩の大きなものではなく、小さい共同体を作っていく。それぞれの内容は多様でいい。ただし、メンバーが困ったときは助け合うところは外せない。そんな共同体を作りながら、自然を含めて多様な関係を積みあげていくことが、今後の課題でしょう。その中で、私たちの生命活動がどんなつながりでできているのか、少しずつでも見えていくのではないかと思います。 (終わり)

©2002-2012 地域・アソシエーション研究所 All rights reserved.