

C.G.ユング
僕はユングの本を読んで、より一層芸術に対する好奇心を得るようになりました。そして人間に対する好奇心も覚えます。しかし、この僕の好奇心は、単なる興味本位ではなく、心あるものだと思っています。
ある意味芸術作品は芸術家の見る夢です。さらにその夢は、非現実的なものではなく、むしろ現実社会と密接な関係がある(芸術作品だけではなく個人や社会も)ことを知ると、「作品を鑑賞すること」あるいは、「作品を創作すること」は、単なる道楽でもなければ、現実逃避でもない。それらの意見とは、まったく正反対に位置し大変意義深いことであると考えるようになりました。
これから、ユングの本を読もうと考えておられる方には、是非とも『夢判断』や『精神分析学入門』といったフロイトの代表的な作品からお読みになられることを薦めします。フロイト心理学とユング心理学は、ある意味対立しています。どちらが善い?悪い?ではなく、異なっている部分、変化している部分、を感じながら読むことが、楽しめる秘訣だと思います。
また、僕は心理学者では決してありませんし、日ごろ心理学者のような眼で以って、人や世間を見ようとは思いません。芸術的な感性で人や世間を眺めた方が、ずーっと生きいきとしたものに感ぜられるからです。僕も含め専門家以外の方々は、ディレッタントとしての自覚が必要だと思います。何十冊、何百冊心理学の本を読んだところで、ディレッタントはディレッタントなのですから・・・・・・。
ユングやフロイトやアドラーの本もまた、ニーチェと事を同じくして、「ふ〜ん、そういう考え方もあるなあ。」ぐらいに受け止めた方が、人生は豊かになるような気がします。(何せ僕は、各界の各種論文よりも芸術の方が、芸術よりも自然の方が、断然僕らを幸せにしてくれると思っているんです。)
それでも、僕はユングの本に随分と勇気を与えてもらいました。大変楽しい書物たちです。
「変容の象徴」(野村美紀子訳/ちくま学芸文庫)


第一部『前史』から抜粋
ベルヌーリはバーゼルの社交界におけるニーチェの態度を次のように描いている。「あるときかれは隣席の婦人に次のように語った、『先ごろ夢をみたのですが、目の前のテーブルに乗っていたわたしの手の皮膚がふいにガラスのように透明になったのです。手の骨や組織や筋肉の運動がはっきりみえました。それから突然手のうえにふとったカエルが坐りこんでいるのがみえて、それと同時にそれをのみこまねばならない、という抵抗できない強制を感じました。いやでたまらなかったのですが、がまんしてのみくだしました』その若い女性は笑った。『お笑いになるんですね』とニーチェはおそろしく真剣にたずね、なかば問うような、なかば哀しむような深い目を隣の女性にじっと注いだ。そのときこの女性は、いま神託が比喩の形で告げられたのだ、ニーチェは細いすきまからかれの内面の暗い奈落をかの女にかいまみせたのだということを、完全に理解はしないまでも、感じたのであった」さらに一六六ページにベルヌーリは次のように書き記している。「かれの服装が非のうちようがないほどきちんとしているということは、無害な自己満足よりむしろ、ひそかな苦しい嘔吐感から生じる服にしみをつけることへの恐れがそこの表現されているのだ、という真相もかの女は知ったかもしれない」
周知のとおりバーゼルへ行ったときニーチェはごく若かった。そのころかれはちょうど、他の若ものなら結婚のことを考えるような年齢だった。かれはわかい女性と並んで坐って、自分の体の透明な部分におそろしいむかつくようなことが起こったが、それをかれはそっくり体内へとりこまねばならなかった、と語った。ニーチェの生涯を惜しまれる若さで終わらせたのがどういう病気であったかは、ご承知のとおりである。まさにこのことを、かれは隣席の婦人に告げねばならなかったのである。かの女が笑ったのはじつにおろかなことであった。
第二部『英雄の誕生』から抜粋
この豊かな世界が、ひとりの人間に愛の対象をさしだすことができないほど貧しい、というようなことはもちろん考えにくい。世界はだれに対してもかぎりなく広い空間を提供している。むしろ人間から愛の可能性を奪うものは、愛する能力の欠如である。リビドを物や人に向けてそれらを自分にとってみずみずしくよろこばしいものにすることを知らない者に対してだけ、この世界は空虚なのである。したがって代償物を自分自身のなかから取りださざるをえなくさせるものは、外界の対象の欠如ではなく、自分の外にある物を愛情をこめて抱きとる力の欠如である。生活の労苦や生存競争のいとわしさはたしかにわれわれの意欲を減退させるだろう。だが、外的状況の不幸といえども愛を妨げはしない、むしろ最大の努力へと励ますことさえありうる。現実社会の労苦が、たとえば神経症をひき起こすほどにリビドを継続的に抑えつけるということは決してない。神経症の必要条件は心の葛藤だからである。抵抗だけが、心因性の精神障害の出発点になりうる退行を産みだすことができ、意欲に忌避を対置する。愛することへの抵抗は愛の不能を産む、あるいは不能が抵抗としてはたらく。リビドが現実世界へひろびろと水を注ぎだす絶えることのない川の流れにひとしいように、抵抗は、力動的な観方をすれば、河床からたちあがって水がその上をこえたり迂回したりして流れてゆく岩のようなものではなく、河口とは逆に水源へ向おうとする逆流にひとしい。たぶん心のある部分は外界の対象を欲するが、別の部分は主観の世界へ戻りたがるのである。そこではかるがると建てられた空想の宮殿が空中に浮いて手招きするのだろう。
「神話学入門」カール・ケレーニイ&C.G.ユング
(杉浦忠夫訳/晶文全書)

「元型論」「続・元型論」
(林道義訳/紀伊國屋書店)
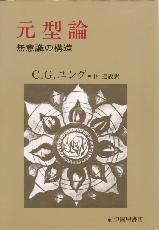

「無意識の心理」(高橋義孝訳/人文書院)
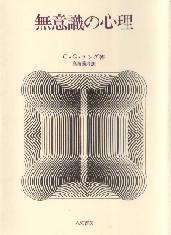
第二章『性愛理論』から抜粋
人間が自分の本性の裏側をはっきりと見ることを学び知るようになると、それによって人間は周囲の人々をもよりよく理解し愛することを会得するようになるだろう。阿諛が減り、自己認識が増すと、周囲の人々に対する関係は必ずや大いに改善されることになるのだ。なぜかというと人間は、ともすれば自己自身の本性に対する不公平で強引な態度を以って、周囲の人々にも接しがちなものだからである。
第八章『無意識の把握、治療に関する一般的な事柄』から抜粋
一見全くまっとうな人間であって、そこに特別のノイローゼ的症状は全然見受けられない。それが医師や教育家である場合もある。彼らはむしろ、逆に自分たちがまともであることを鼻にかける。彼らは事実正しい教育の標本であり、その上ひどくまっとうな意見や生活習慣の持ち主なのだが、彼らのまともというものは実は潜在的な(隠れた)精神病の人工的補償なのである。御本人は自分がどんな状態にある人間であるかについては全然御存知ない。彼らが彼ら自身の状態に関してごくぼんやりと感知していることは、間接にただつぎのような事実の中に洩れ出てくる。つまりそういう人たちは心理学や精神病学に殊更に興味を持ち、まるで蛾が灯に吸い寄せられるように心理学や精神病学に惹きつけられるのである。ところで分析は今述べたような場合にあっては、例の貴重な補償作用を破壊し、無意識は今やもはや鎮められない空想や、それに続く興奮状態の形で噴出してくる。そういう興奮状態は場合によると直接に精神病に変化して行くことがあり、あるいはまた精神病になる前に自殺へとひとを駆り立てることもある。こういう潜在的精神病は残念ながらあまり珍しいものではないのである。