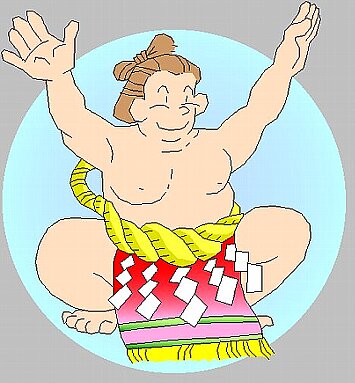
中高年の運動療法
1.中高年者の特徴
非常に個人差が多い
加齢現象(最大心拍数の低下.筋肉量特に速筋線維の減少.神経系調節力の低下.体脂肪の増加)を体に抱えている。
特に多いのが循環器の疾患で、ついで筋骨格系である。特に60才から骨関節結合織の疾患が増えてくる。
筋トレの効果は筋量の増加よりも神経系の協調性向上に因る筋力の増加による.
2.スポーツ外傷
高齢だからといってスポーツ障害の頻度が高くなると言うことはない。
原因としては、転倒、衝突がもっとも多い。
いかに転ばないか、次いでいかに上手に転ぶか、当たるか、を練習する(筋力.調整力).不幸にして転んでも、ぶつかっても、骨折を起こさないようにいかに強度を保つか(骨密度)を考えておく。
3.運動処方の違い
内科--運動できる体かチェック。カロリーを消費する目的で処方。
整形外科--運動できるのは前提として、運動による障害を早期発見しようとする。痛くなく運動器を使うためにはどこをどう鍛え、どこをどう使うかを目的。
4.成人病患者の運動療法--歩行
「にこにこペース」最大酸素摂取量の50%、60分週3回--分速50-60・
「しかめっ面ペース」最大酸素摂取量の75%、60分週3回--分速100・時速6キロ
ややきつい運動負荷であり、若年者の体力強化の指標。東海道53次の移動設定スピード、日本陸軍の移動スピードと同じ。
「減量の目標」は1週間で2000キロカロリー(一日あたり300キロカロリー)が理想とされている。分速70-80・だと100分に相当する。
5.足腰の痛みに対する処方--スクワット
若い人の使いすぎ症候群と好発部位が良く似ており、負荷が短期間に集中したか長期間にわたってゆっくり起こったかという違いだけ。
「長く歩く技術、体力」をつける必要あり。
「立ち方、構え方」立つているときのバランスを良くし、立つために必要な筋力の強化。
四股、腰割り--相撲にヒントがある。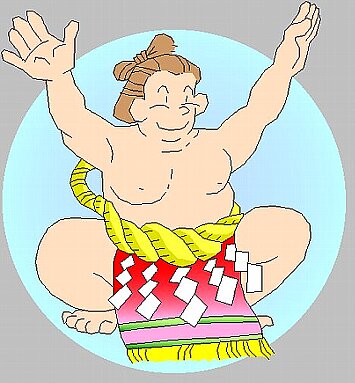
肩幅より少し幅広く立つ。
膝が足の長軸(第2趾の方向)を向くこと。
足の中央に重心が来るようにする。
膝が前に出ないようにしながら、胸を張って腰を落としていき太腿を水平にする。
机に手を載せて支えながらするのが良く、食前や就寝前に行う。
6.元気な人に対する処方--歩行.水泳.片足立ち
水中歩行.水泳.1日1万歩歩行--体脂肪の減少.持久性体力の維持
閉眼片足立ちの練習--神経系の調節力向上