科学の世界ほどでないにしろ、どの様な仕事に置いても反論は避けて通れないもの
と思われます。さまざまな人が反発し、受け入れることを拒みます。しかし、本質的に正
しい仕事は必ず残っていきます。大切なのは、自分がどういう方向を見つめて進もうと
しているかなのではないでしょうか。
科学もビジネスも、そして政治も、「何のために」と言う視点が抜け落ちればその場し
のぎの弱さを持ちます。


教育・個性 social 3.
目先の反論を恐れずに「何のために」という観点を持ち続けよ
朝日新聞04.01.25より 生物物理学者 ジェイムズ・ラブロック
日本人は勤勉で、もっともっと良い製品を作ろうと一丸になろうとします。英国も、日 本も自分の力を声高に宣伝するのが得意な民族ではありませんから、いい製品を作れ ば分かってくれると信じる。その奥ゆかしさがわたしは好きですが、しかし、次は何をす ればいいかと問われるとき、「もっと技術と理論の叡智を世界にアピールせよ」と言いた い。
科学の世界ほどでないにしろ、どの様な仕事に置いても反論は避けて通れないもの
と思われます。さまざまな人が反発し、受け入れることを拒みます。しかし、本質的に正
しい仕事は必ず残っていきます。大切なのは、自分がどういう方向を見つめて進もうと
しているかなのではないでしょうか。
科学もビジネスも、そして政治も、「何のために」と言う視点が抜け落ちればその場し
のぎの弱さを持ちます。


反論や避難は決して心地よいものではありませんが、それがあるからこそ、自分一人 では考えが至らなかった視点を与えられる。検証することで自分の理念や信念の正し さを確信できる。 生き残る仕事は、必ず反論を乗り超えます。自分の仕事はどうか、自分の生き方はど うか。忙しい毎日でも、踏みとどまって確かめて行って下さい。
自分は何をしたいのか 朝日新聞04.01.12より 作家 村上 龍
若者の就職率が低下しているのは当然だと私は思います。会社だって大変な競争に さらされていますから、誰でもいいから新人が欲しいなんて所はありません。政府主導 で雇用をなんて考えていたら時間がかかり、リスクが多すぎます。政府は最低限のセイ フティネットを作った後は、ある程度放っておくのがよいと思います。
私は、フリーターには未来がないと言ってきましたが、それは次の理由です。フリータ ーでビジョンを持っている人は未来がないといわれても気にしない。問題は、本当は不 安なのに何とかなると思考停止している人達です。
仕事や就職イコール入社という考え方の弊害は、社会が狭く見えてしまうことです。 子供には、まず社会にはどんな仕事があるのかを示し、仕事や職業というものには広 い地平があるということを伝えた方がよいと思います。子供が本当になれるかと言うこと より、何かの好奇心の対象を通して、社会や世界に関心を持ち、自分で情報を集めた り、本を読んだりすることが重要だと思います。世界と主体的に関わると言うことは、主 体的に情報にアプローチするということです。好奇心の対象が見つかれば、「学ぶ」事 の重要性が自然にわかります。そして、子供とか若い人達にはその為の時間が十分に あるということがわかるはずです。
時間は資源です。目的意識もなく、日々バイトで自分の人生という資源を切り売りし ていることは恐ろしいことです。中高年の男性は時間という資源が減っています。だか ら、生き方を変えたり、考え方を変えるのが難しい。若者や子供に未来があるというの は、時間という資源を持っているからで、それ以外には何もありません。この膨大な時 間は、その子供の好奇心の対象を探すために、そして探した後に、その対象を通して 社会や世界を知るために使った方が合理的ではないでしょうか。
自分の人生は、自分で決めるものだ。自分の好きな仕事で経済的に自立し、一人ひ とりの自由を獲得してみたらと言いたいのです。 いい学校、いい会社、それで人生は安泰という時代が長く続いたので、それに変わ る標準モデルが見いだせないのです。だから、ゆとり教育をどうするとか、日本の雇用 はどうなるのかとか、マクロで考え、語るしかなかった。本当は、問題はとてもシンプル です。
大人になると働いて金を稼がねばならない。だったら、いやな仕事よりも、好きな仕事 の方がいいに決まっている。そういうことです。
潜在能力を探し、自らを育てる習慣を身につけよ
朝日新聞03.09.28 東大総長 佐々木 毅
就職して企業に身を投じることで人生を安定させる時代は、本当に終わりました。
企業に忠誠を尽くしてくれる多くの社員を集めて、その企業の戦略のもとに一丸となる働き方は現実に崩れ始めています。企業や組織は必要に迫られて、個人が今持っている能力を手に入れることに必死です。
これからは、常に、自分は何が出来るのか、どのような力を磨いていくべきか、 その可能性に目を向けて歩き続けなくてはならないと思います。 自分の手で自分を追い込み、自分に体験させて知らなかった能力に出会ったり、 潜在的な力や興味を発見する。つまり、それは個人を育てるということなのです。 組織に入って皆と同じように行動する慣習を破るためでもある。
与えられた問題を自分の持っている技術で解決するだけのスペシャリストではなく、 問題そのものを発見する能力と解決する技術を併せ持つ、 プロフェッショナルを目指して欲しい。見えてこない問題を浮き彫りにする能力、 それを粘り強く、そして、ずっと鍛え続けていって欲しいと思います。
一度手にした専門性だけで、良い仕事をやり続けていくことは難しい時代になっています。 自分を客観的に見ると不足している部分は分かるものです。見ぬ振りをしてはいけない。 また、将来目指している分野があれば、ためらわずに学び始める。 すぐに効果を求めるものではなく長い目で自分を育てていく努力は生涯必要なものです。 自分には何が出来るのかと問われることを想定し、集中力を持って生きていくこと。 この集中力があれば、自分なりに色々なものが見えてくることになり、 セールスポイントを深めていくことが出来る。
今目の前にある今日の仕事が自分のすべてであるという刹那的な仕事人生ではなく、 自分のものの見方、自分の人生の歩き方の地歩を固めていく
方法を模索して欲しいと思います。
信頼関係結べぬ大学生
日本経済新聞99.03.14 立正大学カウンセラー 繁田 千恵
§人の反応に過敏
小、中、高校の不登校、いじめ、学級崩壊が、大きな教育問題になっている。95年からは文部省によるスクールカウンセラーの度も実施され、各自治体も独自のカウンセリング制度を導入するなど、スクールカウンセラニーズが高まっている。人材養成のために各大学は、心理学部の新設や大学院を増設するなどの対応を急いでいるが、現状は十分とはいえない。
ところでその大学自体には、すでにこうした相談活動の制度が40年以上にわたって地道に続けられているのをご存じだろうか。
第二次世界大戦後、占領軍であった米国は日本の教育の改革の制度のために多くの使節団を送り込んできた。52年に年に国務省から派遣されたロイド博士らと日本の文部省及び東大、京大、九大が中心になり厚生補導研究会が作られ、学生に対する個人的サービスという構想がもたらされ、学生に対するカウンセリング制度が誕生した。
現在は国公私立大学の約60%に導入されてる。
学生相談室、学生相談センター、保健管理センターなどと、実際の形態・名称は大学によって様々だが、「心の専門家」である臨床心理士、あるいはカウンセラーがいて、学生、父母、特には教職員の心理的な悩みについて相談受けている。
学生の悩みを聞いていると、彼らの抱える悩みは二つに大別できると思う。
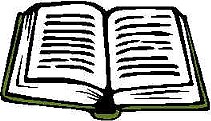
第一のカテゴリーは自分の能力に関するもので、学業、対人関係、進路などである。高校までは良くも悪くも受験という目標があり、それに向かわざるを得ない自分がいた。しかし大学に入ると、クラスルームも自分の机もなく、自分が主体的にに時間割を決め、授業を受けていかなくてはならない。
このような環境の違いに初めは戸惑う学生が多い。周りがみんなテキパキと行動し、自分より優れて見え急速に自信喪失してしまう。
自分の居場所がないと感じ、授業が分からないまま次第に休みがちになり、ついには退学という事態になるケースも多い。
第二のカテゴリーは精神面の問題で、過度に人間関係に敏感な学生でる。人の反応ばかりが気になって、本当に自分が何をしたいのか分からなくなってしまう状態から、無気力になったり、人の視線や自分の行動に関し神経症的な症状を表す。視線恐怖症、赤面症、潔癖症(反復手洗い行動ど)、摂食障害、睡眠障害など様々な症状がでる。
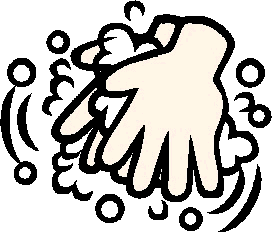
学生の心理状態は最近十年で様変わりしているが、特にここ3、4年は自己信頼、他者信頼の困難さから生じる問題が多い。
一つの理由小、中、高でいじめ、不登校がかなり普遍化し、大きな事件でない限り取り上げられなくなったことと関しているように思える。
静かに潜行している日常的いじめで、自我形成の大切なときに人間に対する信頼を持ち得なかった少年期の問題がそのまま大学での青年期に持ち越れてしまっている。
「スタンドパイミー」の映画に代表される少年期特有の同性に対するあこがれと信頼を経験しないまま青年期の入り口に立ち、大学という自主性を尊重する環塊に置かれると、周りのだれもが信頼できない自分に気づく。
そこから友達作りをしようとしても、本当の信頼関係を結べるに至る道のりは遠い。
§当たり障りない話
すべて時間をかけないことを良しとする環境で、インスタント食品やインターネット、車などに囲まれていると、時間をかけて信頼関係を作る努力は難しく思えたり、ばかばかしく感じてしまう。それよりも当たり障りのない軽い会話だけしてお互い深く立ち入らず、傷つけ合うこともなく、すっと通り過ぎてしまおうとする。
もう一つの理由は親子関係の変容だろう。幼児期の母子関係が個人の基本的信頼感形成に重要な役割を持っていることは言うまでもないが、思春期,青春期にきな影響力を持つ。

彼らの父親は数年前までは会社人間として、家庭での父親の役割より社会や企業の中での役割にエネルギーを投資してきた人が大半だ。そして、現在はリストラにおびえる中高年に代表される。
本来、父親は子供にとって、善悪、正義と不正義の判断基準であり、社会の規律やや規範の教師でもあった。「お父さんはおまえたちのために一生懸命会社で頑張っているんだぞ」という姿を見せていられるとき、または父親不在でいるときは、子どもが父親の姿を勝手に理想像として作り上げることも可能だった。
しかし今は本況に脅かされた自信のない男性の実像が目前にあるとしたらどうだろう。信頼していた親が信頼できず、自分もまだ何も自信が持てない状態であれは自分の将来に対する不安が増大するのは当然だ。
母親は弱体化した夫に代わる対象として、子供に自分の夢や希望を託し、過保護、過干渉になりがちである。子供は家庭でも家族間の信頼関係を築けなくなっている。
§親密さに対し飢え
しかし、彼らも、人間本来の欲求である親密さに対する飢えは感じている。それ故に、自己開発セミナーや新興宗教、怪しげな政治団体などに父親、母親に求めても得られなかった厳しさとぬくもりを求めてしまつたりもする。
現在、マニック・ディフェンス(躁的防衛)という言葉が、しばしば精神科医、心理療法科の間で交わされている。精神分析でいう防衛規制の一種で、にぎやかに、明るく、能動的に振る舞うことで、内心の不安や怒りを隠すような行動を指す。
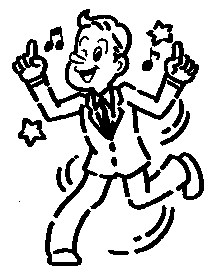
毎日のテレビ番組、特にバラエティー系のものや、そこに常に登場する人気タレント諸氏をよく観察すると、多くのマニック・ディフェンスの症状が見られる。
それは日本人の古来持つ真性でもあるだろち。学生も不安になれは自己を防衛するために一生懸命明るく振る舞う。しかし心の奥深く潜在する不安は消えることはない。
不安や怒り悲しみなどのマイナスの感情を自分で認め、しっかりとそれと向きあって、だれのためでもなく自分のために生きる人生をスタートさせる足場として、これからも大学のカウンセリングルームが機能していくことを願って、毎日学生と向き合っている。
罪悪感持たぬ青少年の増加
フランス思想家ルジャンドル
産業化された社会に共通の現象として、学校や子供社会の暴力が深刻になっている。罪悪感を自分のものに出来ない世代がどんどん生み出されている。
彼らは、尊重しなければならない規則があるにも関わらずそれを教わらず、子供だけで自由にさせられて、自分自身を築き上げる方法を見失っている。
人間としての自分を組み立てることが出来なくなった結果、自己破壊的な状況に追い込まれているのです。---「モンタージュの崩壊」
若い世代がモラルをなくしているのは、彼らのせいではない。むしろ彼らは破壊されているのだ。若者が崩壊しているのは、大人が背負いきれなくなった重荷を彼らに負わせた結果です。自分のことは自分で勝手に組み立てなさいと次の世代に言う。そんなことは過去になかったことです。
本当は子供が求めているのは、何が良くて、何が悪いのか。黒か白かを誰かがはっきりさせてくれることです。

日本の状況については、おそらくは政治の問題も関係していると思います。政治がどうなっているかというのは、一人一人の個人のアイデンティティを作り出す基盤だからです。政治の世界が腐敗している。あるいは、手段を選ばずに金持ちになれるような野蛮な状態が放置されている。それは次の世代のモンタージュをさらに荒廃させる。
次の世代のために、何が出来るのか。コンピューターは何もしてくれません。すぐ出来ることは、間違っていることに対して、大人がはっきり「否」と言うことです。そして、子供が自分の居場所を見失っている時に、方向を示す地図を教えてやる。あるいは、自分が分らなくなった若者に、自分を映す鏡を差し出してやる。それは大人の世代の責任なのです。
崩壊現象を説く鍵は「思想の壊滅」だと考えている。誰も有効な思想を見つけられない。そのために、自分を組み立てられない若者たちが、教祖がすべてを指示してくれる宗教セクトに引かれていくという現象が起きている。
問題に気づくのは、いつも破滅的なことが起きてからです。事態はまだ悪くなるかもしれない。解決に三世代かかるかもしれない。
しかし、崩壊の中から新しい何かが生まれる。私はそう考えている。
マニュアル.コンピユーター化されてしまった学生
早稲田大学教授 吉村 作治
今の学生は昔に比べて真面目なんです。根が真面目ではなく、形が真面目なんです。
「ちょっと悪ブル大学生がいいな」と思えばそういう風になる。本当のワルでないのにワルぶれる。逆にワルでも真面目ぶれる。何て言うかコンピューター的なんです。
ですから、創造性が非常に乏しい。創造性というのは自分で作るもの。興味を持ってなんでもかんでも自分の中に取り込んで、矛盾だらけになりながら自分というものを作っていく。そのベースに知識というものがあるんです。
時間さえあれば創造できると思っている人がいるけれどもそれは無理。今の連中というのは、頭の中味が空洞化していますから、まわりはきちっとしているんです。コーティングだけは。
今の若い子は、自分で考えたり、調べたりしないんです。それに、「自分が必要なことは対応できるように前もって知らされているのが普通で、それがないということはおかしいんだ。」と来る。
十年前は人に聞いた。その前は聞かないで自分で考えた。今では、学生は話を聞いただけでは解らない。黒板に書いたり、OHPを見せないとダメなんです。昔は黒板になんか書かなかったです。

今の人は人に聞かずに自分で考えない。ほとんどがマニュアル。自分好みのことについてはものすごく知っているけれども、他のものには興味を示さない。だから、博識のある人が少ない。
昔は何を聞いても知ってる人っていっぱいいたでしょう。
今は自分で決めて選んだもの以外の情報は排除してしまう。
音楽の個性のばす教育
1999.01.14読売新聞 指揮者 小沢 征爾
§1.東洋も西洋もなく
音楽はとても個性的なものです。
今ここで同じ音を聞いて、うるさく感じるか、感じないか、意識するかしないか。個人によって皆違う。
音楽会で、あなたと僕が1メートルと離れていないところに座っていても違う影響を受けている。そう言う意味で音楽は個人的なものです。これは21世紀になっても変わらないものと思う。
それに、楽器や声帯よりもいい音を出せる音源がまだない。技術の進歩で限りなく近づけることは出来ても、同じ響きを機械が作ることを想像できない。音楽会に行くことの大切さは変わらないものと思う。
時間がうんとかかる。そうすると結局は天才の出現を待たねばならない。天才を待つのはどの国でも出来る。日本は勤勉さを生かして、うまく教育方法を考え出せば、うまくいくと僕は確信しています。
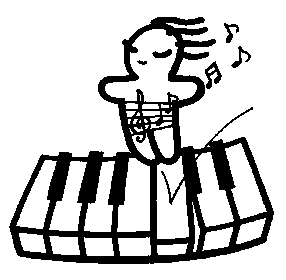
§3.個の強い先生が必要
個をのばすことに主眼をおけば、音楽の教育はうまくいくと思う。それには、個の強い先生がいなければならない。しかも、その生徒にとって大事な時期に。作曲とか指揮、声楽は中学高校ですかねえ。ピアノやバイオリンはもっと前から。
個を重視する先生で、音楽家として質も良くないとだめです。これが難しい。
今、質の良い音楽家が先生になりたいと思うような環境がない。そうじゃない人が先生になっている。
日本は今、危ういところへ来ている。悪い方に向かっている。個を信じ、他人の個も大事にし、「個が大事だ」ということに早くならないとだめだと思う。
日本の社会と科学者のあり方
高木 仁三郎
分からないことを大切にし、「やっぱりちょっとおかしいぞ。」と感性を働かせるのが科学者の大事な役目なのに、実際はそうはなりにくい。
日本人は「分からないこと」への対応が不得意なのでしょうか。近代科学技術は日本人にとって、あくまでも西洋からの借り物で、都合の良いところだけ使おうとする。疑問があれば徹底的に議論していったん止まってでも壁を越える作業をすることをせず、見て見ぬふりをして通り過ぎてしまう。
自分の会社勤めの経験では、小さな疑問にちゃんと対処しない雰囲気があった。
そしていつも会社の方針や幹部の意見が通る。その積み重ねで、末端の個人を黙らせてしまい、同時に全員を一つの結論に巻き込んでいく。後で何か言うと、「おまえあのとき黙っていたじゃないか」となる。
自分としても、期間内に確実に成果の上がるものだけを選んでいる。
結局、私がぶつかってきたのは、組織の中でちょっと自分を主張すればかどが立つという日本型システムなんだと思います。これが、自由な議論と将来の選択肢を閉ざしている。
今、地球そのものがおかしくなっている。まさに「うばわれし未来」です。奪われつつある未来を取り戻すことこそ、今科学の最大の課題でしょう。
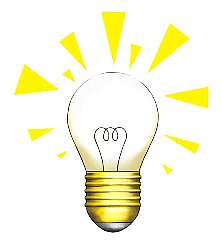
それには大組織などに帰属して安住するのではなく、なにをするのかを自分で考え、市民と共同して転換の時代を担う、自立した科学者である活動家が必要なんだと思う。