
人間関係・命 social 2
社会、家族の絆とは 日本福祉大学創立50周年記念シンポジウム 2003.10.26朝日新聞
私達は、生まれて生きていく上で、様々な悩みを抱えているわけですが、その中でも、人と人との関係、人間関係、それにまつわる悩 みが実は大部分を占めているのではないかと思います。
1. 引きこもり---- 映画監督 小林貴裕 引きこもりの原因は、自分でもよく分かりません。兄弟なり、両親なりの仕方の刺激のおかげで、「自分が違う生き方が出来るので はないか」と考えだすようになり、だいぶ楽になりました。かすかながら、「つながり」というか「動き」が、兄弟の間、親子の間で回 復してきたのです。どんな物事にも両面があって、引きこもりはきつい面もあったし、後悔する面もあるけれど、自分の見直しをす るというプラスの面もあったと思います。
2. 父親の自殺-----児童相談員 山口和浩 父親は「もう死にたい」と繰り返し言っていましたが、僕は子供三人置いて死ぬことはないだろうと思っていました。父親の死後、 僕は、父親を殺したのが自分ではないのかと、ずっと自分を責め続けました。大学時代に親を自殺で失った同世代の人に出会 い、自分と同じ苦しみを抱えていることをやっと知りました。そして、「同じような体験をし、悩み苦しむ子供達」を減らしたいという 思いから自殺防止に関する活動をはじめ、社会と自分が少しずつつながっていったような気がします。物理的につながりが途切 れてしまった父親ですが、八年という時間が経つことで、家族のなかでも父親との思い出話が出来るようになってきました。そして、 父親のことを考え直すことによって、もう一度繋がることが出来たと思います。でも、家族のなかでタブー視された部分に外から安 易にメスを入れることは出来ないと思います。
3. 愛着障害と愛着過剰----日本福祉大学副学長 加藤幸雄 愛着障害は些細な刺激に過敏に反応して過剰防衛的に反応してしまう。 愛着過剰は支配や保護になれてしまい、対人不安が強く、守られているときは動けるけれども、そうでないと動けなくなってしまう。 リラックスした人間関係を持てない。 他人の目を気にする。自分が傷つくことを恐れ、他人を傷つけることを恐れる。「みられ意識」が強いと、あるがままの自分が確か めることが出来ないまま、周りからの期待にどんどん応えようとして過剰に頑張ってしまう。自分を肯定できない不遇の感情を持 つことがあります。大人達は、若い人に、過剰な期待をせず自信を持って社会関係を結んでいく機会を作ってあげる必要がある のではないか。
6.もっともっと抱き合うこと----脚本家 小山内美江子 子どもを、親を愛しているなら一歩踏み出して「愛している」と言って下さい。その言葉は、「アイラブユー」である必要ありません。言 いやすい言葉で良いのです。その言葉が耳にはいると「ああ、私って必要なんだな」「私、いていいんだな。もっと頑張ろう」と言う 気になります。人間はお互いの体温があることを確かめ合うことで安心し、一緒に頑張ろうという気になるのです。
7.ありのままの自分を見せ、いま一緒にいることを喜ぶ----新聞論説委員 川名紀美 「どうしたら人と人とのつながりを築くことが出来るか、あるいは、回復することが出来るのか。」を考えてきました。やはり人間を見る ときに、その人が自分に役立つかではなく、いま一緒にいること、出会えたことを喜ぶような姿勢で人とお付き合いしていったらい いのではないかと思う。また、私達は誰でも演技をせずに、本当にありのままの自分を見せてそれでも受け入れてもらえる場や関 係があったら、生きていくのもどんなに楽で楽しいかなと思います。
乳幼児の記憶
イギリス科学誌ネイチァー02.1.30号
ハーバード大学コーナーリストン博士
赤ちゃん12人ずつの3つのグループに、
それぞれ生後9ヶ月、17ヶ月、24ヶ月の時点で
「掃除の時間」といってテーブルをふくなど
言葉と動作のいくつかのセットを実験者がやって見せた。
そして4ヶ月御、そのセットをやってみて
幼児がどれだけ動作をまねられるか試した。
結果
生後06ヶ月 24時間前のことが思い出せる
生後09ヶ月 01ヶ月前のことが思い出せる
生後13ヶ月 01ヶ月前のことが思い出せる
04ヶ月は全くが思い出せない
生後21ヶ月 04ヶ月前のことが思い出せる
生後28ヶ月 04ヶ月前のことが思い出せる
2歳になる前後から長期の記憶が急速に発達する事を証明した
抱きしめるということ
朝日新聞2002年1月9日より

愛情を伴う積極的な受容。あなたを愛しているとか、大切に思っている時にする行為である。
子供にとっては、いつでも抱きしめられることは必要不可欠なんです。
幼少時に親に抱きしめられ大切にされているという自信のある子供は、親から離れて好きなことができる。
しかし、自信がないといつまでも怖くて親の手元からでていけない。親から抱きしめられずに育った子供達が、今親の世代になっている。彼らの多くは、抱きしめることの大切さが理解できていない。だから、子供がちょっと泣いただけで、抱いてあやすどころか虐待に走ってしまう。抱きしめるべき時期に抱きしめて、やがてはその手を離して子離れする。こうした当たり前のことがうまくいかなくなっています。
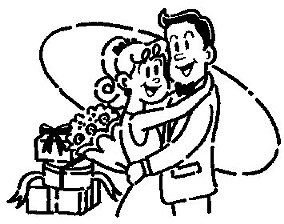
また、抱きしめると必ず相手の反応があります。時には、拒絶されることがある。この拒絶を恐れるあまり、抱く相手を人間ではなく、思い出や夢のような抽象的で自分の都合の良いものに変えられるものを対象にするようになる。要するに、彼らには今の自分が一番大事なのである。こういった人が増えています。
寂しいとき、つらいとき、人は抱きしめて欲しいと思う。相手を腕に抱えて、思いのすべてを注ぐ。だがその手はいつかは必ず手放さなければならない。そのときの辛さを思いつつなおさしのべる腕。やはり、抱擁は、人間の最も基本的な動作の1つであると思う。すべてを受け入れ、包み込む行為。だからこそ抱きしめることは重要な愛情表現なのではないでしょうか。
希薄な家族の絆/夢を持てぬ子供
読売新聞1999,06,30上智大学教授・精神医学 福島 章
日本の自殺者が前年比35%も増加して年間三万人を超えたという。しかも、自投者の中では働きざかりの五十歳代が最も多く、四十歳代の増加も目立った。
半世紀近く前は、青年の自殺が多いのが日本独自の特徴として論じられたが、近年の日本では、自殺率は年齢とともに上昇するという世界の大勢に一致していた。だから、働きざかりの年代の自殺者の増加という現象は注目に値する。
不況によるリストラ、失業、倒産などが、これらの自殺の多くの引き金になっていると
考えることはもちろんたやすい。しかし、いくら不況だ、失業だといっても、今は明日食べるものに困るという時代ではない。
問題は、逆境におかれると、彼らがすぐに生きる目標や元気を失い、絶望してしまうことにある。
ところで、これまでの自殺学の研究によれば、家族とともに暮らす人は自殺率は低く、単身生活者に自殺率が高いというのが定説であった。
つまり、自殺防止のかなり重要な因子は、家族の強い絆である。
そこでふりかえってみると、昨年に自殺が増加した世代は、かつては高度経済成長の担い手であり、エコノミック・アニマルなどと呼ばれるほど仕事熱心な人々であった。
しかし、経済活動が生きがいとなってしまった分、家族に時間と関心をふりむけるゆとりに乏しかった。家庭は妻に任せきり。子育てにも夫婦の絆を育てる努力にも、彼らは多くを割かなかった。
ふたたび人口動態統計を見ると、はたして、昨年は離婚も二十四万組あまりと増加し、離婚率(人口千人当たりの離婚組数)も過去最高の一・九四になったという。
しかも結婚後二十年以降の「熟年離婚」が増加している。
問題の世代の人々は、これまで右肩上がりの時代に順風満帆の活躍をしてきた温室育ちである。そこで、挫折に弱く、諦めも早い。少しうまく行かないとすぐに、人生からも結婚生活からも「一ぬけた」と宣言したくなる傾向がある。
しかし、勝手に「一ぬけ」ようとするパートナーの後ろ髪をつかんで引き止めてくれるはずの家族の絆がもっと強ければ、自殺や離婚がこれほど増加することはない。
つまりここでも、青年期・壮年期に、男達が妻との対話や子育てに注ぐ時間があまりにも乏しかったツケが回ってきている。
昨今、晩婚や離婚が増加しているばかりではなく、最初から結婚しない男女も増えている。当然、出生率もますます低下している。
こうした動向は、家族を介して人が生きる希望をつないだり、次の世代を産み育てようとする意欲を失いつつある現状を端的に示している。この時代の社会システムの大きな変化は、日本の家族や人間関係を確実に変容させつつある。
こうした家族機能の空洞化は、子供の心理にも大きな影響を投げかけている。
日本青少年研究所が最近、発表した国際調査によると、日本の中高生は、アメリカ・中国・韓国の同世代に比較して、社会への希望や将来への夢が極端に少ないという。
例えば「二十一世紀が希望ある社会」になり、「今より豊かになる」と思う生徒は、他国では六S九割を示すのに、日本では半分を大きく割り込んでいた。そして「勉強がよくできる」「高い社会的地位につく」などの夢をもった子供はアメリカの中高生には多いが、日本では自分の趣味をしむ」「その日その日を楽しく暮らす」などという「こぢんまり志向」が大勢を占めた。
ここにはもちろん、今日の受験戦争や偏差値競争の渦の中で、勉強が得意でない子が早々に人生ゲームからリタイアを意識させられがちであるという状況もある。
この時代の、先行き不透明な閉塞感が、子どもの世界にも影を落とし、彼らの野心や意欲を蝕んでいると見ることもできよう。しかし、それよりももっと根本的な問題は、理想や野心のモデルとなる「父親的な存在」のイメージが、今やますます希薄になっていることにある。
アメリカで自己心理学を創始した精神分析医コフートによれば、幼い子供は、一方で母親の共感や称賛によって自尊感情を養い、他方、父親的な存在を理想化し、これと同一化することによって人生に理想や創造的な目標を見いだすという。
したがって、働き蜂になって家庭に不在でありがちな父親をもった場合、
子供は未来に夢や希望を抱く基盤を奪われていることになる。
もちろん不況などによる経済活動の不如意で打ちのめされ絶望している父親も、不在の父親と同じようなもので、子どもの希望や野心を育てることができない。
子どもたちの心理は、時代の気分や親の姿をまさに正直に映し出す鏡なのである。
36億年の命
柳沢 桂子 生命科学者 2000.02.02朝日新聞
生命化学をやっていると、命の敬虔さというか、命はそれを持っている人のものだなんて思い上がりであると思うんです。
三十六億年の歴史を持つ生き物が、その歴史を辿って、今、私の所にたどり着いている。で、大きな宇宙の中の一つの点みたいなものですから。
私は、この地球環境の中に生かされている。花も草も虫もいろいろな動物もいて、中の一つとして私がある。宇宙全体を一つの大きな布みたいに、私は感じている。
だけど、その中の一本の糸、勝手に抜いちゃいけないし、抜けるべき所まで来ているのに、無理に置いておくのも良くない。宇宙から頂いた命は、きちっと宇宙にお返ししなくちゃいけないものだと思っています。人
間はどこから来たのか、人間とは何か。その二つの答えは、生命化学が出しちゃっている。どこへ行くのかは分かりませんがね。
私一人生きるために、たくさんの死がある。
私の身体が出来るためにはたくさんの細胞が死ぬ。
生と死のごうごうという流れの中に私が泡のように浮いている。
脳の回路の中に、神を信じるようなものがある。
人間、動物は、非常に自己中心的です。でないと生きていけない。
その自己中心性を少しでも捨てると、思いやりがで来てくる。二つは相反するものだけれども、私たちが神様に求めるものって、仏やイエスのように全部思いやりになった人です。自己保存本能で生物は進化してきたといわれるが、人間は他人のことを考えるし、他人にも考えて欲しい、思いやりを持って欲しい。
宗教はそういう所から芽生えてきていると思う。宗教を合理的に説明できれば、みんなが安心して信仰するようになるんじゃないかな。
人間や群で生活する生き物は、生まれたときから、社会性を求めるように仕組まれ、そう成長していく。ひよこなんかは放っておくより、手で包んでやる方が早く寝る。そのときに気持ちよくなる脳内物質がでているらしい。
人間も同じで、私が一番苦しいときも、癒してくれたのは、人でした。ただそこにいるだけで救われる。事実として。癒しというものが物質的にあると思います。
哲学は人間の科学ですから、生命化学とつながっていく。これからの哲学は生命化学で立証されたことを抜きには成り立っては行かない。
生命科学は次の世紀に、哲学や宗教も含んだ大きな生命の科学になって行くんじゃないかと思うんです。
生命科学は悪魔にも、天使にもなるので良い方向に進んで欲しいと思います。
生命化学、欲望と歯止め
国際基督教大学教授 村上陽一郎
§1.医療分野での革新
「二十一世妃は生命科学の時代だ」。クリントン米大統領は昨年の年頭教書で宣言したが、この見通しは間違っていないだろう。
振り返ると十九世紀は「化学」の世紹、二十世把は「物環学」の世紀だったといえる。ミクロの世界では分子の振る舞いから原子核の解明へと進み、マクロの世界では宇宙の果てまで視野に収めた。時間的にも、百億年をはるかに超える太古の宇宙創成の時代の出来事に迫るまでに至った。
そうして、今世紀半ばに登場してきたのが「生命科学」だ。遺伝子DNAの解明に始まり、脳科学やヒトゲノム解析などの形で隆盛を誇り、来世把半ばまで相当な勢いが続くだろう。エイズ、がん治療、生殖技衝などの医療分野で、華々しい寧新が期待できる。
では、科学・技術の進展は、私たちを幸福にするのだろうか−。誤解してはならないが、科学も技術も社会から離れて存在しているわけではない。科学・技術は、政治、経済、産業、軍事、医療・福祉といった社会システムの中に、有機的に組み込まれている。どんな科学・接術が開発され使われるかは、社会が実現したいと願う価値観に大きく依存する。
産業革命以降の社会は「効率」を最重要の価値掲げ、料学・技術も、効率達成に貢献すべく組み上げられてきたという側面があ。一股には、技術が新繚を開発したから社会がわしくなったといわれが、社会が高速拶動を欲たからこそ、こうした技術も開発された。
§2.「技術と欲望」の連鎖
ところが今世絶後半になって、人類がかつて経験したことのない状況が出現た。爆発的に進展した科学・技術が人間の欲求を追い越し、それまで人間が気きもしなかった可能性を示するまでになったのだ。
競い合うようにエスカートする「技術と欲望」の連鎖。最近の生殖技術は、その典型だろう。
不妊にむ夫婦に人工授精技術が提供される。すると「私たちの場合も」と欲望は増幅され、技術の側も「望む人がいから」と、第三者の精子を使った人工授精、体外受へと奉仕を続けた。
心臓患者が飲んで死者まで出た性的不能の治療薬バイアグラの問題も、この連鎖がみ出したものといえる。
こうした無限連鎖に歯止めかけたり、断ち切る英知を、人関は持ち合わせているのだろうか。
まず、直接当事者である科学者はどうだろう。科学者は時として、社会に対して驚くほど無責任な態度取ってきた。原爆を開発した科学者たちですら、そ多くは「研究自体は善。悪とすれば、自分たちの知識を勝手に利用した軍人、政治家である」と主張した。
現代において「真理の追究のためには何をしてもいい」という考えが許されるだろうか。オウム真理教の事件は示唆に富む。教団科学技術省の研究者らは、猛毒のサリン、VXガスの開発を指令され、知諭と技を駆使してやりとげた彼らは教団に対する責任を果たしたが、大きな文脈のなかで見れば、とんでもな反社会的な行為に加担してしまったことは明らかだ。
特に今世紀半ばに、科学・技術は原爆を製造し、遺伝子組み替え技術を開発した。人類の生存を脅かしかねない強大な力を手にしてしまったことを、科学者は改めて認識すべきだろう。
§3.特異な「生い立ち」
聖職者、医者、法曹といった伝統的な知的専門家集団は、外部社会に対する倫理条項を含んだ自発的な内部規範を持っそいる。
信者、患者など依頼人がおり、人間の生死に直接かかわる職業であるが故に、社会と通じる回路を備えてきたわけだ。
だが同じ知的専門家集団でありながら、科学者だけが社会的な責任に無自覚なまま、やってこられたのはなぜか。それを理解するには、科学者の特異な「生い立ち」をたどる必要がある。
§4.十九世紀に”産声”
科学者は一般に、十六世紀に地動説を唱えたコペルニクスや十七世妃に万有引力を発見したニュートンらを先達とし、四百年にわたって偉大な歴史を刻んできた集団だと思われている。だが、実は彼らは近代的な意味での「科学者」ではかった。
科学者は十九世妃に、やっとひ弱な産声をあげた新参者であり、幼少期には社会から認知されるほどの力を持たなかった。聖職者医者・法曹のように、依頼人の幸福や社会全体の益、自らの力の限界といた問題を突き付けられる経験もなかった。
直接の依頼人を持たなかったため、外部社会に対して責任を負うことなど夢にも考えなかった。科学者が時に驚くほど無自覚、無任な発言をするのは、こうした背景がある。
ニュートンらを仲間に引きずりこんだのは、十九世紀の第一世代の科学者たちだった。新参者が華々しい家系図作りに熱心なのは世の常。光化学会初代会長ジョン・ドレーバーが一八七五年に著した「宗教と料学の闘争史」は、「頑迷な聖職者たちの無理解にもかわらず、われらが科学者だれだれは」といった語り口で、ガリレオ、ケプラー、コペルニクスらを大先輩として持ち上げている。
だがこれら先達の研究動機は、神の作品である宇宙や自然を解き明かしたいという宗教的熱意だった。ニュートンは、なぜ重力がくかと聞かれ、「神がそした力を働かせているから」と答えた。コペルニクスは地動説を考えた理由「神の作った宇宙のあらるものを照らしだすランン(太陽)を、神が中心外の一体どこに置けただろうか」と説明した。
このようにキリスト教自然観、人間観を持ってたこュートンらを、今の科学者と同一視することはでない位「神離れ」を企てたのは、十八世紀ヨーロッパの啓蒙主義者だった。
仏の思想家ディドロらが「啓く」べきだと考えた「蒙」とは、真っ先にキリストだった。啓蒙主義は、自分たちが縛られてきた考え、習慣から宗教的要素をそぎ落とし、それらが迷妄に過ぎなかったことを明らかにしようという知的努力だった。
啓蒙主義者が神の代わりに信じたのは人間理性だった。これが楽観的過ぎたのではないかという近代不安も、ここから生まれて来るわけだが。
§5.前世紀の意識のまま
神離れの時代を経て生まれた科学者は、宗教的価値や倫理的義悪を排除したのこそ真の学問という時代精神を忠実に実践し、成果を上げた優等生だった。知識が知識としてのみ成立している点こそ科学の優越だと考える彼らが、社会へ目を向けないのは、当然の帰結だとも言える。そこに人の心をかき立てる面さ、楽しさが詰まっていれば、なおさらである。
問題は、科学者が今世紀に成人し、化学兵器や原を作り、クローン人間すら作れるほどの力を持つにっても、前世紀の意識から脱皮していないことにる。二十一世妃が生命科学の世妃になるならば、この事態は極めて危険だ。
この分野は原子核研究などのように大きな装置や金がいらないので、外からは科学者が何をしているか見えにくい。先月、韓国の料学者が人間のクローン研究をしていたと報道されたがあの研究を秘密にしておきたと思ったら、隠し通せたのではないか。
今や科学者自分達の研究は人類共通の福利につながるか、特定集団の欲求実現に奉仕するだけなのか、あるいは災厄を生むこことはないのか、責任をもって判断する義務がある。
§6.暴走抑制する手段
科学そのものに倫理観や善悪の価値観が内在していないとすれば、なおのこと科学者コミュニティーがまず内部基準を設け、行ってもよい研究か検討するシステムを構築していかなけばならない。それは、料学の暴走を抑制する一つの手段になるだろう。
最後に忘れてならないのは、われわれ一般の市民にも、応分の責任があるとうことだ。料学・技術の力の大きさを考えれば、責任を科学者だけに押し付け済ますことはできない。
自分たちの税金が科学研究にどう配分され、何を目指して研究され、その結果何が起こる可能性があるのかを知らずに、現代社会を生きていくことはできないだろう。それは直接、私ちの生き方・死に方にかかわる事柄なのだから。
物理の難しい方程式などは知らなくてもいい。だが自然探究の面白さを知りそれを土台に料学・技術理解し、考え、発言し、責任を分担することができないのでは、現代人として格だと思う。その努力をけることこそが、二十一世紀社会を成熟させていくことになる。