かつて、スポーツ中継の代表といえば、プロ野球巨人戦の生放送だった。緊迫しようが、凡戦だろうが、物理約な時間に沿って流れていた。リアルタイムが売り物のはずなのに、「テンポが遅い」 「試合が最後まで見られない」

知る・持つ・買う social1.
時間を編集する--- せわしない消費の渦へ 文化の現場から 宮本茂頼 朝日新聞2007.01.10
録画しながら放送する「ディレイ」と呼ばれる手法がある。「限られた時間の中で試合終了まで余すことなく放送したい」とTBS編成部の守屋慎司次長。試合の途中で中継が終わることはない。細やかな時間配分で、視聴者に配慮した「編集」もできる。例えば、作戦タイム。タイムに入ってCMにつなげても、盛り上がる場面なら中断前の状態から再開する。時には、活躍する選手の紹介映像も挿入する。この部分は、現実よりも時間が膨らんだことになる。
かつて、スポーツ中継の代表といえば、プロ野球巨人戦の生放送だった。緊迫しようが、凡戦だろうが、物理約な時間に沿って流れていた。リアルタイムが売り物のはずなのに、「テンポが遅い」 「試合が最後まで見られない」

「時間を編集する」感覚は、新しいメディアの登場でより顕著だ。携帯電話にダウンロードし、どこでも読める手軽感が魅力の電子書籍。「新潮ケータイ文庫」の連載小説で人気の作家内藤みかさんは「メールのような読みやすさ」と、スピーディーな時間の流れを心がける。一人称主体で、これまで登場人物は最大で5人だった。
音楽配信でも、アルバムを時間をかけてじっくり聴き、音楽家が企図した作品性を理解する鑑賞スタイルは崩れつつある。大手CD店のタワーレコードが昨秋から始めた月額制の聴き放題による配信サービスで、ダウンロードできるのは約200万曲。1曲3分としてもすべて聴くには10年以上。ここでは、聴き手に配慮し、時間を圧縮するかのように効率よく音楽を楽しむための道具立てが整えられている。
同社が「レコメンド(推薦)」と呼ぶ選曲リストだ。ジャンルや時代別に「編集」されたリストを示
し、数十曲単位の音源が数回のクリックで手に入る。膨大な音源に摸する聴き手を導くためには、「いかにリストの曲を聴いてもらい興味を喚起するか」と担当の五味陽介さんは許す。
博報堂DYメディアパートナーズのメディア環境研究所の中村博所長は「アルバムという購入単位での必然性があまり感じられていない」と断じている。
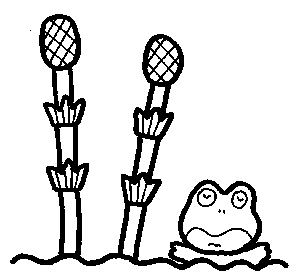
鑑賞者の興味をそらさないよう、時間をあらかじめ編集したり、編集の手だてを示したり。こうした傾向はどう始まったのだろう。
東京大の橋本毅彦教授(科学技術史)は、海外の著作に紹介されたこんな例を挙げる。テレビのリモコンが生まれ、視聴者は番組に飽きると次々とチャンネルを変えるようになった。その結果、番組の作り事は、視聴者を引きつけておくため、よりテンポの速い映像を作るようになった。
リモコンを手にして、視聴者が、いわば「編集の主体」となった。それに対抗するかのように、制作者は退屈さを取力除く「時間の編集」を目指す。いまやハードディスクレコーダーによって、いったん録画したものを早送りしながら、視聴するスタイルが広がる。多彩で膨大な素材があふれる一方で、時間は編集される。私たちはより豊かになったのだろうか。
東京大の松原隆一郎教授(社会経済学)は「消費者が接する情報が多様化しても、個々人が深く興味を持てるものには限界がある」と指摘する。 そのため、興味外の分野では、巧みに時間が編集されたような、刺激的で分かりやすいものに追従する。そして享受すると、容易に次の対象に乗り換える。流行は一極集中型となり、サイクルも短くなっている、と分析する。時間はますます頻繁に編集され、編集のための道具立ても次々に現れる。正確に動く時計のもと、時間をうまく使い、豊かな生活を目指す。それは近代の目標の一つだった。
「時間意識の近代」の著者で、時間論を研究する西本郁子さんは、「時間の大切さを教えられ、仕事を効率よくこなすことが目標とされた。しかし、その結果、仕事はより増えた。さらに、短い余暇そのものにまで効率性が持ち込まれている」と言う。
まるで「時間の圧縮」を目指すような忙しいパック旅行や、ハードディスクに録画した番組を早回しでチェックし、おすすめリストでダウンロードした音楽のさわりを聴くこと。これらはどこか重なって見える。
鑑賞者にとって無駄や雑音と思われるモノはあらかじめ排除された「編集された時間」を生きる。心地よさの一方、せわしない消費の渦に巻き込まれているのかもしれない。(宮本茂頼)
金で買えないものなどあるわけない
ライブドア社長 堀江 貴文
朝日新聞2004.11.20 be on Saturday
「何で命に値段が付くんだ。」小学生の頃、両親が加入する生命保険で自分の死亡時に給付金が支払われると聞いて、人の命に値段があることが本能的に受け入れられなかった。ビジネスでは、当然金がすべて。親子の無条件な愛に金が介在する違和感。これがカネとの格闘の原点となった。
世の中、お金で買えないものはないし、お金の前ではすべてが平等なんです。いくら貧乏でも、才能があれば、それをお金に換えられるし、頑張った分だけ報われる。頭がいいとか、運動能力が高いとか、芸術的な才能があるとかって、絶対的な基準で比較はできない。でも、稼ぐお金で推し量ることはできるんです。
「お金で買えない価値がある」等というのは、自分が努力しないことに対する逃げ、自分の才能が足りないことを認めたくない逃げですよ。僕は、自分に才能がないんだったら、努力するか、あきらめるかはっきりしろよって言いたい。
夢はないですね。飽きっぽいんで。知的好奇心を満たすため、毎日、毎時間、違うことをやってそれは満たされている。夢みたいな感傷的なモノ持たなくてもいいんです。
大学にはほとんど行っていません。東大は、入ったことが重要で、後は「何年入学だよね」「あっ同じじゃない」って、人脈も勝手にできるんですよ。
インターネットの世界は大きな市場があるし、ビジネスもオセロゲームのように、数手先には白黒の展開ががらりと変わる。自分がナンバーワンになる道がある。普通の経営者は年をとっていてスピードが遅い。一番時間がかかる情報収集と知識の吸収ができていない。みんな余計なことばかりしている。人に会うなどリアルに(現実)にモノを吸収するのは物理的に限界があるわけですからメールでもネットでも本を通じてでもどんどんインプットする。圧倒的なスピードと効率でやれば十分差別化になる。僕、ビジネスでも、同じ人に会うのは、せいぜい一二回。後は、担当者に投げちゃいます。
サラリーマンになろうと思ったことは一度もありません。まず、搾取されるじゃないですか。一番こき使われて、大卒の初任給が22万とか。日本の企業ってまだまだ年功序列でしょ。六十歳越えて社長になって、権力握ってカネ持っても、何もできないじゃないですか。食べる量だって減るから、うまいものもあまり食えないし。しかも、ポストはピラミッド型で、社長になるのは一人。こんなネズミ講みたいなシステムを何で信じるのかって。
よくある波瀾万丈って、結局能力が低いだけなんですよ。世の中、失敗のケーススタディがあふれているだから、それを反面教師にしていったら波なんかあり得ないですよ。生来の「飽きっぽさ」が、絶えず、次の飛躍の鍵となる新たな事業を探させる。実態がわからないと揶揄されるが、「儲かることなら何でもやる。」選択の基準は、人が滅多に手を出さないところにあえて踏み込む。要は、他人が注目しないところを狙うこと。うまくいけば、一番儲かるんですから。「逆バリ」の発想です。方向性など後付けでかまわない。
「あいつは変わったやつだと思ってくれるのは、願ったりかなったり、だって誰も真似しないでしょ。それがチャンスなんです。」 だからこのまま突っ走る。
社長をやっていていいのは、最低限儲かれば、何をやつても構わないこと。社長と創業メンバーは一心同体ではない。社長は会社の支配権すべてを常に掌中に収めるべし。
消費者の購買動向
〇〇.12.16毎日新聞
最近の物の買い方は、「低価格志向」と「自分の価値に合う物の飽くなき追求」という二極化が著名になってきた。
低価格志向は納得のいく品質でありカツ低価格の物を専門店に扱うところが受けている。
自分の価値に合う物としては、1つにはブランド品がある。
ブランドといっても次の三要素のどれか1つをハッキリと持っていないと残れない。それぞれの要素を代表するものブランドだけが生き残った。
1.トレンド−−−グッチ・プラウダ
2.安心感−−−−ルイヴィトン
3.高級感 −−−エルメス
その要素を明確に打ち出せなかったものはブランドであっても消えてなくなった。消費者は、同じ要素を持ったブランドをいくつも買うだけの余裕はないのである。
ブランドの資産価値
朝日新聞98.11.03経済気象台
たくさんものを売る会社や大きい会社に勤めることは、この時代、必ずしもハッピーでなくなっている。「強い会社」より「いい会社」がよいと勤めている人も思いだした。顧客も結局はそういう会社やブランドとの巡り会いを望むようになってきた。
市場反応が鈍くなったので、企業は一時的な数字を作るためになりふり構わぬ商売を繰り返した。自らの付加価値をディスカウントし、よそのヒット商品の後追いと物まねを恥とせず開発や研究投資を押さえて次の時代への布石を怠けてきた。
もう商品だけで競争する時代でもなく、何か別の信号を送らないと、顧客はずっとあちらを向いたままに思える。
市場や世の中が変わると言うことは「客が変わる」と言うことであり、「競争相手が変わる」ことであり、「闘うステージが変わる」ということである。
見知らぬ客が従来と別の動機で買っている。日本人が外国人になったと思うしかない。
自分の強みと弱みの点検を急ぐこと。中でも無形の所有財としての「ブランド」について考え、磨きをかけること。
次の世代の武器は、信頼感、イメージ、値打ち、会社の品格、サービス、経営の姿勢、社会との関わり、品質、安心感などを総合した「ブランド」しかない。
買うということ
五木 寛之
一時、シンプルライフという言葉が流行ったことがありました。出来るだけ簡素な、ものにとらわれない暮らしをしようという気持ちはわかるのですが、やはりそれだけでは何か物足りない気持ちになります。人間には、物を選び、物を観察し、その物を自分で手に入れ、所有しようとする本来の欲望が備わっているのではないでしょうか。
お金のことで苦労し、血と汗を流している人ほど、どういうものか無駄遣いすることがあるのです。一見逆のようですが、それはお金に対する人間性のささやかな反抗とでも言えるんじゃないでしょうか。
お金を浪費する、やけっぱちになって、紙屑のように使う、そのことでもって、こちらの方が主人なのだぞ、お金に使われているんじゃ無いぞ、と心の中でうっぷんを晴らしているのかもしれません。
お金に復讐することで、人間性を回復しようとしているのです。
見事に物を買うことが出来る人は人生の達人であろうと思います。
何を買うかという事は、いわば全人格がそこに反映すると言っていいでしょう。大げさなことを言うようですが、同じデザインの物が五つの違った色で並んでいるとき、そのどれをチョイスするかという事は、選ぶ人の個性や、生活環境や、育ってきた背景や、思想やそのすべてがおのずとにじみ出てしまうからです。お金を使うことが趣味というのは馬鹿げているようですが、物を買うことが趣味というのは決して非難されることではないような気がします。物を選ぶ--そのことはいわば自分を賭けることでもあるのですから。
物を持つということ−所有のきしみ
朝日新聞より
「これはわたしのものだ」。そのような所有の感情は、それなしにじぶんがありえないと思われるほどに、<わたし>というものの存存の核をなしている。わたしの身体、わたしの持ち物、わたしの家、それらを他人が思いのままにするとき、わたしたちはじぶんの存存が否定された、綾辱されたと感じる。
それだけではない。じぶんの物と他人の物とを混同することは、社会の秩序を根幹から揺るがすような出来事となる。実際、自己の生命と財産の私約所有が公的に認められていることが、長らく市民の自由の基礎とされてきた。
その間に、国家が別の国家を所有することもあった。そして二十世紀の世界は、公有か私有かという、生産手段の所有り様式と生産物の分配方法とによって、社会主義的な国家体制と社会主義的な国家体制とに大きく二分されてきた。
さまざまな問いなおし
ところが、その所有の制度が、いま、社会のいろいろな場面できしみだしている。たとえは、土地がかつての高度成長期やバブル期に投機の対象として統制不能なまでに高騰し、バブル崩壊後は企業にとって不良資産として重い荷物になっている。
マイホームも一生かけてローンを返済する条件でようやく手に入れられるささやかな「夢」の象徴であったが、バブル崩壊後の地価の下落で引っ越しても借金だけが残るという酷い状況になってきた。
知的所有権の問題も深刻で、著作権等の個人的権利の保護が厳密になされる映画のように、関係者が多くまた公開後の別メディアでの放送権なども絡んでくる事業のばあいには,費用と手続きがかさばって制作行為そのものが困難になる状況も生まれてきている。
あるいは、臓器移植。ここには、脳死体の、あるいは(臓器堤供・売買のばあいは)生きた身体器官の処分権がだれに帰属するかという問題がある。身体の所有権をめぐっは、それが当該対象の可処分権と同一視されて、いわゆる自己決定の論理をかたちづくてきた。
臓器の堤供も、ファツションとしての身体変工/美容整形やピアシング)や「援助交際」という形態をとった売春も、しぱしは身体の自己所有という視点から正当化が試みられる。「わたしの身体はわたしのものなんだから、わたしがどうしようと勝手じゃない」というふうに。
最後に親権の問題、そして個としてのアイデンティティーの問題。
行動の決定権をもつという意味で(わたし)を所有するのはだれか、<わたし>はどういう意味で家族や会社に帰属するのか、またどういう意味で<わたし>はわたしのものなのか、いった問題がここにはある。このように、「所有」という概念と制度がいま、わたしたちの社会的な存在から個人的な存在まで、さまざまなレベルで問いなおされつつある。
利用型経営の構想描く
さて、六月に大野剛義が『「所有」から「利用へ』日本経済新関社)を上梓した。表題どおりの、社会の仕組みの大きな変換を提案する著作だ。
バブル崩壊後のデフレの時代には、保有資産のかなりの部分が負の資産、つまりは不良資産となり、「どれだけ資産を『所有』しているかではなく、限られた期間に人、モノ、カネの資産をどれだけ有効に『利用』できるかで企業の優劣が決まる」、これが大野の基本的な主張である。
大野はここで、「所有」によってひと・モノ・情報との長期的・継続的で固定的な関係をあらわし、「利用」ということでそれらへの柔軟で流動的な関係をあらわしている。
前者は事物との安定的な関係をもたらすが抱え込みや囲い込みによって閉鎖的なものとなるのに対し、後者が可能にする速度と開放性を時代が要請していると説く。
「所有」から「利用」へ、このコントラストのなかで、日本経済がいま迫られている大きな変換をくみ取ろうというのだ。
したがって議論は、あらたな所有論を展開するというよりも、むしろ所有型社会の病根を扶り、あたらしい利用型経常の構想を描くという内容になっている。
たとえば企業が社員を抱え込む組み(年功序列や終身雇用、企業内組合)、会社間の株式持合いや系列関係、さらには累進課税制度や苛酷なまでの相続税や贈与税、含み益に依存した経営、退職金給与引当金の計上方法や子会社を通じての利益操作の容認、土地に対する低率の国定資産税など、税制、会計制度じたいが資産の保有に対して有利にはたらくような古い仕組が、いまでは企業経営の足かせになっていると指摘する。
そして高収益、受注生産、顧客のニーズの変化に機敏に対応する営業、分社化によるスモールビジネスの集合体としてのネットワーク型経営など、彼のいう「利用」型経営のイメージを膨らませていく。
大野がここで指摘した、土地や株式資産をはじめとして「所有」そのもの自己目的化するような意識の刷り込みを、思想の次元で取り上げるのは、熊野純彦の『レヴィナス』(岩波書店)だ。
この本は、ひとはじぶんでないもの、つまり他なるものをこそ所有するわけで、そのかぎりで所有は他の肯定であるが、わが物として所有するとはその他なるあり方を中断するいうことでもあり、そのかぎりで同化という、他なるものの否定に終わるに終わると主張する。
その意味での所有の不可能性から熊野はレヴィナスとともに「所有と定住」のかなたに思いをはせる。
二つの議論、統合が課題
何かをだれかのものとして主張するその所有のほんとうの根拠がどこにあるのか(熊野)、そしてわたしたちの社会の所有のかたちはいまどういう問題を孕み、どういう変革を求めているのか(入野)、その二つの議論のあいだを、これから埋めていかなければならないだろう。
田中角栄元首相による列島改造案を深く憂え、それと平行するかたちでなされた司馬遼太郎の対談集『土地と日本人』、
近年では自己所有」の観念の検討を手がかりに書かれた二つの対照的な所有論、身体・生命の所有という観点からわたしたちの社会の基本的主廟として所有の問題の広がりを縦横に論じた立石真也の『私的所有論』と、
リバタリアニスム自由尊重主義)の原点から基本的人権としての市場的財産権について論じた森村進『財産権の理論』、
さらには大野の議論にも大きなヒントを与えた松井孝輿の、環境問題を背景とした「所有からレンタルヘ」という提言などが、これまで前史としてあった。
これらを前提として、「所有」という概念と制度についての根本的な見おなしの作業が、これから次の一世紀をにらむ社会構想の中で本格的に取り組まれることになるだろう。
知るということ
生きるヒント 五木 寛之より
見テ 知リソ、知リテ ナ見ソ
日本民芸館 初代館長 柳宗悦が「心うた」の中で書いている言葉です。
「見てから知るべきである。知ったのちに見ようとしない方がいい。」という意味でしょうが、実はもっと深い意味がある。
我々は知るということをとても大事なこととして考えています。
しかし、物事を判断したり、それを味わったりする時には、その予備知識や固定概念がかえって邪魔になることがある。
だからまず見ること、それに触れること、体験すること、そしてそこから得る直感を大事にすること、
それが大切なのだと言っているのではないでしょうか。
勉強することは、大事なことです。本を読み、知識を得ることは歓びです。
しかし、知ることの危うさもかならずつきまといます。このプラスとマイナスの両極の間に私達は生きています。
*****刺抜き先生から一言****
たえず、知識を仕入れるごとに疑ってかかって自分で納得してから吸収すること。
しかし、これではとても試験の時には間に合わないので
「まず知識を受け入れておいて、あとから自分で反復して吟味し直す」のが良かろう。