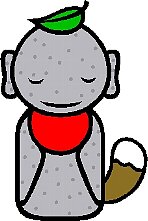
「さよならのしかた」一期一会
2004.07.23
0.「刺抜き地蔵の御札」おばあちゃん
いちばんショックだったのは、十五年来ずっと診ていた93歳のおばあちゃんです。
私に「刺抜き地蔵の御札」を持ってきてくれた人です。雨の日も、風の日も、
休まずに私の外来日に決まって通院していました。手縫いのモンペを身につけ、
診察台に上がるのも人の手を借りようとしない気性の強い人で、決して弱音をはかない人でした。
診察が済むと両手を合わせて「ありがとうございます」といつも言われ、
こちらが気恥ずかしい思いをしていました。
自分のことよりも残された息子のことを心配していました。息子はどうも心の病を持っていたらしく、
心配するあまりに十二指腸潰瘍出血を起こしてしまいました。入院して一週間としないうちに、
息子は自殺してしまいました。そのことを本人に知らせるべきか大変迷いましたが、
知らせないとますます心配してしまうと考え、翌日に伝えました。すると、意外や、
「もうこれで自分の治療に専念できます」と吹っ切れた顔をして言いました。
経過は順調で、歩くリハビリも進み通院となりました。
そして、歩けるようになったので酉の日の「御札」を届けてくれる様になったわけです。
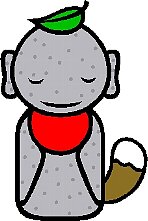
着物に燃え移り、体表面積の15%という火傷を受け、
自分のことは自分でするという強い信念の持ち主でしたので、
「退院したらこちらの外来で診よう」といくら待っていても音沙汰がありません。
五月の末、届いた手紙にはこうありました。
「母元気に過ごして、施設で療養していましたが突然、亡くなりました」
年を取ってくると毎日、毎日が「最期の日」なんだ。 沢山のこと教えてくれて有り難う
この恩人に敬意を表して、とげ抜き先生と自称することにしました。
1.上京してきた孝行息子
76歳で痴呆と心の病を両方持ったおばあちゃんで、転倒して大腿骨頚部骨折にて入院しました。
手術の説明するために家族と連絡をしようとしたら、息子さんは名古屋にいるということで、とりあえず電話してみました。
大事な母のことなので、すぐに話を聞きに行きますということになり、手術の二日前の午後に会いました。
母に会って安心した顔をし、メモ用紙に、きちんと内容をメモし、「なにぶん宜しく」と言って立ち去りました。
母親思いの「孝行息子」だなあとそのときは思いました。
翌日の未明、病院の電話がけたたましく鳴りました。
名古屋からで、「深夜、自宅に帰る途中に交通事故に遭って亡くなりました」とのことでした。
「ええっ?」 「まさか」 「そんな」
返す言葉がありませんでした。
本人には知らせないで欲しいということなので、「都合悪くてなかなか来れないの」と説明することにしました。
翌日の手術の時には、術者である私が精神的に動揺してはいけないと自分に言い含め、
立ち会った全員で黙祷をしてから執刀しました。
経過はきわめて順調で、麻酔の覚め方もよく、離床もスムース、リハビリも見違えるように生き生きとしてきました。
きっと、「息子さんの想い」がしっかり支えているのでしょう。
いまでも、息子さんは亡くなる前に、「想い」を伝えるために母のところまで「やって来たんだ」と私は思っています。
2.独り煙にまかれる
お隣の80歳の独り暮らしをしていたおばあちゃん。
後で近所の人から聞いた話である。
明け方、消防車のけたたましい音に近所騒然となる。ガラスは熱気でひび割れ、高窓は煙とすすで汚れていたという。
痴呆で足が不自由な母いわく「火は家まではこなかったみたい」。
どうも、救急車で連れ出されたが、息をしていなかったようであったという。
以後、どこに居るやら話は無く、どうも密葬をしたらしい。
近所付き合いをまったくしていなかったお隣さんだけに、
「誰ともさよならをせず」に寂しい終わり方をしたものである。
合掌。
3.孫のBridal旅行中、親戚に囲まれて
友人の母の話である。
孫が沖縄で結婚式を挙げるから、親戚じゅう揃って旅行しようということだったらしい。
旅行中、現地で倒れ、帰らぬ人となってしまった。
何もこんな時にどうして--−という気がし、
結婚式の思い出としては、当人達にはつらい思い出となってしまった。
しかし、喜びと悲しみ、生と死は裏腹であり、
去っていった人の立場から考えると、みんなに囲まれて、
「最期の楽しい思い出」とともに去っていったお母さんは、とても幸せであると思う。
孫の成長をあの世からしっかり見守ってくれるでしょう。
![]() ひとこと
ひとこと
それぞれの仕方を見ていると、「今生きていること自体」の質を問い掛けられている思いがします。
人と人との出会いは、その時その時がいつも最期であり、大切にしなければならない。
特に、年寄りには残された時間が少ないので、物事を先送りせずに「思い立ったらすぐ実行」を心がけるべきでしょう。
一期一会という言葉がありますが、「一生に一度限りの機会。」という意味です。
PS.
一期一会の語源は、「茶会に臨む際は、その機会を一生に一度のものと心得て、主客ともに互いに誠意を尽くせ」といった、茶会の心得からである。
利休の弟子宗ニの「山上宗ニ記」には「一期に一度の会」とある。
それぞれ「一期」と「一会」を辿ると、「一期」は、もと仏教用語で、人が生まれてから死ぬまでの間を意味し、「一会」は、主に法要などで、ひとつの集まりや会合を意味しており、仏教とも関係の深い言葉である。