
心療整形外科――――全人的治療のすすめ
0.心の痛み
「病は気から」というが、日頃よく見る症状(腰痛、頚部痛)のなかには、「体がいやだ」と言ったり、「心の痛み」としか思えないようなものが散見される。
共通することは、「早く痛みを取ってほしい、痛みだけでも取れれば」と言って鎮痛消炎剤をたくさん要求し、そのわりには、「ちっとも薬は効かない」早く早くと焦っていることである。少し話を聞いていくと、「痛くてよく寝られない」、「食欲がなくなった」、「最近疲れ気味だ」、などと言うことが多い。
これらの症状は、いわゆる「うつ」のもので、もがけばもがくほど泥沼に沈んでいくのである。「薬が切れると痛くなる」のは自然であるが、「ちっとも効かない」と言うのは、「体が痛い」からではないことになる。いわゆる「心の痛み」を考えなければならない。
正確には、心は痛くないのだ「辛い」だけなのだ。「体で痛みを感じる」のだ。だから、すぐに精神科に行かずに内科や脳外科や整形外科を受診することになる。患者さんの「痛い」を「辛い」に置き換えて診察に当たれば間違うことはなかろう。

これは、生真面目できちんとやらなくては気がすまない人に多い。筋膜性腰痛症、慢性過労症候群などでも同じ仕組みである。体が「いやだ」と言って止めさせようとしているのに、本人が拒否しているから厄介である。「体を休ませるように危険信号として痛みを起こしているのだ」、「自分の体のペースに合わないのだから時間がかかるよ、すぐには治りません」といくら説明してもなかなか納得してもらえない。それどころか、「早く治せるはずなのに出来ないのはおかしい」とまで言い出す人もいる。体と心が一つにならずに、分かれて別のことを考えている。自分の体をいたわったり、時には褒めてあげないと頑張らなければならない時に力が出るわけない。心と体が喧嘩をしていたのではいけません。
やはり、自分の体は自分が大事にしなければ良くならないのである。
2.自分が得する痛み
これは、治らない痛みである。「痛み」は当人にとって必要なものであり、無くなっては困るからである。子どもがヒステリーを起こして母親の注目を集めたいがために、どこどこが痛いと笑いながらいうのは、これである。大人の場合は、少し複雑で巧妙である。特に休業補償金が絡むと治るものまで治らなくなる。支払い打ち切りが決まると途端に来なくなる人をたくさん知っている。
金の切れ目が縁の切れ目なのか。
3.予想外のやられた痛み
交通外傷が典型的である。ぶつけられて痛い思いをし、救急車に乗せられて、行きたくもない病院に運ばれ、入院となって身の自由が奪われ、挙げ句の果てには、痛いであろう受けたくない手術が必要と言われた時の気分である。
「何でこんな目に遭うのか。あいつの所為だ。それにしても頭にくる、この痛み何とかならないのか藪医者め。」何度もこのような顔に遭遇した。イライラをぶつけようもないので近くにいる人に手当たり次第にぶつけてくる。このような時には、「安静にすること自身」がつらいのである。当面は、痛み止めと点滴で眠気を誘い、安静にすることに全力を注ぎ、イライラが静まって入院生活を受容するまで待ってから手術の説明をした方がよい。
心の準備ができるのを待つことである
4.事故の起こる三要素
交通事故の起こり方を見ていて次のようなことに気付いた。事故には三要素ある。自分側、相手側、それを取り巻く状況。「たとえ青でも突っ込んでくることがあるから」と周囲に自分が気をつけていれば、事故の頻度は激減する。「今まで平気だったから」と油断したり、「自分は間違っていない」と過信した時が危ない。見通しが悪い所や時間帯、音楽を聴いたり、他人とのおしゃべりに夢中になっている時、ボーとしている時、居眠りしそうになっている時、こういった環境の下で、相手が不注意をすればたちどころに事故が起きるのだ。
ぶつけないのは当たり前で、「ぶつけられないような運転方法、移動方法」が必要なのである。
また、安全は、「今まで何も起こらなかった」という意味でしかなく、「これからも平気だ」という意味ではないのだ。これと同じようなことが、政治経済で起きている。銀行の預金もしかり、年金の給付額もしかり、自分の命でさえも不確実なのだ。
自分の体は結局他からは守ってもらえずに、自分で守るしかないのだ。
医療事故についてもこのことはいえる。「今までは平気だったんですがねえ。」では通用しないのである。起こりそうなリスクを全身で予想し、
常に「我が身に突然降りかかってくるものだ」と思っていることが必要である。
人生も半ばすぎUターンすると嫌でも考えざるを得ない。「老いは音を立てずにやってくる」とはよく言ったものである。ついこの前まではふつうだったのに、明日は何が起こるかわからない不確実な時代に入った。
もう順番待ちに入ったのに遠くにあるようでいつ来るか分からぬ死期。つらい、嫌なことばかり目につくようになる。自分に自信が持てなくなり、悪いようにばかり考えてしまう。これが、「うつ」のはじまりである。
痛みに対して敏感になり、痛がることで「周囲の目を自分に向けさせて分かってもらいたい」と無意識に行動する。呆けてしまえば、辛いことはすべて忘れ、自分中心に世界が動きますので、幸せな時間にひたることができますが、呆けきれないうちが問題になります。
こんな時には、自分が楽しくなることをすることです。
「一回キリの人生なのだから楽しまなければ損」と自分に向かっていってみましょう。
「老いてきたこと」は「自分が人生の勲章をたくさんもらったこと」と考えましょう。
後ろ向きに今までのことをあれこれ考えても何も出てきません。出てくるのは、溜息だけです。
少しでも「楽しいこと」を少しでも「たくさん」できることを「幸せ」に思いましょう。
これが「プラス思考」です。
6.「治る」ということ
辞書を引くと、「病気やけがが良くなって,元の健康な状態に戻ること」とある。
「元通りになる」、「元気になる」、と「治る」はどこか違うように思える。一度傷ついたものは、一見元に戻ったように見えても元の状態ではない。ましてや、年をとってからの回復はなかなかである。たとえ不愉快でも、勇気を出して「治らぬ部分がある」と自己の老化を受け入れてあきらめることも必要である。死についても同じことで、人は遅かれ早かれ死を迎える。そのことを素直に明るく正面から受け止めてはどうであろうか。
いつまでも、高い得点を目指すのはやめましょう。90点を目指していたのを70点にした途端気持ちが楽になり心に余裕が出てきます。人間は、「治らぬ部分を抱えた存在である」ことを認めることで、道が一つ開けるのではないでしょうか。
医療でできるのは、悪くならないような「方向付け」だけである。
7.人間「パンダ」説
パンダは「黒いまだらが白い体にあるから」愛らしい。真っ黒だと憎たらしいが、真っ白でも物足りない。
善人と悪人、健康人と病人についても同じことがいえる。白でもなく、黒でもなく灰色のように均一でない。いつもは、白で、時に黒く、黒ばかりと思えば、白いところがあるので人間の魅力を感ずる。
これを精神科的にいうと、
人間は一見まともに見えても、おかしいところを少しは必ず持っているし、
一見おかしい人と思えても、優しい人間らしい心を持っているということである。
個性とか、多様性という言葉ありますが、まさしくパンダみたいな「まだら模様が魅力的」なのです。
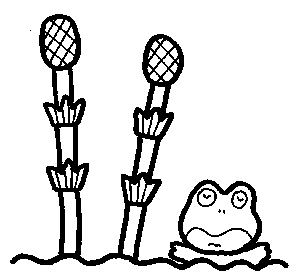
心身共に病めている人と接していて思うことは、とても自分に素直である。Pureなのである。一見、健康な人は心で思っていないことを口にしたり、嘘を平気でつく。心の病の人は、嘘をつくだけ周囲への気配りをしなくなっているか、嘘をつく必要がない。
その結果、自分中心で自分の気持ちに素直である。
9.診療のヒント
これだけの薬が効かないようなら、もしかして神経が敏感になってしまって、ちょっとしたことでも我慢が出来なくなってしまっているのかも知れません。
ひょっとしてこういうことが、ありませんか。食欲、睡眠、最近変わったこと、ストレス,と訊いていくうちに何かのキーワードに当たったように急に
「実はこんなことがあって、―――」と今まで言わなかったことを突然しゃべり出すことがある。ここまで引き出せればしめたものです。
「使う薬は、抗うつ剤といって体の調子を整えるものです。昼眠くなることはありません。1日2日では効いてきません。痛みは鋭さがだんだん取れてきて気にならなくなってきます。一週間続けると楽になったと実感できるでしょう。すっかり痛みがなくなることはありませんが心配ありません。」
時間をかけて自分の体に対する理解を深める。
自分にあったペースまで下げて心に余裕を持たせられれば、大成功です。