体の中を覗いてみる道具としては眼底鏡、胃カメラが知られています。ビデオカメラの小型化、軽量化に伴い膝にも鉛筆より細いカメラ(膝関節鏡)が出来ました。膝の中の様子をテレビの画面に映し出してどこが傷ついているかかたちどころに診断し、同時に治療もしてしまうというものです。ところが困ったことに胃カメラと違って入れる穴が膝にはありませんので、小さな穴を開ける必要があります。穴の大きさは1針すつ2箇所でバンドエイドに隠れる大きさです。また、膝には筋肉があるので麻酔しないと力が入っておたがいに検査がしにくくなります。そこで、10分くらいなら外来にて局部麻酔で行うことがありますが、しつかり行おうとすると腰の麻酔が必要になります。麻酔をかけると歩けなくなるので入院が3日間は必要です。抜糸は7日目に行います。何よりもガパッと大きく切らないことが一番の利点です。
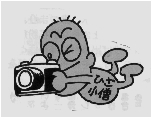
§2.膝の「入れ歯」の話
年をとって先づ弱って来るところと言えば歯です。歯も小さな虫歯のうちは削って詰めることをしますが、何本も悪くなってくると「入れ歯」になります。膝の骨も年を経て使い込んでくると軟骨がすり減って、地肌が直接触合って痛みの原因となります。痛い部分の骨を薄く削って金属をかぶせるということで痛みをとり、噛み合わせをスムースにするというわけです。コンピュータ−を用い設計し、人間の膝の形そつくりで、軽くてよく滑るものがどんどん出来ています。「人工関節」というとごつく感じますがこのことです。痛みに速効的でガ二股も同時に治るので、60-65歳以上の高齢者に適しています。但し、40-50歳台で飛んだり跳ねたりする人には不向きで、時間がかかつても「自分の骨」で、もたせることを考えます。
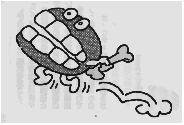
§3.膝の「油」の話
筑波山のガマ油なら皆さんもよく知っているでしょうが、膝にもいい「油」ができました。ヒアルロン酸ナトリウムというと何のことかよくわかりませんが、無色透明でドローとしている液体です。膝の関節の袋の中の「油」の成分に相当し膝の曲げのばしをスムースにする働きをしています。若いうちは関節の袋が自分でよく「油」を作りますが、年をとると次第に生産が追い付かなくなり、骨の軟骨がすり減って地肌が擦れ合い、膝がギシギシ音かするようになります。そこで古い自転車には油をさすように、ヒアルロン酸ナトリウムを膝に注入して「油をさす」ことが行われています。毎週1回、5-10回行うと滑りがよくなり、この間に自分の軟骨の修復が進み痛みは軽減してきます。
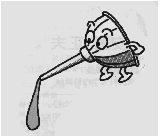
§4.「がくがく膝」の話
膝の筋力は四十歳台より急に低下してきます。いのゆる「足腰が弱くなってきた」ことと関係しています。特に膝を伸ばす筋力の低下が問題ですので、椅子に座ったまま片方すつ足を水平まで挙げたまま5秒すつこらえることを交互に行うと膝がしっかりしてきます。これは毎食前に10回ずつしましょう。立っているときには、肩幅に足を外向きに開き、いわゆる仁王立ちになって少し膝を曲げたまま5秒間こらえる練習も階段昇降時に踏ん張れるようになり効果的です。若い人がけがをしてからなった場合には、膝の靱帯を摂傷している可能性が大きいので、膝外来の受診をすすめます。
§5.「膝の音」の話
しゃがむと「コリコリ」音がするのは膝の「おさら」の軟骨がすり減っているためにおこります。軟骨の傷が大きい場合やいわゆる油切れの場合にひどくなります。痛みがなければ放置しますが、痛みを伴う場合には、「油をさす」ことや膝を伸ばす筋力強化が必要になります。
§6.「膝の水」の話
膝の水を抜くと「くせ」になるかと心配する人がいます。膝にお金がたまるのならいいのですが、水がたまるのは有り難くないものです。これは関節軟骨の削りカスの刺激による清膜炎が最も多い理由です。カスの量が多いとなかなかひかず「くせ」なるものもあります。カスと水を抜いて油をさして本来の軟膏の自己修復復の助けをすることを行います。若い人で膝を捻ってから水がたまるようになった場合には半月板に傷が入ってあこる場合もありますので注意がいります。関節鏡検査が必要なこともあります。
§7.「ガ二股」の話
「ガ二股」とは膝の○脚変形のことを呼びますが、これは膝関節の内側ばかりが片減りしたためにおこるものです。変形がひどく、歩くときに痛みを強く感じるようになり湿布や鎮痛剤にても治らなくなった場合には、人工的に骨折を作って「ガ二股」を真っ直ぐにすることが必要になります。
§8.「おすわり」の話
膝の曲がりが悪くなる原因としては、・関節面がすり減ったり、骨のとげができて形がイピツになる場合と・軟骨の間のクッションの働きをしている「半円板」に傷が入り、ポソポソになりつっかえてしまう事が多いようです。この様な場合には、無理せすに椅子を用いるようにしますが、どうしてもおすわりしたい時には入浴中にしゃがんでみることをすすめます。これは、風呂にはいることにより体重が軽くなり、膝が暖まつて柔らかくなり曲がり易くなるからです。若い人で、急に膝がひっかかった」ような場合には半月板の損傷が最も疑われますので、膝の中を調ベる関節鏡検査が必要になります。
§9.「ジンタイ」の話
ジンタイって、人体のことかと思われるかもしれませんが、「靱帯」と書くいわゆる「スジ」のことです。特に骨と骨をつないでしっかりと支える「スジ」です。一つの膝には、主な靭帯が前後内外の計4本あって、各々の方向を支える働きをしています。1本だけのびても大した障害はありませんが、2本以上切れると「捻り」に対して弱くなってきます。持に、テニスや、バレーボールでは致命的となります。この様なスポーツを続けたい場合には自分の体のスジを使って、作り直すことをします。リハビリをスピードアッブするために合成線維でできた組紐(人工靭帯)で補強することも行われていす。現に全日本女子バレーボールチームの名セッタ−中田選手はこの手術をしています。しかし、靭帯は残念ながら普通のレントゲンフィルムには写りませんので、手触りで診断されます。最近「MRI」といって超伝導磁石を用いた検査の画像では鮮明にとらえることが出来ます。この検査は大きな磁石の中にただ寝ていればよく、レントゲンの被爆もありませんから大変楽なものです。
§10.湿布の使い方について
けがをしたら冷やすの?暖めるの?よく聞かれる質問です。−般的には、けがをして3-4日は冷やして出皿、腫れを最小限にするようにします。5-7日たてば、暖めて血流をよくし腫の退くのを助けます。この場合の冷やし方たは氷やアイスノンを用いることをいいます。混布は貼るときにスーとして冷たく感じるため、これを冷やす目的のためと思われるようですが、湿布剤の鎮痛消炎効果を期待しているのであって、冷すためのものではないのです。慢性的な痛みは暖めると和らぎます。
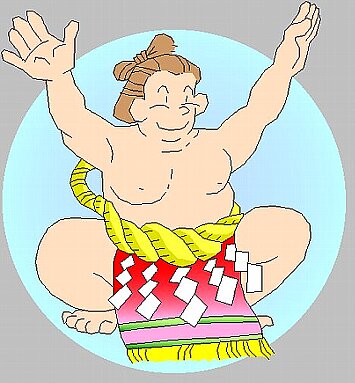
§余談 「力士の膝」の話
おすもうさんというと巨体を想像し、何キロという体重を考えます。でも、体重にふさわしい骨の太さをしていて、特に十両以上では脂肪ぷとりではなく意外にしまった肉をしていることが多いんです。相撲という競技は1分以内に勝負が決まるため、息を殆どしていません。筋肉内にたくさんたくわえておいたグリコーゲンという栄養を−気に使って力を出すわけです。だからマラソンのような持久力をつけるトレ一ニングは適していません。ダッシュのみです。以前、私はハワイ出身の超大型力士の治療チームに加わっていました。彼は膝の半月板と靭帯の損傷をしていました。普通なら手術適応でしたが、年に6場所もあって入院して治療を受けるには忙しすぎるし、第−、手術用ベットは150キロ以上では壊れてしまうし、誰がどうやって麻酔をかけるかが問題でした。結局、除痛を主として減量と筋力強化行うことにしました。膝に油をさして滑りをよくし、温水ブールの中を泳くのではなくただ早く歩き回る方法です。これは水の中では体重が軽くなるなるためゆっくり歩くと大した筋力はいりませんが、速く進もうとすると水の抵航が大きくなるために筋力を−層必要とするものです。特に下肢の筋肉のトレーニンクには最適と思います。このトレーニングの成果があって「負け越せば、大関を引退」という瀬戸際をみごとクリアーし、今ではス夕−となりました。