
バッハとの出会い
§1.バッハと右脳 01.09.24
小学校で習ったときは、「音楽の父」だという。白髪のおじさんで、何が父だかわからんかった。学校では、納得のいくまで音楽を聴かせてくれないし、昼休みにでも、少しは先生のお薦めの音楽を流してくれればいいのに、時間がないという理由で少しも聴かせてくれなかった。美しい音色と旋律のある音楽を聴きたいとこのころから思っていたのは、ちょっと変な小学生だったのかなあと思う。でもその頃、確か、「トッカータとフーガ」だったと思うが、こんな世界があったのかと驚いたのはよく覚えている。
バッハのことは何も意識せず、ピアノを習い、「バイエルが音楽の基礎だ」と思いこんでいた。後半の部分まで進んで、シャープが三つになると、何がなんだかわからなくなって譜面をみるのがいやになった。
今考えると、譜面の音符を一つずつ考えていてちっとも進まなかった。これは、左の脳ですべてを処理しようとしていたための不適合だったんだろう。どうもへ理屈は左の脳で処理をして、無意識のパターンは右の脳で処理するらしい。だから、寝ていても降りる駅が近づくと目が覚めるし、酔っていても知らずに自宅にたどり着けるのだ。このパターンをどんどん増やしていくと、「自分の潜在能力の開発」になるはずだ。パターンで覚え、何も考えずに自然に手が動くようになるまで、しっかりと右の脳を鍛えておけばよかった。

横道に逸れるが、「ピアノを習っている人は英語がよくできる」ということを聞いたことがある。ピアノは丸暗記であり、パターンの繰り返しである。屁理屈ばかり先行するとちっとも進まない。英語も丸暗記である。パターンの繰り返しである。英語のアクセントは音楽のメロディーと同じである。だから、共通するところがあるのでしょう。英語を学ばせるなら、まず音楽を習わせよう。そして、語学を学ぶなら、「まず一年は、テキストなしで何回も聴くことが一番だ」と思う。テキストをみるとやった気がするが、ちっとも身に付いていないのは皆さんよく承知です。わかっちゃいるけど出てこないのである。
§2.浪人生と受難曲 01.09.25
中学・高校はバッハとは全く無縁であった。自由を翻弄していた。ビートルズの影響を受けて、バラードが好きになった。イエスタディ・ミッシェル・ノルウェーの森など人恋しくなるような音楽に好かれていった。ギターを始めたのもこの時で、楽譜が読めたのと音程がわかるのは非常に役に立った。ギターは和音で音を出すので、人にとって「いろいろな気持ちのいい組み合わせがある」ことを知ったのである。この組み合わせの基本をバッハが作ったとは思いもよらなかった。高校2年の時大学の紛争が飛び火して高校でも学園封鎖となり、まともに勉強しなかった。しかるべく浪人生となる。
浪人生とは精神的に非常に不安定で、立場も大学生でもないし、社会人でもないという変な立場である。重苦しい雰囲気に飲まれそうになることしばしばであった。受験が処刑であり、合格が復活のようでもあった。落ちれば「人間として扱われずに、地獄に堕ちるかもしれない」という恐怖の念にいつも囚われていた。十字架を背負ったイエスキリストの像が頭をよぎった。
こんな時に、お茶の水の予備校の近くのレコード店で「マタイ受難曲」なるものを見つけた。「何だこれは?」聴いてみると何ともいえずに重い出だしである。十字架を担いで道を歩かされる場面では、聴いているのが苦しくなり、逃げ出したくなった。でも、これ以上苦しい感じはないなあと思ったとたんに、自分の気持ちがすっと落ち着いてきて、雑念がなくなった。何か元気が出てきた。不思議だった。J.S.バッハ作曲と書いてあった。何のためにこんな音楽を作ったのだろうと思った。
後で解ったことであるが、「人の幸せは絶対的なものではなく、他との比較で決まるものである」。人の不幸をみて喜ぶのは全くこの事である。「不幸な人と比べれば自分はなんと幸せなことか。」そう思ったとたんにいつもとちっとも変わらないのに幸せな気分になっている。これは、女性週刊誌に毎回必ず人の不幸の記事がこれでもかと載せられているのをみれば理解できる。それと同じで、重く沈んでいるときには、明るい音楽はだめで、もうこれ以上暗いものはないというような音楽を聴かせると元気になってくるものだ。
§3.ビバルディとバッハ 01.09.28
大学時代といえば、寮に住み込み深夜放送を聴きながら、麻雀をよくやったものだ。この時に、「ジェットストリーム」という城達也のイージィーリスニングの番組がありよく流れていた。ここで、「G線上のアリア」を聞いたときにはなんとバィオリンの響きの良いことかと感動した。もっと聴きたいと思うところで尻切れトンボになってしまうのはいつものことである。欲求不満になっていたところ、朝早起きをしたときに、6時だったと思うがNHK-FMで皆川達夫の「バロック音楽の楽しみ」を聞く機会があった。ここで、ビバルディのフルートソナタ「忠実な羊飼い」をやっていた。素朴で、耳に優しく、わかりやすいリズム。思わず聞き入ってしまった。
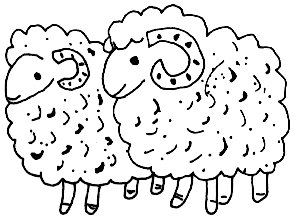
元々、フルートは女が吹く楽器でちっとも迫力がないやと勝手に思っていたものだから、以外や以外という感じであった。癒すというか、落ち着くというか、聞いていていい気持ちになるのであった。これもなかなかいいなぁ。でも、今さら楽器なんかやれるかい、と思う傍らでフルートに対するあこがれの念はどんどん深まっていくのであった。
自由な立場になると、それまで抑圧されていたものがいっぺんに出てきて自分が解放されるのであろうか。重い十字架を背負って生きていた自分が、この解放される日を待っていましたとばかりに、試験の当日には頭のてっぺんから力が体中にみなぎってくるのを感じたことをよく覚えています。G線上のアリアを聞いたときは、何か「昔もっと聞きたかったもの」が急によみがえった感じでした。なんで、音楽に惹かれるかよく自分でもわからないのですが、根っから好きみたいです。とにかく、バッハとビバルディは聴きまくりました。
そこでわかったことだが、バッハはそれ以前の時代の作品を楽器を替えて演奏したりしているんですね。著作権侵害という概念はなかったらしく、私ならこんな風にするという案配がふつうであったようである。リズムが同じものもかなりあった。「自分の主張がはっきりしていれば同じ材料でも使って差し支えない」という良き時代であったのでしょうか。
§4.「受難曲」と呼吸 01.10.08
大学の卒業試験・医師免許の国家試験と再び6年ぶりの受験がやってきた。これに落ちてしまえば、ただの人で今までにやってきたことがすべて水の泡になってしまう。すっかり忘れていたあの抑圧された気分がよみがえってきた。心が穏やかでなくなってきた。
とその時、「マタイ受難曲」を聴いてみた。気持ちが妙に静まりすっきりして力がみなぎってきた。呼吸が静かになり、時のたつのがゆっくりとなるのを感じた。通奏低音の響きが「ゆらぎ」というか心地よいものに聞こえた。1分間に40サイクルぐらいで、Largoのテンポであったことが後でわかった。
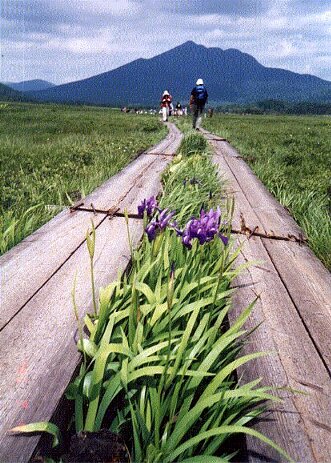
イライラしたり、不安になったりすると自然と呼吸が浅くなり、荒くなってくる。ゆったりとした音楽に合わせて耳を傾けていると自然と呼吸がリズムに合ってきてゆったりとしてくる。気持ちがすっきりしてくるというのは、きっと脳波もゆったりとしてきてアルファ波を出しているためであろうか。「癒し」とか「リラクゼーション」とかいうものはきっとこのことをいうのであろう。
今では、どこでも受難曲を聴くわけにはいかないので、イライラしてきたと思ったら、外へ出て、ゆっくりと気功のような踊りをしてみると、あら不思議、気持ちが落ち着いてくる
のである。まず、呼吸を整えよう。
§5.受難曲を聴き比べて 01.10.18
去年はバッハ生誕250年ということで、さまざまな演奏会があった。普通はマタイ受難曲とヨハネ受難曲とロ短調ミサ曲がよく採り上げられるのであったが、横浜合唱団が芸術劇場でなんとマルコ受難曲なるものをやったので聴きにいってきた。
福音史家がストーリーを読み上げ、イエスのバスと群衆の合唱で進行し、感情表現のためのアリアと人々の感情を表すコラールが所々に配置されていた。マタイ受難曲とにている曲が所々に見られた。アリアが少なくコラールが多かった。それほど重々しくなく、なにかモダンささえ感じだ。
マタイ受難曲は、重々しくしっかりと重くのしかかってくる感じがある。ヨハネ受難曲は、軽いテンポで軽快でヤンキーな感じである。ロ短調ミサ曲はこれらをすべて統合して完成された感じがある。
バッハがひとりでこれだけの曲を書いたとは信じがたいものである。人間の業とはとても思えず、宇宙人の地球人への「癒し」のための贈り物であったのかもしれない。なんてことを考えさせてしまう。
§6.バッハとジャズとピカソ 01.11.20

バッハの音楽は、リズムも和音の展開も厳格に規定されているために、多少崩しても元のリズムがわかる。それは、ジャズメンたちに格好の材料を提供することとなった。どんなに崩しても元に戻りやすいためか、キースジャレットなどの沢山のジャズメンが挑戦している。
しかし、基礎がしっかりしていないで崩すとめちゃくちゃになってしまうので、やはり音楽は、バッハから入っていく事になるのである。
「崩すもの」といえば、絵画の世界のピカソを思いだした。フランスのピカソ美術館に行ったことがあるが、彼ははじめの頃は写実的な絵を描いていたのでびっくりした。現実にあるものを正確に写し取れるようになったところで、次に自分流に感じたことを表現する。これが「崩すこと」なのだと思う。それが進むと、自分の感性のみの世界を展開するようになっていく。こうしてピカソの絵になったんじゃないであろうか。
絵を見ていると、「この絵はどういう気持ちで何を表現しようとして描いたのか」とこの頃考えるようになってきた。少しは鑑賞のしかたが深まったかな。ジャズもこのように楽しむとおもしろくなる。
§7.教会は音を丸くする 14.10.18
2014年9月に、バッハゆかりの地ケーテンのヤコビ教会とアウグスヌス教会で、古楽器による室内楽を聴く機会があった。
受難曲以来、こんな曲がどんなところでどのように演奏されていたかは非常に興味があるところで、
ワクワクしながら郵船ツアーに参加した。
まずSpalla、ビオラを大きくして分厚くしたもので左肩にかけて弾く。
Kuijukenの無伴奏チェロ組曲は、ホールで聴くストラリバリウスCelloの力強さとは異なり音量は少ないがまろやか。
確かに耳あたりがよい。うっとりしてしまう感じ。
少人数で十分な響き。天井が高いので、余韻が3秒近くありホールの2秒少しとはやや趣きが違う。
それにしてもバイオリン弾きが何でチェロを弾けるんだろう。疑問が沸いてきた。
構えが同じなので、当時はバイオリンとチェロの違いがあまりなかったのかもしれない。
次にバイオリン。Brandenburgを聴いたのだが
天井の高いせいもあって余韻が長いためVnとVlaが弾いているのが混ざりあってパイプオルガンの響きに聴こえる。
弦楽器ではなく、管楽器になっているではないか。これには驚いた。
室内楽は近くで聴くなら古楽器、しかも少人数でないと響きすぎて喧しくなりそうである。