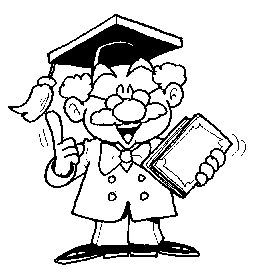
人生に革命が起きる100の言葉
著 Alfred Adler 訳小倉広
ダイヤモンド社 1600円
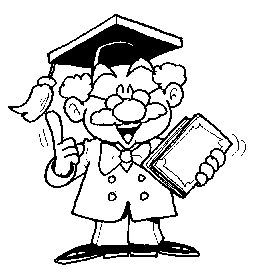
世界はシンプルで、人生は思いどうり
すべてあなたが決めたこと
自己決定性について
そのままの自分を認めよ
劣等感について
感情には目的がある
感情について
性格は今この瞬間に変えられる
性格(ライフスタイル)について
あらゆる悩みは対人関係に行き着く
ライフタスクについて
家族こそが世界である
家族構成について
叱ってはいけない、褒めてもいけない
教育について
幸せになる唯一の方法は他者への貢献
共同体感覚について
困難を克服する勇気を持て
勇気について
他人の課題を背負ってはいけない
課題の分離について
自己決定性
001 現在の人生を決めているのは「運命」や「過去」のトラウマではなく、自分自身の考え方である。
人生が困難なのではない。あなたが人生を困難にしているのだ。人生はきわめてシンプルである。
002 自分自身が下してきた決断は誰かに強制されたものではなく、自分が、自分の意志で下してきたもの。
人間は自分の人生を描く画家。あなたを作ったのはあなた。これからの人生を決めるのもあなた。
003 自分自身の力ではいかんともし難い事柄をどのような気持ちで受け取り、どのような意味づけをするか、
は常に私たちの選択に委ねられている。
たとえ不治の病の床にあっても、天を恨み泣き暮らすか、
周囲に感謝し余生を充実させるか、自分で決められる。
004 材料はあくまでも材料でしかありません。それをどのように使うか、という自由を私たちは持っている。
遺伝や育った環境は単なる材料でしかない。その材料を使って住みにくい家を建てるか、
住みやすい家を建てるかは、あなた自身が決めればいい。
005 自らアクシオンを起こすことでしか運命は好転しない。人は誰もが自らを変える力を持っている。
「親が悪いから」「パートナーが悪いから」「時代が悪いから」「こういう運命だから」
責任転嫁の典型的な言い訳である
006 人は未来への「目的」により行動を自分で決めている。自分の意志でいつでも自分を変えられる。
人は過去に縛られているわけではない。あなたの描く未来があなたを規定しているのだ。
過去の原因は「解説」にはなっても「解決」にはならないであろう。
007 人は人生の敗北を避けるために、あらゆるものを利用する。
人は人生の敗北を避けるために、時に人は自ら病気になる。「病気でなければ出来たのに」
そう言い訳をして安全地帯へ逃げ込み、楽をするのだ。
008 健全な人は、相手を変えようとせず自分が変わる。不健全な人は、相手を操作し、変えようとする。
「どちらが悪かったのか」に時間や労力をつぎ込むくらいならば、
その分のエネルギーを未来の解決に費やす方がはるかに生産的です。
009 人は「認知」や「意味づけ」を変えることで、いかようにでも思考、行動、感情を変えることができる。
「やる気がなくなった」のではない。「やる気をなくす」という決断を自分でしただけだ。
「変われない」のではない。「変わらない」という決断を自分でしているだけだ。
010 同じ環境に育っても、人は自分の意志で、違う未来を選択できる。
遺伝もトラウマもあなたを支配してはいない。
どんな過去であれ、未来は「今ここにいるあなた」が作るのだ。
劣等感
011 あなたが劣っているから劣等感があるのではない。どんなに優秀に見える人にも劣等感は存在する。
劣等感は「人よりも大きく劣っている人特有」のものではありません。
いつまで経っても永遠に目標は未達成。だからこそ、そこに劣等感が生まれるのです。
012 劣等感を抱くこと自体は不健全ではない。劣等感をどう扱うかが問われている。
劣等感をバネにして、「なにくそ」と頑張る人は、「劣等感」は持っているが、
「劣等コンプレックス」を持っていない。
013 あなたができない本当の理由は、環境を言い訳にして「努力から逃げている」ことにある。
劣等感を言い訳にして人生から逃げ出す弱虫は多い。
しかし、劣等感をバネに偉業を成し遂げた者も数知れない。
014 人は「ほめられる」という「正の注目」を得られないとわかると、
「叱られる」という「負の注目」を集めようとする。
人生をみじめにするような努力(おこられるようにする)は止めるべきだ。
015 強がりはコンプレックスの裏返し。
「強く見せる」努力は止めて、「強くなる」努力をすることだ。
016 世話好きな人は、単に優しい人ではない。
相手を自分に依存させ、自分が重要な人物であることを実感したいのだ。
017 ルドルフドライカースによる「不適切な行動の4つの目標」
人は注目されないと、悪さをしてまでも「注目を集めよう」とする。
それに失敗すると、「力を示す」、「復讐」
さらに今度は自分の無能さを見せつけて課題から「回避」するようになる。
018 過度の劣等感は健全ではなく、克服する必要あり。
元になる過度の思い込みは冷静に立証を試みれば消えていく。
019 不完全さを認める勇気を持つ人だけが本当に強い人間であり、幸せになれる。
できない自分を責めている限り、永遠に幸せにはなれないであろう。
今の自分を認める勇気を持つ者だけが、本当に強い人間になれるのだ。
感情
020 悲しいから涙を流すのではない。相手を責め、同情や注目を引くために泣いているのだ。
本人も意識してないうちに、涙により同情を集めたり、注目を得たり、
時には抗議や復讐であることもある。成功パターンとして繰り返し使われる。
021 カッときて自分を見失い怒鳴った、のではない。
相手を「支配」するために「怒り」という感情を創り出して利用したのだ。
感情の使用目的は、一つは相手を操作し支配する。もう一つは、自分自身を突き動かすため。
022 感情は車を動かすガソリンのようなもの。感情に「支配」されるのではなく、「利用」すればよい。
感情という心の声にジッと耳を傾けることで、一歩踏み出す、もしくは退くきっかけが見つかる。
023 不安だから、外出できないのではない。外出したくないから、不安を作り出しているのだ。
不安という原因により行動が規定されるのではなく、逆に目的が先にある。
リスクをとりたくないのだ。
024 子供は「感情」でしか大人を支配できない。
大人になっても、感情を使って人を動かそうとするのは幼稚である。
025 嫉妬でパートナーを動かそうとすればいずれ相手は去っていくであろう。
私たちは言葉を用いて理性的に話し合い、互いに利益がある結果を手にすることができる。
026 彼氏に対しては甘えた声で。配達員にたいしてはキツイ声で。
人は相手と状況に応じて行動を使い分ける。
あらゆる人の行動には「相手」と「目的」がある。推測し観察すると相手の気持ちが見えてくる。
027 「わかっているけどできません」とは、単に「やりたくない」だけなのだ。
意識と無意識は矛盾しているようでも、
同じ一つの目的に向かって統一的に相互に補うように働いている。
同じように、理性と感情も矛盾しません。それらは一つです。
それが分割できない統一体すなわち「全体論」なのです。
028 「無意識にやってしまった」「理性が欲望に負けて」とは、自分や相手を欺くための「言い訳」でしかない。
責任を取りたくない、敗北を認めたくない、良心の呵責を包み隠すために、
「自分は悪くない。無意識と感情が悪いのだ」と言い訳し、自分と他者を欺きたいだけなのです。
029 怒りなどの感情をコントロールしようとするのは無駄である。感情は「排泄物」なのだ。
ライフスタイルとは、物事の捉え方・認知の中核をなす基本的信念です。
私たちは、相手の言動や世の中の出来事という刺激にダイレクトにするのではありません。
その間にその人なりの捉え方、すなわち「認知」があるのです。
「認知」の根底には自己否定的なライフスタイルが隠されていて、これを正さなければならない。
性格(ライフスタイル)
030 ライフスタイル(性格)とは、人生の設計図であり、脚本である。
性格が変われば、人生はガラリと変わるであろう。
「世の中の人は自分を受け容れてくれる」「自分は人から好かれている」というライフスタイル
の人は、自ら会話の中心になる。
「世の中の人は自分を拒絶するに違いない」「自分は好かれるはずがない」というライフスタイル
の人は一言も話さない。性格の奥にある核となる信念を見つけ、変えると、行動/感情が変わる。
031 性格の根っこには、三つの価値観がある。
自己概念「私は◯◯である」、
世界像「世の中の人々は◯◯である」、
自己理念「私は◯◯であらねばならない」という三つのセットにより決まってくる。
自分を変えていく第一歩が、自分の性格がこの三つのセットからなっていることを知ることである。
032 人はライフスタイルを10歳くらいまでに自分で決めて完成させる。そして、それを一生使い続ける。
私たちは試行錯誤を繰り返して、
「こうすると、相手はこう反応する」「これはうまくいった」「これはうまくいかなかった」と学習する。
033 私たちは認知バイアスを通してしか世の中を見ることはできません。
同じ場面に出会っても受け止め方は十人十色。
ピンク色のレンズの眼鏡をかけている人は、世界がピンク色だと勘違いしている。
自分が眼鏡をかけていることに気づかない。完全に客観的な見方をすることはできないのです。
034 使い慣れたライフスタイルが支障きたしても、人はそれを変えようとしない。
現実を曲げても、自分は正しいと思い込む。
私たちは認知バイアスから逃れることはできない。
認知バイアスにより自分に都合の良い情報だけを取り入れ、それ以外は例外として処理する。
自分にとって都合のいいように解釈をねじ曲げて、
「これまでの考え方は正しかったのだ」と無理やり納得しようとする。
その方が楽であり、そうでないと不安になる。
035 ガミガミと叱られ続けた人が暗い性格になるとは限らない。
親の考えを受け容れるか、おやを反面教師にするかは、「自分の意思」で決めるのだから。
影響要因によりライフスタイルが自動的に決まるのではなく、
本人が「目的論」的にライフスタイルを選び取り、自分の意思で完成させていくのです。
036 幸福な人生を歩む人のライフスタイル(性格)は、必ずコモンセンス(共通感覚)と一致している。
歪んだ私的論理に基づく性格では、幸せになることはできないであろう。
共通感覚とは個人にとっても組織や家庭にとっても、共に受け容れられるような意味づけ。
私的論理とは、個人にとってだけしか受け容れられない、共同体では受け容れがたい意味づけ。
037 「怒りっぽい性格の人」など存在しない。「怒りという感情をしょつちゅう使う人」なのだ。
怒りを持つか持たないか、ではなく、怒りをどのように扱うか、
怒りをどれくらいの頻度で利用するか、を変更すること。
それが性格を変える、ということなのです。生まれ変わることではありません。
038 自ら性格を変わりたいと思い努力すれば、性格は死ぬ1から2日前まで変えられる。
現在の性格の中核的信念である「自己概念」「世界像」「自己理想」をきちんと把握する。
対人関係(ライフタスク)
039 すべての悩みは対人関係の課題である。仙人のような世捨て人さえも、実は他人の目を気にしている。
040 「最近ウツっぽいんです」「忙しくて休みが取れないんです」
内面の悩みに見える言葉も、すべて対人関係に起因している。
私たちの言動や感情には、すべてそこには「相手」がいて、
自らの優位性をアッピールするという「目的」があります。「使用の心理学」なのです。
041 完全に対人関係からの悩みから開放されたければ、宇宙でたった一人きりになるしかない。
人は一人では生きていけません。対人関係から逃れることはできないのです。
042 あらゆる人生の課題は、対人関係に集約され、それはわずか3つに集約される。
「仕事の課題」、「交友の課題」「愛の課題」後の方ほど解決は困難。
043 「◯◯してくれない」という悩みは自分のことしか考えていない何よりの証拠。
あなたのために他人がいるわけではない。一人ひとりが等しく自分の人生の主人公であり、
誰もが等しく世界の中心に居たいと思っている。
044 交友や愛の課題における失敗から逃れるために、必要以上に仕事に熱中し、週末の休日さえも恐れる。
仕事に熱中する理由は、「今ある交友や愛の課題」「未来の交友や愛の課題」から逃げること。
045 「愛の課題」とは異性との付き合いや夫婦関係のことである。
遠くから見ているうちはいい面が目につくものです、
いつも一緒にいると相手の嫌な面ばかりが目についてしまうのです。
046 配偶者を従わせ、教育したいと思い、批判ばかりしているとしたら、その結婚は決してうまくいかない。
結婚するということは、相手を誰よりも大切に思い、自分の事以上に相手を大切にすることです。
「自分が何を手にするか」「自分の要求をいかに押し通すか」と考えるのではなく、
「相手に何を与えられるのか」「相手をいかに喜ばせられるか」を常に考え、実行する。
しかも、それをどちらか一方だけではなく、双方が共に実行する。あくまでも二人が平等であり、
奪うことよりも与えることを大切にする。それが結婚生活を幸福なものにする唯一の方法です。
家族構成
047 子供にとって家族は「世界そのもの」であり、親から愛されなければ生きていけない。
そのための命がけの戦略がそのままの性格形成につながる。
子供は親の愛や関心を引くために、「いい子になる」「自分の弱さをアピールする」「問題行動を起こす」
などの戦略を実行している。そのうちで、成功したやり方が生き残り、
その後大人になってもずっと繰り返して使われます。それがその子の性格になっていくのです。
048 第一子、中間子、末子など兄弟間で得意分野が異なるのには理由がある。
兄弟の間での「親の愛」を巡る奪い合いが始まり、それぞれ違う分野で認められようとするから。
049 第一子は、初めての子として両親の愛を独占する。
しかし、第二子の誕生と共に突然「王座と特権」を奪われるのだ。
その後、かっての「帝国」を取り戻そうとするだろう。
第一子は年長であるために、兄弟の中で体格や知能において優れており、
リーダーの役割を担います。また、非常に高い目標を掲げ、
それを追いかける勤勉な努力家になりがちで、
「自分はいつも一番優れていなければならない」「いつも正しくなくてはならない」といった
理想主義、完璧主義になりがちです。そのために背伸びをして無理をしてしまいます。
また、法律や権威、世間体を重んじる保守的な性格になる傾向があります。
050 中間子は親の愛を独占したことがないため競争的、攻撃的で、すねた人になりがちだ。
「自分の人生は自分で切り拓かなくてはならない」と思う傾向がある。
追いつくべき目標が明確にあるため現実主義になりがちで、「名よりも実を取る」傾向強い。
第一子と競合しない分野での自分の特徴を出そうとする。
051 末っ子は甘やかされて育ちがちだ。問題児になる確率が高い。
そのため、自分では努力せず、無力さをアッピールして人にやってもらおうとする「永遠の赤ん坊」になる。
手本となる兄弟が上にいるため、対人関係が上手。
そして一番上の兄弟と同盟を結び、中間子と対抗することがよくある。
052 一人っ子は、親の影響を多く受ける。
また、末っ子と違い、兄弟がいないために、人間関係が不得手な人が多い。
常に親の愛と注目を独り占めして育つために、甘やかされ、わがままで自己中心的な子供になる。
周囲には常に大人ばかりいるために、自分のことを無力で劣った存在であると思いがち、
自信なく依存的。年長者との対人関係のみうまくなり、
同世代の子供との人間関係が苦手となる傾向にある。
053 身振りや話し方が親に似るのは理由がある。
親と同盟を結んでいることを他の家族にアピールする、
または衝突しながらもその親が持っている権力を手に入れようとする。結果として本当に似てくる。
054 子供は両親が持っている価値観を無視することができない。全面服従して受け容れるか、全面反抗するのだ。
家族価値は子供の価値観形成に大きな影響を与えます。
しかし、子供の性格が親の価値観により「原因論」的に決まるのではなく、
自分の意思で服従するか、反抗するかを決めている。(自己決定性)
055 子供は親が貼ったレッテル、例えば「しっかりした子」「甘えん坊」「恥ずかしがり屋」などに対して過剰に応えようとする。
親の期待に背いたら、見捨てられてしまうかもしれないと考えるからです。
逆に、行きすぎると、逆効果になる。
056 家族構成と子供時代を把握することにより現在の性格を明かにする。
家族布置分析では、幼少期に一緒に暮らした家族の
年齢・職業・性格・身体的および頭脳的な優越性・社会的な地位・職業などを明かにする。
幼少期の早期回想分析では、本人が記憶している最も古い記憶
もしくは最もビビッドな記憶を3から5個話してもらい分析する。
教育
057 叱られたり、ほめられたりして育った人は、叱られたり、ほめられたりしないと行動しなくなる。
そして、評価してくれない相手を敵だと思うようになる。
ごほうびや褒め言葉で相手を釣る限りは、一生それをやり続けなければならない。
しかも、私たちが見ていないところでは、相手はその行動を取らなくなる。
私たちが見ているときしか、その行動を取らない。
逆に、罰や叱ることで相手の望ましくない行動を防ぐのも同じことです。
自分の意思で行動を止めるのではないので、強制がなければ問題行動を続けるに違いない。
058 叱ると一時的には効果がある。しかし、本質的な解決にはならない。
むしろ、相手は活力を奪われ、ますます言うことを聞かなくなるであろう。
ガミガミと口うるさく叱られることで子供は自信を失い、深く傷つき、勇気をくじかれます。
困難に挑戦する活力を奪われ、困難から逃げ、不適切な行動をとるようになるでしょう。
また、罰を与えられたり、脅かされたりしたことで、
相手を恨み、余計に意固地になり、益々言うことを聞かなくなります。対等な目線で会話をする。
059 間違いをわからせるには、親しみのある話し合いをすれば良い。大切なのは、信頼関係を築くことだ。
相手の問題行動のすぐ後にその場で説明をしてはいけない。
それは、言葉の表現が穏やかなだけで実際は叱責になるからです。
しばらくしてから、自分がどう感じるかを伝えるにとどめ、自分の意思で行動を変えるのを待つ。
060 問題行動に注目すると人はその問題行動を繰り返す。
叱ることは、悪い習慣を身につけさせる最高のトレーニング。
相手の問題行動を止めさせたいのであれば、問題行動を見つけたとしても注目せず叱らない。
問題行動をしていない時に、適切な行動の方に注目し、認める。問題行動に注目するには逆効果。
わずかであっても、正しく適切な行動に着目する。それが教育者の取るべき正しいスタンス。
061 他人と比較してはいけない。ほんのわずかでも、できている部分を見つけ、それに気づかせる事が重要だ。
比較されることにより、子供は自信を失い傷つきます。
そして劣等感を肥大させ、間違った方向で劣等感を保証しようと試みます。
多くの場合、それは問題行動となります。
親子に限らず、先輩と後輩、上司と部下の間においても同じことがおきます。
周囲に人と比較すべきではないのです。
正しい例を示したいのなら、比較は相手の過去と現在を比較することです。
相手の「自己ベスト更新」をほめるのです。
062 人は失敗を通じてしか学ばない。失敗を経験させ、自ら「変わろう」と決断するのを見守るのだ。
できるようになってから任せるのではなく、任せるからできるようになる。
063 罰を与えるのではない。
結末を体験させるのだ。
子供が食事の時間になっても帰ってこなかったら、一切叱らずに食事を出さなければよい。
064 親が子供に苦労をかけまいと子供を助けることがある。すると子供は本当にできなくなる。
「この子は私がいないと何もできないの」と子供を自分に依存させ、
それにより自分の存在意義と価値を高めます。
そして結果として子供を「親なしでは何もできない」依存的な子供にしてしまう。
親がすべきは、子供が一人で課題を解決できるように勇気づけることだけなのです。
065 人の育て方に迷った時には、自分に質問するのだ。「この体験を通じて、相手は何を学ぶだろうか?」と
そうすれば、必ず応えが見つかるだろう。
共同体感覚
066 自分だけでなく、仲間の利益を大切にすること。受けとるよりも多く、相手に与えること。
幸福になる唯一の道である。
社会の中で居場所がないことは大変悲しいことです。
「周りの人が自分をわかってくれない」と愚痴るのではなく、自分から周囲に貢献するのです。
そうすれば必ず居場所ができます。
067 誰かが始めなければならない。見返りが一切なくても、誰も認めてくれなくとも、「あなたから」始める。
「なぜ隣人を愛せなければならないのだ」「私の隣人は私を愛してくれるか」と尋ねる人は
協力する準備ができておらず、自分にしか関心がないことを露呈している。
人生におけるあらゆる失敗の原因は、自分のことしか考えていないことにある
068 「他者は私を援助してくれる」「私は他者に貢献できる」「私は仲間の一員である」
この感覚がすべての困難からあなたを解放するだろう。
共同体感覚は以下の3つにより構成されている。
他者信頼-- 他者は私を援助してくれる
自己信頼-- 私は他者に貢献できる
所属感----- 私は仲間の一員である
069 自分のことばかり考えてないだろうか? 奪う人、支配する人、逃げる人、これらの人は幸せになれない。
共同体感覚は低いが活動性が高い人。
相手よりも自分を優先した活動を大いにし、周囲の人を「支配する人」
共同体感覚も活動性も低い人。二つの種類がある。
「相手から奪う人」人から何かをしてもらうことを当然と思い、感謝しない。
自分を支援しない人を恨み怒る。
「世の中から逃げる人」うまくいかない対人関係を面倒に思い、人と会わずに引きこもる。
070 人は居場所がないと感じると、精神を病んだり、アルコールに溺れたりする。
他者に貢献することで居場所を確保すればよい。
犯罪者、精神病者、アルコール依存症,性的倒錯者、自殺する人、
一見するとまったく違う問題を抱えているように見えるが、問題の根は「共同体感覚」の低さ。
相手よりも自分のことを優先するが故に、相手から支援されているという実感を持てず、
社会に孤立する。居場所がないと感じてしまいその補償行動としてそれぞれの問題行動を起こす。
071 「仕事で失敗しませんでした。働かなかったからです」
「人間関係で失敗しませんでした。人の輪に入らなかったからです」 彼の人生は完全で、最悪であった。
失敗や敗北を避けるための確実な方法は、チャレンジをしないことです。
課題を克服のためには、困難を克服する活力/勇気とその方向付けとなる「共同体感覚」。
072 相手の権利に土足で踏み込んではならない。
権利を尊重し、自分で決めさせるようにすれば、人は、自分を信じ、他人を信じるようになるであろう。
強制すると対立と権力闘争がおき、共同体感覚は育ちません。
相手に自分で決めさせ、相手の権利を認めると、対立が消え、相手は冷静に判断できる。
073 「よくできたね」と褒めるのではない。「有難う、助かったよ」と感謝の念を伝える。
感謝される喜びを体験すれば、水から進んで貢献を繰り返すだろう。
上から目線で「褒められる」よりも横から目線で「感謝される」ことが自己信頼と他者信頼に有効。
貢献と感謝の体験を増やすことが共同体意識を養う上で最も大切なことです。
074 苦しみから抜け出す方法はたった一つ。
他人を喜ばせることだ。「自分に何ができるか」を考え、それを実行すればよい。
小さな徳を積むことも有効です。空き缶を拾う。お年寄りに席を譲る。エレベーターで先を譲る。
周囲の話に合づちをうつ役にまわるなど。
自分よりも相手を大切にすると、共同体感覚は高まります。そして、幸福へまた一歩近づくのです。
075 自分と違う意見を述べる人はあなたを批判したいのではない。
違いは当然であり、だからこそ意味があるのだ。
自分の意見を押し付けてはいけない。相手が自分と違う意見を持つことを許容する。
076 自分の不完全さを認め、受け入れなさい。相手の不完全さを認め、許しなさい。
相手と自分の不完全さを認めることも共同体感覚を高めるための不可欠な具体策。
077 「信用する」のではなく「信頼する」のだ。「信頼」とは裏付けも担保もなく相手を信じること。
裏切られる可能性があっても相手を信じるのである。
共同体感覚は「信頼」をベースにしています。
自己信頼と他者信頼は共に、裏付けなく裏切られる可能性があっても信じることから始まる。
相手を疑っているうちは、信頼関係は築けません。無条件に信じるのです。
078 「自分は役立っている」と実感するのに、相手からの感謝や褒めの言葉は不要である。
貢献感は「自己満足」でいいのだ。
相手からの感謝や評価がないと貢献感を感じることができないとしたら、
あなたは常に相手に依存していることになる。
相手が褒めてくれなかったら相手に怒りを感じ、感謝を求めてしまう。
それは、本物の貢献感ではありません。相手に依存しない自己満足でいいのです。
079 判断に迷ったときは、より大きな集団の利益を優先することだ。
自分たちよりも仲間たち、仲間たちよりも社会全体。そうすれば、判断を間違うことはないだろう。
080 理不尽な上司や学校の先生に、無理やり認めてもらう必要はない。市場価値の高い人間になればよい。
より大きな共同体で考えればよいのだ。
勇気
081 「勇気」とは困難を克服する活力のことだ。
勇気のない人が困難に出会うと、人生のダークサイトへ逃げていってしまう。
人生に困難はつきものです。
仕事の課題、交友の課題、愛の課題、それぞれにおいて次々と困難は押し寄せてきます。
そして、困難により私たちの共同体感覚は試されます。
余裕のないときでも「相手を思い、相手を優先する」共同体感覚を持てるかどうか。
私たちは日々試されているのです。
082 人は「貢献感」を感じ「自分に価値がある」と思えるときにだけ勇気を持つことができる。
周囲の人の行動に対して「ありがとう」「あなたがいてくれて助かった」「あなたのお陰だよ」
そう伝えることこそが周囲に対する勇気づけになるのです。
083 他人の評価に左右されてはならない。
ありのままの自分を受け止め、不完全さを認める勇気を持つことだ。
自分のことばかりを考えている人、すなわち勇気を持てない人は
「相手よりも自分のことばかりを優先」して共同体感覚を投げ出す。他人の評価を気にする。
相手への貢献よりも、自分がどのように見られているかを気にするからです。
勇気のある人は他人の評価を気にしません。
誰からも褒められず認められなくても、自分が相手に貢献できていることに満足を感じるからです。
相手がすることに条件をつけないで、ありのままの相手をそのまま受け容れ認める。
「人からどう思われようと関係ない」「ありのままのあなたでいい」と気づかせ、勇気づけ。
084 ほめてはいけない。
ほめることは「あなたは私よりも下の存在だ」「どうせあなたにはできっこない」と相手に伝えると同じ。
ほめることは上から目線です。
勇気づけは横から目線です。
085 失敗や未熟さを指摘してはいけない。できないからといって取り上げてもいけない。
相手の勇気を奪ってしまうからだ。自ら困難を克服する機会を奪ってしまうのだ。
指摘により、相手は自らの無能さと劣等性を思い知らされる。
そして、指摘した本人は、知らず知らずのうちに自分が優れた存在であることを相手に見せつけ、
優越感を感じます.その結果、相手は勇気、すなわち困難を克服する活力を失ってしまうのです。
現段階の能力不足と相手の価値は何の関係もありません。
086 人の心理は物理学とは違う。問題の原因を指摘しても、勇気を奪うだけ。解決法と可能性に集中する。
勇気をくじく行動とは、相手の問題探しをしてダメ出しをすることであり、
原因究明の名の下に、失敗した者を吊し上げ、責め立てることです。
087 人の行動の95%は正しい行動である。しかし、私たちは「当たり前だから」とそれを無視してしまう。
わずか5%しかない負の行動に着目してはいけない。
できている部分に着目をする。それこそが勇気づけになる。
088 ものの見方を変えるだけで世界はガラリと変わる。
「暗い」のではなく「優しい」のだ。
「のろま」ではなく「ていねい」なのだ。
「せっかち」ではなく「素早い」のです。
「お節介」ではなく「親切」なのです。
「鈍感」ではなく「自分の世界を持っている」のだ。
「失敗ばかり」ではなく「たくさんのチャレンジをしている」のだ。
089 大切なことは「共感」することだ。
「共感」とは相手の目で見、相手の耳で聞き、相手の心で感じることである。
相手に共感したつもりになって、自分の視点を押し付けていないか。常に自問すること。
090 命令口調をやめて、お願い口調や「私」を主語にして伝えると、それだけで勇気を与えられるだろう。
命令口調でいわれると、「自分の立場や状況が尊重されていない」と感じ、
不快感と共に勇気をくじかれたと感じる。
相手にYes Noの選択の余地ある問いかけにするだけで、「尊重されている」と感じ、勇気づく。
091 「ケーキ、食べちゃったの?ひどい!」などと怒り、睨みつけてはいけない。
「食べたかったなあ。残念だ」と伝えるのだ。
そもそも「怒り」は二次感情です。
本来は一次感情である「寂しさ」や「悔しさ」「悲しさ」が先にあり、
それが相手に理解してもらえないときに「怒り」へと変わっていくのです。
そんな時はYou message
の二次感情「怒り」ではなく、一次感情のI messageで伝えれば良い。
それが勇気づけにつながるんです。
092 「まだ無理だ」と思っても、やらせてみる。
失敗しても「今度はうまくできるはず」と声をかけることが大切なのだ。
家族における親や、企業組織における管理者は、自分が発する言葉が相手に自信つけるのか、
自信を失わせるのか、を常に考えておかなければなりません。
失敗を避けるために発した言葉が勇気くじきになってしまうぐらいなら、
失敗させることも視野に入れなければなりません。
093 甘やかすと相手の勇気を奪ってしまう。
手助けしたり、ちやほやするのではなく、独り立ちの練習をさせよ。
親が子供を信頼し、独り立ちできるという可能性を信じているならば、
子供が泣き叫んでかんしゃくを起こしても、それに負けずに、泣きたいだけ泣かせておけばいい。
そして、おもちゃを与え、一人遊びができるように準備させる。それが子供を勇気づけになる。
094 間違いを指摘せず、原因究明という吊し上げもせず、「こんなやり方はどうかな?」と提案する。
それこそが、相手を育てる有効な方法である。
問題指摘から助言すると勇気くじきになってしまう。
原因究明のプロセスを省略して、いきなり建設的な問題解決だけを提案する。
吊し上げが勇気づけに変わる。
095 楽観的であれ。
楽天的とは悲観的に検証し、悲観的に準備し、その上で肯定的に行動すること。
悲観主義は気分のものであり、楽観主義は意志のものである。
過ぎてしまった過去をくよくよと考えるのをやめ、「未来」を不安視することなく、
「今現在」できることだけに集中する。
096 行動に問題があるとしてもその背後にある動機や目的は必ずや「善」である。
「善」である動機に着目して、相手を勇気づける、
その後で他の方法を選択できる可能性について話し合えば良い。
課題の分離
097 あなたが悩んでいる問題は本当に「あなたの問題」だろうか。
その問題を放置した場合に困るのは誰か、冷静に考えてみることだ。
あらゆる人間関係のトラブルは、他人の課題に土足で踏み込むことから起こります。
098 妻の期限が悪い時、夫が責任を感じてはいけない。
不機嫌でいるか上機嫌でいるかは、妻の課題。
妻の課題を勝手に背負うから苦しいのだ。
099 それが「あなたの課題」ならば、たとえ親に反対されても従う必要はない。
自分の課題に足を踏み込ませてはいけないのだ。
また親の考えをねじ伏せて無理やり賛成させるのも「親の課題」に足を踏み込むことになります。
100 陰口を言われても、嫌われても、あなたが気にすることはない。
「相手があなたをどう感じるか」は相手の課題だから。
私たちは他人の感情や行動をコントロールすることはできません。
できないことをしようとするから苦しいのです。
つまり、他者からどう思われているかを気にするから苦しくなる.
課題を明確に分離すればいいのです。