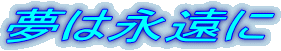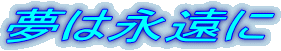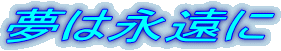
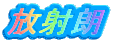
俺の左側には赤黒い大地が広々と広がっている。
暴風とそれに飛ばされる砂粒がヘルメットのスクリーンを叩く。
ほんの5メートル右側には、深さ数百メートルの断崖がワニのように口を開けている。
2100年5月21日出発の、第八次火星探検隊の一員として、俺はこの地に立っているのだ。
重力が地球と比べて少ないから、かえって歩くのが難しい。
充分訓練はしているものの、ちょっと早歩きをしようとすると、すぐにバランスを崩しそうになる。
「高橋、もう少し奥の方の砂を採取してみてくれ」
ヘルメットに内蔵された小型スピーカーが、離れた着陸船内にいる仲間の声を伝える。
俺は指示された場所の方にじわじわと進む。
俺のヘルメットの頭頂部についたテレビカメラで、船内の仲間は、その様子をモニターしている。
右斜めの、より崖に近い方では倉田が同じように作業をしていた。
彼の銀色の宇宙服が太陽光線を反射してきらめいている。
小型の金槌で指示された場所の岩を砕き、かけらを宇宙服のポケットに俺は収めた。
そしてもう一歩踏み出す。
その時何かが目の端をかすめた。
「うわー助けてくれ」
突然倉田の悲痛な叫び声がスピーカー越しに聞こえた。
振り返ると、地面から突き出た赤い芋虫のような触手が倉田の右足を捕らえていた。
その側からは更に何本もの触手が蠢き這い出していた。ビッグワームの、しかも青いやつだった。
ビッグワームの中でも一番凶暴で恐ろしい相手だ。
このあたりでは出た事がなかったのに。あいつらの領域はもっと東の鉄を多く含んだ砂漠地帯だったはずだ。
倉田を助けたかったが、あいつが相手ではとても無理だ。
強力な武器も無いのに、あんな化け物相手に戦えるわけが無い。
俺は仕方なく倉田を見捨てて、船の方に急ぐ事にした。船の方でもわかっているはずだから応援が来るだろう。
しかし俺の目の前にいきなり化け物の触手が現れた。
回り道しようとしてバランスを崩した。
倒れる俺の左腕と両足は、芋虫のような触手にからめとられる。体が宙に浮く。
身動きが出来ない。
目の無いビッグワームの丸い顔が迫ってきた。
直径一メートル位の大きな口。
その周囲にきちんと十センチはありそうな楔形の牙がまるく並んでいる。真っ赤な口の中の襞がゆれうごめいてるのが見えた。
必死で逃げようとする俺を、その大きな口はくわえ込み、そしてあっさり首を食いちぎった。
真っ暗になった。
痛みはほとんど感じなかった。
ハードディスクのカリカリいう音がかすかに聞こえていた。
ポッドの中で目を閉じたまま、意識だけが緩やかに現実を認識し始める。
一回目の擬似人生が終わったのだ。
採点はどうだろう。
倉田を見殺しにしたのが減点の対象になってなけりゃいいのだが。
暴風雨の中を旅客機は揺れながら飛んでいる。嵐の中の木の葉のようだ。
あちらこちらで気分が悪くなった人が、袋を口に当てていた。
ふわりと数秒間体重がなくなる感触は気味の悪いものだった。
僕は乗り物酔いには強いほうなのだろう、特に吐き気を覚えることも無かった。
僕の両親は、まだ袋を手にしてはいなかったが、すでに顔色が悪い。
まだ目的地に着くまでは1時間ほどこの大荒れの天気の中を揺られないといけない。
僕は気分を紛らすためにヘッドフォンを耳に当て、座席横のラジオのスイッチを入れた。
『はーいとうとうノストラダムスの大予言の時がやってきましたね。皆さんいかがお過ごしですか。梅雨の終わりの大型の低気圧が来てますが、この梅雨が終われば、さんさんと輝く夏の太陽が、皆さんを待ってますよー。さあ一曲目……』
ディスクジョッキーの声が華やかに響いて最初の曲がかかる。
古いフォークソングだった。
飛行機が一瞬大きく揺れた。
体重が無くなり、逆にシートベルトが身体を圧迫する。
周囲の手荷物などが浮かび上がり飛び回る。
悲鳴が上がる。
それに合わせるようにパニックが広がる。
墜落しているのだ。
高度がどんどん下がり、耳が気圧の変化で痛くなる。
手荷物のバッグか何かが飛んできて頭にあたり、僕の意識は一瞬薄れた。
がくんと大きな衝撃があった。
壁が何かに擦れる音、波しぶき。衝撃がえんえんと続く。なかなか静まらない。
着水し、海上を滑っているのだ。
いつまで続くのだろう。
不安を感じる余裕も無く、ただこの時間を客観的に冷めた目で見ている僕がいた。
機体が止まったようだった。それでも波のうねりで、ゆっくりと動いてはいる。
スチュワーデスが何か叫んでいる。
救命ボートの準備をするので少し待つように言っているのだ。
その指示を聞かずに我先に出口へ向かう人々。怪我人はそれらの人々にすがりつく。
でも彼らは怪我人をかまったりはしない。
彼らはとにかく出口に急ぐ。僕は両親を見た。気を失ってぐったりしていた。
阿鼻叫喚の中、両親の事はあきらめて、僕は出口に向かう。
もう少しという所で、大きな水の塊が僕の身体を押しやった。
吹き飛ばされるようにして、もと居た座席の方まで転がる。
「助けてくれ」
男の手が僕の袖を引っ張った。
そんなのにかまってる暇はない。
急がないと沈んでしまうのだから。
御免よ、と一言いって僕はその男を蹴飛ばした。
男は口から血を吐きながら後ろの座席に張り付いた。
両親はまだ気絶したままだ。
僕は彼らをゆすって起こそうとするが、頭を打っているのかなかなか起きてくれない。
やっぱり無理だ。
僕は出口に急いだ。もう少しだ。もう少しで救命ボートに移れる。
その時、また水の塊が僕を覆って吹き飛ばす。
翻弄され、撹拌され、僕は空気を抜き取られたビニール人形みたいにしぼんでしまう。
僕の意識も同じようにしぼんですぐに消えてなくなった。
ハードディスクのカリカリ音がやけに響いてる。
二度目の擬似人生が終わったようだ。
俺はゆっくりと浮かび上がってくる自我というものに疑問を持ちながら、それでも安堵を胸いっぱいに感じて、記憶を呼び覚ます。
あと八回の擬似人生が終われば、更正期間は終了して、ここを出られるはずだ。
そのときは自分の生まれた時代からすでに100年の年月が経っていることになるが、自由の身になれるのならたいした問題じゃない。
最後の一回で、その時代にあった人生を体験できることになってるから、まごつくこともないだろう。
低周波の機械音が立ち上がった。
ポッドが再び作動を始めたのだ。
三回目の擬似人生に向かって俺はゆっくりと降下していった。
「別れてくれ。もう君とはつきあえないんだ」
好男の言葉は私には理解できなかった。
まるで聞き覚えのない単語の羅列。スワヒリ語か古代中国語でもあるような……。
「実は、先日見合いして…、わかってくれよ。君には悪いと思ってるんだ」
好男は私の両肩をつかんだ。
山頂の展望台。私達以外は誰もいない。
空には満月がどっしり腰を据えてるけど、街頭が明るいからあまり目立てないでしょんぼりしてる。
この人の愛とはなんだったのだろう。
私を散々抱いてきたのはただの欲求不満解消のため?
私の肩をゆする彼に私はつばを吐きかけていた。
自分でもそんな事をするなんて思っても見なかったから、少しびっくりした。
彼の右手の手のひらが私の頬を打ち、ひどい音を立てた。
私はあなたを許さない。絶対別れないから。
私の言葉に彼はめまいがしたのか、すっと身体が沈んだ。
でも倒れそうになったんじゃないのはすぐにわかった。
彼の手が私の太腿に回されてきたから。
こんなところで何をする気?
私の声に彼は力いっぱい答えた。声ではなくて、体力で。
私の体は浮き上がり、展望台の柵をこえようとしている。
私は必死に彼につかまるけど、彼は身体ごと押し付けるように私を柵の外側に放り出した。
最後の手が離れた後、地面に着くまでの数秒がやけに長く感じた。
アスファルトは硬く、冷たく、私の頭蓋骨を粉砕してくれた。
血がしぶきが周囲に撒き散らされたけど、月明かりの中でそのきれいな赤黒い霧をみた人は誰もいなかった。
三度目の擬似人生では俺は女になっていた。
おかしいな。どうしてだろう。
俺は男なのに……。
そうだったよな。俺は……男だよ。
って、そうかしら?女だったような気もするけど。
プログラムのどこかにバグでもあったのかしら。
でもいいわ。目が覚めればわかることだから。
四回目の擬似人生が待ち遠しいな。今度はどんな人生かしら。
犯罪者に対する死刑の代わりに擬似冬眠システムが採用されてからちょうど二十年になる。
死刑廃止論が優勢になっても、死刑囚を釈放するわけには行かないし、終身刑にすればその食費等で結構金がかかる。
擬似冬眠システムで100年間冬眠刑にするのが、人道上も問題なく、経費的にも安上がりなのだった。
結局死刑に相当するほどの大罪を犯した人間は、100年後という、すでに生きてる人間にとってかかわりになる可能性のない世界に島流しというわけだ。
消費する電力など取るに足らない。
地熱を効率よく電力に代えるシステムが実用化されてからは、電気は人間が使いきれないほど、無尽蔵に存在する物になっていたのだから。
ただ、この擬似冬眠システムはハード的には問題なかったが、ソフト的にはプログラムのバグがあることがわかってきた。
被験者の人格を再教育するために擬似人生の夢を見させるのだが、そのプログラムに落ち度があって、被験者の人格にあわない人生を体験させてしまう事があるのだ。
たとえば、男に女の夢を見させたり……。
そのプログラムの改正を政府に要求するために、私は取材活動を行っていた。
そして思ってもいなかった別の鉱脈を掘り当ててしまった。
擬似人生の中でも、現代以降を背景にした世界観の中には、当然のように擬似冬眠システムが存在するという事。
つまり、擬似人生の中で犯罪を犯したものは、夢の中で、さらに夢を見させられることになるのだ。
普通なら十年間の擬似人生を十回経験して、それで冬眠から覚めることになるのだが、その中でさらに十回の人生、そしてその中でさらに夢を見る。
まるで合わせ鏡の無限の通路に迷い込んだかのごとく、時間間隔の異なる夢の世界に永遠に閉じ込められる事になるのだ。
通常の世界では百年間という限られた時間でしかないのだが、その中には無限の時間が存在する。
地球上で何千年の時が過ぎようと、ブラックホールの中ではほとんど時間が過ぎないのと同じように、現実と夢の中では時間の尺度が違うからだ。
これらの事を取材していた私は、いつのまにか政府の監視下に置かれていた。
そして発表原稿をまとめていた私の部屋に、男達は土足で上がりこんできた。
裁判も何も無く強制的に連れてこられたのが、擬似冬眠ポッドの前だった。
政府にとって私の記事はそれほど都合の悪いものだったのだろうか。
私には理解できない。
擬似冬眠システムが、こうも安易に使われだしているなんて……。
棺おけのふたが閉まり、私は闇に包まれた。そしてゆっくりと深い眠りに落ちていく。
永遠の始まりだ。
無限の物語は今始まるのだ。
すべてのストーリーの主人公として私は生まれ変わるだろう。
汽車が国境の長いトンネルをぬけると、周囲は真っ白な雪の世界に変わっていた。
今朝目覚めてみると、自分が昆虫に変わっていることにきづいた。
家族もびっくりしてるみたいだが、もちろん一番驚いたのは俺だった。
赤黒い大地が周囲に広がっている。
強い風が吹き、砂粒が俺のヘルメットのシールドにあたる。
神経に障る嫌なかさかさした音が聞こえる。
基地からの命令で、俺は奥の方の土を取りに足を踏み出した。
軽い体重は、かえってバランスを崩しやすい。
すぐ側の崖が奈落のそこに沈み込むような大口を開けて、さながら俺を飲み込む恐竜の口にも見えた。
深い穴。
永久に落ちつづける底なしの穴がそこには開いていた。
夢は永遠に 終わり