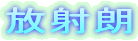PTAという言葉を聞いたら、普通の人なら口うるさい保護者の集まりを思い浮
かべる所だろうが、私達透析患者にとってはその言葉は恐怖の言葉である。
透析患者は普通左右どちらかの前腕部に、血液透析用の血管形成を行っている。
これをシャントという。
血液透析というのは、その部分に針を、出口と入り口の2本刺し、血液を取り出
し、ろ過した後に戻すのだが、長年やっているうちに血栓が固まったりして一部が
狭くなってしまう事がよくある。そのままにしておけば、完全に閉塞してしまい、
透析が不可能になってしまう。
以前はそんな時、すぐに手術していたものだが、最近では技術が進み、このPT
A(何の略かは知らない、気になる人は自分で調べてください。日本語では血管拡
張術というらしい)という処置にとってかわられるようになった。
これが聞くところによるとすごく痛いらしいのだ。
もちろん病院の先生達は我々を痛めつけるのが趣味ではないので、麻酔を使った
りしてできるだけ痛みを和らげるように努力してくれる。
それでもまだかなりの痛みを伴うらしい。
幸いな事に、透析暦十年になるが、私はまだこの処置を受けた事は無かった。
今日は七月も始めの月曜日。はじめてこの処置を受ける事に恐怖を感じ、できれ
ば逃げ出したいといっていた末吉じいさんの付き添いでレントゲン室にやってきた。
でも病院の廊下というのはどうしてこんなに暗いのだろうか。
蛍光灯の半分はわざと消してある。
経費削減のためにしてるのだろうが、こんな所を見ると、ひょっとしてこの病院
は危ないのではないかと要らぬ心配をしてしまう。
まあ、此処がつぶれても別の病院に移ればいいのだから患者としては関係ないの
だが、いとしい看護婦の小久保さんが失業するのはかわいそうだ。
まあ看護婦さんも病院を代わればいいだけかもしれないが……。
暗い廊下のベンチで待っていると、レントゲン室の中から末吉じいさんのらしい
悲鳴が聞こえてきた。
「ぎゃー痛い痛い!殺す気かよお!放せ、ばかやろう」
威勢のいいじいさんの絶叫は廊下を伝って受け付け前ロビーまで聞こえてるよう
だ。
風邪か何かの外来患者がチラチラこちらを見て不安そうな顔をしている。
受付の事務員もやりにくいだろうな。
「吉岡さん駄目ですよ。手を動かさないでください。もうすぐ終わりますから、我
慢して」
高岡先生の声だ。彼はまだ30代で、若いがとても親切な先生だ。ちょっと鼻が
上を向いていてユーモラスな顔つきだが、患者としては難しい表情の似合うインテ
リジェンスにあふれた医者より、彼のような三枚目風の医者の方が安心して診ても
らえる。
末吉じいさんのPTAが始まって約一時間が経過している。
普通1時間半から2時間かかると言う事だったから、そろそろ終わりならかなり
早い方だろう。
手持ち無沙汰に、携帯電話を取り出してゲームをやってると、私の前に看護婦の
格好をした人が立った。
「駄目ですよ山岸さん。病院では携帯電話は使わないでくださいって張り紙してあ
るでしょ。電磁波が出て検査の機械を狂わせたり、心臓のペースメーカーを狂わせ
たりするんですから」
私が見上げるよりも早く、いとしい看護婦、小久保さんの愛らしい声が降ってき
た。
「ああ、そうだったね。ごめんごめん」
私は慌てて電源を切った。
ふふふ、と彼女は立ったままで私に笑いかけてくる。
「山岸さんは優しいんですね。吉岡さんの付き添いですか……」
彼女の笑顔はとっても素敵だ。
ただかわいいだけでは無くて、小悪魔的な黒い雰囲気をもってる。ちょっと意地
悪そうな表情をするときもあり、そこがまたいいのだ。
「まあね。あのじいさんはわがままだからね。私がついてきてくれないとPTAな
んかしてやらないって駄々をこねてたんだよ」
「PTAはかなり痛いそうですからね。でも大声出して暴れる人はあまりいません
けどね。あ、でも、わがままかもしれないけど、針刺し中にお尻触る誰かさんより
は質(タチ)がいいかも……。今日は触らないんですか。誰も見てないからチャン
スですよ」
小久保さんはそう言って腰をひねり、私の方に丸いお尻を突き出した。
看護婦の制服からすらりと長い足が伸びている。ひきしまったウエスト。そして
そこからふっくらしたヒップが張り出している。
その緩やかにカーブしたヒップの線に向かって、私の手は引き付けられるように
伸びていった。
もう少しで天国に到着するというところで、階段は無常にも崩れ落ちる。
「おっと危ない」
彼女は瞬間的に腰を引くと、笑いながら去っていった。
「だっめでっすよー」
去りぎわに放った彼女の声が暗い廊下にかすかに聞こえた。
悔しさがわきあがる。
小娘の分際で倍以上年齢の違う私をからかうとは不届きである。
でもかわいいから許すけどね。
「うがあー」
また末吉じいさんの悲鳴がした。まったく、若いときは船員をしていた海の男が、
病院の処置くらいで悲鳴上げるなと言いたい。
小久保さんのお尻に逃げられた事で、さっきより意地悪になった自分なのだった。
「さっきは死ぬかと思ったよ。あんなに痛いとは思わなかった」
私の右隣のベッドで、生死の境をさまよってきたといわんばかりに笑顔を引きつ
らせながら末吉じいさんは語った。
「麻酔打ってもらったんでしょう。効かなかったんですか」
私は顔だけ向けて言う。
私達は透析ベッドで、今まさに血液を吸い取られて洗濯機で洗われている状態な
のだった。すべての光を吸着する黒曜石のようだった血液が、赤さを取り戻して二
人の体にそれぞれ戻ってくる。
「あんなもん効くもんかね。血管は奥の方にあるんだよ。皮下麻酔じゃ駄目さ」
「吉岡さんの声、受付の方まで聞こえていましたよ」
私が言うと、じいさんの声のトーンが一オクターブ上がった。
「ええ?あそこの部屋はきちんと密閉されてるんだろ。レントゲンが出るんだから」
彼は知らなかったようだ。
「密閉はされてるようですが、インターホンのスピーカーから聞こえてくるんです
よ。レントゲンの技師さんと中の医者のやり取り用のインターホンですね」
「……知らなかったなあ。そいつはちょっと恥ずかしいかな。へへへ」
じいさんの照れ笑いにはこっちまでおかしくなった。
その後二人で他愛の無い世間話をしていると、先程じいさんの処置をされていた
高岡先生がやってきた。
私とじいさんのベッドの間に立って、じいさんに話し出す。
「どうですか。痛みはもうないでしょう」
彼はじいさんのシャントの様子を点検にきたようだった。
「いいですよ。もう大丈夫みたいです。ところで先生、先程は騒いでしまってすい
ませんでした」
「いいんですよ。痛い処置ですからね。でも痛ければ痛いほど血管が広がってる証
拠だから、それだけやった価値があったって事なんですよ」
この辺はマニュアルどおりのお決まりのせりふという感じだった。するする出て
くる。
「そうだ。何かお詫びをしたいと思ってたんですが、先生釣りなんか好きじゃない
ですかな」
何を思いついたのか末吉じいさんがそんな事を言い出した。
「え、釣りですか。あまりやった事は無いけど、人にも勧められてるし、趣味にす
るには良いようだから今度やってみようかと思ってるところですけど」
「それはちょうど良い。ぜひ今度私の船で御一緒しましょう。看護婦さんも誘って。
私の船は豪華じゃないけど10人くらいは余裕で乗れますから、他にも誘って皆で
いきましょう」
格好悪い所を見せてしまった代わりに、今度は自分の船でいいところを見せよう
という魂胆がわかりすぎるほどに透けて見える。
なんとも単純なじいさんだが、だからこそ皆に好かれるんだろうな。
「山岸さん、あんたも一緒に行きましょう。付添してくれたお礼だよ」
じいさんが先生の体を避けるように顔を回して私に声をかけてきた。
「いや、私は船は苦手なんだ。すぐ酔ってしまうんですよ。遠慮しておきます」
残念そうなじいさんの顔を見ると少し心が痛んだが、船酔いしやすいのは本当の
事だ。
「じゃあ、いつにしますか」
高岡先生は乗り気のようだ。あとは看護婦も何人か誘って皆で楽しいひと時を過
ごすのだ。末吉じいさんが楽しいのなら私もうれしい。
「いま潮のめぐりがいいから早いうちがいいなあ。来週の日曜日なんかどうですか」
とんとん拍子に話は進んで、日曜日が船釣りの日に決まったようだ。
たくさん釣れればいいが。最近では沖のほうに船で行ってもあまり大きな獲物は
釣れないと知人がぼやいていた。ちょっと昔は船で出なくても沿岸の波止場あたり
で結構な黒鯛が良く釣れていたものだが、自然環境の変化というのか破壊というの
か、魚の数も減ってきてるのだろう。
「山岸さんも釣りに行かれるんですよね」
駐車場でクルマに荷物を積み、帰り支度をしていると、後ろから声をかけられた。
振り向く前からわかっていた事だが、その子供みたいな声の主は小久保さんだっ
た。私の胸が騒ぐ。今、彼女は山岸さんも、と言わなかったか?
「ひょっとして小久保さん、末吉じいさんに誘われたのかい?」
私の問いかけに大きくうなずいて彼女は言った。
「ええ。今度の日曜日なんですけど。あたしは釣りにはあまり興味ないんですけど、
すごくきれいな浜のある無人島に行くから、まだ少し寒いけど泳ぎもできるから行
かないかって誘われて。ちょうど新しい水着買ったところだったし、喜んでお供し
ますって言っちゃいました」
唖然としている私に彼女は更に聞いてくる。
「山岸さんも行くんでしょ?」
「ああ。もちろんさ。ちょっと忘れ物したから取ってこよう」
不思議そうな顔をしている彼女を残して、私は末吉じいさんの元へすっ飛んでい
った。
ロッカールームに末吉じいさんは居た。
透析後のだるい表情で、荷物を整理していた。
「ええ? 山岸さん行かないって言ってたじゃないか。もう定員いっぱいだよ。残
念だけど、また今度な」
末吉じいさんの返事はつれなかった。
わざわざPTAの付き添いまでしてやったというのに……。
「でも、なんでまた。船酔いするからって言ってたじゃないか」
タバコに火をつけて、じいさんが言う。
「いやあ。船酔いしていたのはずいぶん昔の事だし、もう大丈夫かなって思って。
それにせっかくのお誘いを断るのも悪いしね」
駄目なら仕方ないが、まだ一縷の望みを託しながら私は藁にすがる。
「わかったよ。本当は定員オーバーなんだけど、そんなに遠くに行くわけでもない
し、何とかするよ」
じいさんのにかっと笑った口から黄色い歯がのぞいた。
タバコの煙も、ヤニ臭い息も今日だけはまったく気にならなかった。
当日は朝からあいにくの曇り空だった。午後には晴れ間がのぞくという予報だが、
今にも雨がぱらつきそうだ。
待ち合わせ場所の船着場にやってきてみると、すでに今日のメンバーはあらかた
来ていて、気の早い連中は缶ビールを空けている。
「山岸さん、こっちですよ」
私が近づくのをすぐに見つけた小久保さんが、大きな身振りで手を振った。
看護婦さんが、小久保さんをいれて4人。それに医師が高岡先生と南先生、レン
トゲン室の有森さん、事務員の上田君の4人がきていた。
南先生は高岡先生の先輩にあたる医師で、中年に入ったばかりなのにすでにおで
こがかなり広くなっている。その額を赤らめて、嬉しそうにビールを飲んでいた。
レントゲン室の有森さんは一度定年退職した後に、入社したらしく、60過ぎの
白髪頭が私と同じだ。事務の上田君はまだ30代前の小太りの青年だった。
まだ未婚であり、その予定も今のところ無いらしい。
肝心の末吉じいさんは見当たらない。
「じいさんはまだみたいだね」
そこにいる人たちに一通り挨拶をした後、小久保さんに聞くと、彼女は一つうな
ずいて言った。
「船はここじゃなくて別の所にとめてあるそうなんですよ。そこは駐車場が狭いか
らここで皆を拾っていくって言ってました。もうすぐ来るんじゃないかな」
小久保さんの今日の格好は赤いTシャツに色の抜けたジーンズ、それに麦藁帽子
をかぶっていた。麦藁帽子にサングラスがちょこんとのってる。
白衣以外の姿を見ることが少ないわけじゃない。先日みたいに仕事帰りの彼女を
見かけることも何度かあったし……。
でも、今日ほどラフな格好は初めて見た。ジーンズがウエストをぐっと締めてる
からヒップがその分強調されている。新しい水着を買ったと言っていたが、今から
とても楽しみだ。
「君もビールもらえば? 私に遠慮する事はないんだよ。私は慣れているから」
そばにいる高岡先生達もみんな缶ビールを飲んでるのに、もらおうとしない小久
保さんはきっと私に悪いと思ってくれているのだ。
透析患者にビールは禁物だから。
アルコールが悪いんじゃなくて、水分を取りすぎるのがまずいから。
「ええ。でも私はまだいいですよ。昼間から飲む気分にもならないし」
「へえ、夜なら結構飲む気分にもなるのかな。割と強い方だったりして」
二人で話してると、横から高岡先生が割り込んできた。
「知らないかもしれませんが、小久保さんはお酒強いんですよ。忘年会なんかで一
緒に飲んでたら、こっちが先につぶれる位なんだから」
高岡先生はあまり強い方ではないんだろう。すでに頬と耳たぶが赤くなっている。
でも、新しい知識を知らされたおかげで小久保さんの輪郭がまた一つシャープに
なった。
変な事言わないでくださいよ、先生が弱すぎるんじゃないですか、と小久保さん
が高岡先生の肩を叩いた。
結構この二人仲が良さそうだ。しかし高岡先生は既婚者のはずだったが……。
私が要らぬ心配で気をもんでいると、沖の方からエンジン音を響かせながらボー
トが近づいてきた。末吉じいさんの船だった。
メンバーの多数決で今日の予定は船釣りではなく、無人島に渡っての釣りとキャ
ンプに変わっていたらしかった。知らなかったのは私だけだった。
それで参加者が二人減ったという事だ。
キャンプと言っても泊りがけではなくて昼間に行うデイキャンプというやつだ。
船のエンジンの振動と、海風がとても心地よかった。
曇り空もしだいに明るくなり、一時間かけて無人島にたどり着いたときにはすで
に青空が見え始めていた。
無人島といっても、夏の間はキャンプ客が来る島のようで、簡単なものだったが
コンクリートで船着場も作られていた。
じいさんが手馴れた手腕で船をそこに着ける。はしけ板を渡して、乗客が上陸を
始めた。
みんな、酔ってる割にはてきぱきと仕事をこなしていく。
砂浜にタープを張り、その傍に適当な岩を持ってきて囲炉裏を作る。そして焚き
火を燃やす。
鉄板をおき、バーベキューの準備をする。
「じゃあ、ここは私が見てますから、釣りをする人はたくさん釣ってきてください」
小久保さんが言うと、男性陣の多くが荷物を片手に先ほどの船着場の方に歩いて
いった。
ここに残ってるのは、小久保さんを入れて看護部の二人と私だけになった。
「山岸さんは釣りに行かないんですか?」
看護婦の山中さんが聞いてきた。彼女は30代になったばかりの中堅看護婦だ。
仕事もできる。彼女の針刺しは、一番痛くないと患者の中では評判だった。
外見はまあ普通で、特に美人とはいえないが、ショートカットにしたうなじは清
潔感にあふれていた。
「私は釣りはあまり趣味じゃないんですよ。それより焚き火をする方が好きかな」
本当は小久保さんのそばに居たいだけなのだが、釣りが趣味じゃないのは事実だ。
「じゃあ、ここは山岸さんに見ていてもらって、あたしたち少し泳いで来ようか」
山中さんが小久保さんに言う。
小久保さんも頷いて、二人はおもむろに立ち上がった。
そのままTシャツを脱ぎ、両手がジーンズのベルトにかかる。
「大丈夫ですよ。下から水着着てきてるんです」
山中さんがそう言うと、小久保さんが私を見てふふふと笑う。
先に小久保さんが腰をひねらせてジーンズを脱いだ。
妖しい笑顔と、ジーンズの下から現れた少し太めの太ももに、私は思わずつばを
飲んだ。
「なんだか昔見たCMを思い出しちゃいましたね、何のCMだったかな……」
小久保さんの様子を私と共に鑑賞していた山中さんが、こめかみに人差し指を当
てて考え込んでいる。
「ミノルタのカメラのCMじゃないですか。宮崎美子の」
私が言うと、そうそれそれ、と言って彼女は微笑んだ。
すっかり顔を出した太陽の光が、木漏れ日になってまばらに小久保さんの健康的
な白い肌を光らせていた。
「この水着どうかしら。似合ってます?」
彼女はバレリーナのように私の前で一回りして聞いてきた。
前から結構胸の大きい娘だとは思っていたが、水着で見ると、更に胸の谷間が強
調されて、くらくら来るような興奮を私にもたらす。
すごく似合ってるよといいながら、目をそらせたのは、あまり見つめていると年
甲斐も無く鼻血を出しそうだったからだ。
山中さんも水着になると、二人は私を残して、水中眼鏡をぶら下げながら砂浜を
走っていった。
走っていく二人を目で追いながら、私は焚き火にまきを追加した。
こんな風にさわやかな砂浜で心地いい時間を過ごしてると、私はなんだか不思議
な気がしてくる。私の体の一部はすでに機能を停止していて、ほんの数十年前なら
確実に死んでる状態なのだ。それなのにこうして生きて、楽しい時間を持てている
のはいいことなのか、それとも悪い事なのか。
透析患者の中には、このまま死ぬまで苦痛の中で生きるくらいなら、いっそのこ
と透析技術なんてない昔に生まれたかったという人も大勢いいる。
医療がいくら進歩しても、人間は生まれてきた以上必ず死んでいくのだから、そ
れなら苦しみと供に生かすよりも楽に死なせる事をもっと考えるべきだと彼らは言
う。
私も以前はその意見にほとんど賛成していた時もあった。
私は本来無宗教の人間なので、宗教的な理由で自殺を嫌悪する立場ではないし、
楽な方に流れる人を叱咤するつもりももうとう無いのだが、彼らの意見はやや感情
的に過ぎるように思う。
これから来る高齢化社会に向けて、その議論はさらに白熱していく事だろうが、
私はどうもどっちつかずで旗色不鮮明だ。
ケースバイケースで考えていかないと、答えなんか出ない問題だろう。
焚き火の炎を見ていると人間は哲学的になるものらしい。
いつに無く難しい事を考えて、私の頭はキリキリ痛んできた。
そして、私の頭痛を解消してくれる二人がこっちに向かって走ってくるのが見え
た。きゃ、熱い!と悲鳴をあげながら……。
砂浜が焼けてきてるんだろう。まだ太陽が雲影から出てそれほどたっていないの
に、初夏の太陽は思いのほか強烈なようだ。
「すっごく水がきれいでしたよ。青い熱帯魚みたいな小さな魚も見つけたし……」
やや興奮気味で話すのは小久保さんだ。
濡れた水着が肌に張り付いてしっとりとした色気を振りまいている。
焚き火を燃やす私の横に、ちょこんと腰掛けてきた。
濡れた太腿が目にまぶしい。
「あたしは小さなイカがたくさん泳いでるのを見たわ。イカの赤ちゃんね」
山中さんはおでこにのせた水中眼鏡を外して、軽く水を切った。
このままずっとこうしていられれば素敵なのに。
患者の血をろ過する透析ベッドのずらりと並んだ光景とはえらい違いだ。
プシッという音がして、山中さんが缶ビールの栓をあけた。
「ほら。泳いだ後のビールはすごくおいしいよ」
まだ遠慮している小久保さんに、私はクーラーボックスからよく冷えたのを一本取り
出してあげた。
「ありがとう」
そう言って彼女もニップルを引きあけた。
彼女の喉がおいしそうにビールを飲み下す。
「山岸さんもかなり汗かいたんじゃないですか。一口だけ飲みますか」
小久保さんの差し出す缶ビールを私は受け取る。
そして彼女が口をつけた缶に私も口をつける。歓喜と供にほんの一口だけ冷たい
ビールが私を潤してくれた。苦い味わいが喉を下っていく。私は体の隅々まで細胞
が生き返るような感じを受け取った。
昼食時が近づいてきた。
私達はバーベキュー用の肉や野菜を鉄板の上に並べ始める。
油のはじける音と肉の焼ける匂いが周囲に湧き上がり、もうそろそろ食べられそ
うになるかという頃、釣りに出ていた一行が帰ってきた。
「うわあ。美味しそうな匂いだ」
高岡先生はひょいっと荷物を放り出すと、左側に腰掛けた。小久保さんの右側が
私で、左側が彼になる。
「ところで先生釣れたんですか」
小久保さんが彼にビールを渡しながら聞いた。
「いやあ。大きなのがかかったんだけど、逃げられちゃったよ」
残念そうに彼が答える。
「でも、こっちのほうがもっと美味しそうだ」
彼は小久保さんの白い太腿を見下ろしてにやついている。
「冗談はやめてくださいよ。はい、肉焼けてますよ」
小久保さんは立ち上がると、紙の皿を取ってバーベキューを取り分ける。
「ほうら、結構大きいのが釣れたんだよ」
クーラーの中から50センチはあろうかという黒鯛を自慢げに差し出しながら末
吉じいさんは言った。
先日の名誉挽回が出来たと喜んでるのだ。
「今からここで3枚におろして刺身にしてやるよ。女の子達はよく見ておいたほう
がいいぞ」
じいさんはそれ用に持ってきた滑らかな板をまな板代わりにして、四人の若い看
護婦達に注目されながら、実に手際よく刺身を作り始めた。
和気あいあいとはこういう場面を言うのだろうと、思わず私の目じりも下がって
しまう。
しかし、そんな楽しい昼食の時間も、小久保さんの一言で急速に緊迫した時間に
変貌していった。
「あ、また釣りの人かな。ボートが来てますよ」
沖の方を指差して彼女は言った。
振り向く末吉じいさんの顔色がすぐに変わる。
「あれ、うちの船だよ。なんてこった。ロープが解けたんだ。船が流されてる」
じいさんの言葉に、他の皆がざわめきだす。
「まずいよ。今引き潮だから、船はどんどん沖に流されていってしまう」
焦るじいさん。でも他の連中はまだぴんとこないみたいだ。
「帰れなくなると困りますね。明日の透析が受けられなくなる」
私も心配になってきたが、先生方はいたって能天気にしてる。
「大丈夫ですよ。今の時代は携帯電話というものがあるんですから、ちょっと電話
して迎えに来てもらえば良いんですよ」
高岡先生が荷物の中から自分の電話を取り出した。
「無駄だよ。こんな所で携帯電話が使えるもんかね。圏外だよ」
じいさんの言葉が正しかった。皆それぞれ持っているケイタイを見てみたが、圏
内は一つもなかった。
「しょうがないですね。じゃあ誰か泳いでいって船を捕まえないといけないな」
南先生は若手の上田君と高岡先生をチラチラ見ながら言う。
「いや。僕は実は泳げないんですよ。まあ25メートルプールを横断するくらいな
ら何とかできますけど」
高岡先生は顔の前で手のひらをパタパタふるわせる。
「僕は行ってもいいですよ。でも船の操縦はどうしたらいいんですか?」
上田君が末吉じいさんに聞く。
じいさんも行ければいいのだが、海の男とはいえ、すでに年を取りすぎてるし、
透析患者だし、無理は止めておいたほうがいいだろう。
「ああ。エンジンはスターターボタンを押すだけだよ。舵の右側に赤いボタンがあ
る。その横に前進と後進のレバーがあるから。後は舵取りだけだ。船着場に寄せる
必要は無いから船をこの近くまで運んできてくれればいいよ。後は私がやるから」
「わかりました。じゃあちょっくら行って来ますよ」
颯爽と上着を脱いでパンツ一つになった上田君は、皆の期待の眼差しを受けなが
ら砂浜を走っていった。
皆も波打ち際まで見送りに行く。
海に入って勢いよく泳ぎだした彼は、ほんの十メートル行くか行かない所で、動
きが止まり、いったん水中に沈んでしまった。
すぐに浮き上がってばたつきながらこっちに戻ってくる。
「いたたた、足がつったですよ。すいません」
砂浜に上がった彼は脚を伸ばして座り、懸命に足首を手前にまげて足のつりを直
そうとしている。
「駄目だよ。一回つってしまうとまたつりやすくなる。君は休んでいなさい」
南先生が上着を脱ぎながら言った。
「先生が行くんですか?大丈夫ですか?」
看護婦達が心配そうに聞いている。
「大丈夫だと思うけど……それほど距離がありそうにも見えないし……」
「いや、光線の具合で近くに見えるけど、少なくとも1キロはあるよ。それにまだ
流されてるから、のんびり泳いでも追いつけないよ」
じいさんに言われて、南先生も首を振った。
「じゃああたしが行きます。こう見えても高校時代は水泳部だったんですよ。最近
も週に一回はプールに通ってるから体力はまだ衰えてません。船を捕まえて、戻っ
てきます」
意気消沈してるみんなの前で、高らかに右手を上げて言ったのは小久保さんだっ
た。
「でも、女の子一人やるわけには行かないよ」
高岡先生は泳げない自分に腹を立ててるんだろう、ぶすっとした表情だった。
「私も行きますよ。水泳には少しだけ自信があるし、週に二回プールで泳いでるん
ですよ、私も」
皆は意外な表情で私を見るが、泳ぎに自信があるのは事実だ。
プールに通ってるのも本当の事だった。週に二回じゃ無くて月に2回だけだった
が。
「透析患者もやるときはやるんですよ。まあ見ていてください」
不安そうに見守る人たちを尻目に、私は速やかに上着を脱いだ。
水着姿の小久保さんと並んで波打ち際で準備運動をする。
「疲れたら無理しないで引き返してくださいね。万一のことがあったら、大変です
から」
病院関係者の中では最年長で、しかも医師である南先生はすごく困った顔をして
いた。そりゃそうだろう。万一の時に責任追及される一番手なんだから。
「大丈夫ですよ。海は浮きやすいし、水中眼鏡とシュノーケルもあるから休みなが
ら泳げますからね」
私はそう言って海に入った。
水がまだ少し冷たかったが、隣の小久保さんの笑顔を見たら気にならなくなった。
二人で水中眼鏡をつけ、シュノーケルをくわえると、驚くほど透明度の高い水の
中に私達は進みだした。
小久保さんが前を泳いでいる。水中眼鏡でそっちを見ると、彼女の足が、まるで
のたうつ海蛇のように妖しげに私を導く。
思わず彼女の足の間に視線が行って、水中で人知れず顔を赤らめてしまった。
なんて緊張感のない男だろう私は。久しぶりに少しだけ自己嫌悪してしまった。
しかし、大好きな彼女と二人で使命感に燃えながら透明な水の中を進む恍惚感は、
私のこれまでの人生の中でも最高のものかもしれなかった。
数十年前だったらすでに死んでいる自分が、生き長らえてきたのは今この時の使
命を果たすためだったのではないか?
このまま彼女とだったら死んでも悔いは無いだろう。たぶん。
水深は10メートルを超えてると思われるが、海のそこが手に取るようにくっき
り見えていた。貝ガラが表面にびっしりついた岩がごろごろしていて、魚達がその
間を気持ち良さそうに泳いでいる。上からそれを見下ろしていると、まるで自分が
鳥にでもなった気がしてくる。そうだ。鳥だまさに。
とんびなんかはきっとこんな風に下界を見てるのだ。
小久保さんの泳ぎが少し緩やかになった。
疲れてきたのかもしれない。私も少し疲れてきた。
顔を上げて船を捜すと、まだ100メートルくらいはありそうだ。
振り向くと島の砂浜がずいぶん狭く見えている。
かなり沖のほうまできたみたいだ。さっきまでは全くと言っていいほど波もなか
ったが、この辺まで来ると波というかうねりがでてきて、ゆっくりと体が浮き上が
り、沈み込む事を繰り返している。
小久保さんの手足が止まり、うつぶせに浮いているだけになった。
私は側によると、彼女の右手を握ってみた。
大丈夫だというように、彼女の右手が握り返してくる。
もしここで彼女が力尽きたとしたら、私はどうしていただろう。
自分の心臓が苦しいほどに鼓動を強めているのに、その時は気付かなかった。
再び泳ぎだした私達は、今度は何の問題も無く船の側による事が出来た。
目指していた船が目の前に浮かんでいる感動は、私もだったが、小久保さんにと
っても口では言い表せないくらいに大きなものだったろう。
水中眼鏡とシュノーケルを外して船の上に投げ入れる彼女の目は涙で潤んでいた
に違いないが、この状況ではとても確認できるわけが無い。
最後の難関は、船に乗り込むことだった。
船の縁は水面からはかなり高くなる。簡単に這い上がる事が出来ないのだ。
「軽い方があがって重い方が下から押し上げるほか無いね。もちろん軽いのは君の
方だろ」
私の声は自分でも震えてるのがわかった。疲れと寒さによるものだ。
「そうですね。じゃあ、お願いします。今回だけはお尻触られても文句言いません
から」
無理にでも冗談を言って彼女は私をリラックスさせようとする。
ゴールはもうすぐそこなのだ。
這い上がる彼女の冷たくなったお尻を私は思い切り押し上げた。
ぷるんとした感触は、直に肌に触れた感動とあいまって私の股間に数年ぶりの疼
きを与えてくれた。
一度目は失敗したが、二度目に何とか彼女が船に乗り込めた。
そして彼女の手で私も船に引き揚げられる。
船に上がった二人は20分以上全く動けなかった。
泳いでる時はそれほどでもないが、水泳はものすごく体力を使うのというのが、
泳ぎ終わった後に実感される。
「あたし、本当はすごく怖かったんです。でも、水泳部だったし、患者さんのため
というんで一生懸命がんばったんです」
やっと上半身を起こして、彼女が言った。泣いてるようだった。
「私は怖くは無かったよ。このまま死んでもいいって思ってたから」
私も起き上がった。
「山岸さんが一緒に行くって言ってくれて本当に嬉しかった」
彼女は私に抱きついて、なんとほっぺたにキスをしてくれた。
それは緊張感から開放された事と、達成感が行わせた行為だったろう。
それでも充分私に感動を与え、疲れを吹き飛ばしてくれる行為だったことは間違
いない。
「あれ、元気になってる」
私のこわばった股間を指ではじいて、彼女は立ち上がった。
太陽の光を背にして立つ彼女は、きらめく水玉を羽衣のように体にまとった、ま
るで女神の姿だった。
透析室の長い午後2
洋上の女神 おわり