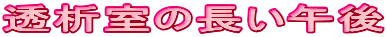人工透析という医療をご存知の方はむしろ少ないだろう。
腎臓の機能が何らかの原因で働かなくなった人たちに対して、行われる医療措置のことである。
私は十年ほど前からこの医療のお世話になっている。
それ専門の無機質な病院のベッドに、いつものように私は横たわる。
私たち透析患者は週に3回、少ない人は2回の人もいるが、このベッドに4時間ほど縛り付けられる。
縛り付けるというのはもちろん比喩だ。
文字通り縛り付けられるのは、頭がボケてしまって、ほうって置くと血管にさした管を自分で引き抜きかねない一部の可哀想な人たちだけである。
週3回というのは、約1日おきに此処に来ないといけないということだ。
最初は生活のリズムが狂い、うっとおしくてたまらないが、さすがに10年も続けると慣れてくる。
私の担当の看護婦、小久保さんがいつもの優しい笑顔でピンクの白衣(ちょっと形容矛盾があるか?)
のすそを翻しながらやってきた。
「山岸さん、体重は量りましたか」
小久保さんはいつ見ても可愛いなあ。
目がくりっとして、確か今年25才になると聞いたが、まだ高校生と言われても不思議に思わないだろう。
色白だし、セミロングの髪をアップにとめて、ナースキャップを付けたそのうなじにはぞくっとする。
「山岸さん!体重は?」
おっと。いけない。
ボーっとしてしまった。
「はい、64.2だったですよ」
彼女は個人台帳の方に目を移し、ちょっと顔をしかめる。
「少し増えてますねえ。あまりお水飲んじゃ駄目ですよ。それじゃあ、13時スタートだから、20分したらまた来ますね」
彼女は私を軽くたしなめると、カウンターのパソコンを操作しに戻った。
私たち透析患者は腎臓がストライキを起こしているから血管内の余分な水分をろ過する事が出来ない。
だから尿が出ない。
飲んだ水は、汗になって排出されなかった分が次に透析するまでの間体内に残る事になる。だから体重が増える。
そして増えた分を次の透析の時差し引く必要があるのだ。
シャントと呼ばれる皮下に留置した管に、普通の注射針の何倍かの太さの針を入り口と出口の2本刺し、そして血液を抜き取り、機械を循環させた後また体内に戻す。
これを約4時間続ける。
終わった後は血液が浄化されるから気分が良くなってしかるべきなのだが、急激な変化が、やはり心臓やその他の内蔵にプレッシャーをかけるのだろう、ぐったりと疲れ果ててしまう。
中にはそのまま具合が悪くなって入院するはめになる場合もある。
つまり透析医療はまだまだ完成された医療とは程遠いという事だ。
私の隣の末吉じいさんの処置をしに、小久保さんがまたやってきた。
末吉じいさんとはもう6年間隣同士だ。
私より10年長く透析をしているそのじいさんは年も8歳上で今年70になる。
ちょうど70の誕生日は友の会で何かしてあげたいな。
今度の会合で提案してみよう。
末吉じいさんは昔船員をしていたそうだ。
今でもベッドから正面に見える窓の外の海を眺めてはいろんな話をしてくれる。
これくらいの波の時が一番酔い易いんだよ。
あまりひどくなると、酔ってる暇がなくなるからね。
これくらい大丈夫と油断してると、いきなりぐえっと吐きそうになる。
一人が吐けば周り中が吐き出す。
酸っぱい臭いで伝染しちまうんだ。
そこまで聞いて、私はもう勘弁してくれと制止したっけ。
あんた顔色悪いよ、なんてまったく鈍感なじいさんだ。
高台にあるこの病院の、数少ない良い所がここからの眺めだ。
西向きの窓は、夕日が射して、夏はブラインドが欠かせないが、海に落ちていく夕陽を眺めるのは心が休まる。
小久保さんが末吉じいさんの世話をしている。
ベッドに寝ている患者を扱うから、上体がかがんで、腰を突き出す格好になる。
ちょうど私の目の高さを彼女の丸いお尻が、右に行ったり左に行ったり。
くびれた腰から張り出したヒップは、女性の魅力のもっとも集中した部分だ。
今日はTバックかな?パンツの線が見えない。
私は左手に隠し持った手鏡を、さりげない振りをして彼女のスカートの下にもっていく。やっぱりTバックだ。
それも彼女のお気に入りの緑のやつだ。
なぜ彼女のお気に入りとわかるかというと、彼女の好きな色が緑であり、このパンツは多分1枚しか持ってないからだ。
何日かにいっぺんだけ見かける。
私はメモ帳に、Tバック・緑、と記入する。
今日はデートの日かもしれない。
ここの事務員の下原という男と付き合ってると聞いた事がある。
今日は勝負の日かもしれないな。
いいなあ若いって。
今度は彼女の可愛いヒップをやわらかくさすってやる。
ゴムまりみたいな弾力が手にかえってきて、嬉しくなる
「山岸さん。駄目ですよ」
彼女はそう言いながらも避けない。
今、針刺しの大事なところだから、避けられないのだ。
でも彼女はそんなに嫌そうじゃない。
嬉しくも無いだろうが、ある程度は仕方ないと割り切ってるようだ。
私はそんな彼女が大好きだ。
すぐに大声あげて変態呼ばわりする看護婦もいるが、そんなのに限って不細工な看護婦だ。
間違って手が当たっただけで、わざとじゃないのに、婦長に言いつけていたりする。
悩み多き患者の数少ない楽しみの一つなのに、それを理解しないんじゃあ看護婦失格というものだ。
しかし、右隣の裕子ちゃんが遅いな。
いつもだったら、既にきていて、私とおしゃべりしているはずなんだが。
「裕子ちゃんはまだ来ないのかな」
私は背中を向けている小久保さんに聞いてみた。
「彼女、先週亡くなっちゃったの。大学病院のほうで……」
振り向いて小さな声で、小久保さんは言った。
看護婦をしていれば、人の死に遭遇することは何度もある。
だが、それでも悲しい時は悲しいのだ。
彼女の目は、何も言わないが、痛いほどその気持ちはわかった。
私の中で、切ない気持ちがこみ上げてくる。
さらに落胆とやるせなさ。
目が熱くなり、涙があふれるのがわかった。
裕子ちゃんはまだ二十歳になったばかりだった。
高校1年のときに慢性腎不全になり、2年後から透析を始めたと聞いていた。
私とは2年間あまり隣同士で、いろんな話をしたもんだ。
先々週、彼女は落ち込んでいたっけ。
彼氏が出来たのは嬉しいけど、こんな身体じゃ結婚なんて無理だと泣きそうな顔をしていた。でも、それでもいいと言っていた。
少しの間だけ、彼に結婚相手が見つかるまでの間楽しく遊んでくれればいい、そんなこと言っていた。
そして次にあった時、こぼれるような笑顔でこう言った。
「彼、結婚しようだって。病気なんて持ってる人は誰でも持ってる、子供が生めななくてもいい。二人で楽しい家庭をつくろうって」
そうだ。彼女は幸せの絶頂だったんだ。
幸せの絶頂でそのまま天国に行ってしまった。
人工透析は先程も書いた通り心臓に負担がかかる。
もとから心臓が弱い彼女のような人は、前回元気にしていても、急にいなくなってしまう事がたびたびあるのだ。
大した理由も無く、まあ本人には重大なんだろうけど、自殺する若い人が多いのに、片方ではこうやって幸せをつかみ損ねて死んでいく若い命もある。
できることなら代わってやりたかった。
その代償なんて、一度お尻触らせてくれるだけで充分だったのに。
「じゃあ。山岸さん針刺ししますよ。今日はちょっと痛いかもしれませんけど、痛かったら罰が当たったって思ってくださいね」
小久保さんがそう言って私の腕を取った。
ピンクの白衣 (やっぱり形容矛盾だよなあ) の胸元から滑らかな肌が谷間を作ってるのが少し見えた。
ちくりと、痛みがやってくる。
透析用の針は普通の採血用の針の何倍も太い。
だから痛みも大きいが、しょっちゅうやられてるんで我慢する事は難しくない。
私の身体からどす黒い血が抜き取られて、機械のポンプの中を循環する。
そして毒気を抜き取られた新しい血が再び帰ってくる。
透析はいつも同じベッドでするから、隣同士になった人は何年もの付き合いになる。
そうして私は幾人かの友人を作ってきた。
裕子ちゃんもその一人だった。
週に3回、4時間ずつ、世間話をしたり、相談事を持ち寄ったり。
出会いはたくさんは無い。
だから別れもたくさんは無いのだけど、普通の場合と違って、ここでの別れはそのまま生死の別れになる事が多いのだ。
透析が始まって2時間ほど、ちょうど折り返し点に差し掛かったあたりで、岡田婦長がやってきた。
私に何か話があるようだ。
彼女はまだ40歳になったばかり。痩せ型の彼女はどことなく陰険な目つきをしている。実際あまり患者の間では評判は良くない。
しかし権謀術策にすぐれでもしないと、この若さで婦長になるのは無理というものだ。陰険なのは当然だ。
「山岸さん。ちょっといいですか」
いいも悪いも無い。こっちは逃げる事も隠れる事も出来ない状態だ。
「山岸さん、看護婦のお尻触るの止めてくださいね。ここはそんなサービスはやってないんですよ、残念ながら」
少し世間話をした後で、婦長は切り出した。
とても残念そうには見えなかった。
「わかりました。注意します」
他にどういう言い方があるだろう。
私は素直に反省するふりをした。
「小久保さん、山岸さんの担当かえてくれって言ってきたんですよ。もう我慢できないって。一応私から言っておくから我慢してと言っときましたけど」
婦長の最後の言葉は私の心にズンとカウンターパンチのように決まった。
あの小久保さんが婦長に告げ口するとはあんまりだ。
信じていたのに。
去っていく岡田婦長を見送りながら、私は発作的に血管に射してある管を引き抜こうとした。
でも途中で止めた。
そんなことをしてみても何も変わらないのがわかってるからだ。
透析が終了に近づいてきた。
針を抜くとき小久保さんと顔を合わせるのが嫌だ。
何かいやみを言ってしまいそうで。
彼女は悪くないんだが、それはわかってるのに嫌がらせをしてしまいそうだ。
小久保さんが私の針を抜きに来た。
彼女はいつもと変わらない笑顔だった。
私と目を合わせても、普通に笑いかけてくる。
ちょっと変だ。
私はそれとなく彼女に聞いた。
「婦長と何か話したの」
彼女は何の事かわからないようだ。
「岡田婦長から何か言われたんですか?ひょっとしてお尻触るなとか?」
少し考えて、彼女が言った。
「そのとおりだよ。君が苦情を持っていったんじゃないの?」
私の腕に針を抜く痛みが走る。
四時間も刺したままだから、抜く時は皮膚が引きつって、刺す時よりも痛い事がある。
「岡田婦長、早くも更年期障害が来てるらしいんですよ、普段でもきついのに、ますますわけわかんなくなっちゃって。私は別に何も言ってないですから。だって、山岸さんの触り方お上手なんですもの、全然嫌じゃないですよ。でもあまり人前では止めてくださいね。変に思われますから」
やっぱり小久保さんは天使だった。
私はこのまま死ぬまでここで透析を受けてもいいと思った。
処置が終わり、私が帰り支度をしていると、右隣の裕子ちゃんのベッドに小久保さんに連れられて若い女性がやってきた。
「今日からこのベッドで、透析を始めます、藤木鮎子さんです。今日は17時スタートだけど、次回から山岸さんと同じ13時スタートになりますから、よろしくお願いしますね」
小久保さんがその女性を、私と反対側のお隣さんの岡本さんに紹介した。
「藤木です。よろしく」
そう言ってぺこりと頭を下げる彼女は、裕子ちゃんと同じくらいの年齢か。
化粧はほとんどしていないのに、切れ長の目とすらりとした鼻筋は美女としか言いようが無い。
別れがあれば出会いがある。
そして、また別れが来るだろう。
でも今度この美女と別れる時は、彼女が死ぬ時ではなく、自分がこの場から消えるときでありますように。
私は一度背伸びをして、窓の外の遠い海を眺める。
赤く焼け爛れた太陽が造船所の倉庫の影に入ろうとしている。
造船所の高いクレーンの影が、真紅の海の上にまっすぐな線を一本引いていた。
透析室の長い午後 終わり