|
|
ハリー・ポッターと賢者の石 |
オフィシャル・ページ(日本語) ヤフーのハリー・ポッター特集 オフィシャル・ページ(英語) |
| 第一章 スター・ウォーズとの共通性 『ハリー・ポッター』をみた最初の感想。 「これって、スター・ウォーズでしょう。」 どうみても、スター・ウォーズそっくりの話。どこがというと、それは全てと言って良いかもしれない。 主人公は選ばれしものであるのだが、不遇な環境にある。ハリーは叔父夫婦の家で育てられていたが、ルークもまた叔父の家で育てられていた。そこに、異世界から主人公を迎えに来る使者(ハグリッド/クワイ=ガン or オビ=ワン)が現れる。異世界へと旅立つ主人公。主人公を支える友人と老賢者。頼りになる相棒。主人公は天性の才能(魔法/フォース)を持ち、その能力は大会(クイディッチ/ポッドレース)での勝利で花開き、人々の信頼を集める。主人公には、父がおらず父の死について疑問を抱いている。神秘的な力の援助を得て、強大な敵を打ち破り、父親の問題を解決し、主人公は精神的に安息と成長を得て、物語はハッピーエンドで終了する。 『ハリー・ポッター』、その物語は、「スター・ウォーズ」(旧三部作と『ファントム・メナス』)にそっくりである。 |
| ハリー・ポッター | スター・ウォーズ |
ハリーは期待される存在 |
アナキンは選ばれし者 あまり人気者でなかったり、影の部分を持つ。  or ルーク・スカイウォーカー |
叔父夫婦に育てられるハリー |
叔父夫婦に育てられるルーク
 |
ハリーを迎えに来る男ハグリッド |
アナキンを迎えに来るクワイ=ガン |
| 頼りになる仲間 ロン(Ron) 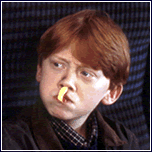 コミカルな役柄 しかし、最後には頼りになる |
頼りになる仲間 |
頼りになる仲間 |
頼りになる仲間 |
頼りになる相棒 |
頼りになる相棒 |
| 老賢者 校長  |
|
天性の才能 魔法 |
天性の才能 |
大きな成功で人々の信頼を集める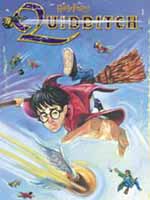 クイディッチの勝利 |
大きな成功で人々の信頼を集める  ポッドレースの勝利 |
| 父親の死の秘密を探る | 父親の死の秘密を探る |
魔法使いのチェス |
モンスターチェス |
| カエルのようなものを食べる カエルチョコ  |
カエルのようなものを食べる |
| ユニバース(世界)の形成 ネーミングの妙 多くの魔法 多くの生物 多くのキャラクター細かな設定 |
ユニバース(世界)の形成 |
| 不思議な力(賢者の石)の援助を得て劇的勝利 | 不思議な力(フォース)の援助を得て劇的勝利 |
これらの共通点は、偶然によるものか。 音楽は、二作品ともジョン・ウィリアムが担当しており、その音楽の印象が、「似ていると」という感想を強固なものとした可能性はあるが、音楽とストーリーテリングは関係ない。 また、『ハリー・ポッター』の特撮はILMがやっており、クイディッチとポッドレースの映像的な共通性は、そうした特撮技術にによって説明できる部分もあるが、やはりこれもストーリーテリングとは無関係である。 『ハリー・ポッター』は、スター・ウォーズ旧三部作との共通性もあるし、『ファントム・メナス』との共通性もある。「ハリー・ポッターと賢者の石」の原作が発売されたのは、1997年6月であり、その頃には『ファントム・メナス』のシナリオは完成しており、どっちがどっちを真似たということではなく、ほぼ同時期に創作されたと言っていいだろう。 では、なぜ『ハリー・ポッター』と「スター・ウォーズ」は似ているのか。 |
| スター・ウォーズとの共通性 |
| 音楽 | ジョン・ウィリアムス | ジョン・ウィリアムス |
| 特撮 | ILM | ILM |
| 俳優 | ワー・ウィック・デイビス  魔法の先生 ゴブリンの銀行員も彼が演じている 一人二役で登場 |
ワー・ウィック・デイビス  一人二役で登場 |
第2章 『ハリー・ポッター』のキャンベル的解読 多くの神話や伝承は、同じようなテーマとモチーフを含み、その物語の展開はほとんど同じであるという。その神話の共通性について詳しく研究したのが、ジョーゼフ・キャンベルの「千の仮面を持つ英雄」である。キャンベルはジョージ・ルーカスが自ら「師」と仰ぐ人物であり、ルーカスは彼の大きな影響のもと、スター・ウォーズを作っている。 実は、スター・ウォーズは「千の仮面を持つ英雄」の原質神話の物語展開を極めて良く踏襲している。ルーカスは、「千の仮面を持つ英雄」をよく読み研究していたようだが、同書の雛型に合わせてストーリーを考えたわけではないと、自ら語っている。結果として、たまたま一致してしまったということだ。 多くの人の共感を呼ぶ物語は、原質神話の物語に近づく。世界3600万部のベストセラーとなり、映画も大ヒットした『ハリー・ポッター』も、多くの人の共感を集めた作品と言っていいだろうが、当然のように『ハリー・ポッター』もまた原質神話の物語展開を踏襲している。その共通性については、下の一覧表にまとめた。 『ハリー・ポッター』と『ファントム・メナス』のストーリー展開は、驚くほど原質神話の物語展開に一致している。しかしながら、スター・ウォーズにおけるキャンベルの影響や、『ハリー・ポッター』のキャンベル的考察は、既に多くの人が述べているところであり、発見としては新味がない。興味のある人は、サーチエンジンでキーワードを入れれば、たくさんの論文や考察が読めばいい(ただし英語)。 私は、もっと別の点に注目したい。すなわち、ほとんどの点で、この二作品は原質神話の典型的なパターンを踏襲していながら、唯一つの点において異なる部分がある。そして、不思議なことに、その相違点までもが、『ハリー・ポッター』と『ファントム・メナス』で極めてよく類似しているのである。 |
ジョーセフ・キャンヘルの「千の顔を持つ英雄」による |
| ハリー・ポッター | スター・ウォーズ | |
| 召命の拒否 | 召命の拒否をしない
 魔法学校からの正体を 心から喜ぶハリー |
召命の拒否をしない
 タトゥイーンから出ることを 無邪気に喜ぶアナキン |
| 超自然的な もの援助 |
魔法(超自然的なもの)の援助 スネイプ先生の影なる援助 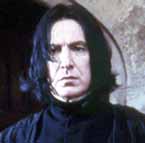 |
フォース(超自然的なもの)の援助 |
| 最初の境界の 越境 |
 魔法の町(ダイアゴン横丁)に 入っていくシーン 魔法学校に着いたときのシーン未知の世界に入って行く好奇心の強い少年 |
 コルサントについたアナキン 未知の世界に入って行く好奇心の強い少年 |
| 鯨の胎内 | 地下深くへの冒険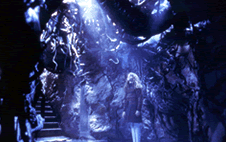 |
バトルドロイド指令船の 内部へ侵入  |
| イニシエーション 試練の道 |
クイディッチの勝利で ヒーローとなる 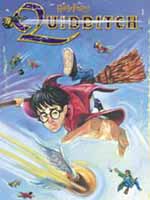 |
ポッドレースの勝利で ヒーローとなる  |
| 父親との一体化 | 父親の敵ヴォルデモートを倒すことにより、父親との一体化を果たす | 『ジェダイの復讐』 ルークのアナキンとの心の交流による精神的一体化 |
| 神格化 |  ヴォルデモートとの対決に勝ち英雄となるハリー |
 ドロイド指令船を破壊し 英雄になったアナキン |
| 終局の恩恵 | グリフィンドールの勝利 大団円のラストシーン |
ナブーの勝利 大団円ラストシーン |
第3章 「召命の拒否の否定」 それは「召命の拒否」をしないということである。 英雄は、必ず「召命の拒否」をする。すなわち、冒険への旅立ちを仲介する使者が,英雄のもとに現れ、冒険への旅立ちのきっかけをつくる。しかし、英雄は最初、冒険に出ることに躊躇し、拒否するのだ。 例として、『スター・ウォーズ 新しき希望』をあげよう。辺境の惑星の農夫にすぎないルーク・スカイウォーカーは、スペース・アカデミーに入りたい、宇宙に飛び立ちたいという願いを抱いていた。そこにレーアの助けを求めるメッセージを持ったR2-D2が現れる。そして、オビ=ワンはルークも一緒に宇宙に行こうと誘う。本当であれば宇宙に行きたくてしょうがなかったはずのルークだが、「おじさんとおばさんたちをおいて宇宙には行けない」と、オビ=ワンの誘いを断る。これが、「召命の辞退」である。 宇宙へ出たいという願いを抱いていながら、実際そのチャンスが巡ってきた場合、しりごみしてしまう。確かに、命の危険性も高いわけで、躊躇するのは当然といえる。 結局、ルークはオーエン叔父、ラーズ叔母の死に直面して、タトゥイーンに残る理由がなくなり、宇宙への冒険に旅立つ決意を固める。 では、『ファントム・メナス』のアナキンの場合はどうか。アナキンもまた宇宙に旅立つことを強く望む少年であった。しかし、ある日クワイ=ガンが現れ、ポッドレースに参加し、優勝するアナキン。そして、クワイ=ガンはアナキンに言う。今日から自由の身だと。そして、宇宙に飛び立ち、ジェダイの訓練を受けさせると。アナキンは大喜びする。二つ返事で、宇宙行きを受け入れる。そこには、「召命の辞退」は存在しない。母シミは自由の身にならないことを知り、多少の戸惑いを見せるものの、宇宙に行く決意は変わらない。 ヒーローとしての用件である「召命の辞退」を、アナキンは満たさない。もし、ルーカスがキャンベルの影響を強く受けているのなら、ここでアナキンは「召命の辞退」をしてもいいはずである。「母を一人でここに置いていくわけにはいかない」と、もっと強く主張するはずだ。「召命」に対するリアクション、戸惑いと沈痛な表情を見せるルークと大きな喜びを全身で表したアナキン。そこには大きな違いがある。 ルーカスが敬虔なキャンベリアンであれば、ルークと同様に、アナキンにも召命を辞退させるはずではなかっただろうか。しかし、アナキンが召命を辞退しなかったことは、ルーカスによってかなり考え抜かれた描写であると考えられる。「召命の辞退」は英雄になるための要件である。すなわち、ルークは英雄になるための要件を満たし、アナキンは満たしていないことになる。 しかし、それは正しいことではないか。純真な少年アナキンは、将来ダーク・サイドに落ちて、ダース・ヴェイダーになる。すなわち、アナキンは一般的な英雄とは異なった存在である。最終的には、「フォースに調和をもたらす者」となるのだろうが、その経過で悪にどっぷりと染まった存在になる。いわゆる一般的な神話における英雄の要件を満たしていないことが、アナキンが善を代表する英雄にはならない、すなわちアナキンの将来の陰りを暗示していると見ることができる。 そう考えると、『ファントム・メナス』では、アナキンはたまたま召命を辞退しなかったという消極的な描写ではなく、アナキンは召命を辞退するのに適した人物ではなかったので、ルーカスは意図的、そして必然的にそう描いたということになる。単なる原質神話のストーリー的模倣に過ぎなかった『新しき希望』とは、大きな違いが生まれてきている。 |
| しかし、「召命の拒否」は、『ハリー・ポッター』にも見られる。叔父の家に世話になっていた両親のいないハリーは、家族にいじめられる日々を送っていた。そこに、ホグワーツ魔法学校からの招待状が送られてくる。そして、怪しげな風体のハグリッドが、ハリーを迎えに行く。髭もじゃで巨体のハグリッドは、すごい迫力である。しかし、ハリーは何の不信感も持たずに、喜んでハグリッドについていく。ハリーはやはり、召命の辞退をしないのである。 このシーンも、常識に照らせば、少しおかしい。この怪しげな風体の男の言うことを素直に信じて、普通の人はホイホイとついていってしまうだろうか。確かに、この家にいたくないという描写はあるが、多少の逡巡や疑いがあったほうがリアルはないか。それが、ホイホイと、喜んで |
|
| ハリーは、ハグリッドについていく。これも、また意図的な描写と考え方が良いのかもしれない。 第四章 原質神話の変質 原質神話の変質が、この二十一世紀に起きようとしているのか。 実は、『ハリー・ポッター』と同時期に公開された、『シュレック』でも「召命の拒否」が否定されている。 シュレックはファークアード卿から、自分の住む沼を返却する約束をもらうかわりに、フィオナ姫の救出を命じられる。シュレックは、その申し出を、何の文句も言わずに受諾する。シュレックは人に命令されたり指示されたりするのが嫌いなマイペースな男として描かれている。あるいは、何かものぐさなところがある男である。その彼が、イヤミの一つも言わずに、ファークアード卿の「姫を救出せよ」というミッションを受け入れてしまうのは、非常に違和感がある。「なぜ、わしがわざわざ行かな、あかんねん」(浜ちゃんの日本語吹替風)くらいのセリフが入っていなければおかしい。しかし、シュレックは、「召命の拒否」をしない。 最近の主要な映画の冒険物語では、いずれも「召命の拒否」が認められない。 これを単なる偶然と考えて、見逃してしまっていいのか? 召命を拒否しない方が、現代人の共感を呼ぶ、だから物語がそう作られていると考えた方が良いだろう。 現代人は、冒険を欲しているのだろうか。経済的にも不安定で将来が見えない現代。堅実に仕事をしていても、リストラに合うかもしれない。イソップ童話の「アリとキリギリス」に例えると、堅実にコツコツと蓄えるアリ的な生き方よりも、今を楽しむというキリギリス的な生き方が美徳とされる。例えば、今の若者は将来の安定を得るためにきちなと就職するよりも、今の自分を生かすために、フリーターとして生きる。そんな、キリギレス的時代に突入した、時代が変化したといえないだろうか? どうせ、今の立場にいても将来の不安は変わらないから、いっそのこと全てを捨てでも冒険するのも悪くない。多分、冒険は時代を超えて、多くの人たちは「したい」と思いながらも、それは物語の世界だけにしたいという保守的な考えがあったかもしれない。それが、「実際にしても悪くないかな」という気持ちが生まれてきている。 あるいは、冒険的に生きないと、生き残れない時代に入ってきているのかもしれない。もし、チャンスが来たのなら、断るのはもったいない。進んでチャレンジしたい、そんな気風が生まれてきているのではないか。 例えば、日本人プロ野球選手の海外進出である。野茂選手が大リーグに行こうとしたとき、マスコミは野茂が大リーグに成功するはずがないと、批判的な報道が多かった。また、多くの日本人もそう思った。そして、野茂以前では、どんなに実力のあるピッチャーでも、日本の成功を捨ててまで、大リーグに行こうとは思わなかった。それが、野茂の成功以後、意識革命が起きた。今や、 一流選手であればフリーエージェント後は、大リーグを選択肢の一つとして考えるのが、当たり前になっている。 冒険への躊躇は、一昔前に比べると、著しく減っている。 こうした社会現象が、世界的なものかどうかは、わからない。しかし、ニューヨークのテロ事件に象徴されるように、世界的にも暗い時代に入っていることは確かであり、冒険や試練の道は小説の中だけではなく、現実のものになっているのである。 『ハリー・ポッター』が世界的にベストセラーになった理由について、いろいろな説が語られている。「召命の拒否」の否定が象徴するように、現代人の意識変質とそれに『ハリー・ポッター』がうまく同調したということは、確かだろう。そしてもちろん、スター・ウォーズもそうした人々の変化を見事にとらえている。 |