|
|
|
|
|
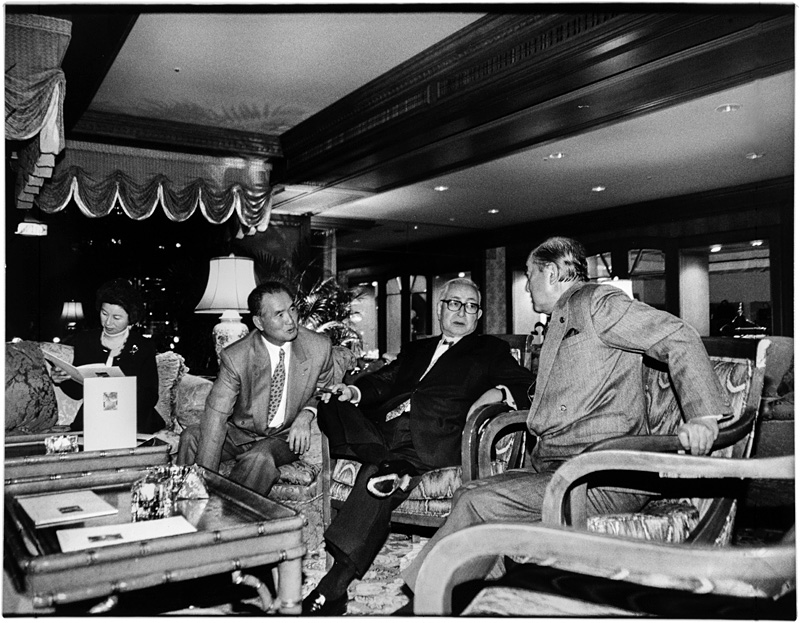 |
1997.12.25 長嶋茂雄、渡邉恒雄氏夫妻らとクリスマスで会食
於フォーシーズンズホテル |
|
|
『 それを自動車でも汽車でもやる。どこでもやる。
寝られない場合には、横になっても同じような想念をもってやる。
そうすると眠りを誘う。これが私の健康の非常に大きな要素で、座
禅のお陰であろうと思いますね。
総理をやっているころ、毎日曜日、全生庵へ座禅に行ったけれど、
数えてみると5年間に172回行っているものね。』
好きなスポーツチームはありますか。
『 長嶋さんが家主だから、ジャイアンツを応援していますね。
ドームには時々行きますよ。私が行くと連敗を脱すると言うんだね
(笑)。だから渡辺社長が、連敗になると券を送ってくれる。』
どんな芸能に興味がありますか。
『 やはり、映画だね。昔は、映画を良く観たもんです。学生の頃は
フランス映画、ヴィリ・フォルストの作品、ジュリアン・デュヴィ
ヴィエの作品、ジャン・ギャバンとか、そういうものが好きだった
ね。最近は時々、歌舞伎を観に行きますね。あとは猿之助とかもね。
梅原猛さんと僕は仲がいい。だから梅原作品を猿之助が演じるとき
は、ほとんど観に行くね。
あとは劇団「四季」だね。浅利慶太君とは非常に仲がいい。劇団
「四季」創設のころから僕はファンで、ずっと長いこと観ている。』
信長、秀吉、家康の中で惹かれるのは誰ですか。
『 信長だね。』
どういう点で。
『 天才的な要素があって、そして新しい時代を築いた人という意味
でね。秀吉や家康というのは、信長の跡を継いだ人ですよ。
まあ人間的欠陥もあったけれど、しかし歴史的な偉業をなしたと僕
は思っている。』
次頁へつづく
|
| |
|
|
|
Copyright (C) 2006 YUICHI HIRUTA. All rights reserved. |
|
|
|
|
|
|
 |
|
| 1999.2.19 自民党の歴代幹事長の会 料亭「新喜楽」 |
|
|
信長、秀吉、家康の中で性格的に一番近いと思うのは誰ですか
『 さあ、3人の要素をもっているね。さもなければ総理大臣でき
ませんよ。
どっちかってといえば、信長的な直感力と家康的我慢力。
我慢力というのは、意外に大事な要素なのよ。時を待つとか。ある
いは怒りを鎮めるとか。』
理屈抜きでウマの合う人、好きなタイプは
『 やっぱり情のある人で、嘘を言わない人だね。それでお互い裸で
付き合える人というのが好きだね。本音が分かる人。』
瞬時に相手を見抜くには相手のどの点に注目しますか
『 人間というものは表情に出るのですよ。それから体容に出る。
体の様子に。「頭容」は直、目容は端、口容は止、手容は恭、足容
は重、体容は粛」という言葉がある。
それだけではないけど、やはり表情に一番正直に出るんだね、人間
は。』
若いころの愛読書は
『 「聖書」は、若いころよく読んだですよ。「生命の実相」、「聖書」
は学生のころから読んでいた。
戦争に行ったときに、私は将校だから、柳行李をひとつ持っていけ
た。その中に持って行ったのは、「聖書」、それから「茶味」とい
うお茶の本、それと「冬の旅」(Winter reise)のレコードでしたよ。
「冬の旅」はフィリピンのダバオへ上陸して、敵がもう退却してし
まって、平和が回復した1週間か10日後に、そこにいたアメリカ
人の住宅に蓄音機があったんで、「冬の旅」をかけた。今でも記憶
しているね。』
尊敬できる政治家はいますか
『 リンカーン、ガンジー、ド・ゴール、マンデラとか、そういう人
を偉いと思ってきましたね。』
次頁へつづく
|
|
|
| Copyright (C) 2006 YUICHI HIRUTA. All rights reserved. |
|