APEXi POWER INTAKE & エアクリーナーBOX |
2006.Apr.25 Renewal |
|
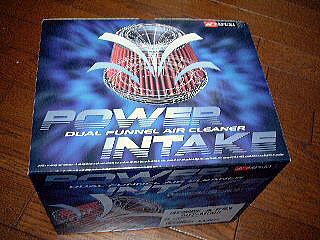 |
純正交換タイプのエアクリーナーからさらに吸気効率UPのため純正エアクリナーBOXを取り払いAPEXiのPower Intakeにも交換することにしました。 本来はECUの書き換えを行い燃調を調整しなくてはいけないので、交換をためらっていましたが、ディーラーの整備士さんが「純正のエアフローメータは結構幅を持たせた設定ですからそのまま使えますよ!」と教えてくれたので、交換に踏み切りました。 更に、遮熱を考慮してアルミ板を加工してエアクリーナーBOXを製作しました。 |
|
Power Intake エアクリーナー |
||
 |
エアクリーナーを取り外した、エアクリーナーBOXの状況です。 お世辞にも効率の良い形とはいえない構造です。 このエアクリーナーBOXをそっくり取り除きます。 ○印のボルト2本を取るとエアクリーナーBOXは外れますが、エアフローメーターがBOXに4本のボルトで取り付けられています。 4本のボルトはエアクリーナーボックスを完全にエンジンルームから取り外した後でないと緩めることが出来ないので、サクションパイプとエアフローメーターを切り離しエアフローメーターも一緒に取り出します。 |
|
エアクリーナーとエアフローメータを取り除く |
||
 |
エアクリナーBOXとエアフローメーターを取り外すと、エアクリナー取り付けのステー金具が現れます。 ○のボルト3本を外し、ステー金具を取り除きます。 真上から止められているボルト2本はPOWER INTAKE本体を取り付けるときに再使用しますので、保管しておきます。 画像では隠れていますが、この2本のボルトの間に実は、ボルト穴があって、後に重要になります。 |
|
エアクリナー取り付けのステー金具を取り除く |
||
 |
取り外したエアフィルターBOXとエアフローメーターです。 エアフローメーターは単品で35000円もしますので、損傷を与えないように丁寧に、エアクリーナーBOXから取り外します。 特に内部に薄いアルミ製のハニカム板がありますので、絶対に傷つけないように扱ってください。 |
|
 |
フィルターは、エアフローメーターを取り付けし、付属のダイキャスト製エアフローアダプターとブラケットを付属のボルトで取り付けるだけです。 純正より抵抗は、かなり少なく吸入効率は格段に良くなります。 いかにも吸っているというような「シュークァー」みたいな吸気音で大きくなります。 取り付け時期が秋口でしたので、むき出しの状態でも良いかなと思いましたが、やはりエンジンルームの熱気を直接吸入してしまう状態では、本来のエンジン性能が発揮できない感じです。 高速道路では、非常に効率よく燃費も良いのですが、街乗りはいけません。やはり、熱対策は必要です。純正エアクリナーBOXはそれなりに意味のある形と構造なんですね。 チューニングの専門書によると吸入エアーの温度がPower-Upには重要で、むき出しのエアクリナーと遮熱を考えたエアクリBOXを取り付けた場合の比較では10〜20馬力の差が出るなんて書いてありました。(多分、極限状態の値だと思いますけど) |
|
当たり前のことですが、空気の温度が低い方が圧縮効率が良いに決まってます。 むき出しではせっかくのPower-Intakeが十分な効率で働いていないですね。 |
||
 |
メーカー製の遮熱BOXがありますが、良い値段します。 エアトレック専用ではオクヤマ製が非常に有名ですが、パイピングなどが付属されていて高価です。それにオクヤマ製のキットを購入した方の話では、BOXが結構干渉する部分があって加工が必要だったの情報をもらたので自作を決断、アルミ板を使用して、メーカー製とまではいかないにしても、それに近い物を製作することにしました。 純正のエアダクトを使用して、外気を取り入れる仕様とすることを条件に製作を始めました。使用する材料に特別な物はなく、全てホームセンターで入手可能なものです。 加工のし易さからアルミ板は0.8mmと1.0mmの物を使いました。 1mmを超えるのアルミ板は曲げ加工や切断加工が大変です。 特に切断加工は、今回はある程度の精度を必要とすることから金属切断用の鋏(三菱マテリアル製)を使った関係で、1mmが限度でした。 寸法は現物合わせで、自作完全ワンオフ物の製作です。 |
|
| 左は、Houzan製手動ベンダー | ||
 |
手動ベンダーを使って、遮熱BOXの形を作成します。 予め各部の寸法を測りながらの現物合わせです。 まずは、遮熱Boxの固定用のネジ穴を底に開けます。穴は3箇所ですが、真ん中は単独でシャシーに取り付けるための穴で6mm、両サイドの穴は、Power-Intake固定用ステーと遮熱BOX固定の兼用の穴で5mmの穴です。 |
|
現物合わせなのでまだ他の穴加工はしていない |
||
 |
エアダクトの接続部分です。 穴あけの加工は、ハンド二ブラーで行いました。 現物合わせでの製作のため、ベンダーで曲げ加工を行う前に穴あけ加工してしまうと、うまく合わなくなってしまう可能性があるので、形を作ってから穴あけの作業をしました。(ベンダーでの曲げ加工技術がないんです) |
|
エアダクトの接続部分 |
||
 |
外気の導入は重要ですから、ダクトがピッタリとはまるように穴あけです。エアクリーナーを取り付けるダイキャスト製エアフローアダプターも穴あけした遮熱板に借り止めして、取り付け位置をマーキングしました。 各接続部は、リベッターで固定しています。 |
|
エアダクトとの接続状態 |
||
 |
バッテリー側の遮熱板を追加します。取り付けは、リベット止めで処理します。 エアフローメーター側からボルトを予め通しておいてエアクリナー本体とダイキャスト製エアフローアダプターを取り付けます。 ボルトナットは、奥側下が一番取り付け辛いので、そこを初めに締め付けしました。 |
|
エアフローメーターとの接続部分 |
||
 |
エアクリーナーが遮熱されたBoxに取り付けられました。 ここまで出来れば、一安心かな。 |
|
エアクリーナーの取り付け完了 |
||
 |
ヘッドライトや各センサー関係の電気配線が通りますので、○の部分のアルミ板のエッジをゴムで保護しました。 | |
遮熱板エッジの保護 |
||
 |
BOXに蓋が取り付けられれば、かなりの強度が得られるとは思いましたが、バッテリー側の側板は、固定されていないのでクロスに補強を入れた。 | |
エアクリーナーBOXの補強 |
||
 |
クリーナーBOXの蓋も、現物合わせです。しっかりと形を作ったつもりですが、歪みがあるに決まっています。 まず、ベニア板で型を取りました。エンジンルーム前方の曲面の型をうまく取ることが肝心です。 |
|
エアクリーナーBOXの蓋の作成 |
||
 |
型取りが出来ましたら、フランジをつけます。例によって手動ベンダーの出番です。フランジは、1センチとしました。曲面部分(○部分)は、フランジ無しです。曲面なので私の技術ではフランジが作れませんでした。 | |
エアクリーナーBOXの蓋は1mm厚のアルミ板 |
||
 |
 |
|
アルミの地金の輝きがきれいです |
現物合わせの手造りにしては良く出来ました | |
 |
ボンネットの傾斜にピッタリ合い、うまく仕上がりました。 蓋は、4mmのステンレスボルトで取り付けました。 実際に、走行して、ボンネットを開けると、結構な熱気を感じますが、エアクリーナーボックスの中は熱気がなく、しっかりと遮熱されエアダクト経由でフレッシュエアーが導かれているのがわかります。 これで、夏を安心して迎えることが出来ます。 |
|
エンジンルーム全景 |
||
このエアクリーナーボックスの図面を作成しました。 自作の参考になれば幸いです。 必要な方は PDFファイルにてお送りいたします。(LHZ圧縮) |
現物が、完成してから、図面を作成しました。 初めから図面があれば、もっとよかったでしょうに。 図面見本 PDF 14kB |
|