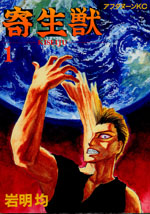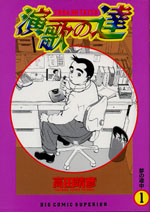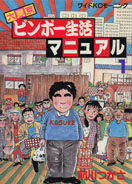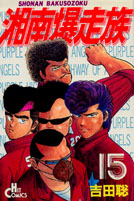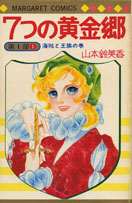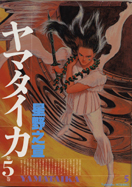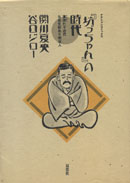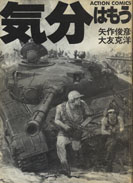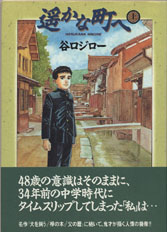
オヤジがノスタルジーを求めて悪いか?!
否、ノスタルジーはオヤジにしかわからないと言いたい。
谷口ジロー氏の傑作登場。前回第3位の『演歌の達』を押しのけていきなり第3位に食い込んだ。
タイムトラベルがらみのSFファンタジーは、もう枚挙に暇がないほどの作品群を輩出している。手垢のしみついたジャンルで光彩を放つにはしっかりとしたドラマがなければならない。ファンタジーゆえ、女の子が主人公の作品群が多い(※註1)このジャンルにあえてオヤジを持っていったところが心憎い。いいぞ!
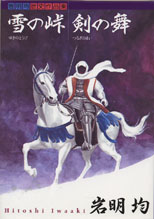
むうう。岩秋均氏、強し。
第2位の寄生獣についで、第5位にも登場。第18位には『七夕の国』もランクインしてしまった。
横山光輝氏が切り開いた歴史ドラマのマンガ化という系譜に属する作品となろうが『三国志』や『水滸伝』『徳川家康』など原作ものをマンガに仕立てた横山作品と違い、自ら取材と考察を重ねてマンガ化したこの作品は自ずとカラーが異なる。秋田に領国を移封された佐竹氏のお家話を守旧派である武官勢力と官僚型新勢力の確執を主軸にまとめた佳作。
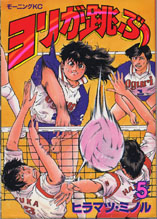
わはははは。
笑えるんだ、これがまた。コミカルなシーンがうまいなあ、この人。
スポーツものは『レジー』とか書いていたけど、こちらの方が断然楽しめる。バレーボールと言えば『アタックNO1』、スポーツマンガと言えば『エースをねらえ』いずれも少女マンガだ。キラキラするか恐るべき求道の世界に身を委ねなければ成り立たないかと思われた女子スポーツマンガに新風をふきこんだ一品。
おふざけと恥ずかしいくらい真剣な熱血ものの絶妙なブレンドが効いているこういう作品の方が好みだな。

自分を騙し騙し日々生きていることに後悔と諦観を感じる中高年労働者の皆さん、若かりし日々の夢を思い出しましょう。耀いていたあの頃に戻りましょう。
絵のタッチとシチュエーションのアニメオタクっぽさからはやや意外なほど内容は示唆に富み、大人のマンガであったりする。
作者はこのあと、真正面から大人のドラマ造りに傾倒してゆくが、この作品のバランスのよさを捨てることはないと思うがなあ。
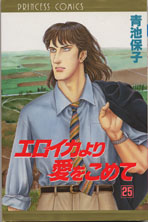
それにしても作者の青池さん、絵のタッチがどんどん変わっていった。昔のマンガではよくあることなんだけど。
もともとはオカマ系シチュエーションコメディなんてものを少女漫画の世界で確立させていたんだけど、そこから一歩踏み外してみたら、結構面白い作品になっちゃったのがこれ。
ギャグというか、シチュエーションコメディを国際情報戦にうまくひきこんだなあ、ヤラレタというのが率直な感想。でも、これ本当に終了しているのか?
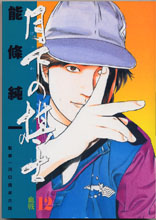
「かはっ!」とか「くっ!」とかいう擬音で開いた口がそのままストップモーションのようにアップで迫る。
これが能條センセの世界。
日本マンガ界が誇る貴重な絵師のひとりだなあ。
将棋界は演歌、浪花節の世界。
坂田三吉をモデルとしたナニワ棋士の遺志を襲ったヤンチャなヒーローの名人位争奪バトル。多士済々の棋士達との対局が楽し。
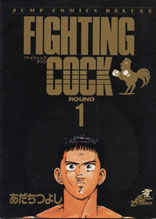
ヤンチャボーイのボクシング譚。
ボクシングほどマンガと相性のいいスポーツも類がない。
やっつけるか、やっつけられるかという白黒のつき方のわかりやすさがエンターテインメントの王道をいっているからか。
リング外の人生ドラマを見せておけば、リング上でのファイトシーンが盛り上がること必定だし。
う〜ん、ドラマ造りの基本はボクシングマンガにあるな、やっぱり。
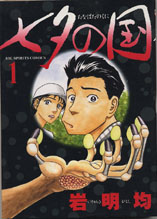
寄生獣のような傑作をあげちゃうと、もう何を書いてもそれ以上には評価されないもんだから、あまりに早すぎる代表作を持つってのは考えモンだ。
岩明氏はしかし豊かな才能、と言うか感性を持っている。それが彼を創造的早世から救っているんだろう。
それにしてもホントこの人、いい絵を書くなあ。まあるい破壊的精神波動とでもいうようなものの扱い方にまたうならされてしまった。

ホンワカしていていいっす。
大久保リトル中華街(作中の創作タウン)を舞台に料理人を志す若者の成長譚を実にオーソドックスに、またマンガらしいマンガタッチでのびやかに書き上げた逸品。
店の格を上げてゆくための『料理の鉄人』のような料理勝負もけっこう楽しめる。

「夢は語るものではなくて、実現させるものなんだ」
ああ、やられた。
筆者は、親に反対されたくらいでだらしなく夢を捨てた経験がある。
安定志向というレールの上に『人並』という列車を載せて走らせてしまった己への悔恨が作中の登場人物のセリフに肺腑をえぐられるのである。
さあ、皆!人に止められて断念するようなら、そんなのは本当の夢じゃない。頑張って自己実現を果たしてくれい!