2006.01.01
2006迎春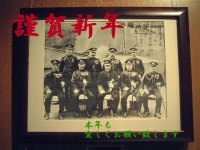 今年も宜しくお願いいたします。 今年も宜しくお願いいたします。
クイズ形式にした画像。正体は日露戦争時、海軍、連合艦隊司令部の面々でした。
佐世保セイルタワー内の掲示物。
中央、ヒゲのおじいちゃんが司令長官東郷平八郎。前列右端の端整なヒゲが参謀秋山真之。 |
|
2006.01.01
佐世保鎮守府長官 ロールオーバーの画像 ロールオーバーの画像
佐世保セイルタワー内の掲示物。
佐世保海軍鎮守府歴代長官の写真である。第8代は東郷平八郎。(画像右端下段の切れかけの写真)日本海海戦で天才と評された秋山真之の良き理解者としてサポート役に徹した島村速雄総参謀長が写真中央。 |
|
2006.01.06
浦賀水道上空 東京湾上空から浦賀水道を望む。 東京湾上空から浦賀水道を望む。
右手前が房総半島。左奥は三浦半島。房総半島の突端が館山である。両半島に挟まれた東京湾の入り口が浦賀水道。
ペリーも来たし、太平洋戦争時、米軍艦載機もこの水道上空から東京に侵入していった。 |
|
2006.01.16
渡月橋(京都嵐山) 京都は山である。 京都は山である。
山の姿がいいのだ。橋も寺も庭も、背景に山があってこそ千金の輝きを放つ。筆者レベルではその山の表情を伝えきることができないのが残念である。ゴメンなさい。
橋を境に上流は、大堰川、下流が桂川。川幅の豊かさと山を背に実にいい絵の橋である。 |
|
2006.02.05
四天王寺(大阪) 聖徳太子が532年に建立した日本最古の仏教官寺。寺なのに鳥居もある。左右に二体の仁王像を収める南大門(仁王門)から五重塔、金堂、講堂などの伽藍が一直線に並ぶ「四天王寺式伽藍配置」で有名。五重塔は八代目。過去7回も戦災、雷、台風で損壊し、昭和34年に「もう嫌だもんね」とばかりにコンクリで再建。 聖徳太子が532年に建立した日本最古の仏教官寺。寺なのに鳥居もある。左右に二体の仁王像を収める南大門(仁王門)から五重塔、金堂、講堂などの伽藍が一直線に並ぶ「四天王寺式伽藍配置」で有名。五重塔は八代目。過去7回も戦災、雷、台風で損壊し、昭和34年に「もう嫌だもんね」とばかりにコンクリで再建。
|
|
2006.02.05
四天王寺(大阪) ロールオーバーの画像 ロールオーバーの画像
左の本画像は「講堂」から「金堂」「五重塔」「南大門」を伺っているが、こちらは、「南大門」からの画像。
「講堂」の裏側には、「石舞台」や「亀ノ池」などが並んでいる。大阪の古刹は北の「太融寺(たいゆうじ)」南の「四天王寺」の二寺に代表される。両寺とも京都に比べ庶民的である。 |
|
2006.02.18
東舞鶴

来た!つひに来た、舞鶴へ。
海軍鎮守府の置かれた軍港の街。
初代鎮守府長官は東郷平八郎。
今は海上自衛隊舞鶴地方総監部が置かれ、第24護衛隊を旗下に置き、在籍艦隊に、第3・第63護衛隊を持つ。第3護衛隊の旗艦は「はるな」4,950トン。画像は、第63護衛隊の「しまかぜ」4,650トンである。 |
|
2006.02.18
東舞鶴(はまゆき)
ロールオーバーの画像。
自衛隊桟橋に舞鶴地方総監部所属の艦艇群が停泊している。
土・日・祝日は敷地内を見学できるのだ。今日は岸壁までとの許可。
機能性に徹した精悍なシルエットの護衛艦とミサイル艦が4隻、連なっている。先頭は「しまかぜ」、その後ろに第3護衛隊所属の「はまゆき」2,950トン、第24護衛隊所属の「あぶくま」2,000トン、第2ミサイル艦隊の「うみたか」200トン。なかなか壮観である。 |
|
2006.03.04
蘇洞門(小浜) 蘇洞門。 蘇洞門。
たぶん、読めないと思う。
「そとも」と読む。
小浜。
たぶん、読み間違えている。
「おばま」と読む。濁るのだ。
小浜は、何県でしょう?
先般、東舞鶴で同様の質問をしてひったまげた。関東圏の知人が皆、壮絶な間違いをやらかしている。「大分」と言う人もいれば、「静岡」「神奈川」と言う人もいる。真鶴とちゃうよ。 |
|
2006.03.04
蘇洞門(小浜) ロールオーバーの画像。 ロールオーバーの画像。
蘇洞門めぐりの遊覧船からの眺めである。蘇洞門は、若狭湾にある。
だから、東舞鶴のように京都だと思うでしょう?残念。福井県でした。
内外海(うちとみ)半島の断崖、奇岩、洞門を遊覧する50分。
波が静かならば、突端の大門・小門に上陸できるそうだが、この日は波高く上陸は中止であった。 |
|
2006.03.22
知恩院三門(京都) 京都・東山花灯路2006 京都・東山花灯路2006
ライトアップされた知恩院三門。
京都はライトアップ天国である。3月中旬、春分の日までの10日間ほど、東山の観光スポットが夜間拝観やスポットライトで彩られる。それが花灯路(はなとうろ)
知恩院は浄土宗の総本山。
開祖法然がこの地に庵を結んだのである。三門は高さ34米で日本最大。 |
|
2006.03.22
清水寺と市内(京都) ロールオーバーの画像。 ロールオーバーの画像。
清水寺の舞台と、そのむこう京都市街の夜景である。
市街でひときわ明るくそびえているのが京都駅前の京都タワー。ライトアップと言えば京都タワーだ。いつも輝いている。まさに京都の夜を照らす「ろうそく」なのである。ライトアップ、夜間拝観の清水寺界隈は人だらけ。おそらく地元民はいないだろうな。 |
|
2006.03.29
秋月 黒田家の支藩、秋月藩。 黒田家の支藩、秋月藩。
石高5万石の小藩である。
しかし、名前がいい。
「秋月藩」。
かっこいいなあ。
福岡県の県央に位置する山里にひっそりと佇む静かな城下町である。 |
|
2006.04.09
嵐山 京都、嵐山。桜が満開の日曜の朝、観光シーズン真っ只中である。 京都、嵐山。桜が満開の日曜の朝、観光シーズン真っ只中である。
溢れ返る観光客で芋洗い必至の情勢だ。しかし、桜の嵐山を消化しないのは在阪生活者の沽券にかかわる。早朝5:40に家を出、7:00に人もまばらな嵐山着。10:00には帰阪。
|
|
2006.04.09
嵐山 ロールオーバーの画像。 ロールオーバーの画像。
土手を降り、川中に張り出す護岸のコンクリート堰に足をかけ決死の撮影(んな大げさな)。土手にたむろうカメラおじさん達が筆者の真似をしようとするも、足元のおぼつかなさに皆断念。ふ・ふ・ふ歳をとると足元がねえ。 |
|
2006.04.16
金沢 金沢城、石川門からの眺め。 金沢城、石川門からの眺め。
東京ではすでに葉桜。
大阪でもかなりの花が散っている。
しかし、北陸の桜は今である。
週末に向かって満開の桜が咲き誇る。花冷えのおかげで花が散らずに済んでいるようだ。
夜にむかって雨が降りだした。
花見客には可哀想な天気だ。 |
|
2006.05.01
博多 福岡タワーからの眺望。 福岡タワーからの眺望。
高さ234メートル、海浜タワーとしては日本一の高さを誇る。天神方面(東方向)にむかっての画像。人口海浜公園のマリゾンを足下に見下ろし、シーホークホテル&リゾートとその後背にヤフードームを望む。
撮影日は3月末なので、そこのところは、ひとつ。 |
|
2006.05.01
博多 博多のロールオーバーの画像。 博多のロールオーバーの画像。
やはり、福岡タワーからの眺望。
方角は南。こちらには、西新(にしじん)がある。
「西新」って言われても・・・「何?」ってことだと思う。
筆者もそこまでは抑えきれていない。
ま、とにかく、そういうことで。
ひとつ。 |
|
2006.05.13
藤棚(水戸偕楽園) 桜が終われば、「藤」か「つつじ」。 桜が終われば、「藤」か「つつじ」。
藤棚の藤はきれいだ。
桜が華美、つつじが豪奢とすれば藤は高貴。
ただし、それはあくまでも飼い慣らされた藤棚での話。野生の藤はけっこう怖いですぜ。(詳細は紀行「スーパーひたちの車窓から」をご覧ください) |
|
2006.05.21
鞍馬 京都市内から約30分。 京都市内から約30分。
洛北の避暑地、鞍馬に着く。
叡山電鉄(通称EIDEN)鞍馬駅からすぐに鞍馬寺の仁王門がある。
時まさに新緑の季節。
緑が目に眩しい。
筆者が最も好きな季節が来た。
鞍馬山周遊は全長約2.5キロ。 |
|
2006.05.27
貴船 「きふね」ではない。濁る。「きぶね」なので、そこのところは、ひとつ。 「きふね」ではない。濁る。「きぶね」なので、そこのところは、ひとつ。
叡電「鞍馬駅」のひとつ手前が「貴船口駅」。そこから貴船川に沿って2キロほど遡上する。
天武天皇の時代に改築記録が残っている貴船神社。西暦600年後半の話ですぜ。・・・しかも改築だし。 |
|
2006.06.17
鎌倉(明月院) 北鎌倉まで横浜から20分。北鎌倉は鎌倉の隣駅である。 北鎌倉まで横浜から20分。北鎌倉は鎌倉の隣駅である。
撮影日は6月10日の土曜日。
なかなかの人出である。関東圏で歴史を感じさせる土地と言えば、やはり鎌倉である。京都が混むように鎌倉も混むのである。
2000株の紫陽花が待ち受ける明月院。明月庵としての創建は1160年。 |
|
2006.06.24
小田原

小田原城の花菖蒲。
花菖蒲祭りを開催中であった。
画像奥のレトロな建築物は、図書館らしい。昔は小学校があったような気もするが、遥かな遠い記憶なので人には言わないように。 |
|
2006.06.24
小田原

ロールオーバーの画像。
花菖蒲園から紫陽花が群生する櫓までの絵。手まりのような紫陽花がビーズを撒き散らしたかのような印象を与える。入梅後の心もとない空の下、艶めかしい景色である。 |
|
2006.07.22
本部半島(沖縄) ちょいと多忙でトップページ更新が滞っていたが、一気に挽回である。 ちょいと多忙でトップページ更新が滞っていたが、一気に挽回である。
(何をだ?)
とっくに梅雨明けした沖縄に夏を求めて逃避行である。本部(もとぶ)半島は那覇から90キロ弱、北部の大きなこぶのような半島だ。那覇からの距離は京都-須磨間に匹敵する。(ちゅうても関西じゃなきゃわからんか)須磨ってのは三ノ宮の3駅西寄りでして・・・。えい、東京-箱根湯本間と同じようなもんじゃい。 |
|
2006.07.30
美ら海水族館(沖縄) 7/20・21の沖縄行の画像である。 7/20・21の沖縄行の画像である。
「美ら海」と書いて、「ちゅらうみ」と読む。高さ8.2メートル、幅22.5メートルの大水槽のアクリルパネルは世界一の厚さ60センチ(すごいのか?)
複数のジンベエザメの飼育は世界初。マンタの群れもここでしか見られない。アクアリウムマニア垂涎の水族館である。言うまでもないことだが、筆者はマニアではない。
沖縄県、本部半島の海洋博覧会記念公園内に、この水族館はある。 |
|
2006.08.05
湯布院 久しぶりのご当地当てクイズ「ここは何処でしょう?」 久しぶりのご当地当てクイズ「ここは何処でしょう?」
答えは湯布院(大分県)
駅前に聳える秀峯「由布岳」の標高は1584メートル。
その日、頂は雲間に隠れること多く、その全容をなかなか現さない。画像はJR湯布院駅の駅頭からのもの。金鱗湖までのびる町内唯一のメインストリートの先に雲間に隠れる由布岳がそびえている。アルプスの街にあるような錯覚さえ覚えさせる一瞬。 |
|
2006.08.05
湯布院 JR観光特急「ゆふいんの森1号」 JR観光特急「ゆふいんの森1号」
ヨーロピアンテイストの車体、車両連結部はデッキとして渡り廊下が張られ、客席の位置が通常車両よりも高い。車窓を愉しむための設計である。
筆者は、無論マニアではないので、偶然、この列車に乗ったのだが、帰路は、やはり偶然、「ゆふデラックス」という車両に乗車。どんな車両かは、上の画像にマウスポインターをあてていただければおわかりいただけるが、こちらは、運転席が2階にあり、スーパーシートでかぶりつき車窓が楽しめる。マニアではないが、偶然、この最前列のシートに座った筆者であった。 |
|
2006.08.05
九州の特急 鉄道マニアの方へのサービスショットである。無論、筆者は違う。 鉄道マニアの方へのサービスショットである。無論、筆者は違う。
特急のフォルムの多彩さで突出するJR九州。九州にマニアが多い一因はそこにあると筆者は睨んでいる。
画像左上から右に、「ソニック(博多-大分方面)」「ハウステンボス(博多-ハウステンボス)」「きりしま(鹿児島中央-宮崎)」2段目左から「みどり(博多-佐世保)」「ゆふデラックス(博多-湯布院・別府)」「かもめ(博多-長崎)」3段目左から「ゆふいんの森(博多-湯布院」「リレーつばめ(博多・門司港・小倉-新八代)」「九州新幹線つばめ(新八代-鹿児島中央)」 |
|
2006.08.17
那智の滝
133メートルの高さから落下する飛瀑は日光華厳の滝を凌駕する。
滝そのものがご神体である。
「那智の滝」は和歌山県にある。
直撃は免れたものの西方に進路をずらした台風が巻き込むように引き起こす東側の雲の流れが紀伊半島南部に雨をもたらした。
滝壷から舞い上がる水煙とたっぷりと雨滴を孕んだ水蒸気が一枚岩の頭頂部や周囲の樹林を白く包み込む。まさに水墨画の景色である。 |
|
2006.08.26
高度2万6千フィートの雲海 遠く九州に上陸した台風の影響は東北地方にまで及んでいる。 遠く九州に上陸した台風の影響は東北地方にまで及んでいる。
台風の渦の外延部から押し出された雲の群れが列島の各所を覆っている
名古屋上空は、厚い雲に覆われていた。陽光を受けて輝く雲の峯
高層にたなびく雲と低層の雲海の間を飛ぶ機上からの画像。
「ジェットストリーム」の世界である。
故、城達也氏の声が聞こえないか? |
|
2006.08.26
富士山 ロールオーバーの画像 ロールオーバーの画像
雲海の上を飛ぶジェットは静岡上空で雲の切れ間に遭遇した。
内陸部を飛ぶ航路右手に雲を突き抜けて孤峰が浮かんでいる。
富士山のシルエットである。
海岸線を飛ぶ西行き航路ならば、もっと近くを飛ぶので、山容が明確にとらえられるのだが、それでも、これはこれで美しいではないか。
|
|
2006.09.01
夏への扉(沖縄) 去り行く夏への追想の1枚にこれ 去り行く夏への追想の1枚にこれ
7月中旬の沖縄行の写真
今年の夏はこれで決まり
久しぶりに夏を満喫したような気がする。夏休みが始まる前に一度消費したのがよかったのかもしれない。
夏を2度愉しんだような感じだ。
夏の消費パターンは今後、この手でゆくことにしよう。逃避地をひとつ手に入れた筆者であった |
|
2006.09.01
夏への扉(沖縄) ロールオーバーの画像 ロールオーバーの画像
沖縄、海洋博公園内のエメラルドビーチの1枚。
「夏!」
まさにそんな情景である。
そんな夏も行ってしまう。
また来年、会おうね。 |
|
2006.09.03
松島 宮城県、松島湾。仙台、石巻を結ぶ仙石線の途中駅「松島海岸駅」まで約40分。駅から松島までは徒歩ですぐ。沿道には浜焼きの店が建ち並び、縁日のような賑わいである。観光遊覧船で湾内をクルーズする。餌を求めてかもめが寄ってきた。 宮城県、松島湾。仙台、石巻を結ぶ仙石線の途中駅「松島海岸駅」まで約40分。駅から松島までは徒歩ですぐ。沿道には浜焼きの店が建ち並び、縁日のような賑わいである。観光遊覧船で湾内をクルーズする。餌を求めてかもめが寄ってきた。
|
|
2006.09.09
平泉 8月中旬の奥州、平泉。 8月中旬の奥州、平泉。
岩手県の南端、宮城県との県境近くに中尊寺はある。
奥州藤原氏4代の栄耀栄華を偲ばせる広大な中尊寺の境内。
最盛期には堂塔40僧坊300を越えたと言われる。 |
|
2006.09.09
平泉 ロールオーバーの画。 ロールオーバーの画。
中尊寺金色堂。
金色堂の紹介写真は、この角度から撮影されたものが多い。写真の下に「中尊寺金色堂」のキャプションがつく。これが不十分なものだと誤解が生じる。誤解の当事者は筆者だ。
筆者は、この時まで大きな勘違いをしていたのだ。その詳細は「紀行」で。 |
|
2006.09.23
玉置山 奈良県十津川の玉置山。 奈良県十津川の玉置山。
標高は1076m。
撮影は8月16日。雨か霞かはたまた霧か。山頂に近づくと不意に白い混沌に包まれた。道はガードレールもない断崖を縫うように走る。目の前のもやがなければどのような眺望が広がるのだろうか。駐車場に車を置き、玉置神社への道を静かに歩く。 |
|
2006.09.23
玉置神社 ロールオーバーの画。 ロールオーバーの画。
玉置山の玉置神社。
熊野三山の奥の院の社は、途中、修験道が分岐する高い杉木立に囲まれた参道の先に静かに佇んでいた。
折悪しく降り始めた雨にうたれ、なんとも情緒豊かな表情を見せる。
濡れそぼったその姿のほうが好天のもとよりも良かったかもしれない。 |
|
2006.10.02
諏訪大社 諏訪大社、下社秋宮の神楽殿 諏訪大社、下社秋宮の神楽殿
青銅製では日本一と言われる狛犬が見事である。
社はこの神楽殿の裏にある。
さらにその後背には御柱が4本四囲に建立されている。
古格な風情はなかなかのもの
さすがは日本最古の神社のひとつである。 |
|
2006.10.29
天徳院(金沢) 半年ぶりの金沢だ。グリルNew狸で「ヤキメシ」と「能登牛のヒレカツ」を堪能。腹ごなしの帰り道(小立野2丁目から香林坊まではそこそこの距離なのだ)元和9年(1623年)創建の天徳院に立ち寄る。 半年ぶりの金沢だ。グリルNew狸で「ヤキメシ」と「能登牛のヒレカツ」を堪能。腹ごなしの帰り道(小立野2丁目から香林坊まではそこそこの距離なのだ)元和9年(1623年)創建の天徳院に立ち寄る。
三門脇に挽きたて、打ちたて、茹でたての「三たて」蕎麦家、小立庵(しょうりゅうあん)がある。
|
|
2006.10.29
夕景(金沢) ロールオーバーの画像に金沢の夕景を。北国新聞の本社ビルのむこうにホテル日航金沢のシルエットが浮かぶ。さらにそのむこうには日本海。 ロールオーバーの画像に金沢の夕景を。北国新聞の本社ビルのむこうにホテル日航金沢のシルエットが浮かぶ。さらにそのむこうには日本海。
10月最後の土曜日、北陸は目が覚めるような青空が広がっていた。
筆者の入沢時に青空が広がるのはめずらしい。やはり、食い物の旨い冬場に行くことが多いからか。 |
|
2006.11.17
屋島(香川) 香川県、屋島からの眺め。あおむけになった人の横顔のようなシルエットが五剣山。そのふもとの平地部が屋島の古戦場である。敵後背からの奇襲攻撃が必勝パターンの義経は画像右の方角から攻め込んだ。海は左手に広がっている。 香川県、屋島からの眺め。あおむけになった人の横顔のようなシルエットが五剣山。そのふもとの平地部が屋島の古戦場である。敵後背からの奇襲攻撃が必勝パターンの義経は画像右の方角から攻め込んだ。海は左手に広がっている。 |
|
2006.11.17
屋島(香川) ロールオーバーの画像。 ロールオーバーの画像。
屋島城蹟から瀬戸内海を望む。
屋島はギニア高地のようにフラットな高台状の地勢である。
高松港を画像の左手方向遥かに望み(画面には現れないが)、瀬戸内の穏やかな景色が広がる |
|
2006.11.22
呉 呉。「ご」ではない。「くれ」である。 呉。「ご」ではない。「くれ」である。
念のため。
広島県呉市。広島からJR呉線で45分強。快速ならばもう少し早い。
昔、ここに海軍呉鎮守府があった。海のむこうに海軍兵学校のあった江田島も浮かんでいる。 |
|
2006.11.22
呉 かつての呉海軍鎮守府は海上自衛隊呉地方総監部に引き継がれた。 かつての呉海軍鎮守府は海上自衛隊呉地方総監部に引き継がれた。
ちょっと規模が小さいし、所属艦艇も停泊していなかった。
やむをえん。呉と言えば、戦艦大和を建造した呉工廠のあったところ。今、大和ミュージアムと呼ばれる呉海事歴史科学館には十分の一サイズの大和が浮かんでいるのである。 |
|
2006.12.13
北アルプス 海流と気流の類似性を視認。 海流と気流の類似性を視認。
北アルプスの高峰が日本全土を覆っている雲を突き破って聳え立つ。
堤を越えて溢れ出る濁流のように峰の谷間を埋める雲。しかし、中央の尾根に遮られ、そのむこうの谷には入り込めない。まさに気象が液体の流動と同様の様態を示す好例である。夕陽に耀く北アルプスもきれい。
|
|
|
|
|
|
| 戻る →→ Back |
|
|