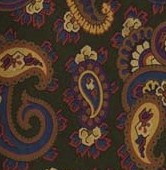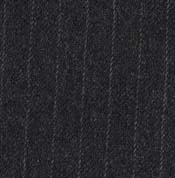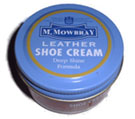靴◆
Shoes →→→back |
| プレイン・キャップ・トゥ |
 |
甲の部分に横一直線のラインが入っているのはストレートチップと同じだが、このラインに小さな円形の模様が入っている。
クラシックなスタイルにも通用する。
オンビジネスにイチオシ。
(YANKO) |
| ストレートチップ |
 |
甲の部分に横一直線のライン(切り替え線)が入っている。
最もクラシックなスタイル。
オンビジネスでもパーティでも通用。
(LOAK) |
| ウイングチップ |
 |
翼のような飾り革と甲の部分に水はけ用のメダリオン(丸い穴)がついている。
メダリオンの数は150程度。アメリカの方がイギリスのものよりメダリオンの数が多い。
クラシックの範疇ではあるがややスポーティなため、スリーピースなどにはあまりそぐわない。
ブリティッシュスタイルに起源がある。
(SCOTCH GRAIN) |
| Uチップ |
 |
爪先にU字のアッパーがついたタイプ。
ややカジュアルな雰囲気。スリーピースなどにあわせるのは本来不似合い。
トゥの切り替え部(モカ縫い部)に立て線が入っているタイプと入っていないタイプがある。
このモカ縫い部が立っているほうがカジュアル度が高く、寝ている(爪先から遠い)方がオンビジネスには向く
(LOAK) |
| プレイントゥ |
 |
甲の部分に飾りが何も無い紐靴。
クラシックの範疇。
ややシンプルすぎるきらいがある。
黒のプレーントゥは堅苦しいイメージを醸し出す。濃い茶にするとややドレッシーになる。
画像の靴はワインレッドの色味がかっている
革はコードバン(馬の尻の皮をなめしたもの)
(JOHNSTON&MURPHY) |
| モンクストラップ |
 |
紐無の靴の中では唯一クラシックの範疇に入る。
修道僧の靴が起源。
甲を巻き込むようにに太めのベルトとそれを留めるサイドの留め具によって成り立つ。
オンビジネスでも通用。
トゥはプレーンなタイプが多い。
画像のデザインはモンクストラップとしては珍しい
(YANKO) |
| タッセル・スリップオン |
 |
甲部にふたつの飾り房がついている。
カジュアル色の強い靴。
オンビジネスとしてはドレスコードのうるさい職場では茶のタッセルは難しかろう。
足元に視線を集めやすいのでコーディネイトに注意する。
(YANKO)
|
| ローファー |
 |
ローファーとは怠け者の意。
アメリカンインディアンの履いていたモカシンに起源をもつ。
カジュアル色の強い靴。はだしもOKなどと言われている。
つま先(バンプ)部分の長さにより靴のイメージがかなり変わる。甲にわたされたストラップ部の穴にアイビーリーガがコインをはさんだのでペニーローファー、コインローファーなどと呼ばれる。ローファーは靴下の露出度が高いので着こなしに注意。
(JOHNSTON&MURPHY) |
| スリップオン |
 |
 アメリカの靴メーカー「コールハーン」はローファー専門のイメージが強かった。 アメリカの靴メーカー「コールハーン」はローファー専門のイメージが強かった。
いつの間にか、ナイキに買収されていたらしい。
エアエッジのようなローファーっぽいスリップオンシューズだ。
「なんか、格好いいでないかい?」 というだけで購入した筆者にしては珍しい物欲起動物件。ソウル部がいかにもナイキしている。ちゃんとエアエッジ仕様だしね。
(COLEHANN) |
衿◆
Collar →→→back |
| ワイドスプレッド |
 |
ウィンザー公爵考案のウィンザーノットでネクタイを結ぶと、レギュラーカラーでは結び目が大きすぎる。このためカラーの角度を広くしたシャツをウィンザー公が考案し、これをウィンザーカラーと呼ぶ。ワイドスプレッドカラーの原型である。ダブルノットもOK。 |
| セミワイドスプレッド |
 |
衿の開きがワイドスプレッドとレギュラーの中間。
タイはダブルノットか、ウインザーノットで。 |
| レギュラー |
 |
一番ポピュラーで標準的なカラースタイル。
メーカーあるいは仕立ての好みによってカラーの長さなどに差が現れる。
衿高もワイドスプレッドより低く猪首の多い日本人に向いている。タイはダブルノットかセミウインザーノットで。 |
| ボタンダウン |
 |
BDシャツなどと標記されるカジュアルなシャツ。
着こなしのサンプルとしてケネディ大統領がひきあいに出されることがあるが、プライベートシーン以外で彼がBDシャツをオフィシャルシーンで身に付けたことはないはず。タイはプレーンノットで。 |
| ラウンド |
 |
丸みを持たせた衿先 |
| クレリック |
 |
袖先とカラー部分が白無地。
クラシックでドレッシーなイメージ。 |
| ピンホール |
 |
左右の衿先を1本のピンで繋いで留めるカラータイプ。 |
| タブ |
 |
左右の衿下から留め具が繋がっているカラータイプ。 |
| ウイング |
 |
フォーマルの範疇。
前立ては比翼仕立てで、ボタンが見えない。
胸部の布は厚め。イカ胸とヒダ胸の2種がある。
布を厚くしただけのシンプルなイカ胸に対し、胸奥にたたみこむようにヒダ状の構造のヒダ胸はややカジュアル寄り。
タイは蝶でも棒でも対応できる。ネクタイが首から逃げてしまわないよう、ベルト通しのようなタイ通しがある。 |
ネクタイ◆
Necktie →→→back |
| ソリッド |
 |
無地。
ソリッドに始まり、ソリッドに終わると言われる。
生地の模様により、表情を出すものもある。 |
| ドット |
 |
水玉。
一番小さいのがピンドット、ポルカドット、コインドットと大きくなってゆく。
ドットは正円で対象形で配置されているものがクラシック
|
| クレスト |
|
家紋・紋章 |
| フラード |
 |
小紋 |
| ストライプ |
 |
 |
右上がりが英国式。右下がりが米国式 |
| レジメンタル |
 |
ストライプの一種。
英国連隊旗に由来する。
色・幅などに厳密な規格を適用する極めて集団帰属性の高い柄。公の席では絞めないほうが無難。 |
| ペイズリー |
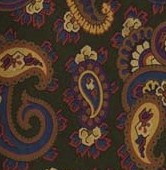 |
羊歯のような渦巻き模様。
英国のペイズリー地方に由来する古典柄 |
| ロイヤルクレスト |
 |
スコットランドの伝統的紋章をあしらったものがクレスト
トラディッショナルな装いには不可欠な柄
このクレストとストライプの組み合わせも重厚
レジメンタルの間にクレストが入って
ロイヤルレジメンタルもあり
|
| オールオーバー |
 |
全面に同一パターンのプリント柄を配置 |
結び◆
Knot →→→back |
| ダブル |
|
樽のような太長の結び目となる大剣を二巻きして作る。
クラシックなスタイルに似合う。
生地・タイのスタイルによりトリプルに巻くことも。 |
| ウインザー |
|
ウィンザー公爵考案のワイドスプレッドに似合う逆三角形のような太結び。ディンプルがきれいに出る。
生地の厚いタイでこの結び方にすると日本人には不釣合いな大きさになってしまうから注意を要する。 |
| セミウインザー |
|
エスカイアーノットとも。プレーンとウィンザーの中間 |
| プレイン |
|
シングルノットとも。一番細身の結び目。
アメリカントラッド。ボタンダウンに合うとされる |
柄◆
Pattern →→→back |
| チョークストライプ |
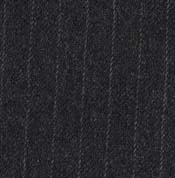 |
黒・紺地などに白いチョークを引いたような縦縞(しま)が特徴。
ストライプ幅は1.5センチ程度。
クラシックスーツに最適の柄。嫌味の無い落ち着いたイメージ。 |
| ペンシルストライプ |
 |
鉛筆で引いたようなイメージの縞模様。
チョークストライプとの違いは縞糸の太さによる。
チョークストライプよりも縞の主張が強くなる。 |
| ヘアラインストライプ |
|
毛髪のように細い縞模様。離れると無地に見える |
| オルタネイトストライプ |
|
2種類の縞が交互に並んだ模様 |
| キャンディストライプ |
|
縞糸がほぼ水平に近く、縞と地の面積がイーブン |
| タッターソール |
 |
白地に赤と黒・黄と茶などの2色の細い格子 |
| ヘリンボーン |
 |
和名は杉綾。ニシンの骨という意味。
ヘリンボーンにストライプが入れると、ヘリンボーンストライプとなる。
グレイまたは茶系で揃えておくのが基本。 |
| ハウンドトゥース |
 |
和名は千鳥格子。
犬の牙のような尖った模様が並ぶ。白黒または白茶の配色が基本。
トラウザー(ズボン)にこの柄をそろえておくと、ジャケットとの着まわしに幅が出る。 |
| グレンチェック |
 |
大柄の大小の格子をまとめた図柄。
チェックは本来カントリー仕様だが、オンビジネスにも通用する夏冬を問わずオールシーズンむけの古典的な柄。 |
| ピンチェック |
 |
横糸に白または色糸、縦糸に色糸を使う極細の平織格子柄ほとんど無地に近い上品な柄。 |
| ギンガムチェック |
 |
平織の格子柄。白地と青、赤、黒など単純な格子。 |
| タータンチェック |
 |
スコットランドのハイランド地方に源流を持つ古典的格子柄。家ごとに名前のついた柄を使用(例えば、靴下に多いアーガイルはアーガイル伯爵に由来するタータンチェックの一種)家格が高いほど多くの色を使用。
ブラック・ウォッチ(青地に緑と黒のタータンチェック)などは紺ブレに合わせるトラウザーとしては最適(紺ブレにはグレイのトラウザーが基本だが・・・) |
スーツ◆
Suit →→→back |
| シングル |
2ッ釦・3ッ釦・3ッ釦中掛 |
| ツーピース・スリーピース |
| ベスト |
5ッ釦・6ッ釦 |
| 2ッポケット・4ッポケット |
| ラペル有・ラペル無 |
| 尾錠付・尾錠無 |
上衣を脱いだときにシャツ姿になる非礼を避けるためにイギリスで考案された。
ベストの一番下の釦は外す。
筆者は5ッ釦、3ッポケットが多い |
| ダブル |
6ッ釦2ッ掛・6ッ釦1ッ掛・4ッ釦2ッ掛・4ッ釦1ッ掛 |
| フランスは6ッ釦、イギリスは4ッ釦が多い。6ッの方がクラシックイメージが強い |
| パターン |
反身・屈身・下り肩・怒り肩・ツキ取 |
身体的特徴を把握してスーツを作ろう
ショルダーラインが怒っているのがラテン式、なで肩が米国式、その中間が英国式
ウエストを絞るのは英国式、ストレートは米国式 |
| 衿 |
ノッチ・セミノッチ・セミピーク・ピーク |
| シングルはノッチドラペル、ダブルはピークドラペル |
| ベント |
センター・サイド・ノー |
| ベントは好みで、英国はサイド・米国はセンター・ラテンはノーベントの傾向が多い |
| 裏 |
背抜・総裏 |
| トラウザー |
ベルト |
ベルトレス・ループ付・持出しループ付 |
| タック |
無・1本・2本 |
| 裾 |
シングル・ダブル |
| フォーマルはシングル。傾向としてダブルがクラシカルに |
| ポケット |
斜め・立て |
| 前立 |
チャック・釦 |
コート◆
Coat →→→back |
| チェスターフィールド |
 |
チェスターフィールド6世愛用のコート。
スーツの上衣を伸ばしたイメージ。着丈は膝下程度。
ノッチドラペルで、上衿は黒のベルベット地、前合わせは比翼仕立て(ボタンを隠す仕立て)が最もクラッシー |
| ポロコート |
|
スポーツ観戦用のコート。クラシックなチェスターフィールドをややカジュアルにしたイメージ、したがって現代のチェスターフィールドはこのポロコートと同様のイメージ。 |
| ステンカラー |
|
正式名称はバルカラー。第1ボタンを絞めてもあけても良い衿型のこと。衿先のボタンを閉めると衿を立てることができる。
ラグランスリーブでオーソドックス。 |
| トレンチ |
|
第一次大戦時、英国陸軍が開発。多くのベルトは手榴弾をつるしたり(Dリング)、銃や双眼鏡を掛けたり(エポーレット=肩章)するのに考案され、長い塹壕戦に耐えられるよう8ッボタンのWブレスト(左右どちらからでも留められる)や肩生地を2枚にしたり袖口にカフストラップ(袖ベルト)を設けたりと防水に配慮が施されている。 |
| ダッフル |
|
ベルギーのダッフルという地名に由来する北欧の漁民が愛用していたコートの総称。英国海軍に採用された。
モントゴメリー元帥がダンケルクの撤退時に漁民から贈られ、タートルネックのセーターの上にそれを羽織った彼のスタイルはつとに有名。彼のコートは淡い褐色だったが、英国海軍は濃紺。これが戦後放出され一般に普及した。 |
正装◆
Formal →→→back |
| モーニング |
|
夕刻までの正装 |
| テイルスーツ |
|
夕刻以降の正装。和名燕尾服 |
| ディレクターズスーツ |
|
夕刻までのモーニングの準礼装 |
| タキシード |
|
夕刻以降の燕尾服の準礼装 |
| ダークスーツ |
|
カジュアル性の強い略礼装 |
| ブレザー |
|
カジュアル性の強い略礼装 |
| ブラックスーツ |
|
ジャパンローカルのオールマイティな冠婚葬祭用和製洋装 |
小物◆
Accessory →→→back |
| 時計 |
|
|
| 鞄 |
|
|
| 手袋 |
|
|
| ベルト |
|
サスペンダー(米国←→英国)ブレイシズ・バックル |
| 財布 |
|
|
| ポケットチーフ |
|
スリーピーク・トライアングラー・TVフォールド・パフ・クラッシュ |
| カフス・ラペルピン |
|
|
| マフラー |
|
|
| 傘 |
|
|
| 筆記具 |
|
|
| 手帳 |
|
|