|
雑木林 春夏秋冬 九谷 六口 数年前まで、東京の練馬には自然があった。 二十一世紀に入り十年近くが経った今、気象上の異変が各地で起 きている。突然の豪雨や竜巻とも思える突風、空梅雨と熱暑。この ような現象は、日本だけでなく地球規模で起こっている。大水や猛 暑がヨーロッパを襲い、地球温暖化は幾つかの国を海に沈めようと している。心配になってくる。確固たる存在であるはずの地球が、 どこか変調をきたしているのではないか。 あるテレビ番組で科学者が語っていた。 「地球の寿命は約百億年です。現在、地球の年齢は、四十数億歳。 あと五十数億年で太陽に飲み込まれます」 なるほど、地球にも寿命があるのか。地球も悠久なる宇宙の中で 命を育む一つの生き物でしかないのだ。そう思うと、何やら愛おし さのようなものを感じてくる。そして、地球上に生きる数多なる生 物に対しても…… 人間も彼らの仲間だ。確かに仲間ではあることに変わりはないの だが、ちょっと他の生物とは異なる部分がある。知恵を発達させ、 技術なるものを発展させたのだ。これは素晴らしいことなのだが、 人間の独り善がりが過ぎているとも言える。快適な生活を送りたいとの 欲求。これを満たすためだけに知恵や技術が使われているのでは…… 異常気象を見ていると、地球は病んでいるのではないかと心配に なってくる。人間は森林を伐採し、焼き払ったが、これは地球にと っては火傷である。コンクリートで覆った。これでは息苦しくなる |
(1)
|
に決まっている。便利な化学製品を生み出し、使い、川や海に捨て
た。皮膚病の原因である。地球の内部から掘り出したエネルギー源 を惜しげもなく燃やし、動力とした。炭酸ガスに覆われた地球は、 着膨れ状態になり、体が火照ってしまうのは当たり前である。 このような状態で、地球は、寿命を真っ当できるのだろうか。心 配になるが、多分、病身のまま五十数億年を生き抜くだろう。問題 は、地球上の生き物たちである。このまま地球の病状が進めば、百 年後、千年後…… いや、何年後かは判らないが、確実に生きるた めに必要な環境はなくなっていくだろう。ノアの箱舟ではないが、 何処かの星を見つけ、移住でもしなければ死に絶えるに決まってい る。 どうも憂鬱になってくる。私はコンクリートの建物の中で、寒け れば暖房を、暑ければ冷房を利かせ快適な毎日を送っている。地球 が病んでいるとすれば、私も病状を悪化させた一人かもしれない。 良いではないか、自分が生きている間は、それほど酷くはならない だろう。それに、ちっぽけな自分が地球を救うことなどできっこな い。気になるのであれば、暖房や冷房を控えめにすれば良い。私が 遣れたとしても、精々これくらいが関の山だ。 私は、五十数年前から東京の練馬に住んでいる。 此処には素敵な自然があった。だが、自然と呼べる環境は二十数年前に終っている。宅地化などにより田圃、畑、野原は埋め立てられ、そして雑木林は切り倒された。いや待て、私が練馬に来た時点で、既に宅地化が始まっていたのだ。やはり私も自然破壊の共犯者なのだ。壊された自然を元に戻すことは不可能に近い。死んでしまった土を回復させることは至難の技だ。 日本には、まだ自然が残っている。地球規模での自然破壊を憂う |
(2)
|
ことも大切なことだが、今、残っている自然に目を向け、大切に守り、共存を考えることくらいはできるのではないだろうか。
自然との触れ合いは人間の心を豊かにしてくれる。特に子供たちにとって大事なことだ。机に向かい、一所懸命勉強することも大切なことかもしれない。夜遅くまでテレビゲームを楽しむことも否定はしない。しかし、自然の中には、思いもよらない感動が待っていてくれる。それに生き物を慈しむ心を養える。 子供の頃、実家の前には武蔵野の雑木林があり、季節の移り変わ りを知る事ができた。四季折々に姿を変える雑木林は、その時々の贈り物を子供たちに与えてくれた。 私も、数多くの想い出を持つことができた。 春  最近は温暖化のせいであろうか、東京の雪は少なくなった。当時は冬になればきちんと雪が降り、春にはきちんと雪が解け、草花の芽吹きを見ることができた。 私が好きだったのは、早春の風景。 白い雪に覆われていた雑木林の所々に、ポッカリと穴が開き始める。その穴から楢、くぬぎ、栗、杉、薄などの濡れた枯葉や落ち葉が見え出す。気の早い草花は、そんな穴の中で緑の芽を出しだす。さー、そろそろ起きなくちゃ。そんな雰囲気であった。そして、暖かい陽の光が、一つ二つと穴の数を増やしていき、茶色や黒の世界 |
(3)
|
が広がっていく。
雑木林には、こんもりと丸い、お供え餅のような雪が点々と残り、春が進むにつれて一つ一つが姿を消していく。陽が当たらないところでは、大きな雪の塊が結構長い間残り、冬があったことを教えてくれる。そして、木々の芽吹きは、そこいらじゅうに春が来たことを告げる。 この頃になると雑木林で気に入った草花の芽を捜し、掘り起こして自分の庭に植えるのが子供たちの楽しみだった。特に、紡錘形の山百合の芽を見つけた時は、有頂天である。何本も見つけ、あの独特の香りのある大きな花が咲くのを待ったものだ。山百合は、百合の王様、王女様である。 幾重にも重なり、濡れていた落ち葉は乾いていき、それとともにふっくらと厚みをもってくる。薄茶色に乾いた落ち葉の絨毯の上に寝転び、暖かい陽の光を浴びるのが私は大好きだった。落ち葉の匂いは、乾いた土の匂い。周りは黄緑色の芽や若葉。 雑木林の前に広がる畑では、寒い冬に麦踏された麦たちが姿勢良くまっすぐに伸びている。梅の花に続き、そろそろ桜が芽吹く季節。 早春から春へ。雑木林の木々は、スッカリ緑色になる。今度は、緑の葉っぱと黒と茶色の幹の世界。そんな中に、薄いピンク色の染井吉野が控えめに花をポツリポツリと付けはじめる。暖かな日、一気に染井吉野は、華やか姿に変身する。待ちに待った季節だ。桜は誇らしげに咲き誇る。そして、少し遅れて山桜が、緑色のしっかりとした葉っぱを見せはじめる。 |
(4)
|
冬の風の音はヒューヒューと聞こえるが、この季節になるとサワサワ、ザワザワと聞こえる。うっそうと茂った木々の葉っぱが擦れる音だ。雑木林を草が覆い、地面は緑一色になる。そして人が歩く細い道だけが土の色である。
この頃になると雑木林の中に入るのは大変である。薄や笹の葉で腕などに傷をつけてしまうのだ。しかも、薄たちは子供の背丈を越えている。気を付けながら林に入り込み、秘密の場所を作る。道からちょっとしか離れていない所でも、周りからは見えない。まだ残る枯れ葉などを集め、小さな丸い場所を作る。そこに寝転ろぶと、見えるのは薄や笹の葉、そして空だけである。そんな中でちょっと気取って本を読んだりする。だが、本を読むのが目的ではない。誰も知らない秘密の場所で何かを遣っている事が楽しいのだ。自分だけの世界だ。 杉の木は格好の展望台だった。テッペンまで登って周りを見渡す。雑木林しか見えない。杉のテッペンも自分一人だけの世界だ。風が吹くと杉の木は揺れる。自分も一緒になって杉の木を揺らす。大きく大きく揺れ出す杉はブランコの逆である。杉の木は強く、いくら揺らしても撓うだけで、折れることはない。空気の中を大きく動いているのは自分だけではないか。そんな錯覚すら感じさせてくれた杉の木。 不思議なものだが、今は高い所から撮った映像などを見ているだけで足がすくんでしまう。高所恐怖症ではないかと思ってしまうのに、子供の頃はこんな遊びをしていた。 雑木林の話から、ちょっと脇道に…… 高い所というと思い出すことがある。小学校の高学年の頃だったと思うが、実家から一キロほど離れたところに高圧線が通ることになった。 |
(5)
|
畑に鉄塔が建設される。空に伸びて行く鉄塔を見るのが楽しみだった。鉄塔が完成した。高さは二十数メートルあったと思う。当時は、建設中であっても囲いなどはなかった。大らかな時代である。夕暮れ時、もうすぐ電線が渡たされるのかと鉄塔を見上げていた。周りには誰もいない。ふと登ってみたくなった。
四角錐の稜線には、きちんと長い鋲が打ってあるので、簡単に登ることができる。難なく鉄塔のテッペンに着いた。素晴らしい景色だった。家々の灯り、少し離れたところにある大通りに流れる車のライト。風は、ほとんどなかった。 何か記念になるものを残したい。私は、ポケットからハンカチを出しテッペンに結びつけた。工事の人が、このハンカチを見てどう思うだろうか。それを思うと愉快だった。だが、まだ納得できなかった。こんな経験は滅多にない。面白い事を思いついた。 こんなところで小便をした人間などいないはずだ。意気揚々と小便をした。実に気持ちが良かったことを覚えている。さて、降りよう。下りも何ら問題はなかった。だが、手が濡れてくる。雨は降っていないのに、良く見ると所々に水が付いている。その時、自分の愚かさを知った。それは、自分の小便だった。 雑木林は、チャンバラごっこにも最適な場所だった。敵味方に分かれ、枯れ枝を刀代りにチャンチャンバラバラ。何ちゃんが本気で切ったと泣き出したり、刀を放り出し取っ組み合いの喧嘩をしたり……。そして、敵味方が、互いに秘密の陣地を作り、先に見つけた方が勝ちになる遊びをした。 この遊びは大変である。仲間同士の誓いがあるのだ。相手に捕らえられても場所を教えないとの誓い。相手を捕らえ白状させるが、乱暴はしない。 当時の子供たちは痛みを知っていた。木に登り落っこちた時の痛 |
(6)
|
み、前を歩く仲間が木の枝を掻き分けたのは良いが、それが跳ね返 り頬にパチンと当たった時の痛み、転んで擦りむいた時の痛み……
皆、遊びの中で痛みを経験している。相手が痛がることは決してしない。偵察隊を出し相手の陣地を捜す。薄で血だらけになりながら捜す。でも、その時は痛くはない。風呂に入った時に痛みを思い出すだけだった。 ガキ大将が必ずいた。その日の遊びを計画し、何人かの仲間を引き連れ指揮をとった。あの当時、いじめっ子は仲間には入れてもらえなかったように思う。仲間に入りたかったのだろうが、いつも孤立していた。ガキ大将は、いじめっ子から仲間を守らなければならない。大抵の場合、年上で体力あるものがガキ大将を勤めた。 春は入学式があり、そして新学期の季節。ガキ大将が抜けていったり仲間が抜けていったり、新しい仲間が入ってきたり…… 私の通った小学校は、古かったが大きく立派な校舎であった。校庭には大きな桜の木があった。この桜は、一つの根から三本の大きな幹が出ていた。三本桜。見事な、そして、本当に立派な三本桜であった。 入学式に合わせたかのように満開になる。この三本桜が小学校のシンボルだった。 小学校の五年生を迎えた時、この小学校は三つに分割された。生徒数が増えたためだ。私たちは団塊の世代と呼ばれている。うろ覚えだが、引越しの時は、地面がぬかるんでいたように思う。新たな小学校に移る時、先生や生徒全員が、手で持ち運べる物を携えて列を成し行進した。 前の小学校は、私の実家から徒歩で三十分は掛かったが、新しい小学校までは歩いて十分ほどの距離。私は、通学が楽になると喜んだが、通学時の思いは、掛かる時間には関係がなかったようだ。私の生活サイクルには、全く変化がなかったように思う。 私は、この小学校の第二回卒業生。何となく第一回の方が、格好 |
(7)
|
が良いのにと考えたことがあった。
我々が去った校舎には中学校が移ってきた。それまでの校舎が狭くなったためだと思う。校舎、校庭、そして三本桜は中学校になった。そして私は、その中学校に入った。小学校の入学も、そして中学校の入学も、同じ三本桜が迎えてくれた。 中学三年生の時、私は入学式で生徒代表として新入生を迎える言葉を話すことになった。別に心配はしなかった。先生が原稿をくれるものと思っていたからだ。だが、入学式が近付いてきたのに先生からは何の話もない。おかしい。先生に聞いてみた。 「先生、入学式で話す原稿は、まだですか」 「何言ってるの。自分で考えなさい」 その時、かなり困ったことを覚えている。だが、ピンと閃いた。私は、三本桜を主人公に迎える言葉をまとめた。その時の原稿は今も何処かにしまってあるはずだ。時の流れを変える事はできない。 その懐かしい三本桜は、今はない。そして、その場所には順天堂大學練馬病院が建っている。 話の順番が逆になってしまったが、私は幼稚園にも通った。長命寺幼稚園。この幼稚園は現在はないが、三本桜がある校舎の隣にあ った。当時は、送迎バスなどない。私だけでなく近所の子供たちも皆、五十分掛けて歩いたものである。幼稚園児の頃から小学校の四年生まで徒歩で通ったことになる。今、考えると良くも通ったものだと感心する。中学に入ると自転車通学が許される。幼い子供が一時間近くも歩き、中学生が自転車。安全を考えればこうなるのかも知れない。 通園、通学路の周辺には、畑、果樹園、野原が広がっていた。道の一ヶ所に、お茶の木畑が続いていた。白い花びら、黄色い雄しべ や雌しべ。子供心にも綺麗だと思った。 |
(8)
|
幼稚園は、お寺の中。大きな寺だった。恐々、寺の本堂を探索したのを覚えている。お寺の裏も雑木林。幾つもの石像が顔をしかめて座っていた。夕方は、怖くて歩き回る事はできない。今も立派なお寺だが、当時の深遠なたたずまいや、幽霊でも出そうな雰囲気はなくなっている。
道の途中には氷川神社があった。縁日にはいろいろな屋台が所狭 しと出た。夏には、いわゆる田舎芝居の小屋が建てられた。今も思い出す場面がある。舞台では綺麗な着物を着た人たちが、良く判らない言葉で話していた。女の人が自分の子供に饅頭を食べさせる。子供は苦しんで死んだ。何てことをする。舞台は、女の人と死んだ子供だけになる。すると、その女の人は子供を抱きかかえ泣き叫んだ。だったら何であんなことするのか。私は全く理解できず、大きなショックを受けたことを覚えている。今、考えると伽羅先代萩だったと思う。広い境内であったが、大人になり懐かしさで訪れた時、そこは意外と狭く感じた。 道草は園児、生徒の特権だ。乾いた田んぼで蓮華を摘んだり、小 川でおたまじゃくしを取ったりした。今だから言えるが、果樹園に忍び込み、果実を取ったりしたこともある。大抵の場合、口にした果実は、美味しくなかった。何故なのか、今もって判らない。 道草で遊ぶ園児、生徒は、遊びに夢中になるとトイレに行くのを忘れてしまう。当時は、公衆トイレなどはない。でも、心配する事は全くない。急にお腹が痛くなっても、ちょっと草むらに入り込めば、そこは、リッパなトイレに変わる。 桜や草花を眺めながら畑を歩き、芽吹きだした雑木林を抜ければ 実家に辿りつく。雑木林の春。活き活きとしたこれからの時間を、約束してくれるような雰囲気。さー、何かが始まるぞ! |
(9)
|
夏
 雑木林の夏は大変です。ギラギラ照り付ける太陽の下、総てが茹だってしまいます。子供の頃の夏休みは、雑木林があれば遊びは此処だけで充分。草いきれでムンムンする中、半ズボンにランニングシャツ、手ぬぐいを首に巻き、頭には麦藁帽子。ハダシに下駄をつっかけ、虫取り網をかつぎ飛び回る。ミンミン蝉、油蝉、そしてツクツクほうし。けたたましさは凄いもの。たまにクマ蝉でも居ようものなら血相変えて追いかける。薄の葉には、カマキリが釜を持ち上げ、松の木には大きな毛虫。八手の葉っぱには、デンデン虫が角を出す。 キャベツ畑、菜の花畑は、モンシロ蝶の天国だった。黄色と黄緑色に彩られた菜の花畑は、陶酔しそうな花の香りがした。そして、嫌になるほど飛び回るモンシロ蝶。優雅に飛ぶのはアゲハ蝶。同じような格好をしていても蛾は嫌われ者だ。ゾッとするほど大きな蛾が街燈にぶら下がっているのを見ると、この世のものとは思えなかった。 夕立の後には、大きな蝦蟇がノソノソと歩き出す。そう言えば、青大将やヤマカガシも良く見かけた。蛙を飲み込んだ蛇のお腹はプックリと膨れ、蛇は億劫そうにノタノタ動く。子供たちはすぐに捕まえ、尻尾を持って蛙を扱き出す。なんとも残酷な遊びだが、これも子供たちの楽しみだった。中には、尻尾を持って振り回し、女の子がキャアキャア騒ぐのを楽しんでいる悪がきもいた。 残酷なものといえば蛙遊びも同じだ。蛙のお尻の穴にストローを突っ込み、息を吹き込む。すると蛙のお腹が膨れてくるのだ。 |
(10)
|
もっと凄い話を聞いた。煙管に溜まったヤニを、おじいちゃんから貰ってくる。そして、蛙の口に押し込むと蛙はバタバタと暴れだす。そして蛙は大慌てで胃袋を出し、水で洗うという。当時、私はこの話を聞き、本当だろうかと疑った。私は見た事がなかったからだ。だが、最近になりテレビで見たのだ。蛙が胃袋を出し、水で洗う映像を。あの子の話は本当だったのだ。
夏の朝は早起きしなければならない。仲間に宝物を採られてしまうのだ。早朝の露に湿った雑木林は、カブト虫やクワガタの宝庫だった。甘酸っぱい匂いの樹液を出す木には、カブト虫、クワガタ、カナブン、蝶などがへばり付き樹液を吸っている。参加者が多すぎるのだ。何時見ても昆虫たちは、おいしい汁が出る場所を巡って喧嘩をしている。喧嘩の真っ最中に足長蜂もやって来る。さすがにこの時は、子供たちは木から離れ、蜂が居なくなるのを待たなければならない。 皆、秘密の木を持っていた。だが、こればかりは好きな子にも教えられない。朝、雑木林で顔を合わせても、互いにソッポを向きイソイソと行ってしまう。 そう言えば家の中にも虫たちが良く飛び込んできた。カブト虫やクワガタ、カナブン。そして皆に嫌われものの蛾も良く飛び込んできた。蛾を外に出すのが大変である。どう考えてもあの燐粉は、気持悪い。ごく稀に玉虫もやって来た。緑の羽の中に虹のような光を放ち、それはそれは綺麗なものだった。不思議と外で玉虫を捕まえた事はない。大抵家の中だった。タンスに入れておくと着物が貯まるらしい。実家でも何匹か綺麗な玉虫を入れていたが、今はどうなっているのだろう。玉虫…… 今、東京に居るのだろうか。> 小さな虫といえば蟻んこである。一升瓶に土を入れ、蟻を飼う。 |
(11)
|
ガラスに沿って巣穴を作ってくれればしめたもの。蟻たちの生態観察だ。でも夢中になるのは大抵一、二ヶ月の間だけ。観察記録を取ろうと頭には浮かぶものの実行する子供はいない。飽きてしまえば瓶の事すら忘れてしまう。
実家の小さな庭では、春に採ってきた草花が綺麗に咲いた。まるでお花畑のようだった。 父は桃の木や無花果、柿などを庭に植えた。それらは良く育ち、実がなると、もぎって食べたのを覚えている。無花果は、白い粘り気のある樹液を出した。果実は美味しいのに、何故、この様な液を出すのか。私は無花果と聞くと、樹液の気持ち悪さ、葉っぱに生えたチクチクした髭のようなものを思いだす。果実は美味しいのに。 雑木林の前に広がる畑では、スイカやトマト、南瓜、トウモロコシ、瓜などが育っていた。畑の脇には、小さなスイカなどを捨てる場所があった。子供たちは、そのスイカを拾ってきて提灯を作る。中身を穿り出し、皮に目や鼻、口を開ける。中にロウソクを入れれば完成だ。夜、これを竹の棒につるしてロウソクに火をつける。用もないのにこの提灯を持ち、林の中を歩き回った。不思議と真っ暗な夜の雑木林でも恐くはなかった。隅から隅まで知り尽くしていたためだろう。でも、トウモロコシ畑は恐かった。トウモロコシは子供の背丈の倍近くに育っている。夜中に歩くと、何かが飛び出てくるような恐さを感じた。昼間は、あのヒゲを鼻につけて遊んだくせに。でも夜は全く違った。 トウモロコシ畑にまつわる恐いこといえば、子供会でのお化け大会だろう。お兄さん、お姉さんたちが計画し、コンニャクや濡れ雑巾、白い敷布、それに懐中電灯でお化けになる。子供たちは、雑木林の中を決められた道順に沿って歩かなければならない。どこにお |
(12)
|
化けがいるかは判らない。何日だったか、その道順にトウモロコシ畑が組み込まれたことがあった。あの時のトウモロコシ畑は本当に恐かった。
その時、おどかされる方よりも、おどかす方になりたくてイライラしたことがあった。早く大きくなりたかった。だが、私が大きくなった頃、子供会はなくなっていた。 夏の夜に欠かせなかったもの。それは、蚊取り線香に蚊帳。 当時、ちょっとした水溜りには、必ずボウフラが体をピンピン動かしていた。自然界は非常に合理的にできている。蚊の卵は、船のような形で水に浮かんでいる。下水道が、まだ完備していなかった頃、夏に蚊が居るのは常識だった。電気式の蚊取り線香などない時代。緑色の渦巻き型の蚊取り線香は、夏の必需品だった。スーッと立ち昇る独特な香りの煙。この香りは間違いなく夏の記憶である。 だが寝る前は大変だ。蚊帳吊りである。蚊帳も独特な香りを持っていた。吊る前の状態は、緑の海。私は、必ずこの海で水泳ごっこをした。ひとしきり泳いだ後、蚊帳を吊るが、これも大変である。天井の隅にあるフックに蚊帳の四隅と真ん中にある紐を掛けるのだが、順番をきちんとしないと四角く開いてはくれない。蚊帳に入る時は、裾をちょっと持ち上げ、さっと入らなければならない。蚊が一緒に入ってしまっては意味がないからである。 蚊帳の中は、ちょっと異なった世界だった。天気の良い夜であれば、雨戸、ガラス戸を開け放ち、うちわで暑さをしのぎながら蚊帳の中からしばし外を眺める。この様なことが、今、何処かで行なわれているのであろうか。 ヒグラシが鳴き始め、ちらほらとコオロギなどが、羽を擦りあわせ出すと、そろそろ秋の訪れである。 実家は、石神井川の北に位置し、川までは二キロほどの距離だった。その間に谷原の交差点を挟んでいた。今でこそ谷原の交差点や |
(13)
|
環八は交通の要所であり、ひっきりなしに車が行き交っているが、当時は交通量は極端に少なかった。信じられないかもしれないが、夜になると静けさを感じるほどであった。特に、雪の夜などは、深々とした静けさを味わう事ができた。
だが夏の夜は、別ものであった。南風に乗り、蛙の大合唱が聴こえてくるのである。 石神井川は水量も多く、流れも速かった。岸には葦であろうか、水面まで葉が覆い被さっていた。立て札はなかったが、泳いではいけないと聞かされていた。私は、一度だけ川に入った事がある。だが、子供にとり葦などで隠された所は不気味であり、何か得たいの知れないものが潜んでいるように感じた。薄気味悪く、寒気を感じてすぐに川から出たことを覚えている。 その後、石神井川は汚れ、どぶ川のようになってしまった。泳ぐ事ができた川が悪臭漂うどぶ川に変身した。これが世の流れかと寂しい気持ちになったものだ。今でこそ石神井川は、護岸工事により様変わりしたが、一時は酷いものだった。石神井川近辺は、二十年ほど前からであろうか、田んぼはつぶされ宅地に変わった。そして、民家が所狭しと作られていった。 当時の石神井川周辺には雑木林と同じような、全くの自然があった。周辺には田んぼが広がり、何本もの綺麗な小川が流れていた。春の田んぼは蓮華草の薄紫色に埋まった。小川には、鮠、鯉、フナ、クチボソ、タナゴ、おたまじゃくしが泳ぎ回り、ザリガニ、タニシ、ヤゴなどが川底を這っていた。かつて、日本の自然が持っていた水中生物、昆虫、草花などの総てが此処に生息していたように思う。そして、優雅な白鷺が真っ白な羽を広げ群れ飛んでいた。 夏は蛙だらけだった。初夏には、ゼリーのような細長い卵や塊を取ってきた。家で水盤に入れ、おたまじゃくし、そして蛙になるのを楽しんだ。 |
(14)
|
しかし、彼らは知らないうちに何処かに行ってしまった。蛙になった彼らを、石神井川に返したことはない。ひょっとすると何処かで干からびていたのではなかろうか。だが、子供は、そこまでの責任は感じていない。
ある夏の日、友だちが鯰を取りに行こうと誘ってくれた。夜中、ワクワクして彼の家に行った。彼は、口の部分が欠けた土瓶を用意していた。布を口に差し込み中に灯油を入れている。それを竹の棒に吊るし、右手にはモリを持っていた。彼は、ニコッと笑い、準備完了だと言った。真っ暗な田んぼのあぜ道を歩き、目指す小川に着いた。彼はマッチを取り出し、土瓶の口から、ちょっとだけ出ている布に火をつけた。土瓶の先からは、チョロチョロと炎が光った。 彼は、土瓶を吊るした竹棒を小川の水面に持っていった。こうすると鯰が光につられて水面に出てくるらしい。彼は慣れていた。見事にモリで鯰を突き捕らえた。灯油の燃える匂いと、黒く光る鯰。あの光景は、いまだにハッキリと思い出すことができる。彼は、鯰は食べると美味しいといったが、私は付き合わなかった。 私が就職し、何年か経ったある日、偶然、彼に会った。彼は大手電機メーカーに勤めていた。会社の話でもと思っていると、彼は急に畑の話をしだした。 「今、畑を持っている。これは農地解放のお陰なんだ。俺んちは、江戸時代から小作農家だった。俺は、長男だから家を継ぐ。そうなると、俺は数億円の地主になる。世の中って判らないよ」 私は数億との数字を聞き、羨ましく思ってしまった。しかし、そう言った彼の表情に、私は何か寂しさのようなものを感じた。 彼は、数年前に亡くなった。彼は絵が上手だった。授業中に彼が描いたアマリリスの絵を今でも覚えている。鯰とアマリリス。この取り合わせは妙だが、私にとっては忘れ難い想い出いである。 彼の死因は肝臓破裂。洗面器一杯の血を吐き、その日の内に亡く |
(15)
|
なくなったと聞いた。毎日酒を飲み、家族が止めても言うことを聞かなかったと言う。この話と私の想い出に残る彼とは一致しない。
彼の葬儀に行った。鯰とアマリリスが鮮明に蘇った。ご両親、そして奥様と子供たちに挨拶し、初めて奥さんと話しをした。優しい夫であり父だったという。だが、何故、彼がそうなったのかは判らなかった。 ザニガニを取るのは簡単だった。小川に網を入れて、そっと手繰り上げる。そうすると一匹や二匹は確実に入っていた。スルメの足を糸の先に結び、小川に入れればハサミでスルメを掴んだザリガニがあがってくる。バケツ一杯取ってきて茹でて食べる人もいた。だが、私の親は、絶対に食べることを許してはくれなかった。多分、海老のような味ではないかと思う。 小さな釣り針に赤虫を餌にして小さいなクチボソ、鮠なども釣った。タナゴは、タモを使ったと思う。タナゴは、上から見ると細い姿だが、瓶にいれ横から見ると楕円形の綺麗な姿を見ることができる。綺麗で可愛い魚だった。メダカも群れをなして泳いでいた。棒を突っ込むと、群れはサッと動く。私は、あっちへこっちへと棒を突っ込み、飽かずメダカの動きを見ていた。その時、私は時間の経過など、全く忘れていたと思う。 麦藁帽子を脱ぎ、首に巻いた手ぬぐいが消えていき、しおからトンボが赤とんぼに、そして、ミンミンゼミが、カーナ・カナカナと鳴くヒグラシに替わると、もうすぐ雑木林に秋がくる。 騒々しく活気にあふれた雑木林の夏。そして石神井川周辺のキラキラ輝く川水辺。 でもこれは、何十年も前のおはなし。 |
(16)
|
秋
雑木林の秋の訪れは、夕方になるとカーナ・カナカナと鳴きだすヒグラシが教えてくれる。どこか寂しげな鳴き声。薄の穂も重たげに頭を垂れ、お月様とお似合いの姿になっていく。 夏休みも、もうすぐ終わりだ。宿題やら自由研究が気になりだす頃。あわただしく朝顔の押し花を作ったり、ヒイラギなどの葉っぱを苛性ソーダで煮て葉脈を取り、色を付けたり。 でも困ってしまうのが絵日記だった。子供の頭には、一週間前のでき事など残ってはいない。仕方がない。たった、二行だけの日もあったりする。 雑木林の秋は、紅葉と栗の季節だ。そして、夏の昼間の騒々しさが、夕方の騒々しさへと変わっていく季節。こおろぎ、鈴虫、ガチャガチャなどが、ちょっと湿った感じの夕方の空気の中で、何で、と聞きたくなる程の騒がしい鳴き声を出す季節だ。 秋の夕方は、騒々しいにもかかわらず、子供心にも何となく、もの悲しい気持にさせてしまう雰囲気を持っていた。 台風の季節。実家のすぐ前にある雑木林の木々が大きく揺れる。木の葉を撒き散らすほどの風。台風の雲は動きが早く、切れ目から青空を見ることもある。月夜の台風は、本当に怖かった。薄暗い空に真っ黒な木々を浮き立たせ、その黒い塊が右へ左へと移動する。ガラス越しに見る黒い塊は、今にも家に襲い掛かってくるような雰囲気を持っていた。恐ろしい悪魔のような形。木造のこの家は耐えられるのだろうか。そんな不安を掻き立てる雑木林の台風。でも夜 |
(17)
|
中になれば、そんな不安も関係なく、子供はグッスリと眠ってしまう。
翌朝、辺り一面は、葉っぱやドングリが付いたままの小枝、木っ端の海になる。地面は薙ぎ倒された薄や野草が波打ったように傾いでいる。ここも又、まるで緑の海。栗拾いやドングリ拾い。栗はおやつに。ドングリはヤジロベイの材料に。細い竹ひごを刺せば、かわいいヤジロベイが誕生する。大きめのドングリは独楽にもなってくれた。 触るとかぶれる漆の木もあった。秋になると葉っぱが綺麗に色づいてくれる。他の紅葉も綺麗だが漆の木の紅葉はまた格別だった。でも、触ってはいけない。綺麗な花には刺があるというが、漆は別の武器を持っている。独特の痒み。夏など遊びに夢中になり、気付かずにかぶれることもしばしばあった。 薄の穂は枯れて乳白色になっている。風が吹くと風に煽られ、あっちこっちへと漂いはじめる。耳に入れると耳が聞こえなくなると大きい子から脅かされ逃げ惑ったものだ。でも、これは本当なのだろうか。 薄の穂を摘み、下の方に持ってくる。そこを結ぶとまーるい可愛い姿になる。鬼子母神のミミズクである。雑木林には、いろいろなおもちゃの材料があった。 薄の穂と言うと想い出すことがある。穂のテッペンを切ると三十センチほどの軽い棒が残る。 私の父は、クラシック音楽が大好きだった。ラジオや蓄音器を聞きながら指揮者よろしく、この棒を振るのである。もう無我の境地。近所の子供仲間がこれを見るのだ。不思議そうな顔をして何やってんの? と必ず聞かれた。何となく恥ずかしかったことを覚えている。父によれば薄が一番軽く、按配が良いとのことだった。 |
(18)
|
木々の葉が落ちると、秘密の棲家が出現する。夏、板切れや荒縄などを使って作った木の上の棲家。上手な子は、昼寝ができるほどの棲家を作った。夏の間は茂った葉が棲家を隠してくれる。だが、秋の訪れと共に、これらが姿を現す。こうなれば、もう秘密ではない。皆が使うことができる。太い蔓を取ってきて、棲家のある大きな木の枝に結わえターザンごっこが始まる。
私も良く遊んだ。だが、漫画で見たターザンのように格好良くはいかない。隣の木に飛び移ろうとするが、出来た験しがない。そもそも片手で蔓を持ってぶる下がるなんて不可能なのだ。後にターザン映画を見たが、漫画と同じように片手だけで格好良く遣っているのである。目を凝らして見た。何と蔓には足を入れるための隙間があり、ターザンは片足をその隙間に入れていた。ぶる下がるのではなく、蔓に乗っていたのである。知らなかった私は、何度落っこちたことか。その度に皆に笑われたのに。 冬 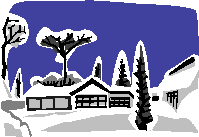 空っ風が吹き出すと冬が訪れる。 雑木林は、茶色一色になる。そして枯葉が二、三十センチほども積み重なる。農家の人たちは、この枯葉を大きな竹篭に集めだす。彼らの家は大きく、家の北側は必ずと言って良いほど薄暗かった。そこに集めた枯葉を積み重ね、腐葉土を作るのだ。 枯葉は、子供たちにとっては恰好の遊びの材料である。子供の背丈くらいの手ごろな木を見つけ、この枝に枯葉を積んでいく。汗だくになりながら積む。すると、枯葉のかまくらができ上がるのだ。 |
(19)
|
その中に入りお手玉や、綾取りをする。外は寒くても中は、体温でホカホカ。ちょっと乾いた土の匂いのするお部屋である。
焚き火などは、雑木林ではしなかった。子供たちは、誰かに言われるまでもなく、キチンと危ないことを知っていた。焚き火は、家の庭でやる。燃料はいくらでもあった。特に杉の枯れ枝は、最高の薪だった。杉の枝を地面に立て火を点ける。爆発とまではいかないが、ボーッと恐ろしい音をあげて燃え上がるのだ。この火柱の周りでインデアンごっこが始まる。ヤッホホー、ヤッホホー。たまに焚き火の上にフライパンを乗せ、ソーセージなどを炒める。これはもう、子供にとっては最高のご馳走だった。 裸足の下駄が足袋の下駄に替わっていく。寒い冬の到来だ。 寒くなると洟垂れ小僧も増えてくる。彼らの服の袖は、テカテカに光っていた。でも、そんな事は気にしない。遊びに夢中なのだ。洟垂れ小僧といっても半端ではなかった。白い洟はまだしも青っ洟である。いちいち洟をかんだりはしない。ズルズルッと吸い込むのである。本当に名人芸。不思議と長くのびた洟が、全部入っていくのである。今は、こんな名人は居ないのではなかろうか。 雑木林の雪は、綺麗な綺麗な別世界。 笹の葉に積もった雪は、丸く可愛い形をしている。可愛い情景なのだが、笹はパッと雪を払いのけてしまう。そして白い雪の中に、まだ緑を残した笹の葉が出ている。白と緑の鮮やかな色合い。 杉の木に積もった雪は、かわいそうだ。ある程度積もると、なだらかな杉の枝は雪の重さで下に撓なっていく。そして、雪は滑り落ちてしまうのだ。その途端、杉の枝は、勝ち誇ったようにピシッと上へと跳ね上がる。私には、この光景が美しい自然のドラマと映った。長い時間、飽かずに眺めていたことを覚えている。 子供にとって雪といえば雪合戦である。毛糸の手袋がビチャビチャに濡れても気にならない。力を入れて丸めると、堅い雪団子にな |
(20)
|
る。これを相手目がけて投げつけるのだ。よくぶつけられたが、作った子供により雪団子の痛さが違った。
雪だるま作りも子供の遊びである。土などをつけずになるべく綺麗に作るには、丸める場所を選ばなくてはならない。落ち葉の上が良いのだが、上手く遣らないと葉っぱがついてしまう。でも、土よりは始末が良い。でき上がった後で葉っぱを取り除けば良いのだ。勝手気ままに目や眉毛、鼻、口を付ける。炭などは勿体ないので木切れを使ったように思う。やんちゃ坊主は、この雪だるま目がけて雪合戦の続き。つくった子供たちとの言い争いが始まる。××ちゃんは、いつもこうなんだからー! 人が折角作ったのにー! 家の縁側では雪ウサギ。ナンテンの赤い実はウサギの目になる。葉っぱは耳に。綺麗な可愛い雪ウサギができ上がる。どうしても家の中に飾りたくなった。お盆に乗せて部屋の中に入れた。でも暖かい部屋では、すぐに融けてしまう。何となく、はかなさのような感覚を知ったのはこの頃か。 冬休み。お正月なのに、やはり宿題がある。宿題を気にしながらのお正月。晴れ着を着こんで、ちょっとおすまし。今と違いお店は全部休みだった。これから数日間は、家にあるものだけで食事をする。おせち料理。お餅は、雑煮、のり巻き、砂糖醤油、それに黄な粉。実家のお雑煮は鶏がらダシのお澄しだった。餅は切り餅。とても美味しい。小さい時から大根と人参、蛸のなますが好きだった。それに今と違い数の子はお腹を壊すほど食べることができた。安かったのだ。芋、牛蒡、人参などの煮しめは苦手だった。 五歳頃からだったと思うが、元旦の朝は早起きをしなければならなかった。初詣である。雪の元旦も雨の元旦も関係なく出かけた。朝、三時頃起きる。身支度を整え、最寄りの駅、石神井公園駅へ。実家から歩きで四、五十分掛かる。四時ちょっと過ぎの電車に乗り |
(21)
|
明治神宮へ。とにかく寒いのだ。神宮の森は底冷えがするのに、原宿の駅から本殿まで歩かなくてはならない。結構、距離がある。手足が凍えたのを覚えている。神宮の次は靖国神社へ行く。初詣のはしごである。
父に理由を聞いたことがある。おじいちゃんも、そうしていたとの答えだった。何故、暖かい昼間に行かないのかと聞いた。この時間が一番空いている。それに一年に一度くらい、寒さに身を引き締めるのも良いんじゃないかとの答えだった。 大學生の頃、友人と年が明けたばかりの一時頃に参拝したことがある。身動きできないほどの混み具合だった。昼間に参拝したこともあるが、やはり人込みが凄い。それに玉砂利を通して土埃が舞う。父の言った事は正しかった。 家に帰るとお雑煮の準備ができている。お腹一杯食べたあとは昼寝である。 父が亡くなってからも、初詣の習慣を四、五年は続けたが、その後、止めてしまった。父と行く事に意義があったのかも知れない。 正月の遊びも豊富だった。独楽、ベーごま、メンコや凧揚げ。それにピストルをパチパチやったのを覚えている。引き金を引くと撃鉄が、細い巻き紙についている丸い火薬を打ち、バンと破裂するおもちゃだ。なぜ、正月になるとやったのだろう。 独楽は、地面だけでなく、掌の上でまわした。綱渡りも楽しいものだった。紐を引き、サッと手のひらに乗せ独楽がまわっている間は、動くことができる鬼ごっこもやった。上手い子は長い間まわしていられるので遠くまで走っていける。下手な子は大変である。鬼を続けなければならない。 缶けりも夢中になる遊びだった。缶をけり、鬼が缶を所定の場所に置くまでに隠れるのだ。鬼は、あっちこっちを捜すが、あまり缶から離れられない。隠れていた子が缶をけってしまうのだ。そうすると初めからやり直しである。要領の悪い子は日が暮れるまで鬼を |
(22)
|
やっていた。泣きたくなるような遊びである。
べーごまは、コンクリートに擦りつけ力(リキ)を付けなければならない。さもないとシートから、すぐにはじき出されてしまう。これは、全くの決戦であった。バケツにシートを張り、何人かがベーごまをまわす。他のべーごまをはじき出し、最後まで残ったベーごまが勝ちである。力のあるベーごまを持つ子供は英雄であった。夜遅くまでベーごまをまわしたのを覚えている。 凧は自分でも作った。竹ひごと紙、それに凧糸。重心決めと尻尾の長さが決め手であった。トンビ凧が好きだったが、さすがにこの凧を作ることはできなかった。 ゴム動力の飛行機も良く作った。お気に入りは東京号。この飛行機は実に良く飛んだ。模型屋からキットを買ってくる。これも竹ヒゴと紙である。プロペラは木でできていた。金物は、このプロペラの芯と、それを差し込み回転させるコの字型の部分とニューム管、それに主脚だけ。ニューム管に竹ヒゴをさし主翼や尾翼を作る。この東京号は、垂直尾翼が、水平尾翼の下に付くのである。ちょっと洒落たスタイルなのだ。丁寧に主翼、水平・垂直尾翼の紙を貼る。貼り終わると霧吹きで水を掛ける。乾くと紙がピンと張るのだ。それぞれが完成すると次は組み立てだ。胴体は細い木である。主翼などの翼を付けていく。ゴムを何本か束ね金属の輪っかをつける。この輪っかをプロペラと尾翼の傍にある金具に付ける。ゴムはたわんでいる。これが良いのだ。余裕を持ったゴムの状態が、タップリと動力を蓄えてくれる。普通は、プロペラを指で廻して動力を貯めるが、手っ取り早く遣るにはワインダーを使う。これだと一廻しで何回分かの動力を蓄えることができる。ゴムは力強く動力を蓄えてい |
(23)
|
く。いよいよ飛行である。 言い忘れたが、東京号の舞台は雑木林ではない。冬の畑である。作物が刈り取られた畑は、格好の場所であった。飛行をさえぎるものはない。雑木林では木々に引っ掛かってしまう。その頃の練馬では、電線もそれほど張り巡らされてはいなかった。畑には広々とした空間があった。タップリと動力を蓄えた東京号の飛行である。この飛行機は、本当に良く飛んだ。空高く、空遠く、心配になるほど良く飛んだ。多分この手の飛行機としては最高傑作だったと思う。正月休みに東京号を作ったのは、やはり飛行空間があったからだと思う。冬の畑は、子供にとっての正に自由な空間であった。
宿題は、お書き初めに自由課題。書初めは正月二日。六畳の部屋に机を置き、一人で静かに筆を持つ。課題は何だったか忘れてしまったが、とにかく落ち着いて書道に勤しむ。ある正月、小学三年生の頃だったと思う。一人で書いていると父が入ってきた。「どうだい?」私は、咄嗟に書き終わったもの書いている途中の和紙を隠した。見せるのが恥ずかしかったのだ。父は言った。 「人に見せるのが恥ずかしいような字なら書かない方が良いよ。自分が一所懸命書いたものなら誰に見せても恥ずかしいとは思わないはずだけど」 意味は理解できた。でも、見せられなかった。父は何も言わず部屋を出て行った。何となく情けなく感じた事を覚えている。 自由課題。夏に比べ冬休みの自由課題は、材料がなく困ったものだ。ある冬休みであった。困っていると、母が言った。 「夏になると、あんなに出て来る虫たちなんだから、冬は多分何処 |
(24)
|
<かに隠れているはずよ。木の皮を剥がしてみたら」
木の皮を剥がす? 虫が居るのかな? 雑木林に行き皮を剥がしてみた。驚いたことにさなぎとか、幼虫、成虫が居たのだ。松、くぬぎ、栗……。どんな名前の虫たちだったかは忘れたが、それらを標本にし、冬の木の中の虫たちとの題でまとめた。ちょっとした評判になったのを覚えている。だが発案は母であった。夏の自由課題で提出した葉脈も発案は母であった。勝手な想像だが、母は自分が遣りたかったことを私に言ったのだと思っている。 冬の風物史とも言えるのが農家の堆肥作りではなかろうか。 麦ワラを刻み、落ち葉を集め、横十メートル縦五メートルほどに積み上げる。ちょうど、台形のような形になる。その上に下肥を振りかける。つまり人糞である。当時は水洗トイレなどはなかった。貯め式の便所である。ある期間がくると農家の人が、肥桶を担いで汲み取りに来た。汲み取った人糞を肥溜めに入れて置く。多分、肥溜めで人糞は発酵するのではないかと思う。その下肥を、刻んだ麦ワラ、落ち葉の上に振りかけるのだ。発酵した下肥は、一種独特な匂いがしたが、新しい人糞の臭いとは違っていた。 数日経つと、この台形に変化が起きる。寒い日には、この台形から湯気が立ち昇るのだ。不思議な光景であった。まるでお湯を掛けたようにユラユラと暖かそうな湯気が立ち昇るのだ。バクテリアの影響なのだろうか、台形の中では激しい発酵が進んでいたのだと思う。そして、次第に麦ワラなどに白い粒々ができてくる。 この頃になると下肥の臭いはなくなっている。多分、これで堆肥が完成したのだと思う。農家の人が帯のついた桶を肩に背負い、畑に堆肥を撒いている姿を良く見かけた。ミレーの絵にあるような姿である。ちょっと驚いたのは堆肥を手づかみで撒いていたことだ。 |
(25)
|
すでに充分発酵した堆肥には、つまらないばい菌などは住んで居なかったのだと思う。だが、子供の目に驚きを与える光景だった。
何回かの雪を経験し、太陽の光が徐々に増してくると梅の蕾が膨らみ、雑木林に積もっていた雪がとけだしてくる。そして、雪の間の所々に丸い黒い穴が見え出す。穴の中には、濡れた落ち葉。そして草花の芽吹き。そろそろ春の到来である。 環八や目白通りが走り、騒々しい車の往来に明け暮れる練馬の一角にも、このような自然があった。大昔から二、三十年前までは、全く同じ自然の営みが繰り返されていたのだと思う。純粋な自然の繰り返しが。 実家の前の雑木林も無くなり民家が建てられた。石神井川も立派な護岸に守られている。あの川辺もとっくに無くなっている。これが人間の進歩。そう言ってしまえば、それまでかも知れないが、確実に自然を壊しているのだ。そして、その進歩の、いや破壊の一翼をこの私も担っている。気が付いた時には、あの素晴らしい自然は無くなっていた。そして、絶対に、あの自然は戻っては来ない。 東京に住む者にとり、身近にあった自然を思い出すことには、何の意味もなくなっているのかも知れない。 故郷は遠きにありて……と詠った人がいた。彼は、東京で故郷金沢を詠ったという。遠くとは、物理的な距離なのだろうか。または心理的な距離。いや、その両方か…… 故郷を持つ人々は、飛行機、列車、車を使えば故郷に戻ることができる。そこが昔通りであるか、変わってしまったかは判らない。 |
(26)
|
だが余程のことがない限り、そこ此処に思い出の場所、雰囲気が残っていると思う。畦道に祭られたお地蔵様、肥後守で名前を刻んだ大木、釣りをした川……。多分、その人は、それらを手で触るだろう。その時、その人はどのような事を感じるのだろうか。
私は、東京生まれで東京育ち。いわゆる故郷というものを持っていない。あえて言えば、何十年か前の練馬が故郷なのかも知れないが、何を使ってもそこに行くことはできない。手で触ることもできない。余りにも遠くに行ってしまった故郷。そして、その故郷は日に日に記憶からも遠ざかっていく。 木の中の虫たち……。そして、カブト虫、クワガタ…… でもこれは、何十年も前のおはなし。 (了) 二00四年七月十日 インデックス・ページに戻る |
(27)