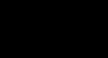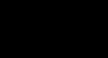世界は、不況の真っ只中にあった。インフレは進み、貨幣価値はどん底であった。
富豪達は、こぞって目の色を変え「金(GOLD)」をかき集めていた。
庶民は、今日の食料を見つけるのも大変であり、俯きながらトボトボと歩き回るだけであった。
このような状況に、追い討ちを掛ける事態が発生していた。
原因不明な病気の蔓延である。この病気に罹ると、まず目に激痛を覚え、数日で頭痛が始まり、そして確実に死に至るという恐ろしい病気であった。
各国の医療機関による原因究明の活動が進められたが一向に成果は挙げられなかった。
全く原因が不明であるため、当然ながら治療方法なども判らず、ただ世界中が、ただオロオロするだけであった。この病気は、年齢、男女の別、人種にも関係無く、全世界的に広がっていった。無論、貧富の差なども関係はなかった。
このような時に、まず、自分だけは助かりたいと考えるのが富豪達である。目の色を変えて蓄えた「金」も、病気に罹ってしまえば何の価値もなくなってしまう。
彼らは、原因究明、治療方法の研究のために集めた「金」を関係機関にバラ撒き始めた。命には替えられないのである。調査・研究は、全世界規模で、あらゆる産業を巻き込み進められていった。皮肉な事に、この活動の影響で経済は活気を帯び、景気も上向きになっていった。
しかし、病気による死亡者は鼠算的に増えていった。地球上の人類が絶えてしまうのは時間の問題であった。人々は、相変わらず俯きながら、トボトボと歩む生活を続けていた。
WHO:世界保健機関から、患者の発生数に関する地域的な分布についての調査結果が発表された。調査結果は、赤道近辺は比較的患者数が少なく、北極、南極に近づくにつれ多くなっていると報告していた。
原因は気温? 太陽光線? 赤外線、紫外線、宇宙線? …… 総て関係なかった。
感染経路については、接触感染、空気感染などあらゆる調査がなされたが無関係であった。原因としてウィルスが疑われた。特に目を中心にサンプルが集められ高性能電子顕微鏡で隈なく調べられたが、新種のウィルスは発見されなかった。
もはや打つ手はないように思われた。
数ヶ月が経った。ある学者が、目に注目しWHOの調査結果に再度、目を通しだした。そして、彼は奇妙な現象を発見した。目の見えない人のなかには感染者がいないのである。やはり、目だ! 彼は、「目」に目を付け研究を進めた。
彼は、最初から原因究明をやり直す事にした。ウィルスから調べ始めた。彼は、大富豪に連絡し資金を調達した。顕微鏡の開発を進めるためだ。
完成した。現存する電子顕微鏡の性能に比べ、数億倍もの解像度を持ったものだ。
超高性能…… いや、「超」を7つ位付けなければ追いつかない程の性能である。名前をつけることにした。「ウルトラ・セブン」。ところが商標登録上の問題が起こった。似たような名前の物語の主人公がいたのだ。名前など、どうでも良いか、とは思ったものの余りにも優秀な顕微鏡である。そこで、ひとつサバを読み「ウルトラ・エイト」とした。
さすが「ウルトラ・エイト」であった。彼は、見つけたのだ。新種ウィルスを。超々微小のウィルスであった。今回は、サバを読む必要のない、超を八つ付ける位の微小さであった。他の原因は考えられない。彼は、このウィルスを病原体と決めつけた。
次に感染経路である。目が見えない人には、感染しないという事は、やはり、空気感染ではないし接触感染でもない。遺伝的なものでもない。では、どうして感染するのだろう。研究・試行錯誤の結果、彼は、目を閉じていれば感染しない事実を掴んだ。と言う事は! まさか?感染経路は、「視線」! そんなバカなッ! 超が8つもつく微小ウィルスである。視線に乗って感染していたのである。
まるで目が合うと石になってしまうメデューサのようであった。このウィルスに名前がつけられた。「メデューサ・ウィルス」。イスタンブール地下宮殿のメデューサもイイ迷惑である。
折角の眠りを邪魔されたようなものである。もっとも動こうにも石の柱が重くジッとしている以外になかったが。
急遽、国連憲章に新たな条文が附加された。「人と目を合わせてはいけない」
奇妙な世界が出来上がっていった。俯きトボトボ歩いていても、さすがに人と話をする時には、顔を上げ相手の目を見てはいた。しかし、これからは、横を向いたまま話し合わなければならないのだ。恋人同士も可哀想そうなものであった。
「君の瞳に愛を……」
「アラッ! いつ、私の瞳を見たの。そんなの真っ赤な嘘よッ。貴方って嘘つきだったのね」
などと折角の恋もオジャンになってしまうのだ。
相撲界でも困っていた。
アナウンサー
「千秋楽、優勝決定の大一番です。両横綱、全勝優勝をかけて最後のシキリに入り
ました。横行司、式村伊太郎。両者土俵の中央。伊太郎、掛け声をかけます」
行司伊太郎
「ソッポ向いて、ソッポ向いて。ハッケヨイッ!」
どうにも締まらない大相撲になってしまった。
そうでなくとも人間関係がギクシャクした時代である。病気の蔓延は一応止まったものの、これでは生活が成り立たない。学者連中は、さらにメデューサ・ウィルス撲滅の研究を進めていた。また、その他の学者達は、せめて話し合う時くらい顔を見つめ合いたいとの人類の要求に応えるべく研究を進めていた。
鏡に顔を映せば大丈夫なのでは、との意見がでた。研究の結果、驚いた事に反射性の少ない鏡であってもメデューサは、100%反射する事が判った。メデューサは、光波よりは大きいのである。しかし、この事実は光明をもたらした。そして開発されたのが、メデューサを拡散してしまう超微小の反射板を無数に貼り付けた、コンタクト・レンズのようなものである。眼鏡では目との間に空間が出来るため完全防御は困難である。反射板は、一つとして同じ角度にはなっていなかった。これを「メデューサ・カバー」と言った。
多少、世の中が暗く見えるが、所詮コレラが流行った中世と同じような時代である。我慢する事はできた。メデューサ・カバーは赤く、光の当たり具合で虹のように輝いた。赤い目を見つめて話すのは気色悪いものであるが、正常に近い会話が出来るようになった。
これだけでも人類は喜んだ。しかし、ウィルス根絶の可能性については既に諦めていた。
ある青年が可愛そうにもメデューサに感染してしまった。激痛が目に走り出したのだ。あと数日で死が訪れるのだ。
彼は、身の不幸を嘆くと同時に子供の頃を思い出した。
「ウサギ追いし、かの山……… そうだ、どうせ死ぬのなら故郷で死のう」
故郷は昔のままであった。緑一面の小高い丘。平野を流れる小川。草花は咲き乱れている。
「良かった。帰ってきて良かった」
痛みの走る目からは大粒の涙が流れ落ちた。丘の上で彼は両腕の上に頭をのせ寝転んだ。
「あー、短いようでも、いろいろな事があったー」
彼は、青空を見た。そして太陽も。
「何年ぶりだろう。地球には青空も太陽もあったんだ」
殆どの人間は、元気なく下を向いた生活であった。青空、太陽など忘れていた。
その時、驚くような事が起こった。眼の痛みが和らいでいくのだ。太陽をもう一度見た。眩しくてどうしようもなかったが、二、三秒見つめた。痛みは去っていった。目を閉じた。全く痛みはなくなっていた。驚いた彼は、急いで病院に駆け込んだ。メデューサ・チェックをしてもらった。メデューサは死滅していた。
メデューサは、太陽光線に弱かったのだ。
青空、太陽を忘れた人間の体自体が、メデューサ・ウィルスを生み出したのだった。
地球上の生物に次々と奇妙な病気、ウィルスが発生するが、総て「自然」を省みない人間の仕業といえる。
全人類が、青空と太陽を見つめた。そして、地球上からメデューサ・ウィルスか根絶した。
「なーんだ、こんな簡単な事だったのか。人間本来の姿に戻れば良いんじゃないか。これからも胸を張り青空を見つめよう」
誰もがそう思った。まるで、目からウロコが落ちたように。
そう言えば、「メデューサ・カバー」は、金目鯛の「鱗」にそっくりであった。
2001.10.06