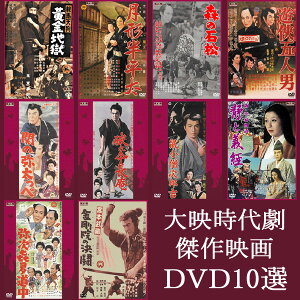1956年、大映京都、吉川英治原作、八尋不二脚本、島耕二監督作品。
▼▼▼▼▼最初にストーリーを書いていますので、ご注意ください!コメントはページ下です。▼▼▼▼▼
寿永3年…
一の谷の合戦で平家を破り、都に戻って来た源義経(菅原謙二)を、一目見ようと駆け寄って来る子供たち。
家来を従え、馬上から群衆を見やっていた義経は、その中に、幼なじみの静(淡島千景)の姿を発見し、見つめる。
静の方も、義経が自分のことを憶えていてくれたと感激するが、同行していた母親は、今や、立派な身分になられたあの方が、そんな幼い頃のことを憶えておられるはずがないと否定する。
それでも、義経に会いたい一心の静は、今日白拍子として招かれている、摂政、近衛基通様の館での宴で、義経と出会えることに期待をかけていた。
しかし、母親は、幼なじみと言うことに乗じて、粗相がないようにと釘を刺すのだった。
基通の館では、華やかな宴が行われていたが、静は、義経が出席しないと知らされる。
その時、源氏の家来が一人やって来て、このような晴れやかな場所へは欠礼したいと、義経の辞退の意向を通達に来たので、それを知った静は、その使者を呼び止め、一通の手紙を手渡す。
それを受け取った義経は、「静やしづ しづのおだまき 繰り返し 昔をいまに なすよしもがな 吉野山 みねの白雪 ふみわけて 入りにし人の あとぞ恋しき」と書かれた静からの文を読み、静と出会った幼い頃のことに思いを馳せる。
静は、幼い頃より、鼓が好きであった…
幼かった義経(清水紘治)と静(加納福子)は、共に一つの鼓を叩きながら遊んだものだった。
義経が陸奥へ堕ちて行くときも、峠から、自分を見送る静(上久保朗子)の打つ鼓の音が聞こえていた。
再び、都に戻って来た義経は、すっかり成長し、美しい白拍子として舞っていた静と再会する。
その時も、鼓の音が響いていたのだった…
我に返った義経は、鎌倉からの使者から平家追討の任を解かれ、今後は、異母兄範頼に任せるとの通達を受ける。
これを一緒に聞いていた武蔵坊弁慶(浜口喜博)は、これでは除名ではありませんか!といきり立つが、義経は、再会の兵は侮れぬと言い、制する。
その後、義経は、佐藤忠信(舟木洋一)に馬を用意させると、鼓の音が響いて来る竹林の中の一軒家に出かける。
そこは、静の住まいであった。
突然の来訪に驚く母親だったが、義経が出迎えた静を抱きしめたので、お供の忠信は気を利かせて、母親を外に連れ出すと、二人きりにしてやるのだった。
灯りが消えたので、静はお顔が観たいと窓を開く。
二人が語らった夜はすぐに明けてしまう。
静は、自分のことを良く憶えておいでで…と感激するが、義経は、忘れるものか、片時も忘れたことはない。もう離さない言い、静、来るか?私の館に?と問いかける。
静は、母親のことを案ずるが、義経は母上も共にだと言葉を添える。
朝まで側の林の中で待っていた佐藤忠信の元にやって来たのは弁慶だった。
源範頼が立ち寄られたと言うのだ。
館で弟の帰りを待ちくたびれていた源範頼の元に、やがて戻って来た義経は、御所に、拝謁の手はずを整えておりましたと詫びる。
範頼は、暮までには、平家をきれいに片付けて凱旋できようと自信満々だった。
鎌倉殿よりの書状は持っているなと聞かれた義経は否定し、聞いた範頼も、その返事に当惑する。
百合野を、そなたの嫁にとの思し召しじゃと範頼は教えたので、今度は義経の方が愕然とするのだった。
鎌倉
源頼朝(上原謙)は、母親共々拝謁に来た百合野(香川京子)に、義経と会うたことがあるか?世の習わしじゃと、勤めてくれと伝えると、梶原景時(永田靖)には、自分の代わりに取りはからうように命じる。
さらに、狭山(大美輝子)ら三人の男女に、義経の動きを探り、こちらに知らせるよう、指示が出される。
都に、義経の妻として百合野が寄越されると知った静は、義経の妻は私一人と憤り、その到着の様子を見ようとしたので、母親に止められる。
部屋に戻った静は、一人で泣くしかなかった。
百合野と、源頼朝の名代として付き添って来た梶原景時を前にした義経は、自分には既に静と言う妻があると断るが、それを聞いた景時は、白拍子など遊女…と軽んじるので、義経は白拍子は遊女ではないと否定する。
それでも、景時は、側室は側室、正室は正室とごり押しをして来るし、百合野も、今さら、鎌倉に帰れませぬと言うので、義経は、いたければいるが良い。静と言う妻がいると言うことを承知ならな…と言い残すと席を立ってしまう。
百合野は、座したまま、じっと耐えるしかなかった。
鎌倉に取って帰った梶原景時は、このことを報告すると、義経と言う男、あの若さで、すでに天下を取ったような気にもなりましょうなどと誹謗し、何らかの処置をするよう進言する。
しかし、そこへ、源範頼が破れたとの知らせがもたらされる。
それを聞いた頼朝は、改めて義経に平家追討を任せようと言い出す。
この戦は、義経でなくてはならぬ、このたびの処置はその後だと家臣たちに命じる。
尾島
船の上に掲げられた軍扇を目がけ、那須の与一 (勝新太郎)は見事、矢を命中させ、それを合図にしたように戦が始まる。
義経や弁慶も、船に乗り込み戦う。
館に残っていた狭山は、鎌倉への密書をしたためていたが、そこにやって来た江戸十郎太(水原浩一)が、叔父の新宮行家 (進藤英太郎)がやって来たと知らせる。
行家が言うには、義経の今回の働きは、鎌倉に完全に黙殺されただけでなく、驕慢の行状ありとして、お咎めの使者が発つ。もはや兄弟の縁を断つとまで鎌倉様は言われていると知らせる。
この知らせを聞いた弁慶は、勝利の宴に酔っていた家来たちを制止していた。
行家が帰った後、静に会った義経は、鎌倉に行き、兄上の誤解を何とか解きたいと伝える。
自分は、そなたさえいてくれれば良いが、わしの為に命を捨てて働いてくれた家来たちに、これ以上哀しいことはないと言う義経に、静は、一時も早うおいでなさいませと、涙ながら進める。
そんな静を観ていた義経は、あしからしばしの別れだ。鼓を打ってくれぬかと頼み、伊豆は久々に鼓を打つのだった。
鎌倉に向かう途中、河原で休んでいた義経一行に、鎌倉から土肥実平(香川良介)がやって来たので、出迎えに来てくれたかと喜んだ義経だったが、実平の知らせは、沙汰あるまで、鎌倉に入ることはならぬ。腰越にて待つようにとの厳命だった。
あまりの仕打ちに、義経は、兄上が…と絶句する。
雨の中、一人、館の中で時を待つ義経は、「静やしづ しづのおだまき 繰り返し 昔をいまに なすよしもがな 吉野山 みねの白雪 ふみわけて 入りにし人の あとぞ恋しき」と言う、静からの手紙を思い出していた。
都で一人、夫の帰りを待つ静も、引き戸に着物の袖が引っかかり、飾りの珠が床にこぼれ落ちてしまう。
やがて、義経の元に使者としてやって来た北条時政(花布辰男)は、このまま都へ立ち返れと言う。
義経は、何とか取りなしてくれぬかと懇願するが聞き入れられない。
せめて真心を込めた手紙だけでも届けてくれぬかと頼み、ようやく願いは聞き届けられる。
「慈訴」と記された義経の手紙には、自分には野心などなく、お会いしてお話しすれば、お疑いはたちどころに解けることです。この十余年、兄弟手を取り合って平家を討って来たのも、亡き父のお恨みを晴らすためだけですと切々と書かれてあった。
それを読んだ頼朝は、陸奥から帰って来た義経を自分が出迎えたときのことなど思い返していた。
あの時と、義経の気持ちは変わりませぬ。お信じくださいますようと手紙は続いていたが、側近たちから、日本国の統一がなるか、ならぬかの時です。義経は人望がありますなどと耳打ちされているうちに、会う必要はない。都へ追い返せと頼朝は命じるのだった。
頼朝が立ち去った後、側近たちは、笑いながら、義経の書状を破り捨てるのだった。
湖で漁をしていた夫を呼び寄せた女房は、又、戦が始まるらしい。義経様は、鎌倉様から21カ所の領地を召し上げられるらしいと噂話を伝えるが、それを聞いた夫は、それは梶原や方條の作り話じゃと言いながらも、戦はもう行かん…と怯えるのだった。
都に戻った義経は、どこからともなく聞こえて来る鐘の寝に気づき、何事かと様子を観に行かせようとしていたが、突如、夜討ちだ!百騎あまりの兵が攻め込んで来るとの知らせが飛び込んで来る。
義経は、門の中には一騎も入れるなと命じ、弁慶が、外から打ち破ろうとする敵兵から門を守ろうと身体で押さえる。
やがて、次々に松明が館の中に投じられる。
頼朝の命により攻めて来た兵は、門を打ち破り、館の中に乱入して来る。
義経は必死に戦い、敵将を討ち落とす。
敵兵たちが退散した後、館の中では、患者の疑いがある狭山が佐藤忠信によって捕らえられていた。
しかし、その場で殺そうとする忠信に、義経は狭山には百合野を送って行ってもらわねばならぬと言い止めると、百合野には、そなたは人形でしかない。明日の定めも分からぬ義経を去って、幸せになってくれと言葉をかける。
そんな義経に会いに来た行家は、院宣が下り、鎌倉を討ってよしという許しが出たと知らせるが、それを側で聞いていた麻鳥(二代目中村鴈治郎)は、義経様!と案じて声をかける。
行家は、身分卑しき下男風情が口を出したので不快がるが、義経にとっては、天の声ですと応じた義経は、天下の大乱を防ぐため、兄と戦うようなら、身を引こう。保元、平治以降、民は苦しんでおります。この民のために、身を引けとわしに告げているのだろうと言うので、せっかく、院で話をまとめて来た行家は不機嫌になり、勝手にせい!と言うなり帰ってしまう。
残った義経は、麻鳥に向かい、もう戦は嫌じゃのうとつぶやきかける。
立ち上がった義経は、いつの間にか静が立っており、今の話を聞いていたことを知ると、これ以上、兄に逆らいたくないと漏らすのだった。
世の中も静まろう。静、夜明けを待って都を落ちようと言いながら、静を抱き上げた義経は、初めて出会ったときのことを思い出しながら、二人の幸せを探す旅と思えば…。そなた一人くらい幸せにできる。わしを信じてくれと語りかけ、それを聞いた静もうれしゅうございますと答える。
家来たちに、思いを残さぬように堀川の館をきれいに整理させた義経は、静にも母親との別れをさせ、世の明けきらぬうちに館を出立する。
都には、義経を謀反人とする高札が立つ。
訴え出たものには恩賞が出ると言うのだ。
麻鳥は、その高札を複雑な気持ちで読んでいた。
吉野の山に逃げ込んだ義経だったが、僧兵たちが後を追って来る。
弁慶が静を背負って、何とか逃走を図るが、前からも僧兵が迫って来る。
何とか、その場は逃げおおせた一行だったが、もはや、女連れでの山越えは不可能と判断した家来たちは、そのことを義経に進言する。
義経は、本意ではないが、ここで別れてくれぬか。敵が狙っているには私だけ。ここからは、山伏でさえ険しい山道と説得し、鏡と砂金を手渡すと、二人の家来に都へ連れ戻るよう命じるが、静が急に苦しみ出したので、それを観かねた弁慶はお連れしましょうと、又、静を背負うことにする。
しかし、その後しばらく山を登った所で、法螺の音が聞こえ、義経も知る千丈坊(南部彰三)と実生坊(東良之助)が現れると、ここから先は女人の身では入ることができません。入れば、吉野だけではなく、他の霊山も呪われますと言うので、さすがに諦めた静は、ここでお別れですと義経に告げる。
それを聞いた義経は、都に帰ってくれるか。生き抜く為の別れだぞと言い聞かせ、そこで静と別れることにする。
静に付いて山を下り始めた家来たちは、都に帰ったら俺たちは殺されるぞと話し合い、突如、静が持っていた鏡や砂金を奪うと、さらには、静が命より大切にしていた鼓まで奪おうともみ合ううちに、鼓は手を離れ、崖下に落ちてしまう。
家来たちに逃げられ、雪が振って来た中、一人山道をさまよい歩くしかなかった。
やがて、雪が積もり始めた崖下に落ちていた鼓を見つけた静は、雪を払い、そっと打ってみるが、思わず絶望感から泣き出してしまう。
その後、自らの上着を脱ぎ、鼓を包んで地面に置いた静は、側の滝から身を乗り出そうとする。
そこに駆けつけ身投げを思い留まらせたのは、こっそり後を付けていた麻鳥だった。
そこでも、体調が悪そうだった静の様子を観ていた麻鳥は、静様、あなたは、御妊娠でございますと告げ、それでも死のうとなさいますか?大切な義経様のお子様を殺そうとなさいますか?と問いかける。
それを聞いた静は、生き抜いてみせます。どんなに苦しいことに会おうともと約束するのだった。
麻鳥と共に、都に戻って来た静だったが、市内にあちこちにいた源氏方の検問は厳しく、ほどなく二人は捕らえられてしまう。
静は、大峰の結界で別れたと言う義経とは、どこで打ち合うのかと厳しい先議を受けるが、何でそんなことが契れようと口を開かなかったので、麻鳥が入れられていた郎のすぐ側で、むち打ちの拷問を受けることになる。
やがて、気絶した静は、麻鳥と同じ牢の中に入れられたので、麻鳥は必死に懐抱するが、静は、殿の御子はきっと生んでみせますとつぶやく。
続いて、牢を出された麻鳥は、自分も拷問を受けるのかと覚悟するが、行く先は本院だと言うので、自分もこのまま、ここに置いて下され!と役人にすがりつくが敵わなかった。
ひとりぼっちになった静は泣き出すが、そんな静の元に、尼になった母親が会いに来る。
麻鳥から聞いて来たのだと言う。
母は、これからは、お前の運が開けるかもしれません。頼朝公より、鎌倉へ送れとご命令が下ったのですと言う。
静は、輿に乗せられ、鎌倉へ運ばれる。
その途中、とある館で休息を取っていた静は、ずっと尾行して来て、こっそり館内に潜入して近づいて来た麻鳥に、鎌倉に入ると、どのようになるか分からぬこの身、この子のことを義経様にお伝えし、静は未来永劫、あなた様の妻ですとおっしゃって下さいと、大切な鼓を託しながら頼む。
鎌倉八幡神社での彼岸祭
鎌倉幕府成立を祝う舞台で、日本一の舞い手として呼ばれた静は、間違いのないよう母親からも念を押される。
しかし、舞台の中央に立った静が口にして舞い出したのは「静やしづ しづのおだまき 繰り返し 昔をいまに なすよしもがな 吉野山 みねの白雪 ふみわけて 入りにし人の あとぞ恋しき」と言う、義経を慕う詩だった。
それを聞いていた頼朝の側近たちは色めき立ち、不敵な女め、このまま見逃す訳にはいけませんと言い出したので、頼朝も、直ちに殺せと命じる。
しかし、殺してはいけません!と、それを止めたのは、横で聞いていた政子(水戸光子)であった。
政子は、このような場であっても夫を慕う静の態度は、まさに女の鑑とも言うべきもの。女の私には良く分かります。助命をお願いしますと訴えたので、頼朝は仕方なく、「舞え!」と命じる。
側近も、静!幕府の門出を祝え!と命じるが、静は、その後も、どこかへ落ちた我が夫、義経のことばかり考えながら舞い始める。
そんな静を物陰から狙う矢があったが、静の毅然とした舞いを観ていると、どうしても射ることができなかった。
静の心の中の目には、どこかの山を進む義経たちの姿が映し出されていた。
「吉野山〜 稲のしらぬき 踏み渡し〜 入りにし人の音ぞ 恋しき〜」
静は、またも、義経を思う詩を歌い、堂々と舞い続けるのだった。
▼▼▼▼▼個人的なコメントはここから下です。▼▼▼▼▼
「新平家物語」ものの一本で、それなりに予算をかけた作品だと思われるが、大作感が弱いのは、キャスティングの弱さに要因があるように思える。
全編を観ると、主人公は淡島千景演ずる静の方であり、義経は準主役くらいの扱いだと分かるが、前半部分は明らかに義経の悲劇性の方に重きが置かれ描かれている。
にも関わらず、義経を演じているには菅原謙二である。
菅原謙二は、脇役としては渋い魅力を持った俳優ながら、義経と言う役を演じるには華がない。
この華がない義経と静のラブロマンスが盛り上がるはずもなく、豪華なセットや合戦シーンなどが映画らしさを感じさせるものの、ドラマ部分はいたって地味と言うしかない。
上原謙や勝新太郎と言った華のある役者も出ているが、彼らの登場シーンはいたって少なく、勝新太郎などは一瞬しか出ないゲスト扱い。
女優陣も同様で、百合野を演じている香川京子などは、ほとんどセリフすらなく、感情の表現のしようもない、まさに人形のような有様。
武蔵坊弁慶を演じている浜口喜博と言う役者も、身体が大きい以外は、ほとんど無名の素人にしか見えず、全く魅力を感じられない。
これでは、ドラマ部分に深みが出るはずもなく、このシリーズの特長である「動く日本画」のような美術的な撮り方以外にこれといった見所がなく、合戦シーンも凡庸と言うしかない。
とは言え、義経と静のラブロマンスと言う基本線はシンプルながらも分かりやすいことだけは確か。
前半の義経メインのドラマと後半の静メインのドラマが、やや分離しているように感じないでもないが、色々、複雑な人間関係や時代背景など、歴史に知識がない観客にも、それなりに付いて行ける内容ではあるだろう。
二代目中村鴈治郎が演じている麻鳥と言う人物の設定が、解説文などを読むと医者らしいのだが、映画で観る限りではどう言う人物か良く理解できず、歴史に疎い自分には、義経や静との関係性が読み解けなかったのが悔しい。