1951年、松竹大船、木下恵介脚本+監督。
▼▼▼▼▼最初にストーリーを書いていますので、ご注意ください!コメントはページ下です。▼▼▼▼▼
広大な浅間山麓の草原で馬を追う男が一人。
そこへ「とっちゃん!」と叫びながら駆け寄る女。
女は、馬追い男正一(坂本武)の長女ゆき(望月恵美子)であった。
彼女が言うには、家出して東京にいるらしい妹のきん(高峰秀子)が、友達を連れて、久々に帰って来ると手紙を寄越したと言う。
正一は、東京で芸術家リリー・カルメンとやらいう奇妙な名前を名乗るようになったきんを、どこか信用し切れていなかった。
何せ、きんは子供の頃、牛に蹴られて泡を吹いて気絶した事があり、それ以来、すこ〜し頭が弱くなってしまい、18になるまで鼻を垂らしていたと言うような女の子だった。
そんな娘が、家出をして以来、時々、一人前に土産等を送って寄越すのも、正直、心の底から喜べなかった。
その頃、村の小学校では、近く行われる運動会用に、生徒たちがオルガンの音楽に合わせて踊りの稽古をやっていた。
そんな校庭の片隅に、幼子の清(城澤勇夫)と連れ立って遊びに来ていたのは、目が不自由な元教師田口春雄(佐野周二)という男。
彼は、妻光子(井川邦子)と結婚して1年目で戦争に徴兵され、その時、目をやられて以来、復員後は、すっかり妻に生活を任せっぱなしの状態だった。
光子は、苦しいながらも馬に荷車を引かせて、わずかばかりづつ丸十の借金を返済しながら、夫や幼子の面倒も見ていた。
唯一の楽しみのためと、無理して購入したオルガンで、作曲の真似事等していたのだが、そのオルガンも、借金を払えず、丸十運送の社長丸野十造(見明凡太郎)に取られてしまっていた。
そんな事情を知った教師の小川(佐田啓二)は、田口の作る曲を好きだったこともあり、校庭のオルガンで、田口が新しく作ったと言う「嗚呼我が故郷」という曲を披露してもらうのだった。
父親の正一が、あまり娘の帰郷に乗り気ではないので、思いきって、小学校の教師をやっている一郎(磯野秋雄)に相談してみたゆきだったが、養子の身の一郎は遠慮して、小学校の校長(笠智衆)に相談するよう助言するのだった。
相談を受けた校長は、父親の正一に、文化や芸術の大切さを説き、東京で有名な舞踏家とやらになっている娘を誇りに思い、暖かく迎えてやるよう、こんこんと言い聞かせるのだった。
かくして、北軽井沢の駅に、リリー・カルメンと友人のマヤ・朱実(小林トシ子)が列車にのって到着する。
同じ列車に乗り合わせていた丸十と、その従業員の信平(三井弘次)は、すっかり様変わりして色っぽくなったきんを驚きの目で見るのだった。
そんなカルメンたちは、出迎えた姉夫婦らと共に、丸十の手配した光子の馬力に乗せられて家に帰り付く。
カルメンは、何となく照れくさがっている父親に再開後、小学校で春雄とも再開を果たす。
実は、子供の頃、カルメンが秘かに慕っていた先生が春雄だったのだ。
彼女は、目が不自由になった春雄の姿を見て同情する。
一方、同じく小学校に付いて来ていた朱実の方は、ハンサムな小川先生に言い寄っていた。
実は彼女は東京で失恋していたのであった。
そんな中始まった秋季運動会、カルメンと朱実は、父、正一が呆れ果てたハレンチな服を着て学校に現れる。
何せ、人から借りて来た衣装だった上に、今日の朱実は、すぐに脱げ落ちてしまうステージ用の衣装。
彼女たちは、丸十が指揮をして、小川先生らが演奏している楽団の側に座る事になる。
すっかり彼女たちに舞い上がった丸十は、それまで演奏していた「天然の美」を止め、急遽、「リンゴの唄」などという流行歌を張り切って演奏しはじめる。
これには、真面目一方の校長も困り顔。
さらに、じろじろ自分達が観られていることを意識したカルメンは、立ち上がって、参観者たちに挨拶を送る始末。
その勘違いのスター気取りに、観覧者たちが笑い転げているのに、彼女は気づかない。
場の雰囲気を改めようと、予定していた田口のオルガン演奏による新曲の披露をはじめたものの、良い所で、丸十に手を触られた朱実が、驚いて立ち上がった瞬間、スカートが脱げ落ちてしまい、場内又又、大爆笑。
これには、さすがの田口も耐えきれず、その場から帰ると言い出し、それを思い止めさせようとする校長の説得空しく、その披露会は台なしになってしまう。
結局、カルメンと朱実はその場から退出させられる事に。
父正一も、娘のハレンチなファッションや言動に腰を抜かし、とうとう寝込んでしまっていた。
すっかり面目を失ったカルメンと朱実は相談しあい、村びとの前で踊ってみせようかと言い出し、牧場で踊りの練習を始めるのだが、その姿を目撃した村の男たちは大騒ぎ。
その噂を聞き込んだ丸十は、これは金になると悟り、信平に彼女たちに交渉に行かせると、自分の会社の倉庫で、観客一人100円の料金をとって、彼女たちの踊りを見せることにする。
その噂を聞き込んだ校長は、芸術だとばかり思い込んで、そんな裸踊りの娘を村に招いてしまった自分の不明を恥じると共に、正一に、彼女たちを止めるよう説得に出かける。
カルメンたちがバケツを叩きながら練習をしている牧場の側まで来た正一だったが、そこへ来てはじめて、娘を心底不憫に感じ、娘が芸術と信じ込んでいるのなら、彼女の好きなようにやらせてやってくれと、校長に頼むのだった。
しかし、丸十の商売丸出しの下品な根性は気に喰わないと、舞台建設中の丸十の所へやって来た正一と校長は、自分の娘を商売に利用したり、目の不自由な田口から唯一の楽しみのオルガンを奪ってしまった丸十をなじり、あろうことか、校長は丸十を背負投げしてしまうのであった。
かくして、その夜、丸十の倉庫に作られたにわか劇場は大入り満員。
丸十が指揮する楽団キューピッドのメロディーに合わせ、カルメンと朱実は、得意げに舞台で踊り始めるだった…。
▼▼▼▼▼個人的なコメントはここから下です。▼▼▼▼▼
日本初のカラー映画。
美しく爽やかな地方色を背景に、都会にかぶれた少し知恵の足りない娘と、のどかな村人たちの価値観の落差を、面白おかしく見せるコメディ。
文化や芸術という言葉を、どこか皮肉ったようなテーマ性も愉快。
ロケが中心となっているせいか、全体的にからっとしており、くどさや下品さはない。
主演の高峰秀子のあけっぴろげな演技も見所だが、友人の朱実を演じる小林トシ子の、いかにも何も考えていないはすっぱな存在感も笑いをさそう。
さらに貴重なのは、笠智衆のおとぼけ演技。本人はひたすら真面目にやっているだけに、なおさら愉快である。
目の不自由な田口のエピソードは、松竹得意の「泣きの要素」で、今観ると、若干違和感がない訳でもないが、あざといというほどでもなく、彼とその妻の会話等には、鋭い人間観察の真理が含まれていたりする。
彼が作ったという設定の「嗚呼我が故郷」という曲も、今聞くと、いかにも陰々滅々とした古臭い曲調で、あけっぴろげでのんびりとした村の雰囲気とはミスマッチで、その落差自体がギャグのように聞こえるのだが、当時は、意外と真面目な名曲として使われていたのかも知れない。
しかし、運動会でその曲が始まるや否や、カルメンらが、いかにもつまらなそうに聞いている所からすると、やっぱり、狙って、ああいう曲調にした可能性もありそうだ。
軽い役をのびのびと演じている三井弘次、又、カルメンたちの踊りを観に来ている高堂国典の短いカットもおかしい。
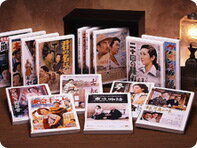 懐かしき“あの頃”映画 DVD全15巻<分割払い>【smtb-S】【送料無料】 |
