1964年、東映京都、紙屋五平原作、高田宏治脚本、倉田準二監督作品。
▼▼▼▼▼最初にストーリーを書いていますので、ご注意ください!コメントはページ下です。▼▼▼▼▼
寛永19年、近江藩琵琶湖、「水の忍者」と称され、漁民と対立している湖族たちの内、捕まった数名が、見せしめのため湖上で逆さ吊りの刑に処せられていた。
同じ琵琶湖に、越前から師匠である松田織部正の霊を弔いに来たのは、柳生の剣を学んだ幕屋大休(大友柳太郎)。
後日、幕屋は、江戸、馬喰町に「正統新陰流幕屋道場」なる看板をかかげて、門人を集うことになる。
これに、いきり立ったのは将軍家御指南役の御墨付きを持つ柳生新陰流の道場。
血気盛んな門人たちを前にして、大殿、柳生但馬守(香川良介)と、師範代庄田喜左衛門(内田朝雄)は、幕屋の背景を説明していた。
幕屋の師匠に当る松田織部正は、もともと、柳生の開祖、上泉伊勢守から柳生石舟斎と共に技を伝授された剣豪だったが、豊臣の門弟となったため、越前に身を置くことになった不遇の人物だったという。
その師匠の無念を晴らすため、弟子の幕屋は、宿敵、柳生十兵衛(近衛十四郎)を倒して、自分が幕府の御指南役になることを使命と考え、その十兵衛が、将軍家光の乗馬のお供で通りかかった前に立ちふさがり、新陰流正統を記した認可帖と、守り刀を家光に示すが、馬を降り立った十兵衛は、軽く幕屋と立ち会っただけで相手にせずその場を立ち去る。
しかし、その十兵衛の着物の胸元は、幕屋の刀で斬り裂かれていた。
庄田と共に、若い門弟たちの軽挙妄動を案じていた十兵衛の心配をよそに、勝手に幕屋を襲撃した8人は、柳生一門全滅を目指し、あらかじめ待ち受けていた幕屋に一瞬にして皆殺しにされてしまう。
そんな中、唯独り、現場から逃げ帰ってきた城所早苗(河原崎長一郎)は、柳生一門から卑怯者と蔑まれるようになる。
その後、幕屋一味に、道場にいた門人たち全員を惨殺され、近江で待つと記された書き置きを発見した十兵衛は、手練の仲間十人を引き連れて一路琵琶湖に向う。
今こそ汚名を晴らさんと、その十兵衛一行に合流し、同行を願い出た城所だったが、全く相手にされない。
その頃、すでに琵琶湖に戻っていた幕屋大休は、手下の田丸宗十郎(神戸瓢介)と面識がある湖族と連絡を取り、彼らを束ねている美鶴(宗方奈美)と面会すると、十兵衛たちを倒して、幕府に召し抱えられるよう互いに協力すると契りを結ぶのだった。
こうして湖族の一味が占領した竹生島への渡し船の待合所へやって来たのが、十兵衛たちとの同行をあきらめきれないで先にやって来た城所早苗。
しかし、城所は、又しても、幕屋たちの仲間に追い詰められてしまう。
そんな所へ到着した十兵衛たち一行は、湖族の待ち伏せを見破ると、捕らえられていた待合所の娘しの(岡田千代)を助け出した後、何知らぬ顔で、湖族が操る船に乗って竹生島に向うのだった。
やがて、そんな十兵衛たちを乗せた船を、水中から無数の湖族の一団が襲ってくる…。
▼▼▼▼▼個人的なコメントはここから下です。▼▼▼▼▼
湖での水中戦を交えた珍しいアクション時代劇。
大袈裟な大作ではなく、いってしまえば、プログラムピクチャーの一本に過ぎないのだが、小粒ながらアイデアに富み、娯楽作品としては十分楽しめる仕上がりになっている。
柳生十兵衛と拮抗する技量を持つもう一つの新陰流の使い手という設定がまず面白い。
その強力なライバルに扮するのは大友柳太朗で、主役十兵衛を演じる近衛十四郎と並べても貫禄に不足はない。
また、琵琶湖に住む湖族という設定も珍しく、夜間の船を挟んでのアクションも新鮮かつ見ごたえがある。
娯楽映画としては、ライバル同士の対決ものというシンプルな骨格がある上に、これら敵の設定が巧く出来ているので面白くならないはずがなく、さすがの柳生十兵衛も窮地に追い込められ、ラストのサスペンスは比類ないものになっている。
おっとりした中年イメージしかなかった近衛十四郎だが、全力で水中を泳いでいる姿を披露するなど、本格的なアクションに挑んでおり、その迫力には驚かされる。
河原崎長一郎扮する未熟な門弟の存在が、後半今一つ生かされていないようにも感じるが、単純な対決ものにならないよう、変化をつけるため加えられた要素なのだろう。
女優らしい女優は登場しない男中心の話ではあるが、湖族の首領であり、大友柳太朗扮する幕屋を助ける美鶴という少女と、十兵衛を助けるしのという少女は、共に新人女優らしいが、なかなか印象に残る重要な役柄を各々演じきっている。
近衛ファンや大友ファンなら必見の一本。
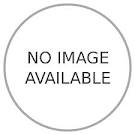 【レンタルアップ中古DVD】十兵衛暗殺剣/中古DVD |
