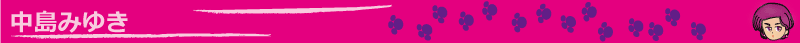
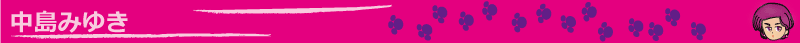
| 僕の夢 |
|---|
|
僕は酔いつぶれた女を背負って、人気のない線路沿いを歩いていた。 都心にあって寂れたアパートの立ち並ぶ一角。そこが彼女と初めて出会った場所だった。 「むにゃ……」 酒臭い吐息に混じって猫の声を背中に感じた。一度足を止め、ずり落ちかけた彼女を背負いなおすと、子供のような寝顔が見えた。 「ちゃんと捕まってないとおっこちまうぞ。俺だって酔ってるんだから」 聞いてか聞かずか、僕の首に回る彼女の腕に俄かに力が入った。 「こら、苦しいって!」
僕は笑いながら怒ると、また誰もいないJRの側道を歩き始めた。
「むにゃにゃにゃ……にゃは……にゃは」
今夜はこの季節には珍しく、少し風が冷たい。今朝まで降っていた雨がまだ残っているんだ。
僕はたまに揺り篭のように背中を揺らす。すると彼女は決まって顔を僕の背中に押し付け、幼子のような寝息を漏らすのだ。
君は僕より年上で、普段は人前で突っ張ってばかりいる。誰にも弱みを見せない。ただ笑顔を見せるときだけ、君は少し
弱気になる。そんな時はいつも、嫌われることを恐れているから。
無事に部屋までたどり着くと、僕は君の上着から鍵を取り出す。 僕が水を汲んでリビングに戻ると、眠っていたはずの君は決まって目を開けているんだよね。 「おかえり」 「ただいま」
僕は今夜もしてやられたと思いながら、美雪の部屋を後にした。 |
