|
| 梓 林太郎 |
生 没 年 | 1933.1.20〜 | 出 身 | 長野県 |
本 名 | 林 隆司 | 学 歴 | ― |
略歴・山歴 | 会社員、調査会社経営を経て、80年「九月の渓で」で第三回小説宝石エンタテイメント小説大賞を受賞。以後、精力的な執筆活動を続け、98年には著作が百冊を越えた。 |
作 品 等 | 豊科署の人情名刑事「伝さん」こと道原伝吉シリーズの「槍ヶ岳 白い凶器」、「風炎連峰」等、北アルプス山岳遭難救助隊員・紫門一鬼シリーズ「「殺人山行 穂高岳」、「殺人山行 不帰ノ嶮」等のほか、「岳人隊」、「雪渓下の密室」、「処女山行」など趣味の登山を活かし、山を舞台にしたミステリーを数多く記している。 |
受 賞 等 | 「九月の渓で」で第三回小説宝石エンタテイメント小説大賞を受賞(80年) |
|

「砂の山稜」より転載 |
|
| 生田 直親 |
生 没 年 | 1929.12.31〜93.3.18 | 出 身 | 東京都 |
本 名 | ― | 学 歴 | 福島県立川俣工中退 |
略歴・山歴 | 「映画の友」懸賞シナリオ入選を機に上京。テレビ脚本家として多くのシナリオを執筆。74年に「誘拐197X年」で推理界にデビュー。以後、精力的に執筆。 |
作 品 等 | 「死の大滑降」、「ヒマラヤ大滑降」など」得意とするスキーを絡めたスキー・ミステリー、「剣岳岩尾根殺人事件」、「『前穂高』殺意の岩峰」などの山岳ミステリーのほか、パニック小説、伝奇ミステリー、時代小説など幅広い分野の小説を手懸ける。他に代表作は「ソ連侵略198X年」、「東京大地震M18」など。 |
受 賞 等 | テレビドラマ「煙の王様」で文部大臣賞受賞(63年) |
|
 「剣岳岩尾根殺人
事件」より転載
「剣岳岩尾根殺人
事件」より転載 |
|
| 瓜生 卓造 |
生 没 年 | 1920.1.6〜? | 出 身 | 東京都 |
本 名 | ? | 学 歴 | 早稲田大学政治経済学部卒 |
略歴・山歴 | 大学卒業後ただちに兵役。復員して「文学者」、「早稲田大学」の編集委員を経て文学活動に入る。 |
作 品 等 | 播隆上人の一生を描いた「槍ヶ岳」、ヘルマン・ブールのナンガ・パルバット登頂を描いた「単独登攀」、数々の遭難事件を題材にした「銀嶺に死す」など史実・事実に基づいた作品を得意とする。他に代表作は「大雪原」、「金精峠」など。 |
受 賞 等 | 「南緯八十度」(55年)が芥川賞候補。「北極海流」(55年)、「単独登攀」(58年)が直木賞候補。 |
|
 「単独登攀」より転載
「単独登攀」より転載 |
|
| 太田 蘭三 |
生 没 年 | 1929.4.19〜 | 出 身 | 三重県鈴鹿市 |
本 名 | 太田 等 | 学 歴 | 中央大学法学部卒 |
略歴・山歴 | 78年に「殺意の三面峡谷」でデビュー。推理作家のほか、レジャーライターとして雑誌「つり人」等にエッセイ等を連載。登山歴、釣り歴は50年に及ぶ。 |
作 品 等 | レジャーライター釣部渓三郎と女子大生上条アキの名コンビシリーズ「奥多摩殺人峡谷」、「南アルプス殺人峡谷」等、警察手帳(オフダ)を持たない異色の刑事・香月功が勇躍する“顔のない刑事”シリーズ「尾瀬の墓標」、「赤い渓谷」、他シリーズでもおなじみの蟹沢係長(警部補)、相馬刑事の活躍を描いた北多摩署純情派シリーズなど多くの人気シリーズを持つ。他に「脱獄山脈」、「誘拐山脈」などの山岳ミステリーや、時代小説などがある。 |
|
 「誘拐山脈」より転載
「誘拐山脈」より転載 |
|
| 加 藤 薫 |
生 没 年 | 1933.9.26〜 | 出 身 | 神奈川県横浜市 |
本 名 | 江間 俊一 | 学 歴 | 学習院大学政経学部卒 |
略歴・山歴 |
69年「アルプスに死す」でオール読物推理小説新人賞を受賞。その後、山岳ミステリー数編を「オール読物」や「小説新潮」に執筆。
(活躍していた時期が69〜74年と短期集中していますが、それ以降どうされてるのでしょう?) |
作 品 等 | 「遭難」、「雪崩」、「残雪」など大学山岳部や山岳会を巡るエピソードを盛り込み、山を舞台にしたミステリー短編が数編あるが、単行本化されている長編は「雪煙」、「ひとつの山」のみ。 |
受 賞 等 | 「アルプスに死す」でオール読物推理小説新人賞受賞(69年)。「遭難」が直木賞候補(70年)。 |
|
|
|
| 北 杜 夫 |
生 没 年 | 1927.5.1〜 | 出 身 | 東京都 |
本 名 | 斎藤 宗吉 | 学 歴 | 東北大学医学部卒、医学博士 |
略歴・山歴 |
大学在学中に「文芸首都」の同人となる。卒業後慶大病院神経科助手、斎藤病院神経科医師として勤める。その間「幽霊」を自費出版。58〜59年に水産庁調査船「照洋丸」の船医となり、この時の体験を書いた「どくとるマンボウ航海記」がベストセラーとなり作家に転進。
65年には京都府山岳連盟隊のカラコルム・ディラン峰遠征に医師として参加。この時の体験をもとに山岳小説「白きたおやかな峰」を執筆。
父は歌人・斎藤茂吉氏、兄は精神科医であり随筆家でもある斎藤茂太氏。 |
作 品 等 |
主な作品は、大人気の「どくとるマンボウ」シリーズを始め、「楡家の人々」、「さびしい王子」、「月と10セント」など多数。
山岳小説としては「白きたおやかな峰」があるが、ほかに、旧制松本高校時代の経験を活かして、「少年」や「渓間にて」でも北アルプス周辺が登場する。 |
受 賞 等 | 「夜と霧の隅で」芥川賞受賞(60年)。「楡家の人々」毎日出版文化賞受賞(64年)。「どくとるマンボウ青春記」婦人公論読者賞受賞(69年)。「輝ける碧き空の下で・第二部」日本文学大賞受賞(86年)。 |
|
 「日本文学史」
より転載
「日本文学史」
より転載 |
|
| 谷 甲 州 |
生 没 年 | 1951.3.30〜 | 出 身 | 兵庫県伊丹市 |
本 名 | 谷本 秀喜 | 学 歴 | 大阪工業大学土木土木工学科卒 |
略歴・山歴 |
勤務していた建設会社勤務を辞めて、青年海外協力隊(ネパール)に参加。協力隊参加中に執筆活動を開始し、79年にSF専門誌「奇想天外」新人賞でデビュー。3年間の協力隊参加、広報誌編集者を経て、国際協力財団派遣専門家としてフィリピンで3年間過ごしたのち、執筆活動に専念。
登山を趣味とし、81年にはヒマラヤ・クン峰の7077mピークに登頂。 |
作 品 等 |
SF小説を中心に、冒険小説、山岳小説、ホラー小説などを書く。主著は「仮装巡洋艦バシリスク」、「星の墓標」、「マニラ・サンクション」など。
山岳小説としては、新田次郎賞を受賞した「白き嶺の男」、山岳冒険小説「遥かなり神々の座」、「神々の座を越えて」などがある。 |
受 賞 等 | 奇想天外新人賞受賞(79年)。「火星鉄道19」で星雲賞受賞(87年)。「白き嶺の男」で新田次郎賞受賞(96年)。 |
|
 「白き嶺の男」
より転載
「白き嶺の男」
より転載 |
|
| 長 井 彬 |
生 没 年 | 1924.11.18〜 | 出 身 | 和歌山県田辺市 |
本 名 | ― | 学 歴 | 東京大学文学部哲学科卒 |
略歴・山歴 | 大学卒業後、毎日新聞社に入社し、整理部に長年在籍したのち編集委員。定年退職後に小説家を志し、80年に「原子炉の蟹」で江戸川乱歩賞を受賞してデビュー。 |
作 品 等 | 新聞社編集委員を探偵役にした「殺人オンライン」、「連続殺人マグニチュード8」など、趣味のやきものを取り入れた「死の轆轤」などがある。同じく趣味の登山を活かした山岳ミステリーとしては、「槍ヶ岳殺人行」、「北アルプス殺人組曲」、「白馬岳の失踪」などがある。 |
受 賞 等 | 「原子炉の蟹」で江戸川乱歩賞受賞(80年)。「遠見二人山行」が日本推理作家協会賞短編部門の候補に(83年)。 |
|
 「槍ヶ岳殺人行」
より転載
「槍ヶ岳殺人行」
より転載 |
|
| 新田 次郎 |
生 没 年 | 1912.6.6〜80.2.15 | 出 身 | 長野県諏訪市 |
本 名 | 藤原 寛人 | 学 歴 | 無線電信講習所本科卒 |
略歴・山歴 |
無線電信講習所(現電気通信大学)卒業後、中央気象台(現気象庁)就職。戦時中、満州国中央気象台に勤務し帰国。気象庁勤務中の1951年に、「強力伝」が「サンデー毎日」の懸賞に入選し作家デビュー。
以後、二足のわらじを履きながら「孤高の人」や「武田信玄」などを執筆。66年に54歳で気象庁を退職。その間、気象庁測器課長として富士山レーダーの建設に携わる。80年、心筋梗塞により死去。
妻は「流れる星は生きている」などを記した作家の藤原てい氏。 |
作 品 等 | 「孤高の人」、「栄光の岩壁」、「銀嶺の人」の3部作など山岳小説はもちろんのこと、「武田信玄」、「武田勝頼」、「新田義貞」など歴史小説でも有名。他に「アラスカ物語」や「珊瑚」など史実に基づいた小説を得意とする。 |
受 賞 等 | 「強力伝」で「サンデー毎日」の大衆文芸・現代部門一席に入選(51年)。同作品を含む短編集「強力伝」で直木賞受賞(56年)。「武田信玄」ならびに一連の山岳小説に対して、吉川英治文学賞受賞(74年)。 |
|
 「郷愁の八ヶ岳」
(に挟まっていたチラシ)より転載
「郷愁の八ヶ岳」
(に挟まっていたチラシ)より転載 |
|
| 樋口 明雄 |
生 没 年 | 1950〜 | 出 身 | 山口県岩国市 |
本 名 | ― | 学 歴 | 明治学院大学法学部卒 |
略歴・山歴 | 雑誌記者、ゲームブック・ライターを経て、87年「ルパン三世/戦場はフリーウエイ」で作家デビュー。ライトノベル中心に手懸けるが、「明日なき山河」以降は、趣味の登山を活かした冒険小説も描いている。 |
作 品 等 | 少女小説など数多くのライトノベルのほか、アクション小説、冒険小説なども執筆。主な作品は、「サイレント・ファイア」、「灼撃の山塊」、「墓標の森」など。 |
受 賞 等 | 「狼は瞑らない」が日本冒険小説大賞第3位(2001年)。 |
|
 「明日なき山河」
より転載
「明日なき山河」
より転載 |
|
| 円山 雅也 |
生 没 年 | 1926〜? | 出 身 | 東京都 |
本 名 | ― | 学 歴 | 日本大学法学部卒 |
略歴・山歴 |
50年、日大法学部を卒業し、同年司法試験合格。裁判官を経て弁護士になる。ラジオ、TV、新聞などの法律解説コーナーでも活躍。77年参議院議員となり、82年法務政務次官。
戦時中谷川岳に通い、終戦直後、安川茂雄らとともに日本山嶺倶楽部を設立、数々の登攀を行う。 |
作 品 等 | 映画化された「遭難・ある夫婦の場合」(映画のタイトルは「妻は告白する」)などの弁護士入江卓夫の事件メモシリーズ等、弁護士という経歴を活かした独特の切り口による山岳文学、法廷サスペンスを開拓。 |
|
 「穂高S壁の殺意」
より転載
「穂高S壁の殺意」
より転載 |
|
| 森村 誠一 |
生 没 年 | 1933.1.2〜 | 出 身 | 埼玉県熊谷市 |
本 名 | ― | 学 歴 | 青山学院大学文学部卒 |
略歴・山歴 |
58年に大学卒業した後、新大阪ホテル、ホテルニューオータニ勤務。67年退職し、スクール・オブ・ビジネス観光学科主任講師に。その間、69年に「高層の死角」で江戸川乱歩賞を受賞、以後数多くの作品を発表。
10代の頃より登山を趣味とする。 |
作 品 等 |
推理小説、社会派小説など幅広く活躍。「野生の証明」、「新幹線殺人事件」、「悪魔の飽食」など著作多数。
山岳小説は山岳色の薄いものが多いが、「密閉山脈」や「虚無の道標」、「青春の源流」等では、山が重要なキーファクターとなっている。 |
受 賞 等 | 「高層の死角」で江戸川乱歩賞(69年)、「腐蝕の構造」で日本推理作家協会賞(72年)、「人間の証明」で角川小説賞(76年)をそれぞれ受賞。 |
|
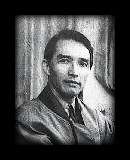 「堕ちた山脈」より転載
「堕ちた山脈」より転載 |
|
| 安川 茂雄 |
生 没 年 | 1925〜77.10.23 | 出 身 | 東京都 |
本 名 | 長越成雄 | 学 歴 | 早稲田大学仏文科卒 |
略歴・山歴 |
大学卒業後、三笠書房に就職。編集長をしながら山岳小説等執筆。編集長として石原慎太郎、有吉佐和子など多くの有望新人を発掘し、ベストセラーを連発。
戦時中から谷川岳を登攀し、円山雅也らと日本山嶺倶楽部を設立、初登攀記録等打ちたてる。のち、第2次RCCメンバー。 |
作 品 等 | 「霧の山」、「朝焼け」など、山に行きたくても思うように行けなかった自らの体験を基にした青春・戦争小説的な山岳小説を記す。他に、「穂高に死す」などのノンフィクション、「山に闘う」(ランベール)等の訳本など署作多数。 |
|
|
|
| 夢 枕 獏 |
生 没 年 | 1951.1.1〜 | 出 身 | 神奈川県小田原市 |
本 名 | 米山 峰夫 | 学 歴 | 東海大学文学部日本文学科卒 |
略歴・山歴 |
上高地山小屋のボイラーマン、写真屋の現像マン、タウン雑誌編集などを転々とする傍ら原稿を書き、77年「奇想天外」誌に「カエルの死」でデビュー。「魔獣狩り」シリーズで人気。
趣味は、登山、鮎釣り、カメラ、等。 |
作 品 等 |
「魔獣狩り」シリーズ、「幻獣変化」シリーズ、「キマイラ」シリーズ、「餓狼伝」シリーズ等々SFを中心に手懸ける。
山岳小説としては、「神々の山嶺」、「月に呼ばれて海より如来る」等。 |
受 賞 等 | 「上弦の月を喰べる獅子」で日本SF大賞受賞(89年)。「神々の山嶺」で柴田錬三郎賞受賞(98年)。 |
|
 「神々の山嶺」より転載
「神々の山嶺」より転載 |