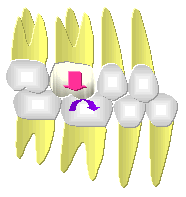
以下のものから、症状を選んでください。
冠やブリッジを入れたところのかみ合わせが高く、その歯やかみ合っている歯に痛みが出たり、動いたりするようになることを咬合性外傷(こうごうせいがいしょう)といいます。
冠やブリッジを入れたとき、かみ合わせが少し高いように感じても、歯医者から「そのうち慣れる」と言われて、後から症状が出てくる場合もあります。歯は髪の毛一本かんだだけでも、それが「ある」ことを認識するくらいデリケートなものです。歯が動くのは、高いかみ合わせから逃げるためです。
強く当たっている部分を削って調整することで、歯の動きもおさまってきます。
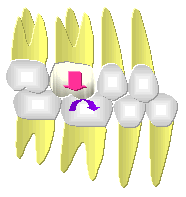
歯ぐきが腫れる主な原因は歯周病か根の先に膿の袋ができる病気(根尖病巣)です。
歯周病の場合には、特に奥歯で根が2つ以上ある歯で、根が分かれる部分に膿が溜まると歯が持ち上げられてかみ合わせが高くなります。咬合性外傷を併発して、あるいは歯周病で歯を支える骨が減少することによって、歯が動いてくる場合もあります。
根尖病巣(こんせんびょうそう)が原因の場合は根の先に急激に膿が溜まることで歯が持ち上げられ、かみ合わせが高くなります。この場合はかんだ時だけでなく、何もしない状態で強い痛みがあります。ゆっくり膿が溜まる慢性の根尖病巣の場合には、根の先の骨が溶けて膿の場所を作るためにほとんど痛みを感じません。
どちらが原因であるかは、歯科医師でもレントゲン写真や歯周ポケット(歯と歯ぐきの境目)の状態、歯が生きているか死んでいるかを調べなければわかりません。
どちらの場合も、まずは抗生物質(化膿止め)で急性症状を抑えます。腫れが強い場合には歯ぐきを切って膿を逃がします。根尖病巣が原因の場合には、神経が通っていた穴(この場合、神経はすでに死んでいます)からも膿を逃がします。
急性症状がおさまった後に、きちんとした歯周病や根の治療を行う必要があります。
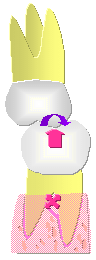 歯周病が原因の場合 |
 根尖病巣が原因の場合 |
何ともないのに歯が動くようでしたら、歯周病が疑われます。歯磨きで血が出てきたり、歯ぐきがさがって根がみえてきているようでしたら、歯周病である可能性は高いといえます。
歯は周りを取り囲む骨や歯ぐきによって支えられています。歯周病で骨がさがることによって歯を支える部分が少なくなると動くようになります。
歯周病の治療が必要ですが、治療後は大抵の場合、骨がさがったなりの位置で健康を回復しますので、歯ぐきは引き締まって血が出ないとしても、ある程度の歯の動きは残ります。かみ合わせで不快感があったり、よくかめない場合には歯をブリッジなどでつなぎ合わせることにより、動きを抑えます。
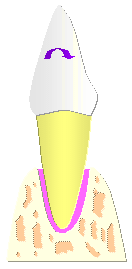
ぶつけたり、強くかんで音がした(痛みが出た)ことで歯が動くようになったときは歯が破折していたり、脱臼してしまった可能性があります。脱臼していても歯が抜けてこない状態を不完全脱臼といいます。
歯が破折している場合、状態によっては根の治療をすることで残せます。それが不可能な場合には、延命処置をしたとしても、最後は抜歯になってしまいます。
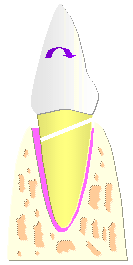
歯の破折
不完全脱臼の場合には、隣の歯と固定することで安静を保ちます。もし、脱臼が原因で神経が死んでしまったら、後から根の治療をする必要があります。
脱臼して歯が抜けてしまった場合(完全脱臼)、根に残っている歯根膜(肉がついている感じ、根の表面が濡れたような感じでみえます)が生きているかどうかが、歯を再植してくっつくかどうかの決め手になります。もし、交通事故や喧嘩で歯が抜けてしまった場合には、早めに歯科医院へ歯を持ってきてください。その際、再植が上手くいくための目安を下の表に挙げておきます。
| やった方がいいこと | 歯は頭の部分を持ってください。根の部分はできるだけ触らないようにしてください。 泥やほこりがついている場合、歯の頭の部分を持って流水で洗います。 痛くなければ、歯を抜けた穴に戻した状態で来院してください。 痛みのあるときは、唇の裏側に歯を入れるといいでしょう。 それも無理な場合は、水か牛乳に浸した状態で歯を持ってきてください。 |
| やってはいけないこと | 根の部分を指でべたべた触らないようにしましょう。 歯を洗うときは根の部分を指でこすらないようにしてください。 ハンカチやティッシュに歯をくるまないようにしてください。 乾燥した状態にすると、歯根膜が早く死んでしまいます。 |