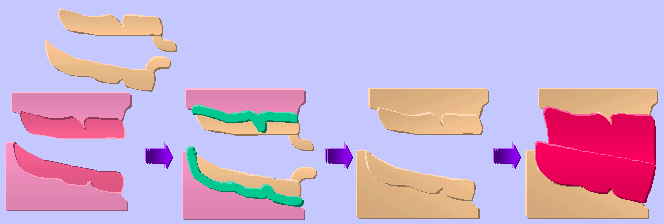
この項目では総入れ歯ができるまでの手順を説明します。
口の中の型取りをします。既成のトレー(型取りの枠)を使う場合もありますが、より適合の良い入れ歯を作るためには、一旦既成のトレーで型取りして作った模型から、その人の口にあったカスタムメイドのトレー(個人トレー)を作り、精密な型取りに利用します。下図左は個人トレーの例です。
個人トレーにモデリングコンパウンドと呼ばれる、熱を加えると軟らかくなり、常温では固くなる材料をつけます。下図で緑色の部分になります。軟化している状態で頬の筋肉を引っ張ったり、舌を動かしてもらったり、口を開閉してもらったり、指を吸ってもらったりして、口の中で動く部分と動かない部分の境目を記録していきます。これを筋圧形成(きんあつけいせい)と言い、入れ歯で覆う範囲が決定されます。
筋圧形成が終了したら型取りの材料をトレーに盛って型を取ります。型取りの材料が固まる前に、再度筋圧形成と同様の操作をし、モデリングコンパウンドで記録した部分が型取り材で厚く覆われてしまわないようにします。
トレーに石膏を流し、固まったら取り出します。
入れ歯の範囲を想定し、ワックスのブロックで上下それぞれに歯が並ぶ部分を作ります。これを咬合床(こうごうしょう)と言います。
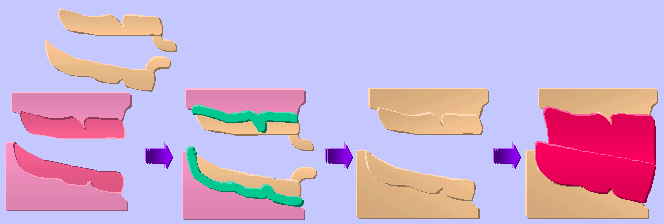
咬合床を用いて、歯が並ぶ平面や高さを決めます。
まず上顎の基準面を決定します。横方向からは、耳の穴上方と鼻の下を結ぶ線と平行になるようにします。前方からは、左右の瞳孔を結んだ線と平行になるようにします。前方からみた平面の高さは、唇の角を結ぶ線にほぼ位置します。咬合床のワックスを削ったり付け足したりしながら平面を決めていきます。
次に下顎の高さを決定します。唇を閉じてリラックスした状態から2mm引いた高さが、噛んだときの高さになります。この時、目と唇の角を結んだ線と、鼻の脇から顎の下までを結んだ線がほぼ等しくなることが利用されます。下顎の咬合床のワックスを軟化させ、ゆっくりと噛んでいってもらいながら、適切な高さになるように調整していきます。ノギスで計測しながら行ないます。
最後に上下の咬合床を固定します。正中の部分と、唇の角の部分(前歯を並べる範囲)をワックスに印記します。
人工歯の形、色、入れ歯の歯ぐきになる部分の色を選択します。
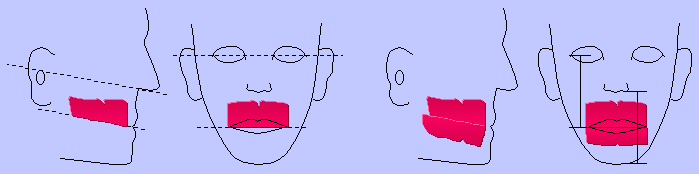
咬合床と模型をかみ合わせを再現する器械に取り付けます。専門的には咬合器(こうごうき)と言います。
ワックスの部分に人工歯を並べていきます。並べ終わった後、歯ぐきに相当する形になるよう、ワックスを彫刻していきます。
ワックスの入れ歯を一度口の中に入れ、歯の並び具合、かみ合わせ、歯ぐきに相当する部分の微調整を行ないます。
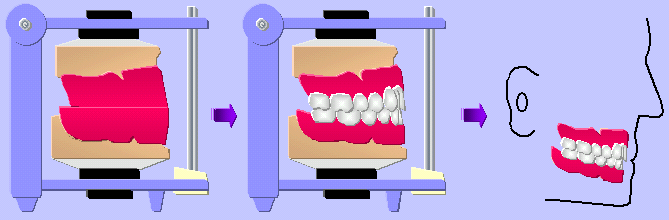
模型を咬合器から取り外し、重合用(じゅうごうよう)フラスコと呼ばれる金属の型枠に入れます。まず、模型の下半分を下側のフラスコ内に石膏でつけます。固まったら石膏の部分に分離材を塗り、上側のフラスコを被せて石膏を流し、ふたをします。分離材を塗ることで、石膏が固まった後に上下のフラスコにきちんと分けることができます。外側から透視すると、下図右のようになります。
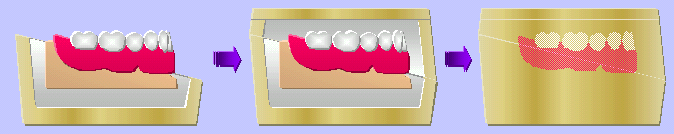
石膏が固まったらフラスコを熱湯につけ、ワックスが軟化したら上下のフラスコを外し、残っているワックスを熱湯で流します。人工歯はフラスコの上半分に石膏で固定された状態になります。ワックスで作った入れ歯の歯ぐきになる部分は、何もない状態となります。
上下それぞれのフラスコで、歯ぐきになる部分にレジン分離材を塗ります。
歯ぐきになる部分に入れ歯用のレジン(プラスチック)を入れます。粉と液を混ぜ合わせ、餅状になったらフラスコのワックスを流した部分につけます。プレスして余剰なレジンを取り除きます。
熱湯に入れて重合し、硬いプラスチックにします。
固まったレジンは人工歯がある上側のフラスコにきます。下側のフラスコと上側のフタを取り外し、木槌でたたいて入れ歯と石膏のかたまりを上側のフラスコから外します。石膏を壊して入れ歯を取り出し、上下のフラスコの間でバリになっている部分を削って修正し、研磨します。
口の中に入れ、かみ合わせや歯ぐきの部分の調整を行ないます。
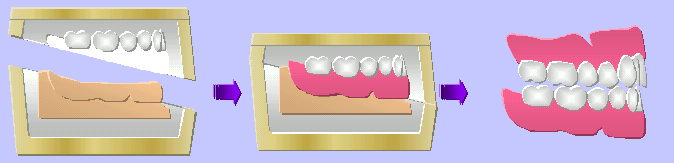
部分入れ歯もほぼ同様の手順で製作します。バネの部分は、ワイヤーの場合には曲げて形を合わせ、金属製のものは被せ物と同様の手順で鋳造します。